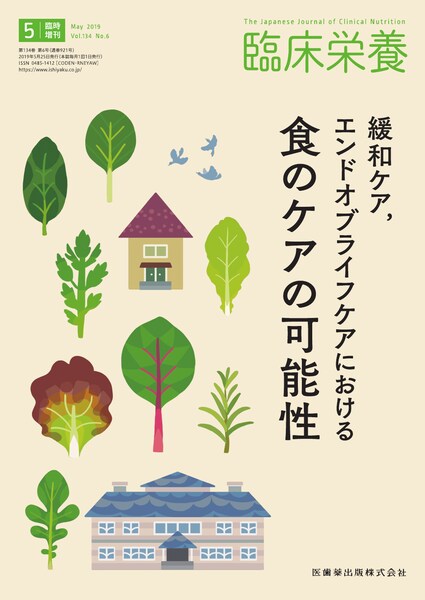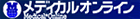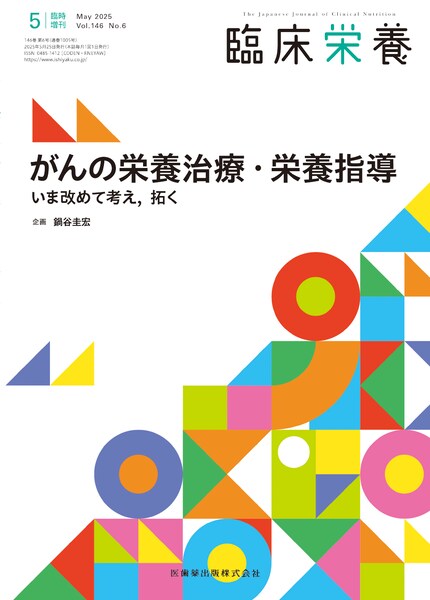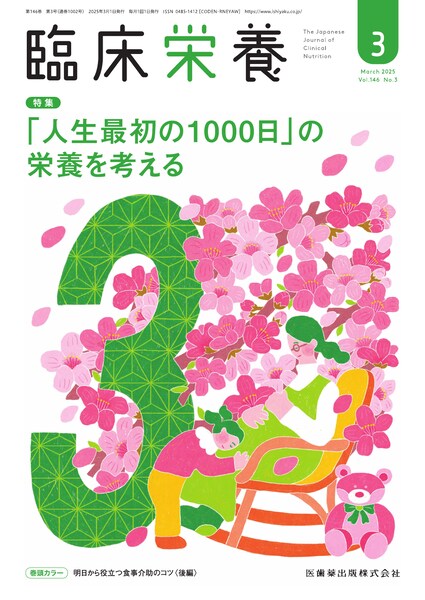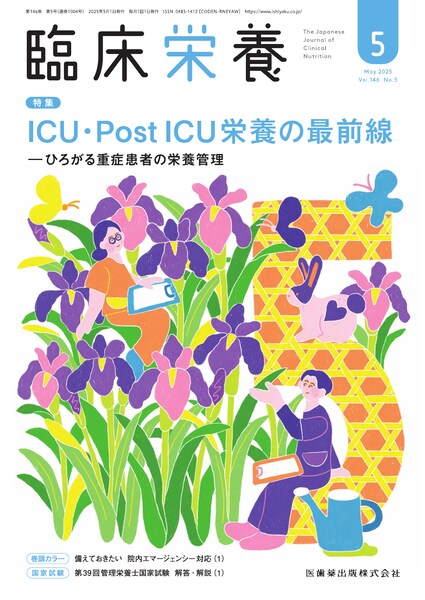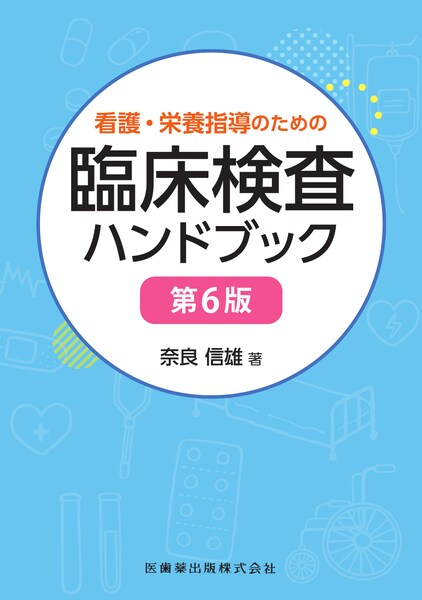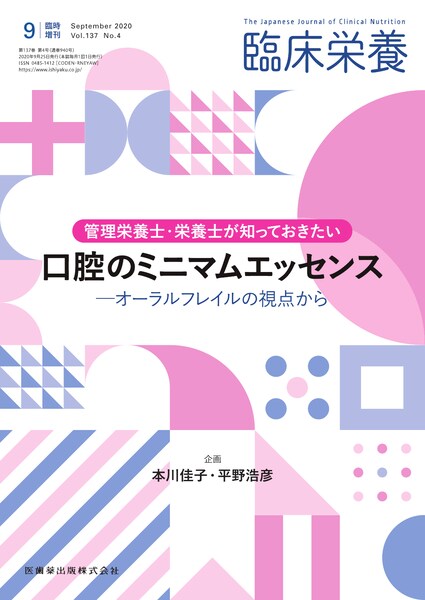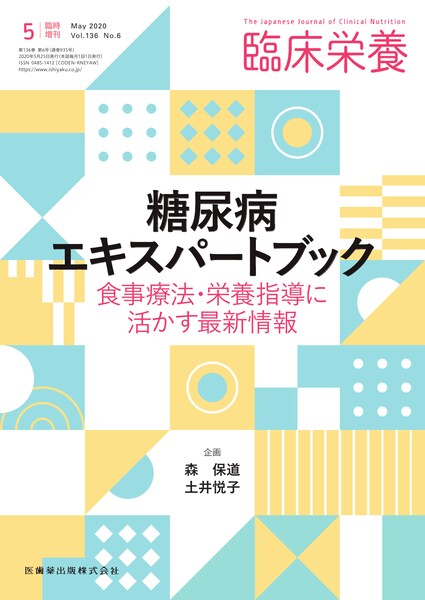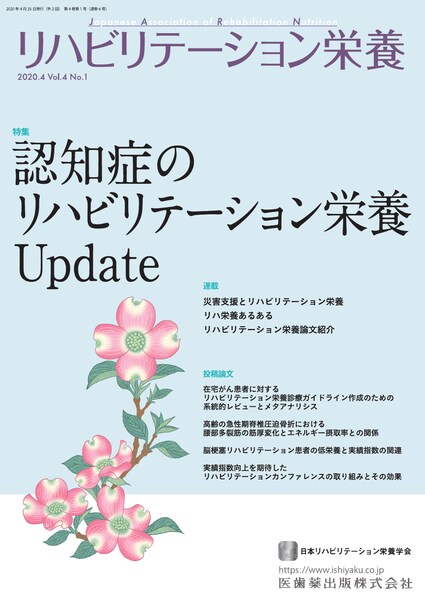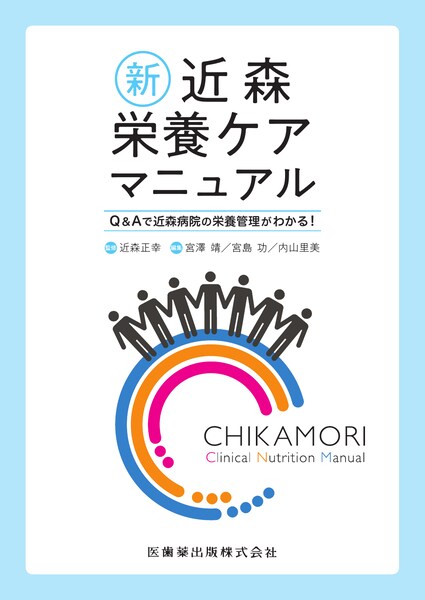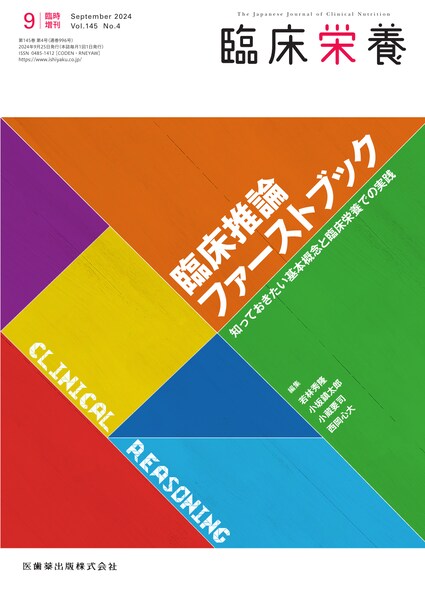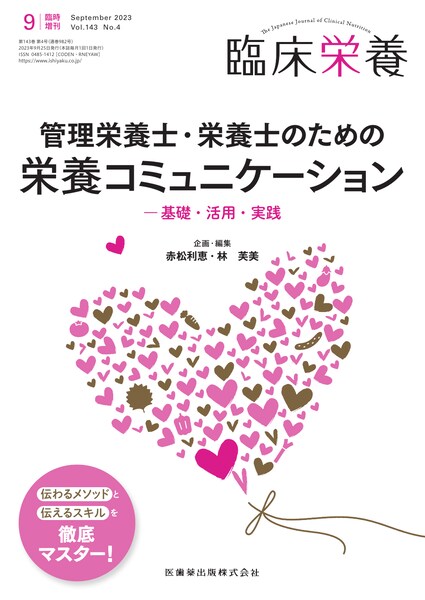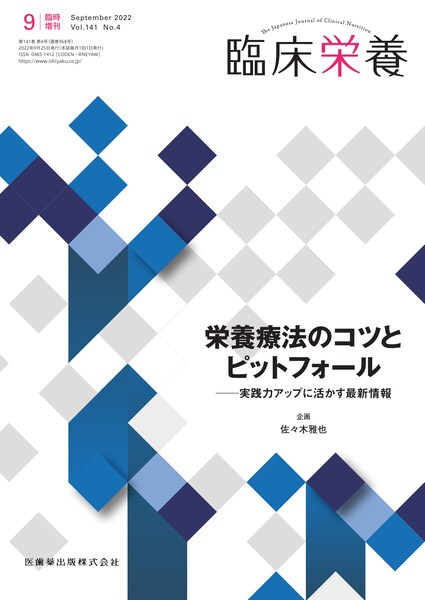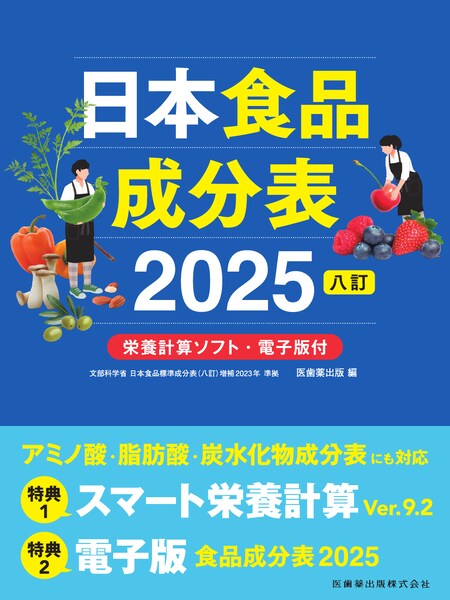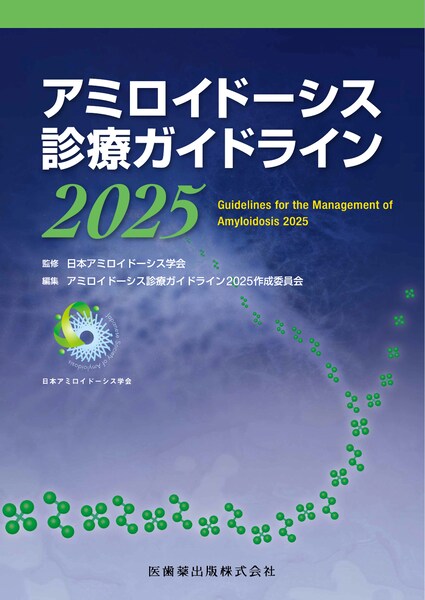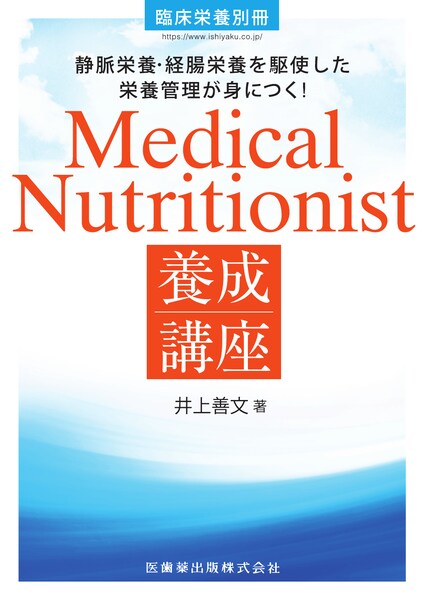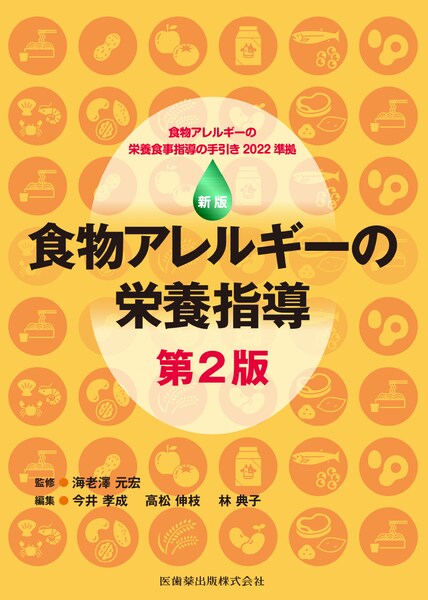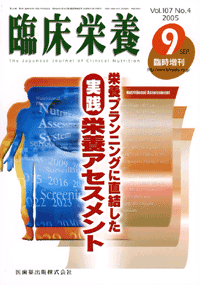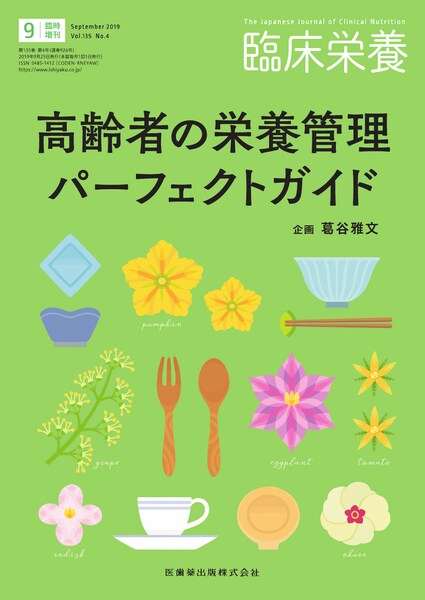目次
Part 1 緩和ケア,エンドオブライフケアの基本と現状
緩和ケアとは(松田良信)
ホスピス緩和ケア病棟とは(岡山幸子)
QOL とは−QOL 評価・測定の基本(宮崎貴久子)
ACP とは−食べることの意思決定に向けたかかわり(濱吉美穂)
スピリチュアルケアとは(梶山 徹)
家族ケアとは(岡本双美子)
遺族のグリーフとそのケア−食への想い(米虫圭子)
在宅におけるホスピス緩和ケアとは(前野 宏)
Part 2 がん患者に出現する症状と緩和ケアにおける治療・ケアの概略
終末期がん患者に出現する症状(諏訪直子・恒藤 暁)
痛み(金村誠哲)
便秘,下痢(谷澤久美・嶽小原 恵)
悪心,嘔吐,腸閉塞(清水啓二)
呼吸困難(今村拓也)
精神障害の診断,せん妄(津田 真)
気持ちのつらさ,睡眠の障害(「眠れない」)(津田 真)
がん悪液質(荒金英樹)
緩和ケアとコルチコステロイド(松尾直樹)
終末期医療における輸液療法・栄養療法の効果(森 直治)
Part 3 緩和ケア,エンドオブライフケアにおける最近の話題
緩和ケア,サポーティブケアにおけるNST とPCT の役割と連携−進行がん患者とその家族の食に関する苦悩へのケア(天野晃滋)
心不全患者に対する緩和ケア(安斉俊久)
慢性呼吸不全患者に対する緩和ケア(坂下明大)
緩和ケア,終末期ケアにおける口腔の管理,口腔ケア(大野友久)
がん患者におけるサプリメントのエビデンス(大野 智)
尊厳死と食事の自己中止−VSED で死期を早める患者について(新城拓也)
Part 4 緩和ケア,エンドオブライフケアにおける食・栄養のケア
最期まで食べることを支える管理栄養士による食支援(川口美喜子)
がん患者における食のケア(藤井映子・今村 岬)
慢性心不全患者における食のケア(村井亜美・山田未奈)
慢性呼吸不全患者における食のケア(岡本智子)
コラム いのちのスープの取り組み−医療者がスープを配ることの意味(津田 真)
緩和ケア病院における食のケア−“食”に求めるもの:栄養士にできること(細見陽子・大嶋健三郎)
特別養護老人ホームでの食のケア(芦澤菜月)
ホスピス型賃貸住宅での食のケア(前田陽子)
在宅での食のケア(前田佳予子)
終末期がん患者に対する食のケアで期待される管理栄養士・栄養士の役割(池永昌之)
電子版の購入
以下のウェブサイトで論文単位の購入が可能です.
※リンク先は医歯薬出版株式会社のウェブサイトではありません.利用方法等は各ウェブサイトへお問い合わせください.