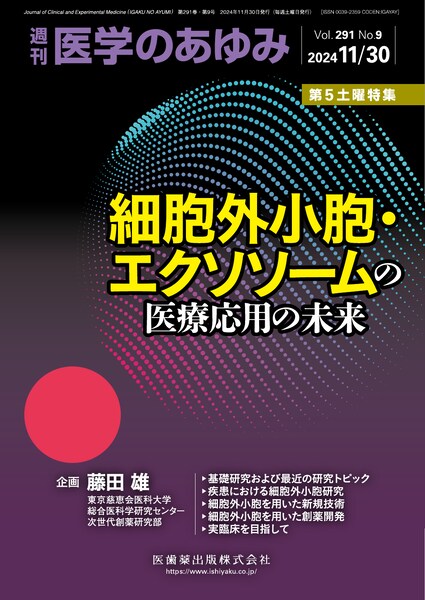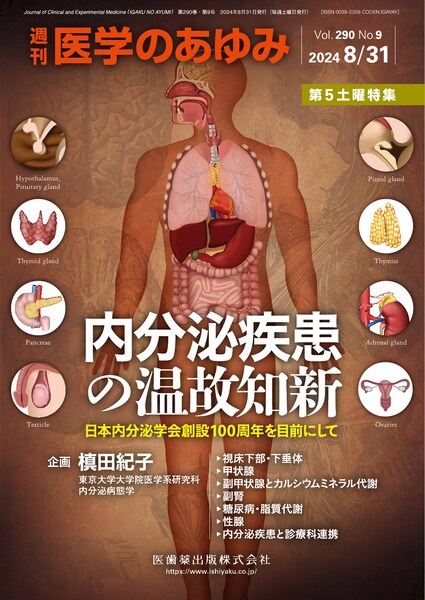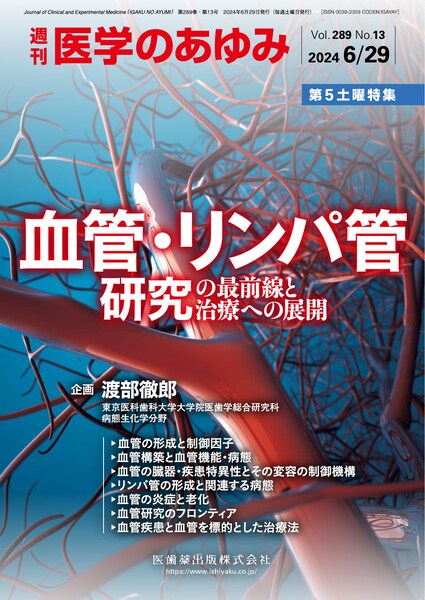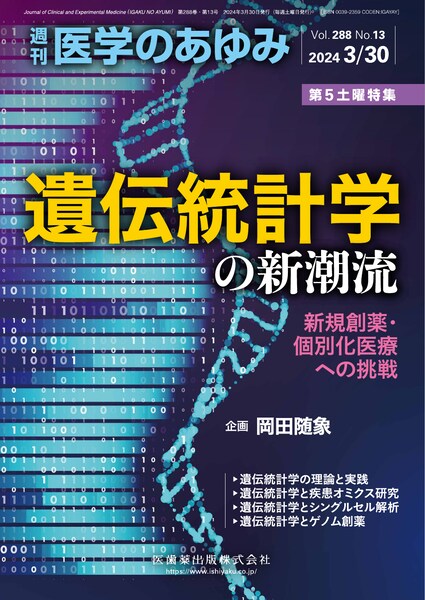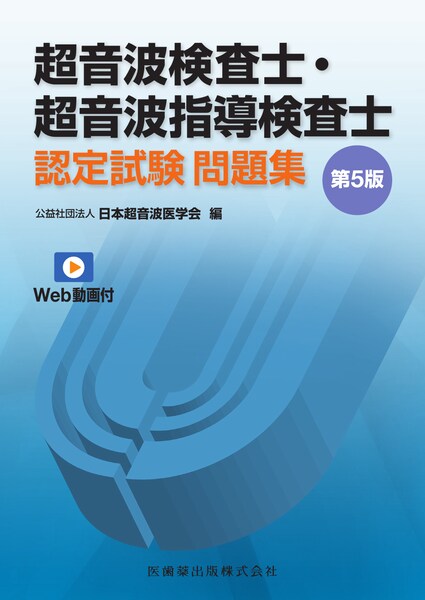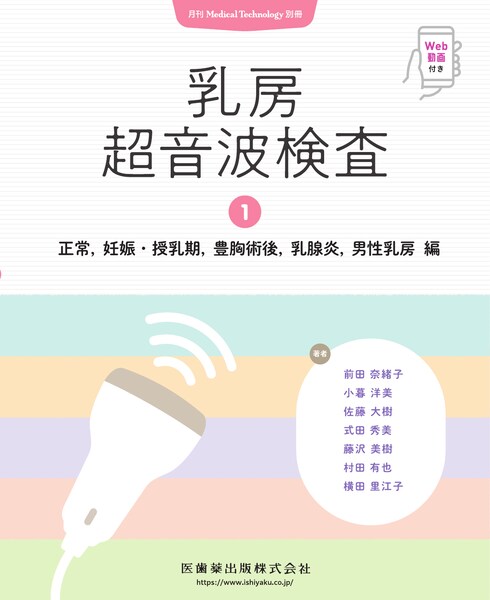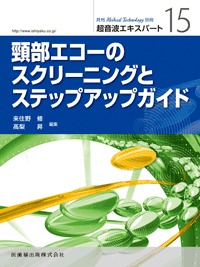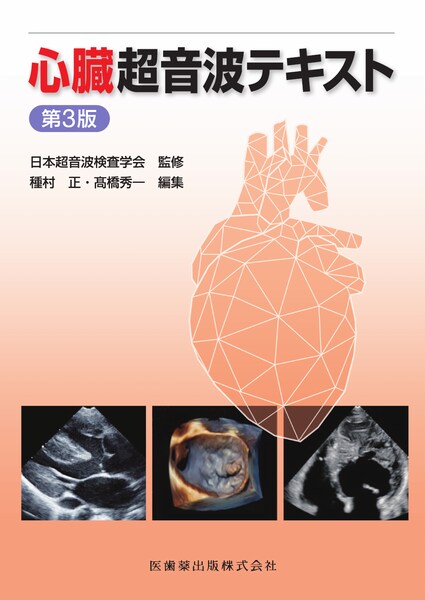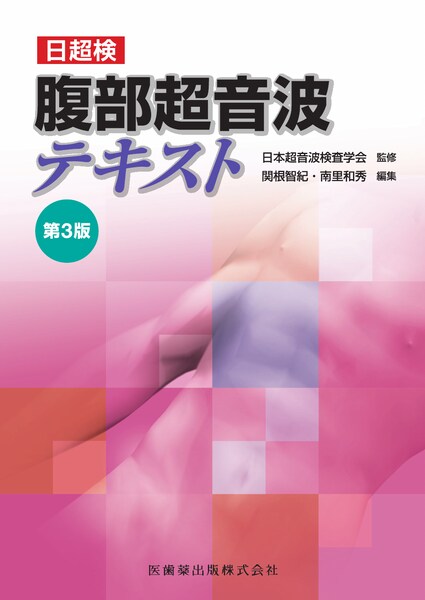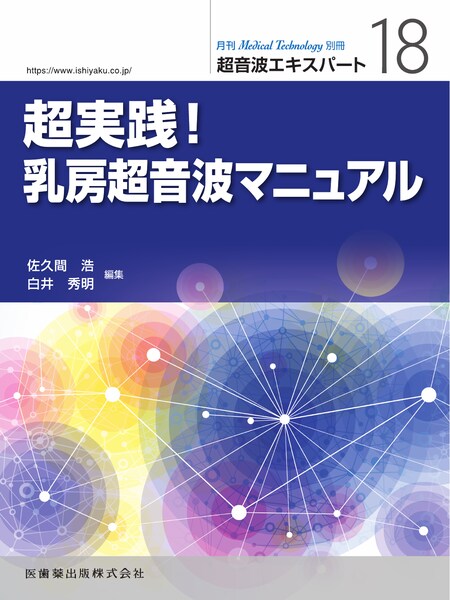�ڎ�
���_�F�Տ������̏���
�@�Q�m����͋Z�p�̐i���ƗՏ������ւ̉��p�@������V
�@���L�b�h�o�C�I�v�V�[�|����ɂ�����Տ����p�Ə����W�]�@����@�@
�@�a���g�D��p�����R���p�j�I���f�f2017 �őO���|ROS1 ��`�q�CPD-L1 ��`�q�CRAS ��`�q�CBRAF ��`�q�@���X�@�B
�@��܊������@���J�@��
�@�Տ��������p��͈͂̈Ӌ`�@�N�@���V
�@�Տ��������̎��ۏF��O�ҔF��@�v�ۖ쏟�j
�@POCT�ipoint of care testing�j�@�e�r�t�l
������
�@�w���R�o�N�^�[�s�����֘A�����@���c��T
�@��ᇐ��咰���ɂ�����֒��J���v���e�N�`���̖����|��N�P��Â̒��S�ց@�g���T��E��
�@�̐��ۉ��}�[�J�[�@�r�c�@��
�z��
�@�S�}�[�J�[�@�Έ䏁��
�@�S�s�S�̃o�C�I�}�[�J�[�FBNP�CNT-proBNP �ɓ��݂䂫�E��
���
�@���A�a�̌����ƌ����@��|�ŋ߂�4 �̘b��@���ԗY��E��c���F
�@�����ُ�ǂ̐f�f�@�g�c�@��
�@����Ӄ}�[�J�[�̎g�����@�|������
�@�r�^�~��D �s���E���R�̐f�f�|����25�iOH�jD ����̈Ӌ`�@����@��
������E���B��
�@������E��������̃Q�m����Á@����N�g
�@�������̃o�C�I�}�[�J�[�ł���ROMA �̏Љ�@�߉�N�j�E���@�P��
�t��
�@�V�KAKI �o�C�I�}�[�J�[�|�ANGAL �𒆐S�Ɂ@��F�@��E�y�䌤�l
�@CKD �̃o�C�I�}�[�J�[�@�Îs����E�a�c���u
�@���A�a���t�ǂɂ�����o�C�I�}�[�J�[�@�ד��N�G�E�֓����F
�ċz��
�@�ċz�튴���ǂ̂Ȃ��̃q�g���^�j���[���E�C���X�����ǁ|�q�g���^�j���[���E�C���X�R���萫�@�e�c�p��
�@�R�_�ی����F���j�یQ�j�_���o�@����@��
�@���������̃o�C�I�}�[�J�[�|�n�����\�e�����֘A�y�v�`�h�𒆐S�Ɂ@�����a��
���t
�@��������WHO ����2016 ���x�����`�q�����@���c�C��
�@���𐫔������ǏǁiTMA�j�̌����@���W���N
�@�w�p�����N�������������ǁiHIT�j�f�f�̍ŐV�����|�a�Ԃ��痝������@���{�Ďj�E��y�@�T
�@DIC �̐V�����f�f��|�Տ������̏d�v���@�����
�_�o
�@�_�o�����ɂ����鎩�ȍR�́@��؏G�a�E��@�i
�@�A���c�n�C�}�[�^�F�m�ǂ̃o�C�I�}�[�J�[�@�r���@��
�P���a�E�A�����M�[
�@IgG �T�u�N���X�����FIgG2�CIgG3 ��X�R�b��
�@���������ǐ��؎����ɂ����鎩�ȍR�̌����|���ȍR�̌����̃A�v���[�`�Ƒ���Ӌ`�@�R��X��
�@�R���������R�́@�M�v�ۂ䂤�E�O���r�p
������
�@���ʕ��͖@�ɂ��ێ�̐v������@��퐴��
�@�ۊ����ǂ̈�`�q�����ł߂������́|�ۂ̓���ƍR�ۖ�ϐ���`�q�@���n�M�F
�@���{���̐V�����ǃ}�[�J�[�g�@�v���Z�v�V���h�@�Ɋ���҂ƌ����@�א�N��E�u�n�L�N
�@�f���O�M�̐f�f�@���ߌ��u
�@�����̓��W�\��
�@���T�C�h�����ڎ�
�@�@�R���p�j�I���f�f����
�@�@��`�q�p�l������
�@�@��ᇓ��s�ψꐫ
�@�@�g���X�c�Y�}�u
�@�@�x�o�V�Y�}�u
�@�@�F��@��
�@�@CLIA '88
�@�@Therapeutic turnaround time�iTTAT�j
�@�@�w���R�o�N�^�[�s�����i�s�����ہj�̏��ێ���
�@�@UCEIS
�@�@��
�@�@LCZ696
�@�@���z���ƍ��`���̃J�b�v�����O�ƃA���J�b�v�����O
�@�@F �`����
�@�@�C���m�N���}�g�@
�@�@���������̔��Ǘv��
�@�@Clonal hematopoiesis of indeterminate potential�i�@CHIP�j
�@�@�n���t�B�u�����iSF�j�̑���n
�@�@���̑��̎��ȖƉu���]��
�@�@�������ǐ��E�����������j���[���p�`�[�iCIDP�j
�@�@�z�X�t�@�`�W���Z�����ˑ����R�v���g�����r���R�́iaPS/PT �R�́j
�@�@��2-GPI ��domain I�ɑ���R�́i�Rdomain I�R�́j
�@�@�}���z��ƃg�����X�|�]��
�@�@�C���e�O����
���M�҂̊֘A���Ђ�T���ꍇ�͉��ɕ\�����ꂽ���O���N���b�N���Ă�������
��y�T�@����d�q�ł̍w��
�ȉ��̃E�F�u�T�C�g�Ř_���P�ʂ̍w�����\�ł��D
�������N��͈㎕��o�Ŋ�����Ђ̃E�F�u�T�C�g�ł͂���܂���D���p���@���͊e�E�F�u�T�C�g�ւ��₢���킹���������D


![�u��w�̂���݁v��5�y�j���W��263��13�� �Տ������̍őO���\�����̌�����W�]����](/photo/28657-m.jpg)
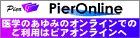
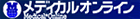
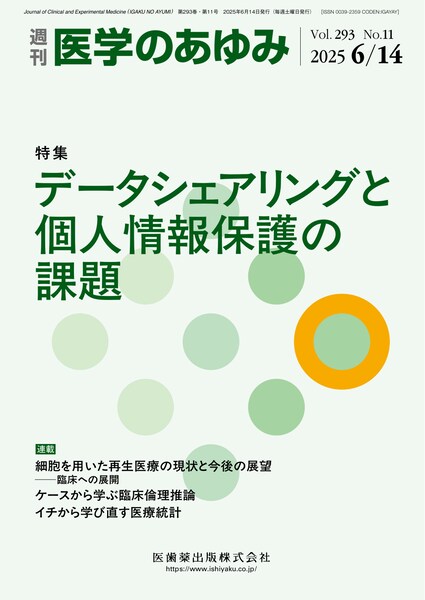
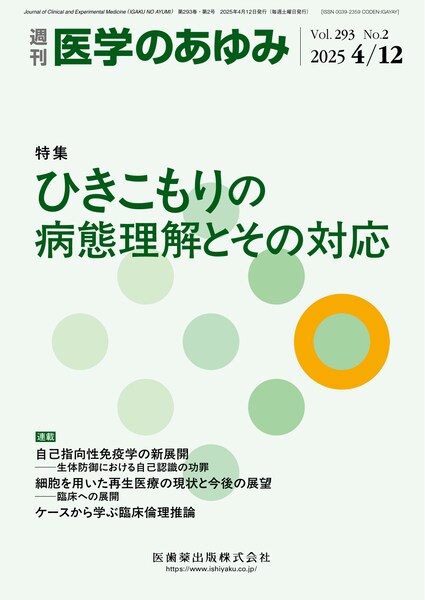
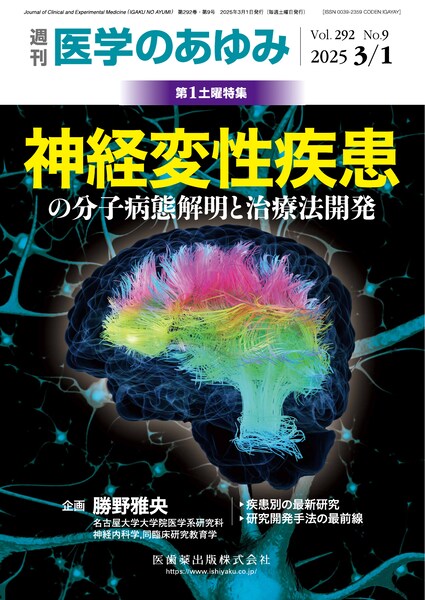
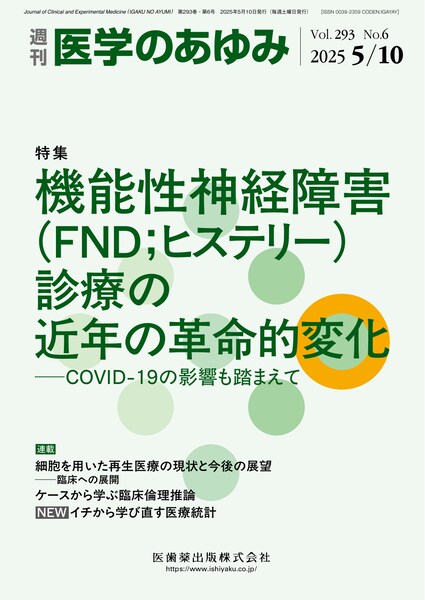
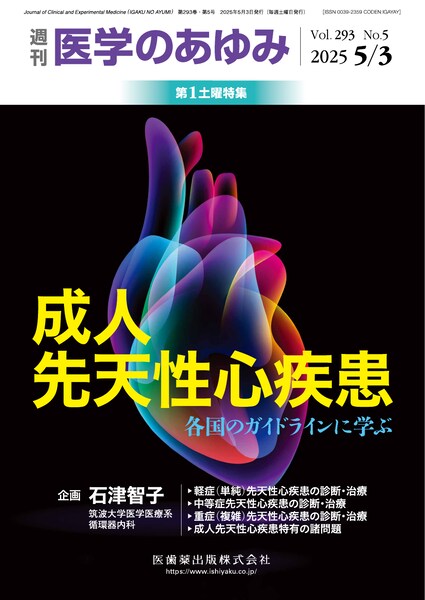
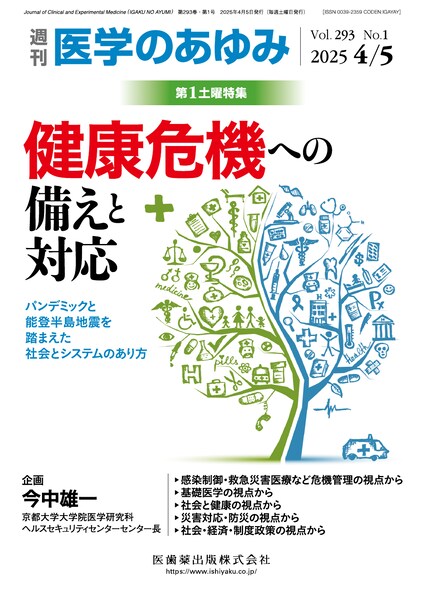
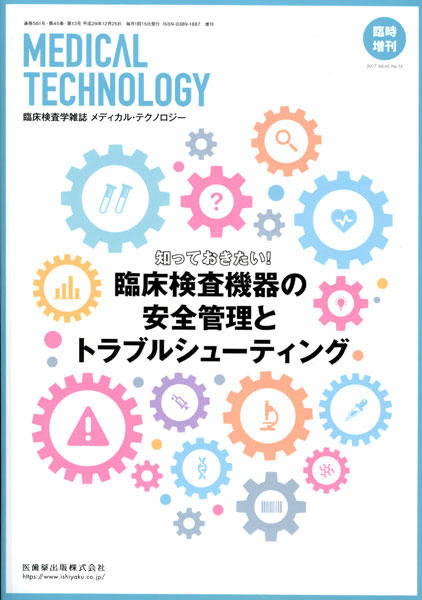
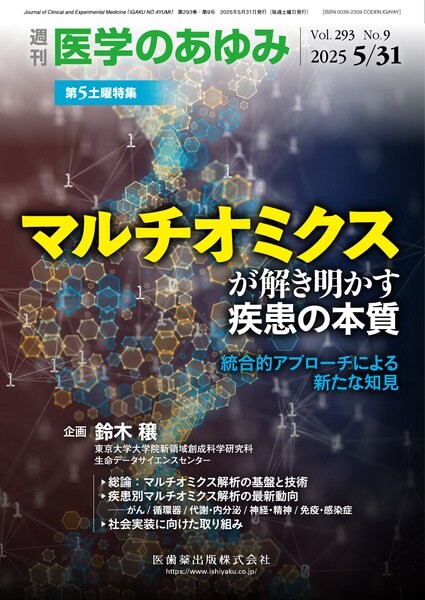
![�]�Ȋw���������i���� ���a�̕a�ԁE�f�f�E���Â̔��W](/photo/28687-m.jpg)