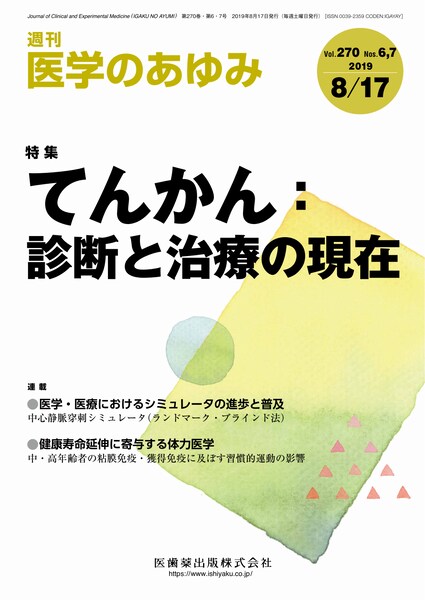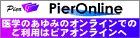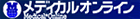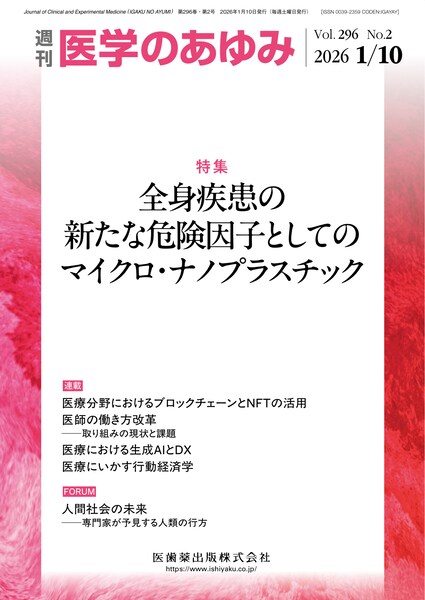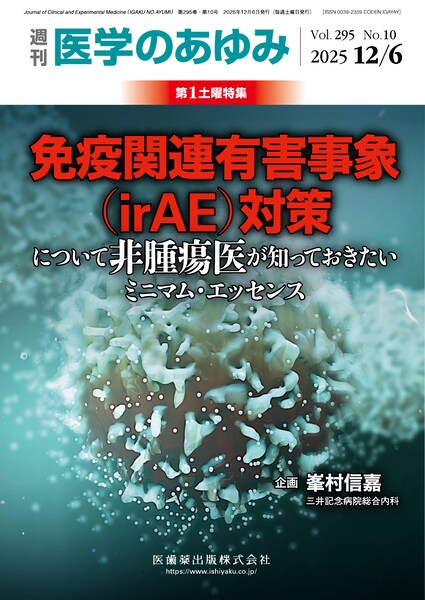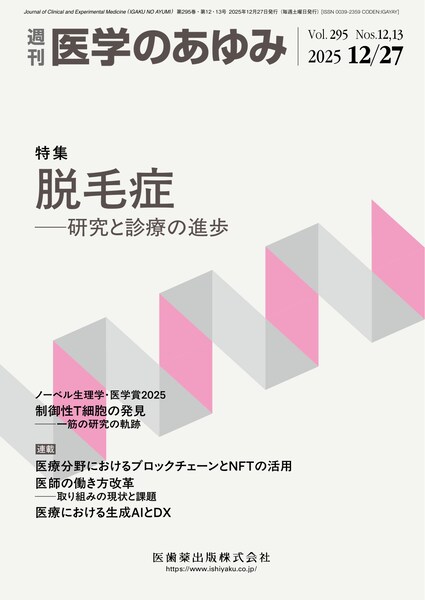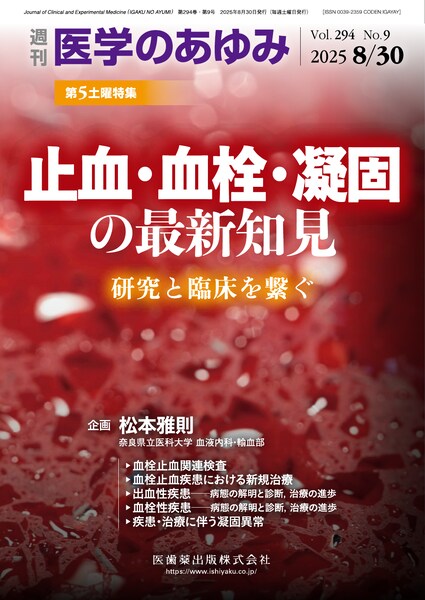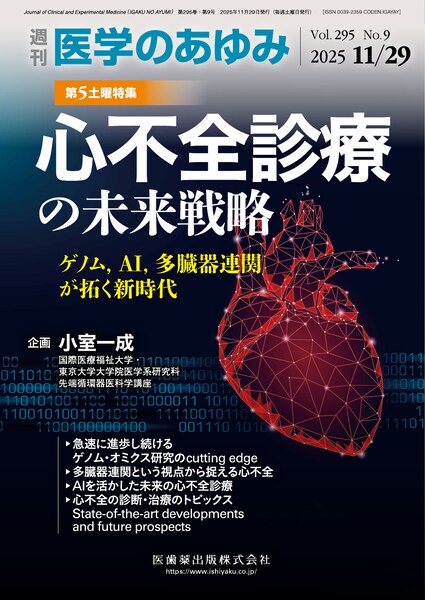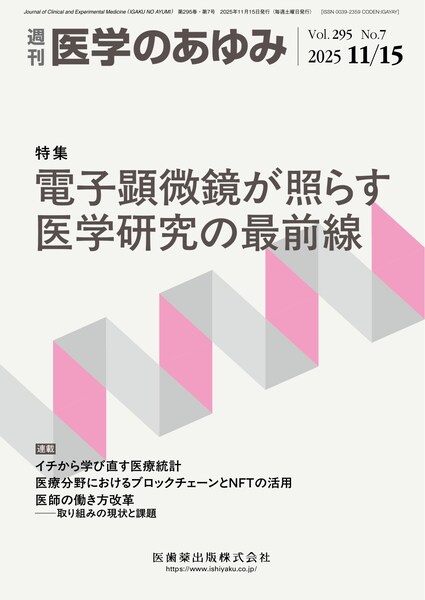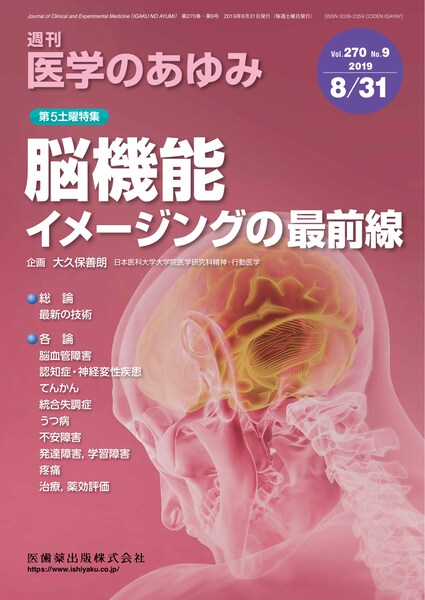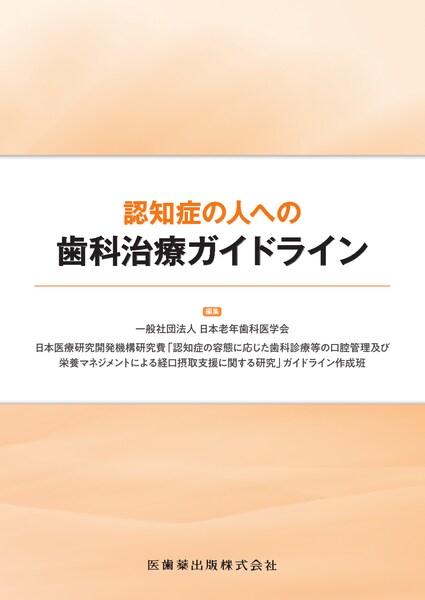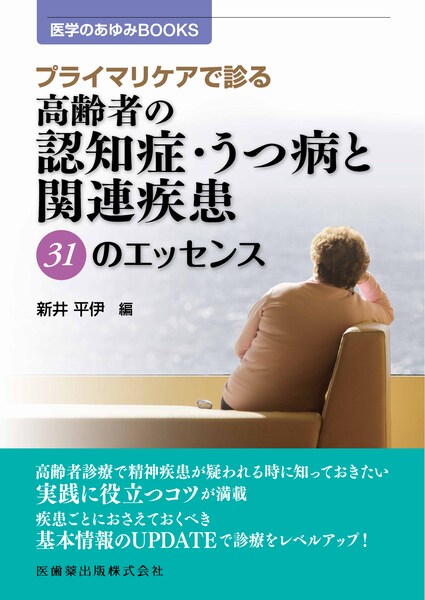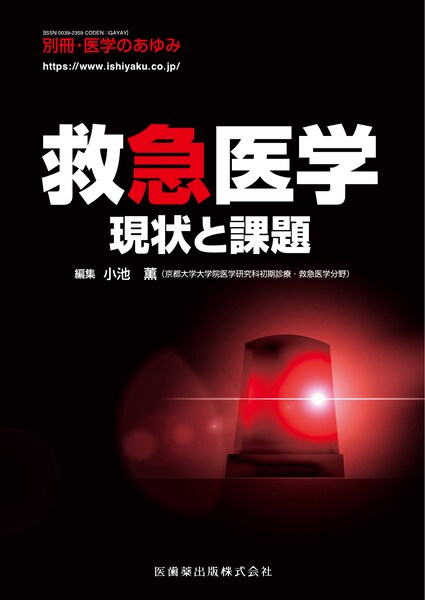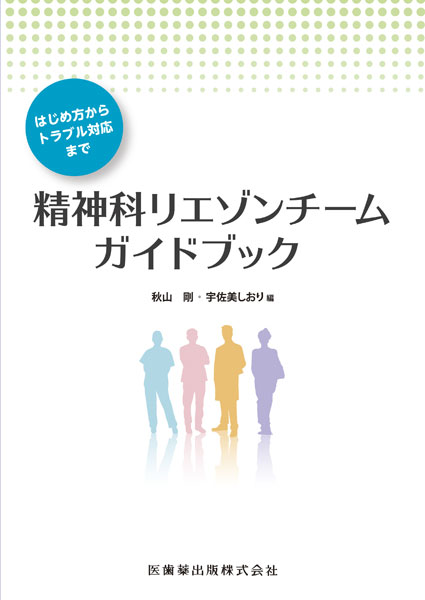医学のあゆみ
270巻6・7号
てんかん:診断と治療の現在
- 総頁数:70頁
- 判型:B5判
- 発行年月:2019年8月
- 注文コード:927007
- 雑誌コード:20473-8/17
内容紹介
・てんかんは,脳神経系の代表的なcommon diseaseであり,わが国には約100万人の患者がいる.その原因は,周産期脳障害,皮質形成異常,腫瘍,感染,頭部外傷,遺伝性チャネル病など多岐にわたる.
・従来は小児に多い疾患と捉えられていたが,超高齢社会となり高齢発症のてんかんが急増した.また近年,自己免疫介在性の部分(焦点)てんかんの存在が明らかとなり,免疫療法で治療できる病態として注目される.
・本特集では,最新の生理・画像検査を取り入れた術前評価から,焦点摘出術やデバイスを用いた緩和療法といった外科治療まで,てんかんの診断と治療の最新情報を解説する.
目次
はじめに 松本理器
てんかんの定義と分類-最新の知見と今後の展望 佐々木亮太・木下真幸子
てんかん発作症候とその鑑別 神 一敬
てんかん診断における検査法Update 宇佐美清英
てんかんの治療:薬物療法Update-Post ガイドライン2018 重藤寛史
てんかんの治療:外科治療Update 臼井直敬
高齢者てんかん 溝渕雅広
自己免疫性てんかん 坂本光弘・松本理器
てんかん重積状態 久保田有一・松原崇一郎
連載
医学・医療におけるシミュレータの進歩と普及(27)
中心静脈穿刺シミュレータ(ランドマーク・ブラインド法) 山東勤弥
健康寿命延伸に寄与する体力医学(15)
中・高年齢者の粘膜免疫・獲得免疫に及ぼす習慣的運動の影響 枝 伸彦
TOPICS
免疫学 第3 の免疫チェックポイント分子LAG-3 によるヘルパーT 細胞応答の選択的な抑制機構 丸橋拓海・岡崎 拓
神経精神医学 最近の飲酒問題への対応-飲酒量低減を治療目標として 瀧村 剛
循環器内科学 心臓を守る心筋D-β-hydroxybutyrate dehydrogenase I とケトン代謝 的場聖明・星野 温
FORUM
Instagramと医療情報 島岡 要・他
パリから見えるこの世界(82) エドワード・O・ウィルソン,あるいは生物界における利他主義 矢倉英隆
次号の特集予告
電子版の購入
以下のウェブサイトで論文単位の購入が可能です.
※リンク先は医歯薬出版株式会社のウェブサイトではありません.利用方法等は各ウェブサイトへお問い合わせください.