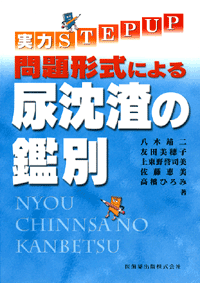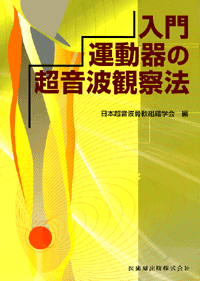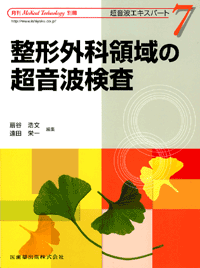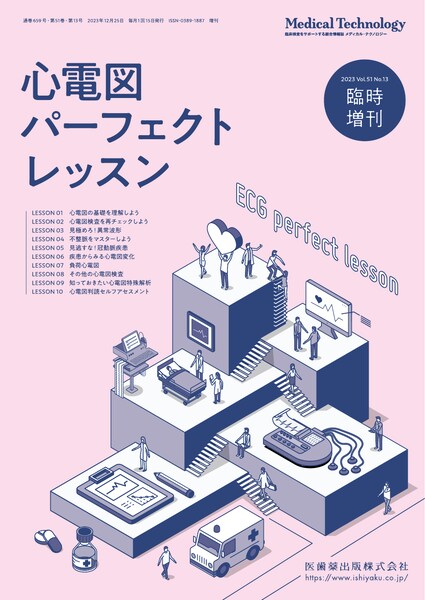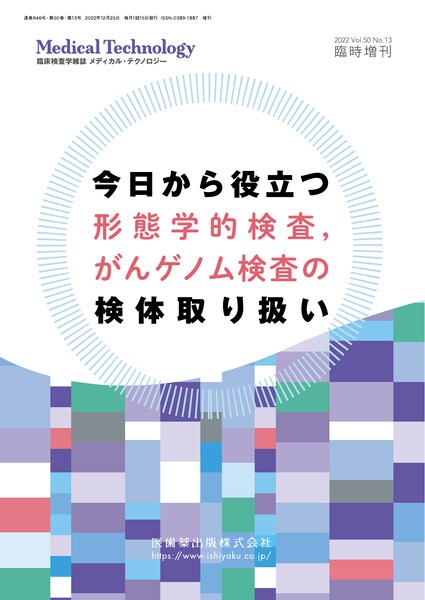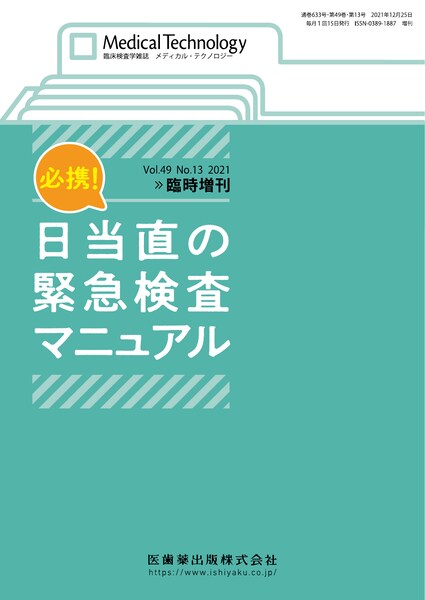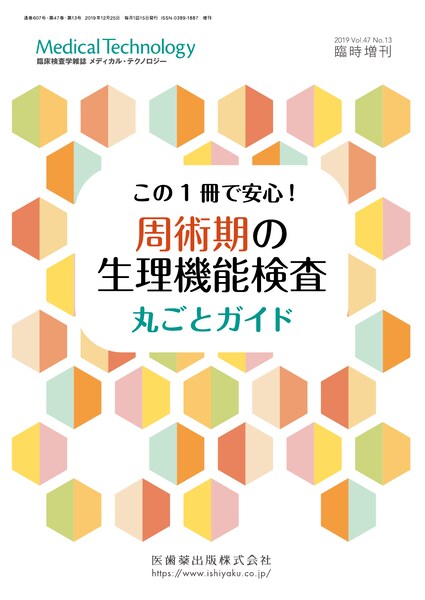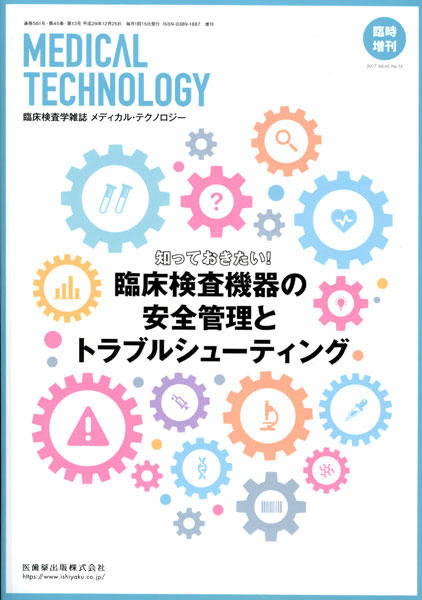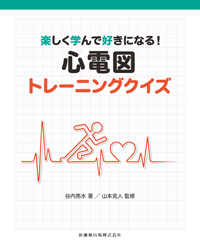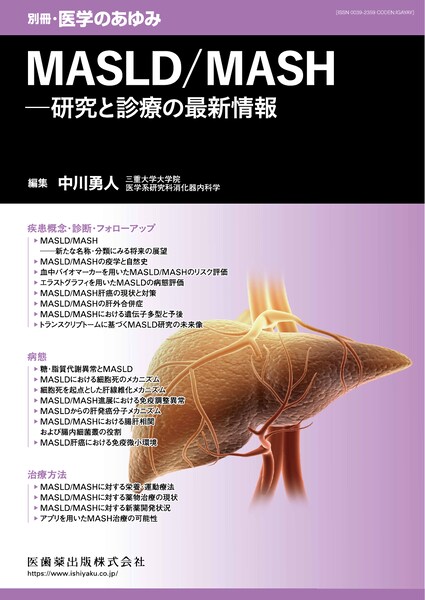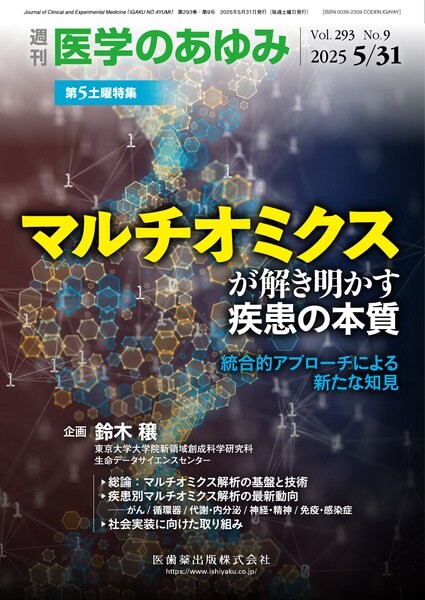�uMedical Technology�v�Վ�������Vol.35 No.13
�����E�ǐ��ǂ̕a�ԁE�����E����
- �����F192�� / 2�F
- ���^�FB5��
- ���s�N���F2007�N12��
- �����R�[�h�F296030
- �G���R�[�h�F08608-12
�������ǂ̌����C�f�Â̊�{�ƌ���ɂ��Ă킩��₷����������D�K���I
���e�Љ�
���~���@�\�́C���Ǒ������Ɍ��Ǔ��𗬂��z��������Ȃ��悤�ɁC���Ǖǂ̑������ʂ����ɂӂ������Č��ǏC���𑣂��C����߂Đ��I�Ȑ��̖h��@�\�ł��D�������C�a�I�Ȍ����`���͌��Ǖǂ������C�����ǂƂ��đg�D�̎��������炷���ƂɂȂ�܂��D
���ߔN�C�S�؍[�ǂ�]�[�ǂȂǂ̓����d�����̌����ǂ́C������ᇂƕ���Ŏ��S�̎���ƂȂ��Ă���C�܂��Ö������ǂ��������Ă��邱�Ƃ��l����C�����ǂ̕a�Ԃ̗����Ƃ��̑�́C����̍ł��d�v�ȉۑ�ł���Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��D
���{���́C�Տ�����ŁC�����ǂ̌����E�f�ÂɌg�����Ƃ̕��X���C���̌����C�f�Â̊�{�ƌ���ɂ��ĉ���D�܂��C�����E�ǐ��ǂ̕a�Ԃ𑍍��I�ɂƂ炦�C�K�v�Ȍ����̒m����[�߁C���Âɂ��ė������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��D
�ڎ�
2. �����E�ǐ��ǐf�f�̌��t����
3. �����E�ǐ��ǂ̉摜����
4. �����E�ǐ��ǂ̎��Âƌ���
5. �����Ȍ����E�ǐ��ǂ̕a�Ԃƌ���
�d�q�ł̍w��
�ȉ��̃E�F�u�T�C�g�Ř_���P�ʂ̍w�����\�ł��D
�������N��͈㎕��o�Ŋ�����Ђ̃E�F�u�T�C�g�ł͂���܂���D���p���@���͊e�E�F�u�T�C�g�ւ��₢���킹���������D



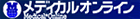
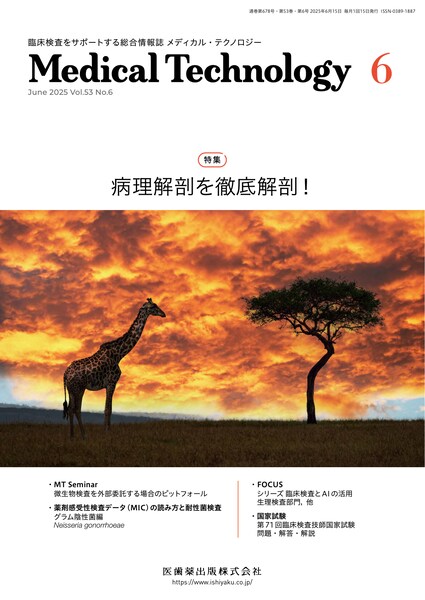
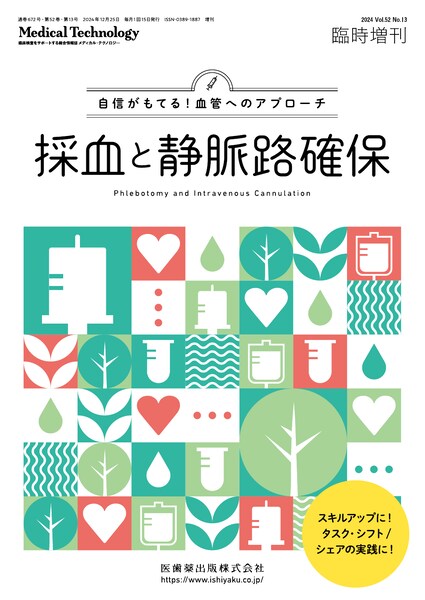
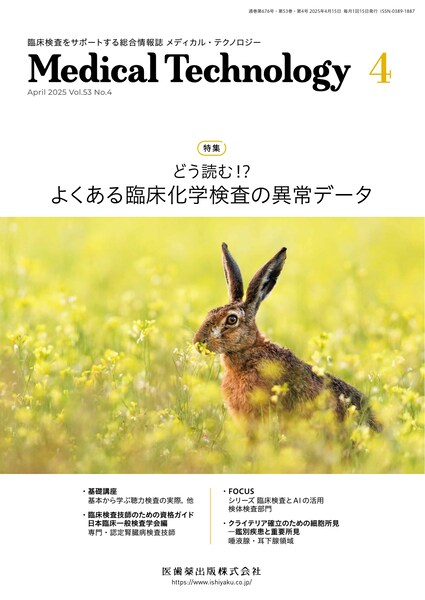
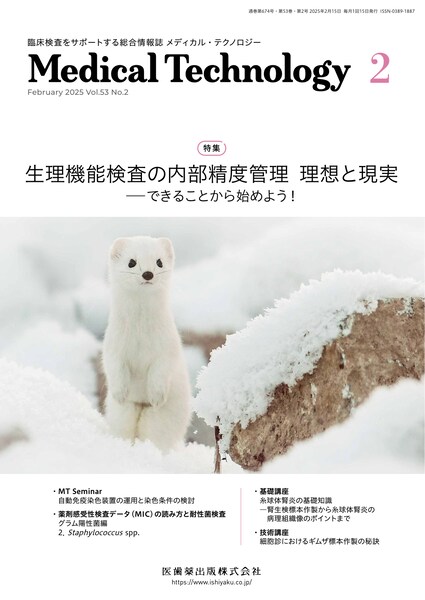
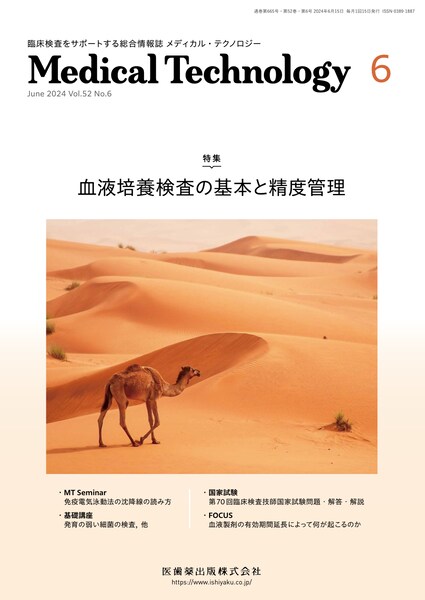
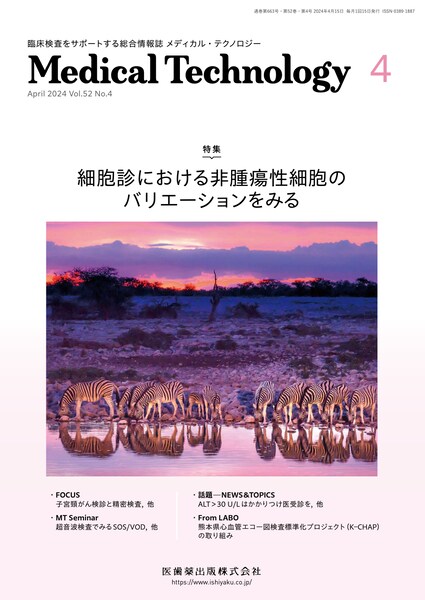

![�������������ƒ����g�����̐i�ߕ��E�]��](/photo/29459-m.gif)