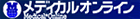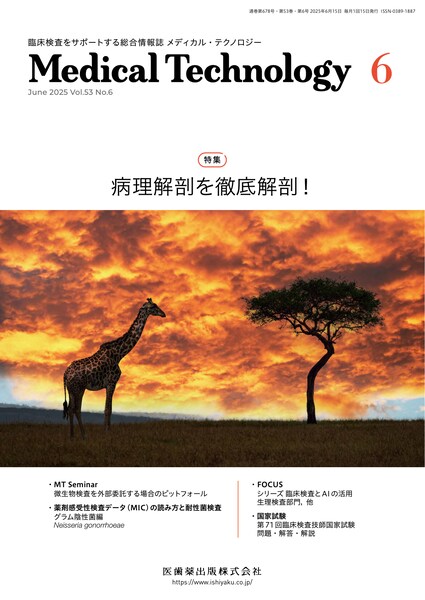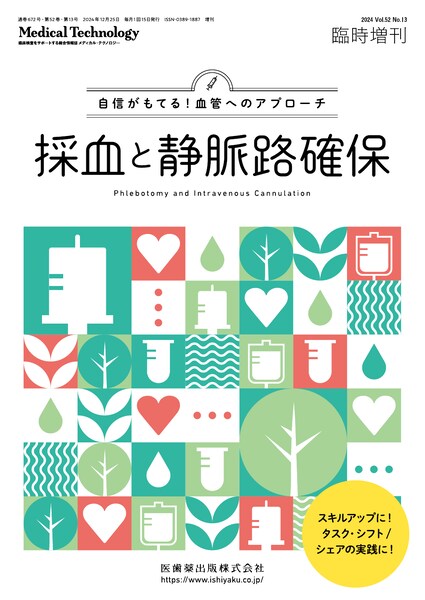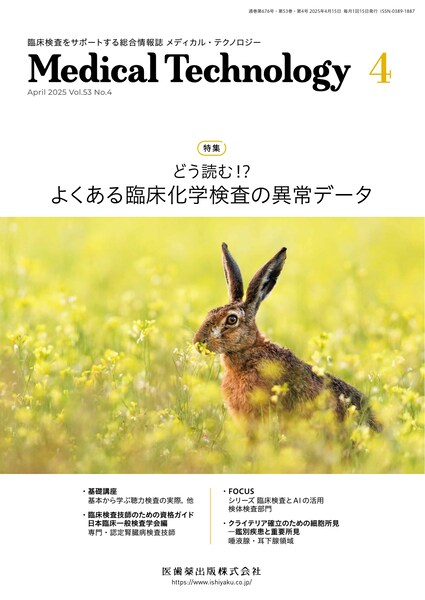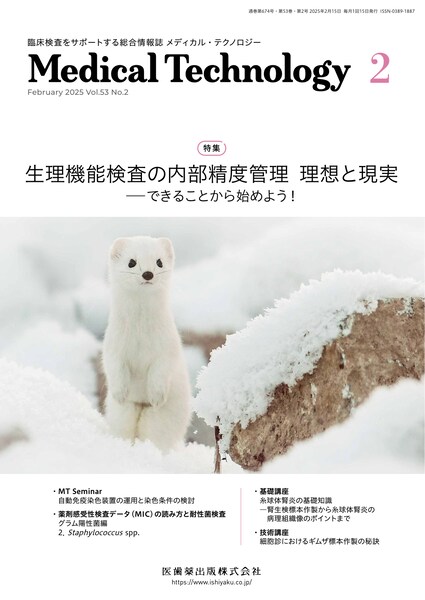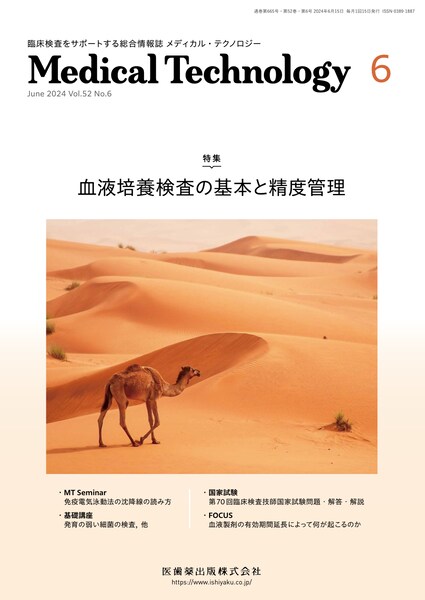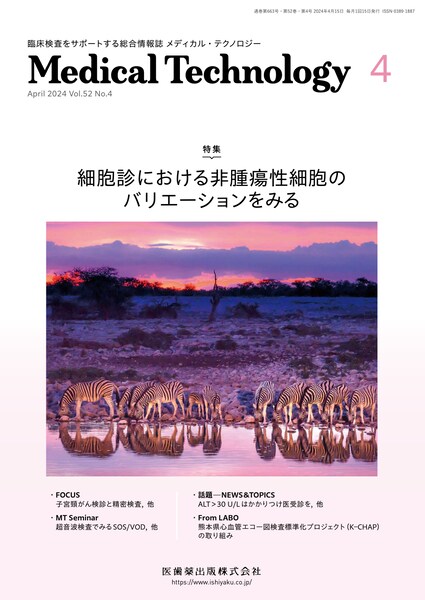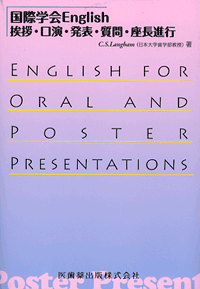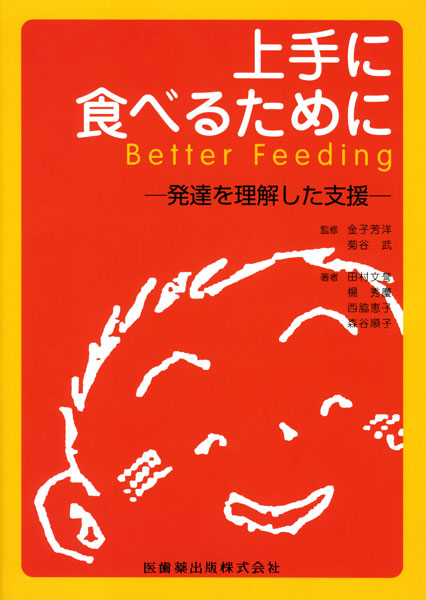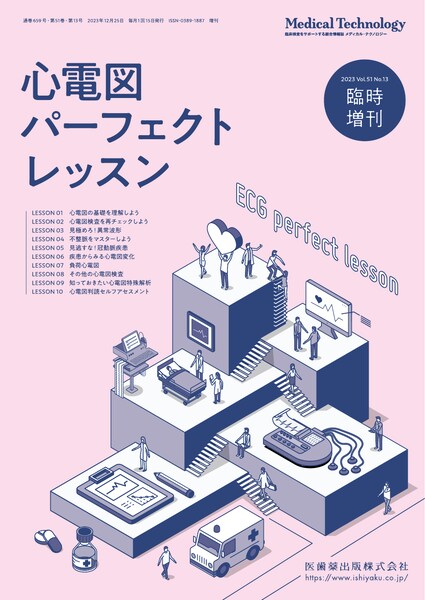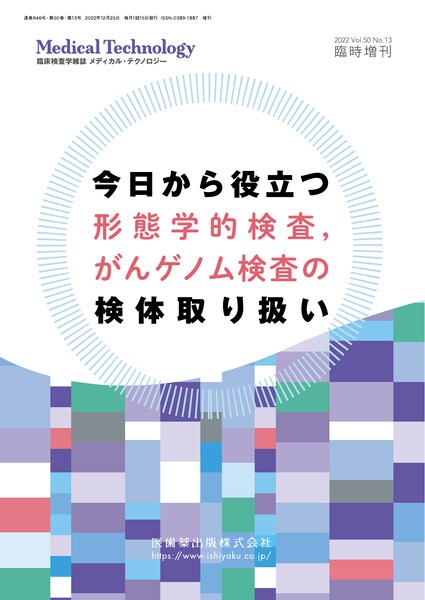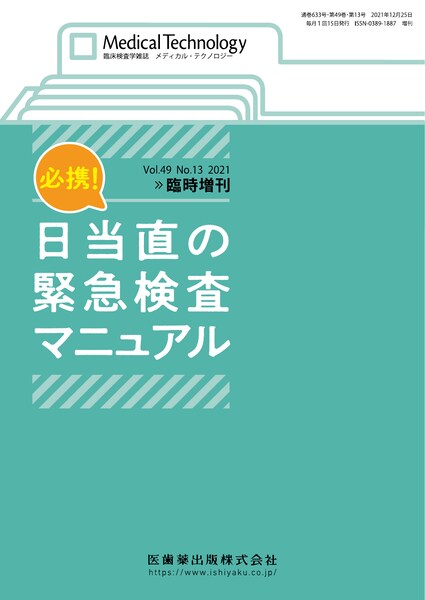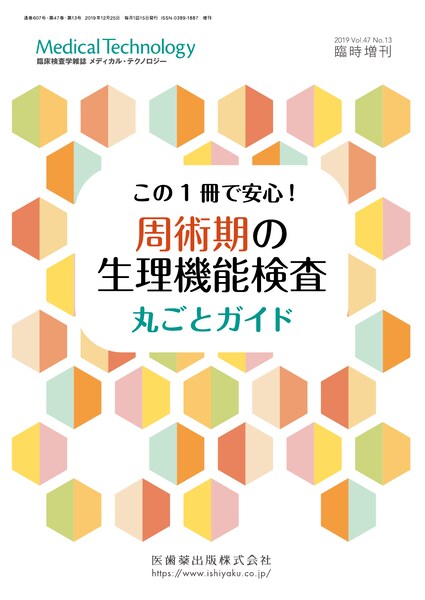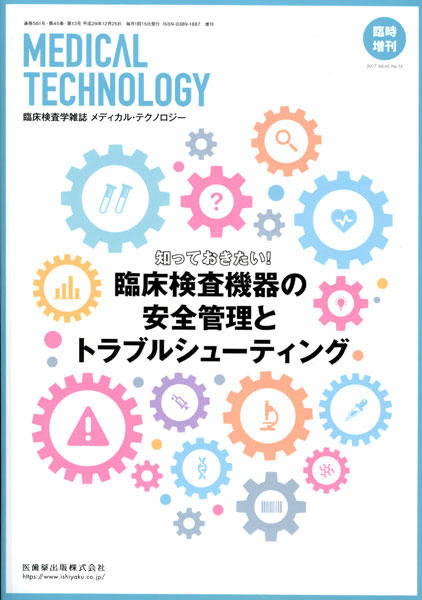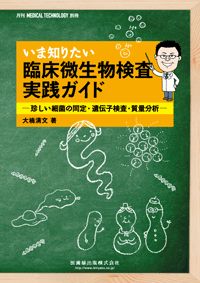�uMedical Technology�v�Վ�������Vol.36 No.13
�����ǐv�������A�b�v�f�[�g
- �����F222�� / 2�F
- ���^�FB5��
- ���s�N���F2008�N12��
- �����R�[�h�F296040
- �G���R�[�h�F08608-12
���e�����ǂɂ܂��v�������@�ɂ��āC���̗��_�⌇�_��c��������ŗՏ��ɗp���邱�Ƃ��ł���悤����I
���e�Љ�
�������ǂ̐f�Âɂ����āC�N���a���̂̐f�f�͏d�v�Ȉʒu���߂Ă���ɂ�������炸�C�|�{�Ȃnj�����̐���ɂ���Č��ʂ�܂łɂ��Ȃ�̎��Ԃ�v���C�K�������������ʂ����ÂɌ��т��Ă��Ȃ��̂�����ł����D�������CPCR�@��LAMP�@���n�߂Ƃ��镪�q�����w�I�A�v���[�`��C���m�N���}�g�@�Ȃǂɂ��ȕւȍR�����o�@���J������C���v���ɋN���a���̂𖾂炩�ɂ��C���Âɖ𗧂Ă���悤�ɏ͕ς���Ă��Ă��܂��D
���{���́C�e�����ǂɂ܂��v�������@�ɂ��āC���̗��_�⌇�_��c��������ŗՏ��ɗp���邱�Ƃ��ł���悤������Ă��܂��D�܂��C���ۂɌ������Ŏg�p���邱�Ƃ̂ł���v�������L�b�g�̊T�v�E�����Ȃǂɂ��āC���[�J�[�̒S���҂��Љ�C���ꂩ��̓���Ɩ��ɖ𗧂悤�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��D
�ڎ�
�e��v�������@
1�D�ċz��̊�����
2.�@������̊�����
3.�@�S�g�C���̑��̊�����
���]
�{���̏��]���������������܂��I
���]�F�R�� ���O�搶�@�i�wMedical Technology�x2009�N8�����f�ځ@PDF�t�@�C���F��107KB�j�d�q�ł̍w��
�ȉ��̃E�F�u�T�C�g�Ř_���P�ʂ̍w�����\�ł��D
�������N��͈㎕��o�Ŋ�����Ђ̃E�F�u�T�C�g�ł͂���܂���D���p���@���͊e�E�F�u�T�C�g�ւ��₢���킹���������D