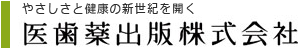Preface�i�{���̂˂炢�j
�@��������x�ɐi�s�������{�ł́C�a�@��{�݁C�ݑ�ő����̊��҂��ېH������Q�ɋꂵ��ł���Ɠ����ɁC�ւ���Î҂���҂���a���Ă��錻��������D
�@���{�ɂ����鍂��҂̚�����Q�́C�]�����̐f�f�⎡�Â𒆐S�ɔ��W���Ă�����ʂ�����D�]�������ǒ���ňӎ���Q���Ȃ��y�ǂ̊��҂̂���51���ɚ�����Q���������C�ŏ���2�T�Ԃ�27���Ɩ������P���C6�J����ɂ�9.1���i���̂����V�K������2.3���j�ƁC���R�o�߂ő啔�������P���Ă����Ƃ���������iStroke,12(4)�F188-193,1997.�j�C�}�����ł͑S�g��Ԃ̉��P��҂��Ȃ���p�p�⍇���ǂ�\�h���邱�Ƃ�1�̑Ή��ł������D���̈���C�ӎ���Q����������C������Q�����R�Ɏ���Ȃ��d�ǂ̊��҂ɑ��ẮC�}������E����Α���������Ŏ���A��ڎw���u�@�\��ړI�Ƃ����P���v�𒆐S�Ƃ����Ή����s�����D���̂悤�Ɏ��R�Ɏ���C�P���ɂ����P�ł������҂Ɋւ��Ȃ���C������Q�Ɋւ��鑽���̌������i�����Ă����D
�@����������ŁC�l���\���̍���ƕ��s���ĉ���ɂ�鐶���I�ȋ@�\�ቺ��p�p�nj�Q�C�i�s���̐_�o�ϐ������C�����]�@�\��Q�C�F�m�ǁC��܂̕���p�C�T���R�y�j�A�C�H����Z�p�Ȃǂ������I�ɏ�ǂƂȂ��Ă���C�����@�\�����ł͂Ȃ���s���Ə������̖��������܂ސېH������Q���������C���R�o�߂�҂�����C�����@�\�́u�@�\��ړI�Ƃ����P���v�ł͎���Ȃ����ґw�������Ă����D
�@�����Ă����̐ېH������Q�ł́C
�@�u����v
�@�u������i�P���E���ÁE�x���Ȃǂ��t�����ĉ��P�ł���C���X�N���R���g���[�����Ȃ���H�ׂ����邱�Ƃ��ł���j�v
�@�u����Ȃ��i�P���E���ÂȂǂł͉��P������j�v
�@�������������Ă���Ccure�i�����j�����ł͂Ȃ�care�i�x������j���܂߂��Ή������߂���D�����Ă��̑Ή��̎��ƌ��ʂ́C�����Ɋւ���Î҂̒m����o���C�Z�p�ɑ傫�����E����邱�ƂɂȂ�D
�@���ې����@�\���ށiICF�j�ɂ��C��Q�́C�u�S�g�@�\�E�\����Q�v�C�u���������v�C�u�Q������v��3�̃��x���ɕ����ĂƂ炦���Ă���D���Ƃ��Ύ��������������Ƃɂ��S�g�@�\�E�\����Q���`���ɂ���đΉ�������C�d�����̂��H�ׂ��Ȃ������������@�ɂ���āC�O�H�ɏo���Ȃ��Ƃ����Q��������H�Ή����X�g�����ŁC�Ƃ����悤�ɁC�ǂ̃��x���́u������v��ڎw���̂��C���߂�ڕW�ɂ��Ă��C���ҁE�Ƒ��ƂƂ��ɍl����K�v������D
�@�܂��ߔN�C��Âɂ����Ă�EBM�ievidence-based medicine�j���d�������悤�ɂȂ������C���̎菇�́uStep 4�F���̊��҂ւ̓K�p�v�ł́C�G�r�f���X�C���Ƃ̒m���ƌo���C���҂̉��l�ρC���҂̕a��Ɗ��Ȃǂ̗v�f�𑍍��I�ɔ��f���Ď��Õ��j�����߂邱�Ƃ����߂��Ă���D�����Ă���Step 4��⊮����T�O�Ƃ��āC����ƑΘb���d������NBM�inarrative-based medicine�j��C���҂ƈ�Î҂̉��l���d������VBP�ivalue-based practice�j�Ȃǂ�����Ă���D
�@�����ېH������Q���Âɓ��Ă͂߂čl���Ă݂�ƁC���Ƃ̒m���ƌo���C�Z�p���\���łȂ��̒��ŁC���Ȃ��G�r�f���X�Őf�f���s���C���҂̉��l�ς��\���ɔ��f����Ȃ����Õ��j�̌��肪�Ȃ���Ă��邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���D�u������v�u�����Ȃ��v�̍l�������C��Î҂̎��_���炾���ł͂Ȃ�ICF��EBM�Ɋ�Â��C�����NBM��VBP�ɏ\���ɔz�����邱�Ƃ��K�v���낤�D
�@���{�̌�������Ă݂�ƌ뚋���x���ɂ���Ė�����117�l�i�N��42,746�l�j���S���Ȃ��Ă���D�܂��H�ו��ɂ�钂�����͖�����11.5�l�i�N��4,193�l�j�ł���C��ʎ��̎��i�N��3,718�l�j��葽���Ƃ��������ׂ��ł���i2020�N�l�����ԓ��v�m�萔�j�D�����ɂ́C
�@�E�뚋�ɂ�锭�M��뚋���x�����N����
�@�E�H�ׂ����Ē���������
�@�E�H�ׂ���̂ɐH�ׂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��C�H�ׂ����Ȃ�
�@����������ƁC�g�̏���������ADL��QOL�����ቺ��������C���̊댯�ɂ��炳��Ă��܂�����C���҂�Ƒ��̗��ꂩ�猩��s�҂Ƃ��Ƃ�ꂩ�˂Ȃ��C�{���Ƃ͐^�t�ȏ����܂��\�����炠���Ì��ꂪ���݂��邩������Ȃ��D�ߔN�͐ېH������Q�ɂ�����ϗ��̖����c�_�����悤�ɂȂ����D
�@�ېH������Q�̎��Â͔�r�I�V��������ł���C�Ή��ł����Î҂����Ȃ��C���E�I�Ɍ��Ă����ÂɊւ���K�C�h���C�����Ȃ��D�Տ�����ł͏��Ȃ��G�r�f���X�Ɋ�Â���T��Ŏ��Âɂ������Ă���Ƃ����̂�����ł��낤�D�w�i�C�������������܂��܂ł���C�������Ή������G�������ېH������Q�ɑ��C
�@�E�ǂ��������āC�ǂ������̂�?
�@�E�ǂ��������Ȃ��āC�ǂ��Ή�������悢�̂�?
�@�E����ǂ̂悤�Ɉ����Ȃ��Ă����C���̂Ƃ���������ׂ��Ȃ̂�?
�@�����̂悤�Ȏ��_����ېH������Q�����ߒ����C���ׂĂ�������킯�ł͂Ȃ��Ă��C�����Ȃ����ƂɈ�Î҂͂ǂ������������Ă����̂����u�܂��ł��邱�Ƃ�����͂����I�v�Ƃ�����Î҂������������D�܂������̏���Îґ������łȂ��C�ł��邾�����ҁE�Ƒ��ɂ�������[�߂Ă��炤���Ƃ��K�v�ł��낤�D
�@�{�����Տ�����ł̈ꏕ�ƂȂ邱�Ƃ�����Ă�܂Ȃ��D
�@2022�N9��
�@�ҏW�ψ��i���s���j
�@���{�Ďm�i��\�j�@�쌴���i�@���R����@����p�N�@����T�q
�@��������x�ɐi�s�������{�ł́C�a�@��{�݁C�ݑ�ő����̊��҂��ېH������Q�ɋꂵ��ł���Ɠ����ɁC�ւ���Î҂���҂���a���Ă��錻��������D
�@���{�ɂ����鍂��҂̚�����Q�́C�]�����̐f�f�⎡�Â𒆐S�ɔ��W���Ă�����ʂ�����D�]�������ǒ���ňӎ���Q���Ȃ��y�ǂ̊��҂̂���51���ɚ�����Q���������C�ŏ���2�T�Ԃ�27���Ɩ������P���C6�J����ɂ�9.1���i���̂����V�K������2.3���j�ƁC���R�o�߂ő啔�������P���Ă����Ƃ���������iStroke,12(4)�F188-193,1997.�j�C�}�����ł͑S�g��Ԃ̉��P��҂��Ȃ���p�p�⍇���ǂ�\�h���邱�Ƃ�1�̑Ή��ł������D���̈���C�ӎ���Q����������C������Q�����R�Ɏ���Ȃ��d�ǂ̊��҂ɑ��ẮC�}������E����Α���������Ŏ���A��ڎw���u�@�\��ړI�Ƃ����P���v�𒆐S�Ƃ����Ή����s�����D���̂悤�Ɏ��R�Ɏ���C�P���ɂ����P�ł������҂Ɋւ��Ȃ���C������Q�Ɋւ��鑽���̌������i�����Ă����D
�@����������ŁC�l���\���̍���ƕ��s���ĉ���ɂ�鐶���I�ȋ@�\�ቺ��p�p�nj�Q�C�i�s���̐_�o�ϐ������C�����]�@�\��Q�C�F�m�ǁC��܂̕���p�C�T���R�y�j�A�C�H����Z�p�Ȃǂ������I�ɏ�ǂƂȂ��Ă���C�����@�\�����ł͂Ȃ���s���Ə������̖��������܂ސېH������Q���������C���R�o�߂�҂�����C�����@�\�́u�@�\��ړI�Ƃ����P���v�ł͎���Ȃ����ґw�������Ă����D
�@�����Ă����̐ېH������Q�ł́C
�@�u����v
�@�u������i�P���E���ÁE�x���Ȃǂ��t�����ĉ��P�ł���C���X�N���R���g���[�����Ȃ���H�ׂ����邱�Ƃ��ł���j�v
�@�u����Ȃ��i�P���E���ÂȂǂł͉��P������j�v
�@�������������Ă���Ccure�i�����j�����ł͂Ȃ�care�i�x������j���܂߂��Ή������߂���D�����Ă��̑Ή��̎��ƌ��ʂ́C�����Ɋւ���Î҂̒m����o���C�Z�p�ɑ傫�����E����邱�ƂɂȂ�D
�@���ې����@�\���ށiICF�j�ɂ��C��Q�́C�u�S�g�@�\�E�\����Q�v�C�u���������v�C�u�Q������v��3�̃��x���ɕ����ĂƂ炦���Ă���D���Ƃ��Ύ��������������Ƃɂ��S�g�@�\�E�\����Q���`���ɂ���đΉ�������C�d�����̂��H�ׂ��Ȃ������������@�ɂ���āC�O�H�ɏo���Ȃ��Ƃ����Q��������H�Ή����X�g�����ŁC�Ƃ����悤�ɁC�ǂ̃��x���́u������v��ڎw���̂��C���߂�ڕW�ɂ��Ă��C���ҁE�Ƒ��ƂƂ��ɍl����K�v������D
�@�܂��ߔN�C��Âɂ����Ă�EBM�ievidence-based medicine�j���d�������悤�ɂȂ������C���̎菇�́uStep 4�F���̊��҂ւ̓K�p�v�ł́C�G�r�f���X�C���Ƃ̒m���ƌo���C���҂̉��l�ρC���҂̕a��Ɗ��Ȃǂ̗v�f�𑍍��I�ɔ��f���Ď��Õ��j�����߂邱�Ƃ����߂��Ă���D�����Ă���Step 4��⊮����T�O�Ƃ��āC����ƑΘb���d������NBM�inarrative-based medicine�j��C���҂ƈ�Î҂̉��l���d������VBP�ivalue-based practice�j�Ȃǂ�����Ă���D
�@�����ېH������Q���Âɓ��Ă͂߂čl���Ă݂�ƁC���Ƃ̒m���ƌo���C�Z�p���\���łȂ��̒��ŁC���Ȃ��G�r�f���X�Őf�f���s���C���҂̉��l�ς��\���ɔ��f����Ȃ����Õ��j�̌��肪�Ȃ���Ă��邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���D�u������v�u�����Ȃ��v�̍l�������C��Î҂̎��_���炾���ł͂Ȃ�ICF��EBM�Ɋ�Â��C�����NBM��VBP�ɏ\���ɔz�����邱�Ƃ��K�v���낤�D
�@���{�̌�������Ă݂�ƌ뚋���x���ɂ���Ė�����117�l�i�N��42,746�l�j���S���Ȃ��Ă���D�܂��H�ו��ɂ�钂�����͖�����11.5�l�i�N��4,193�l�j�ł���C��ʎ��̎��i�N��3,718�l�j��葽���Ƃ��������ׂ��ł���i2020�N�l�����ԓ��v�m�萔�j�D�����ɂ́C
�@�E�뚋�ɂ�锭�M��뚋���x�����N����
�@�E�H�ׂ����Ē���������
�@�E�H�ׂ���̂ɐH�ׂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��C�H�ׂ����Ȃ�
�@����������ƁC�g�̏���������ADL��QOL�����ቺ��������C���̊댯�ɂ��炳��Ă��܂�����C���҂�Ƒ��̗��ꂩ�猩��s�҂Ƃ��Ƃ�ꂩ�˂Ȃ��C�{���Ƃ͐^�t�ȏ����܂��\�����炠���Ì��ꂪ���݂��邩������Ȃ��D�ߔN�͐ېH������Q�ɂ�����ϗ��̖����c�_�����悤�ɂȂ����D
�@�ېH������Q�̎��Â͔�r�I�V��������ł���C�Ή��ł����Î҂����Ȃ��C���E�I�Ɍ��Ă����ÂɊւ���K�C�h���C�����Ȃ��D�Տ�����ł͏��Ȃ��G�r�f���X�Ɋ�Â���T��Ŏ��Âɂ������Ă���Ƃ����̂�����ł��낤�D�w�i�C�������������܂��܂ł���C�������Ή������G�������ېH������Q�ɑ��C
�@�E�ǂ��������āC�ǂ������̂�?
�@�E�ǂ��������Ȃ��āC�ǂ��Ή�������悢�̂�?
�@�E����ǂ̂悤�Ɉ����Ȃ��Ă����C���̂Ƃ���������ׂ��Ȃ̂�?
�@�����̂悤�Ȏ��_����ېH������Q�����ߒ����C���ׂĂ�������킯�ł͂Ȃ��Ă��C�����Ȃ����ƂɈ�Î҂͂ǂ������������Ă����̂����u�܂��ł��邱�Ƃ�����͂����I�v�Ƃ�����Î҂������������D�܂������̏���Îґ������łȂ��C�ł��邾�����ҁE�Ƒ��ɂ�������[�߂Ă��炤���Ƃ��K�v�ł��낤�D
�@�{�����Տ�����ł̈ꏕ�ƂȂ邱�Ƃ�����Ă�܂Ȃ��D
�@2022�N9��
�@�ҏW�ψ��i���s���j
�@���{�Ďm�i��\�j�@�쌴���i�@���R����@����p�N�@����T�q
�@Preface
Part 1�@�ǂ��܂Łu������v?�@�u�����Ȃ��v�ېH������Q�ɉ����ł���?�\���ܗՏ�����ŋN�����Ă��邱�ƁC�����Ă��ꂩ���?
�@�i���{�Ďm�C�쌴���i�C���R����C����p�N�C����T�q�j
�@Intruduction�@�u�H�ׂ�����v�u�H�ׂ����Ȃ��v�̎��_���l����\�{���̊��ɂ�������
�@Problem 1�@�{���Ɂu����������H�ׂ��Ȃ��v�̂�?�\�ېH������Q���҂ɂ������o���ێ�I���̑������߂�����
�@Problem 2�@�d�x�ېH������Q���҂ɑ���u�뚋�h�~��p�v�Ƃ����I���\�Ō�̍ԂƂ��ďn�����K�v�Ȏ�p�K��
�@Problem 3�@���҂��g�[�^���łƂ炦�Ă��邩�\�ł��悭�s���Ă���ԐڌP���ɂ��čl����
�@More Problems�@�ېH������Q�̈�ÁE�P�A����ɂ����邳�܂��܂ȉۑ�\�u������v�l�ɐH�ׂ����Ă��Ȃ�����̉����Ɍ�����
Part 2�@���܂��܂ȗՏ��Ǐ�ƑΉ�
�@I�@�H���ւ̃A�v���[�`��i�߂Ă������߂̑O�����
�@�@I-1�@���҂̈�w�I�Ȉʒu�Â��̗������S�g�̈�w�I���_����i����p�N�j
�@�@I-2�@���o���i����T�q�C���{�Ďm�j
�@�@I-3�@�p���i�֎q�C�Ԉ֎q�C�x�b�h�j�i�|�s�����j
�@�@I-4�@�H����Z�p�i���@�u���C���R����j
�@�@I-5�@�H���`�ԁi�������q�j
�@II�@�Ǐ�E�a�ԂƃA�v���[�`
�@�@II-1�@�o�����s�ǁi�ቺ�j�i����p�N�j
�@�@II-2�@�H�ׂ�����Ȃ��i�����N��j
�@�@II-3�@�ނ���i�쌴���i�j
�@�@II-4�@����������p���Ă��鄟�ېH�����̋@�\�I���_����i����p�N�j
�@�@II-5�@�H�ׂ�Ƃ������M����i�O�c�\��j
�@�@II-6�@�H�ׂ�Ɣx�����J��Ԃ��i�����p���j
�@�@II-7�@�H�ׂ�ƌċz�������i���o���j
�@�@II-8�@�H�ׂ�ƈݒ��̒��q�������i���J���q�j
�@�@II-9�@���o�������Ȃ��Ȃ����P���Ȃ��i���F�v�j
�@�@II-10�@���܂Ȃ��E���߂Ȃ��i���X���N�G�j
�@�@II-11�@�H��`���ł��Ȃ��i�[�ÂЂ���j
�@�@II-12�@�Ȃ��Ȃ����ݍ��܂Ȃ��@1�D�̎��_����i���{�Ďm�j
�@�@II-13�@�Ȃ��Ȃ����ݍ��܂Ȃ��@2�D�F�m�ǂƐ_�o�ϐ������̎��_����i�ᐙ�t�q�j
�@�@II-14�@�H�������Ɏc��i�ꐣ�_���j
�@�@II-15�@�`�������Ă���Ȃ��i���{�Ďm�j
�@�@II-16�@���o���p��ŐH�ׂɂ����i�������q�j
�@�@II-17�@�H���Ɏ��Ԃ�������i���q�M�q�j
�@�@II-18�@�H�ׂ��ڂ��������i���J�q�j
�@�@II-19�@�p�������肵�Ȃ��i�s�ǎp���j�i�k�o�M���j
�@�@II-20�@�H������i�ߐH�j�����܂��ł��Ȃ��i��ؗS�Ԏq�C�匴�q���q�C�k�o�m��j
�@�@II-21�@�\���ȉh�{���ۂ�Ȃ��i�������ہj
�@�@II-22�@�����Ɋւ����p�ɂ��āi����p�N�j
Part 3�@����Љ�
�@1�@�u�����H�ׂ��Ȃ��v�ƌ���ꂽ���C�H�ׂ���悤�ɂȂ���90�Α�̏Ǘ�i���R����j
�@2�@��p�ɂ��ېH������Q���������Ǘ�i����p�N�j
�@3�@��p�K���ƂȂ炸�ΏǗÖ@�ɂ��Ή������Ǘ�i����p�N�j
�@4�@���M�ɂ��{�݂���a�@�ւ̓��މ@���J��Ԃ���90�Α�̏Ǘ�i���R����j
�@5�@�ԐڌP���ł�����x�܂ł͎��������C���ꂾ���ł͐H�ׂ�ꂸ����ύX�ɂ���ĐH�ׂ���悤�ɂȂ����Ǘ�i�쌴���i�j
�@6�@�H�ׂ����肢�Ɋ��Y���Ŏ����s�����Ǘ�i�|�s�����j
�@COLUMN
�@�@1�@���E��J���t�@�����X�ɂ��ӎv����x���i���{�\�j�j
�@�@2�@���҉Ƒ��̎v����(1)�@�o���ێ�[��������Ȃ��[���ɋ߂Â��邽�߂̎x���i�R���䂩��j
�@�@3�@���҉Ƒ��̎v����(2)�@�ݑ�ŐH�ׂ�A�v���[�`������ɂ��Ă�����́i�|�{�~�q�j
�@�@4�@�Ƃ�݂̌��߁i����p�N�j
�@�@5�@���������C����Łi�쌴���i�j
�@�@6�@�Ȃ��Ȃ����Ȃɂ͗��߂Ȃ�?�i����T�q�C�g�c�����j
�@�@7�@���E��A�g�̈���ƂȂ鎕�ȉq���m�̑��O����ɂ��āi�g�c�����j
�@�@8�@�Տ��ϗ��Ƃ��̃W�����}�́g�C�Â��h�i����p�N�j
�@Index
Part 1�@�ǂ��܂Łu������v?�@�u�����Ȃ��v�ېH������Q�ɉ����ł���?�\���ܗՏ�����ŋN�����Ă��邱�ƁC�����Ă��ꂩ���?
�@�i���{�Ďm�C�쌴���i�C���R����C����p�N�C����T�q�j
�@Intruduction�@�u�H�ׂ�����v�u�H�ׂ����Ȃ��v�̎��_���l����\�{���̊��ɂ�������
�@Problem 1�@�{���Ɂu����������H�ׂ��Ȃ��v�̂�?�\�ېH������Q���҂ɂ������o���ێ�I���̑������߂�����
�@Problem 2�@�d�x�ېH������Q���҂ɑ���u�뚋�h�~��p�v�Ƃ����I���\�Ō�̍ԂƂ��ďn�����K�v�Ȏ�p�K��
�@Problem 3�@���҂��g�[�^���łƂ炦�Ă��邩�\�ł��悭�s���Ă���ԐڌP���ɂ��čl����
�@More Problems�@�ېH������Q�̈�ÁE�P�A����ɂ����邳�܂��܂ȉۑ�\�u������v�l�ɐH�ׂ����Ă��Ȃ�����̉����Ɍ�����
Part 2�@���܂��܂ȗՏ��Ǐ�ƑΉ�
�@I�@�H���ւ̃A�v���[�`��i�߂Ă������߂̑O�����
�@�@I-1�@���҂̈�w�I�Ȉʒu�Â��̗������S�g�̈�w�I���_����i����p�N�j
�@�@I-2�@���o���i����T�q�C���{�Ďm�j
�@�@I-3�@�p���i�֎q�C�Ԉ֎q�C�x�b�h�j�i�|�s�����j
�@�@I-4�@�H����Z�p�i���@�u���C���R����j
�@�@I-5�@�H���`�ԁi�������q�j
�@II�@�Ǐ�E�a�ԂƃA�v���[�`
�@�@II-1�@�o�����s�ǁi�ቺ�j�i����p�N�j
�@�@II-2�@�H�ׂ�����Ȃ��i�����N��j
�@�@II-3�@�ނ���i�쌴���i�j
�@�@II-4�@����������p���Ă��鄟�ېH�����̋@�\�I���_����i����p�N�j
�@�@II-5�@�H�ׂ�Ƃ������M����i�O�c�\��j
�@�@II-6�@�H�ׂ�Ɣx�����J��Ԃ��i�����p���j
�@�@II-7�@�H�ׂ�ƌċz�������i���o���j
�@�@II-8�@�H�ׂ�ƈݒ��̒��q�������i���J���q�j
�@�@II-9�@���o�������Ȃ��Ȃ����P���Ȃ��i���F�v�j
�@�@II-10�@���܂Ȃ��E���߂Ȃ��i���X���N�G�j
�@�@II-11�@�H��`���ł��Ȃ��i�[�ÂЂ���j
�@�@II-12�@�Ȃ��Ȃ����ݍ��܂Ȃ��@1�D�̎��_����i���{�Ďm�j
�@�@II-13�@�Ȃ��Ȃ����ݍ��܂Ȃ��@2�D�F�m�ǂƐ_�o�ϐ������̎��_����i�ᐙ�t�q�j
�@�@II-14�@�H�������Ɏc��i�ꐣ�_���j
�@�@II-15�@�`�������Ă���Ȃ��i���{�Ďm�j
�@�@II-16�@���o���p��ŐH�ׂɂ����i�������q�j
�@�@II-17�@�H���Ɏ��Ԃ�������i���q�M�q�j
�@�@II-18�@�H�ׂ��ڂ��������i���J�q�j
�@�@II-19�@�p�������肵�Ȃ��i�s�ǎp���j�i�k�o�M���j
�@�@II-20�@�H������i�ߐH�j�����܂��ł��Ȃ��i��ؗS�Ԏq�C�匴�q���q�C�k�o�m��j
�@�@II-21�@�\���ȉh�{���ۂ�Ȃ��i�������ہj
�@�@II-22�@�����Ɋւ����p�ɂ��āi����p�N�j
Part 3�@����Љ�
�@1�@�u�����H�ׂ��Ȃ��v�ƌ���ꂽ���C�H�ׂ���悤�ɂȂ���90�Α�̏Ǘ�i���R����j
�@2�@��p�ɂ��ېH������Q���������Ǘ�i����p�N�j
�@3�@��p�K���ƂȂ炸�ΏǗÖ@�ɂ��Ή������Ǘ�i����p�N�j
�@4�@���M�ɂ��{�݂���a�@�ւ̓��މ@���J��Ԃ���90�Α�̏Ǘ�i���R����j
�@5�@�ԐڌP���ł�����x�܂ł͎��������C���ꂾ���ł͐H�ׂ�ꂸ����ύX�ɂ���ĐH�ׂ���悤�ɂȂ����Ǘ�i�쌴���i�j
�@6�@�H�ׂ����肢�Ɋ��Y���Ŏ����s�����Ǘ�i�|�s�����j
�@COLUMN
�@�@1�@���E��J���t�@�����X�ɂ��ӎv����x���i���{�\�j�j
�@�@2�@���҉Ƒ��̎v����(1)�@�o���ێ�[��������Ȃ��[���ɋ߂Â��邽�߂̎x���i�R���䂩��j
�@�@3�@���҉Ƒ��̎v����(2)�@�ݑ�ŐH�ׂ�A�v���[�`������ɂ��Ă�����́i�|�{�~�q�j
�@�@4�@�Ƃ�݂̌��߁i����p�N�j
�@�@5�@���������C����Łi�쌴���i�j
�@�@6�@�Ȃ��Ȃ����Ȃɂ͗��߂Ȃ�?�i����T�q�C�g�c�����j
�@�@7�@���E��A�g�̈���ƂȂ鎕�ȉq���m�̑��O����ɂ��āi�g�c�����j
�@�@8�@�Տ��ϗ��Ƃ��̃W�����}�́g�C�Â��h�i����p�N�j
�@Index