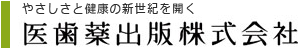推薦のことば
まず書名にもなっている用語「ディサースリア」について述べなければならない.従来,dysarthriaは,神経・筋疾患による構音器官の運動麻痺によって生じる発音の障害と定義され,運動障害性構音障害と邦訳されており,多くの成書ではその用語が用いられてきた.しかし,本書において著者は,さらに広い概念として超文節的特徴であるプロソディや呼吸・発声の障害も含め,従来の用語と区別する意味で,あえて邦訳をせず,dysarthriaの発音に最も近いカタカナ表記として「ディサースリア」という用語を用いている.つまり従来から用いられてきた運動障害性構音障害にプロソディや呼吸・発声の異常を含んだ発話(speech)の障害としてdysarthriaをとらえている.こうした解釈は,Darleyらが1960〜1970年代に提唱したものである.このようなところに著者のこの領域に対する,執念とも言うべき熱意を感じる.本文のなかで,この領域を学ぶ者は「(1)神経・筋系の病変,(2)発声発語器官の運動機能障害,(3)発話の障害」について学ぶべきであると述べている.「発話の障害」のなかには,プロソディの障害,ひいては自然性の異常も含まれることが第5章,第6章で締めくくられている.
著者の基本的な姿勢は,客観的事実に基づいて臨床方針を決定しようということである.医療の分野でよく言われているEvidence Based Medicine(EBM),Evidence Based Practice(EBP)である.EBPに関して言語病理学の領域で中心的役割を担っているのが,Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences(ANCDS)である.ディサースリアの領域での臨床的ガイドラインの作成を行っており,本書では,それに準拠した標準ディサースリア検査(AMSD)をevidenceの中心にすえている.これからのディサースリアの臨床では標準的なものとして取り上げられるであろう.AMSDについては,2004年に著者の西尾博士が上梓した「標準ディサースリア検査」に詳しく解説されているが,本書の第6章でも,その概要がまとめられている.
全体を通して,わかりやすい図表が適切に用いられており,加えて文章が,わかりやすい印象を受ける.著者の説得力のある文章力を評価する.
「よい書物」である条件を私なりにあげてみると,わかりやすいことなどは当然のことであるが,加えて,読者の知識欲を刺激することである.その点,本書は,歴史的事実から最新の考え方まで解説が加えられており,さらに文献が豊富に紹介されていることは特筆されよう.文献を参照しつつ読み進むことによって,読者は知識欲が満足され,将来への学問的展望を得ることができるのである.
各章の終わりに実力テストが提示されている.著者は教科書として国家試験を念頭においているのだろうが,有資格の言語聴覚士にとっても,自分の知識がどの程度,身についているかを確認するのに有用である.最近の欧米の教科書にはよくみかけるスタイルである.
これから言語聴覚士を志す学生諸氏にとっても,臨床の場で働いている者にとっても,ディサースリアを理解し,質の高い診療を行うためにぜひ一読を薦めたい.
2007年5月
国際医療福祉大学言語聴覚センター長・教授
東京大学名誉教授
新美成二
序文
本書は書名が表しているとおり,言語聴覚士のためのディサースリア(dysarthria)の標準的な教科書として,また臨床現場で活躍する言語聴覚士の標準的なガイドラインとして活用されることを目的としてまとめた.
標準的な教科書として今日学際的に認められるには,少なくとも以下の3つの条件が必須であろう.(1)国際的動向に準拠していること,(2)エビデンスに依拠していること(科学的で客観的な態度で著されていること),(3)初学者にも理解しやすく解説されていること,である.しかし,その条件を満たす作業は容易ではなかった.医歯薬出版に本書の出版についてご相談申し上げたのは1999年のことであり,それから今日の刊行までに8年もの歳月を費やしてしまった.しかも,同年にご相談したさいにはすでに本書の原案ができていたにもかかわらず,である.それはなぜかといえば,当時の国内におけるディサースリアの学問的ならびに臨床的状況が,国際的動向からあまりにも遠くかけ離れた水準にあったからである.こうした時代的背景を鑑みつつ,本書の意義について考えてみたいと思う.
ディサースリアの歴史は,「診断の時代」,「治療の時代」,「臨床方針決定の時代」の3期に区分される(Yorkstonら,1999).第一期である「診断の時代」は,1969年に発表された古典的なDarleyらによるメイヨー・クリニックの報告をもって完結し,1970年代に全盛期を迎えた.1980年代の「治療の時代」に入るとディサースリアの評価ならびに治療技術が進展し,一連の手法が開発された.こうした時代を経て,エビデンスに基づいて臨床方針を決定する今日の「臨床方針決定の時代」に入っている.
今日の「臨床方針決定の時代」の中心的役割を担っているのは,Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences(ANCDS)である.ANCDSは,コミュニケーション障害のある成人ならびに小児のQOLの向上を目的として,1983年に設立された高度に科学的な学術組織である.今日に至るまで,コミュニケーション障害の領域におけるエビデンスに基づいた臨床の発展に関して,国際的に指導的役割を果たしてきた.ディサースリアの領域においても,YorkstonやDuffyたちが中心となって積極的にevidence based practice(EBP)を推進し,臨床ガイドラインの作成にとりくんできた.
ところが,国内におけるディサースリアの領域では,残念ながらDarleyらが築いた「診断の時代」でその歩みが滞ってしまった感は否めない.本書を執筆している間にもディサースリアに関するいくつかの専門書が国内で刊行され,総説が著された.しかし,いずれもDarleyらが築いた「診断の時代」を超えるものではなかった.筆者はこれを,「空白の25年間」と呼んでいる.学会でシンポジウムのテーマとしてディサースリアがとりあげられることがあっても,国際的動向にそった討論が展開されることはほとんどなかったように思う.半世紀前の欧米がそうであったように,dysarthriaがなおも「構音障害」として呼ばれ続ける国内の学際的情勢が,その遅滞ぶりを反映していた.このため,国内の言語聴覚士の多くは,1980年以降に米国を中心として発展し体系化された臨床的技術について教育を受ける機会も乏しいまま,古典的なアプローチを臨床の場で施行してきたというのが実態ではないだろうか.
国内には推定で約65〜70万人前後のディサースリア例が存在し(西尾,2006),失語症例と比較してその事例数がはるかに多いと推察するのが近年の傾向である(Duffy,2005).そのなかにはパーキンソン病例のように,言語治療を受けることで高い効果を期待することができるにもかかわらず,実際にはほとんど受けていない疾患群が複数存在する.脳卒中後のディサースリア例で言語治療を受けている事例は少なくないようだが,国内で行われている言語治療のレベルは,やや古典的であり,最新レベルに達してはいないというのが現状と思われる.国際的にはエビデンスに基づいて,新しい科学的なスタイルで的確にリハビリテーションを施行すると,ディサースリアという障害はほとんどすべてのタイプである程度の言語の治療効果が得られることが実証されつつある時代を迎えているだけに,このような国内の実態は非常に遺憾であった.
こうしたなかで,筆者は時が熟するのを冷静に見守ってきた.1999年当時,筆者がYorkstonたちを中心とする米国の進展状況について熱意をもって語っても,ディサースリアが「構音障害ではない」ことを説いても,国内では広く理解を得ることは難しかった.また当時はANCDSにおけるディサースリア部門のガイドライン化の作業は緒についたばかりで,今日のようにその成果が形となっていなかった.さらに何よりも,海外からの借り物ではなく,自分たちの手で日本語を母国語とするディサースリア例を対象とした基礎研究データと臨床研究データをエビデンスとして蓄積して体系化するまでは「標準」と書名に謳える書籍を出すまいと,心に固く誓ってきた.
そして今や,機が熟した.ANCDSの臨床ガイドラインもある程度体系化された.筆者らが過去15年間ほどの間に発表し続けてきた科学的エビデンスもある程度満足できる程度にまで蓄積され,言語治療成績を検討する段階にまで辿りつき(西尾ら,2007),基礎データと臨床データを体系的に整理して扱う局面を迎えた.国内のディサースリアの領域における一般情勢も変動した.ディサースリアは発話障害として正しく理解される時代を迎えつつあり,筆者たちが長年にわたり講演やセミナーで伝え続けてきた多様な言語治療技法が有効であることを臨床の場で実感する言語聴覚士たちの輪は全国的に大きく拡大した.国際的動向に関心を寄せて米国の言語治療セミナーに積極的に参加したり,学会で旺盛に言語治療効果を発表し始めた若手の言語聴覚士たちの成長ぶりは目覚ましい.
冒頭で述べたように,本書は言語聴覚士を目指す学生と現任の言語聴覚士のために著した.より着実に学習を進めることができるように章ごとにそのエッセンスを実力テストとしてまとめたので,読者が自らの知識を確認・再学習するのに活用していただきたい.また,現任の言語聴覚士が基礎から最先端の知識・技法までをわかりやすく学ぶことができるようにも配慮した.とくに第7章の「ディサースリアの言語治療」には多くのページを割き,多種多様な言語治療手技について具体的に解説した.治療手技の解説にさいしては,基本的にはANCDSから発表されている臨床ガイドラインに依拠するとともに,筆者らが日本ディサースリア臨床研究会の協力を得て行ったディサースリアの言語治療効果にかかわる研究から得たエビデンスに基づいた.
また,学生や諸種のセミナーや講習会などで出会った現任の言語聴覚士の方から寄せられた多くの要望に対して,本書をもって応えるように努めた.たとえば,「ディサースリアの基礎理論が難しくて苦手意識を拭いきれない」という声はしばしば聞き及ぶものであり,本書の第1章〜第5章でわかりやすく具体的に解説した.「標準ディサースリア検査(AMSD)の解釈の仕方について教えてほしい」という声もしばしば耳にするものであり,第6章で詳しく解説した.
「空白の25年間」を乗り越えて質の高い言語聴覚士が育成され,そしてそれによりディサースリアのある人が国内のどこの施設でも一定水準のリハビリテーションを受けることができるために,本書がわずかでも寄与することができれば,筆者としてはこれほど嬉しいことはない.
最後に,本書の完成を長年にわたり待ち続けて出版にまで導いて下さった医歯薬出版の担当者に心よりお礼申し上げます.
2007年5月
西尾正輝
まず書名にもなっている用語「ディサースリア」について述べなければならない.従来,dysarthriaは,神経・筋疾患による構音器官の運動麻痺によって生じる発音の障害と定義され,運動障害性構音障害と邦訳されており,多くの成書ではその用語が用いられてきた.しかし,本書において著者は,さらに広い概念として超文節的特徴であるプロソディや呼吸・発声の障害も含め,従来の用語と区別する意味で,あえて邦訳をせず,dysarthriaの発音に最も近いカタカナ表記として「ディサースリア」という用語を用いている.つまり従来から用いられてきた運動障害性構音障害にプロソディや呼吸・発声の異常を含んだ発話(speech)の障害としてdysarthriaをとらえている.こうした解釈は,Darleyらが1960〜1970年代に提唱したものである.このようなところに著者のこの領域に対する,執念とも言うべき熱意を感じる.本文のなかで,この領域を学ぶ者は「(1)神経・筋系の病変,(2)発声発語器官の運動機能障害,(3)発話の障害」について学ぶべきであると述べている.「発話の障害」のなかには,プロソディの障害,ひいては自然性の異常も含まれることが第5章,第6章で締めくくられている.
著者の基本的な姿勢は,客観的事実に基づいて臨床方針を決定しようということである.医療の分野でよく言われているEvidence Based Medicine(EBM),Evidence Based Practice(EBP)である.EBPに関して言語病理学の領域で中心的役割を担っているのが,Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences(ANCDS)である.ディサースリアの領域での臨床的ガイドラインの作成を行っており,本書では,それに準拠した標準ディサースリア検査(AMSD)をevidenceの中心にすえている.これからのディサースリアの臨床では標準的なものとして取り上げられるであろう.AMSDについては,2004年に著者の西尾博士が上梓した「標準ディサースリア検査」に詳しく解説されているが,本書の第6章でも,その概要がまとめられている.
全体を通して,わかりやすい図表が適切に用いられており,加えて文章が,わかりやすい印象を受ける.著者の説得力のある文章力を評価する.
「よい書物」である条件を私なりにあげてみると,わかりやすいことなどは当然のことであるが,加えて,読者の知識欲を刺激することである.その点,本書は,歴史的事実から最新の考え方まで解説が加えられており,さらに文献が豊富に紹介されていることは特筆されよう.文献を参照しつつ読み進むことによって,読者は知識欲が満足され,将来への学問的展望を得ることができるのである.
各章の終わりに実力テストが提示されている.著者は教科書として国家試験を念頭においているのだろうが,有資格の言語聴覚士にとっても,自分の知識がどの程度,身についているかを確認するのに有用である.最近の欧米の教科書にはよくみかけるスタイルである.
これから言語聴覚士を志す学生諸氏にとっても,臨床の場で働いている者にとっても,ディサースリアを理解し,質の高い診療を行うためにぜひ一読を薦めたい.
2007年5月
国際医療福祉大学言語聴覚センター長・教授
東京大学名誉教授
新美成二
序文
本書は書名が表しているとおり,言語聴覚士のためのディサースリア(dysarthria)の標準的な教科書として,また臨床現場で活躍する言語聴覚士の標準的なガイドラインとして活用されることを目的としてまとめた.
標準的な教科書として今日学際的に認められるには,少なくとも以下の3つの条件が必須であろう.(1)国際的動向に準拠していること,(2)エビデンスに依拠していること(科学的で客観的な態度で著されていること),(3)初学者にも理解しやすく解説されていること,である.しかし,その条件を満たす作業は容易ではなかった.医歯薬出版に本書の出版についてご相談申し上げたのは1999年のことであり,それから今日の刊行までに8年もの歳月を費やしてしまった.しかも,同年にご相談したさいにはすでに本書の原案ができていたにもかかわらず,である.それはなぜかといえば,当時の国内におけるディサースリアの学問的ならびに臨床的状況が,国際的動向からあまりにも遠くかけ離れた水準にあったからである.こうした時代的背景を鑑みつつ,本書の意義について考えてみたいと思う.
ディサースリアの歴史は,「診断の時代」,「治療の時代」,「臨床方針決定の時代」の3期に区分される(Yorkstonら,1999).第一期である「診断の時代」は,1969年に発表された古典的なDarleyらによるメイヨー・クリニックの報告をもって完結し,1970年代に全盛期を迎えた.1980年代の「治療の時代」に入るとディサースリアの評価ならびに治療技術が進展し,一連の手法が開発された.こうした時代を経て,エビデンスに基づいて臨床方針を決定する今日の「臨床方針決定の時代」に入っている.
今日の「臨床方針決定の時代」の中心的役割を担っているのは,Academy of Neurologic Communication Disorders and Sciences(ANCDS)である.ANCDSは,コミュニケーション障害のある成人ならびに小児のQOLの向上を目的として,1983年に設立された高度に科学的な学術組織である.今日に至るまで,コミュニケーション障害の領域におけるエビデンスに基づいた臨床の発展に関して,国際的に指導的役割を果たしてきた.ディサースリアの領域においても,YorkstonやDuffyたちが中心となって積極的にevidence based practice(EBP)を推進し,臨床ガイドラインの作成にとりくんできた.
ところが,国内におけるディサースリアの領域では,残念ながらDarleyらが築いた「診断の時代」でその歩みが滞ってしまった感は否めない.本書を執筆している間にもディサースリアに関するいくつかの専門書が国内で刊行され,総説が著された.しかし,いずれもDarleyらが築いた「診断の時代」を超えるものではなかった.筆者はこれを,「空白の25年間」と呼んでいる.学会でシンポジウムのテーマとしてディサースリアがとりあげられることがあっても,国際的動向にそった討論が展開されることはほとんどなかったように思う.半世紀前の欧米がそうであったように,dysarthriaがなおも「構音障害」として呼ばれ続ける国内の学際的情勢が,その遅滞ぶりを反映していた.このため,国内の言語聴覚士の多くは,1980年以降に米国を中心として発展し体系化された臨床的技術について教育を受ける機会も乏しいまま,古典的なアプローチを臨床の場で施行してきたというのが実態ではないだろうか.
国内には推定で約65〜70万人前後のディサースリア例が存在し(西尾,2006),失語症例と比較してその事例数がはるかに多いと推察するのが近年の傾向である(Duffy,2005).そのなかにはパーキンソン病例のように,言語治療を受けることで高い効果を期待することができるにもかかわらず,実際にはほとんど受けていない疾患群が複数存在する.脳卒中後のディサースリア例で言語治療を受けている事例は少なくないようだが,国内で行われている言語治療のレベルは,やや古典的であり,最新レベルに達してはいないというのが現状と思われる.国際的にはエビデンスに基づいて,新しい科学的なスタイルで的確にリハビリテーションを施行すると,ディサースリアという障害はほとんどすべてのタイプである程度の言語の治療効果が得られることが実証されつつある時代を迎えているだけに,このような国内の実態は非常に遺憾であった.
こうしたなかで,筆者は時が熟するのを冷静に見守ってきた.1999年当時,筆者がYorkstonたちを中心とする米国の進展状況について熱意をもって語っても,ディサースリアが「構音障害ではない」ことを説いても,国内では広く理解を得ることは難しかった.また当時はANCDSにおけるディサースリア部門のガイドライン化の作業は緒についたばかりで,今日のようにその成果が形となっていなかった.さらに何よりも,海外からの借り物ではなく,自分たちの手で日本語を母国語とするディサースリア例を対象とした基礎研究データと臨床研究データをエビデンスとして蓄積して体系化するまでは「標準」と書名に謳える書籍を出すまいと,心に固く誓ってきた.
そして今や,機が熟した.ANCDSの臨床ガイドラインもある程度体系化された.筆者らが過去15年間ほどの間に発表し続けてきた科学的エビデンスもある程度満足できる程度にまで蓄積され,言語治療成績を検討する段階にまで辿りつき(西尾ら,2007),基礎データと臨床データを体系的に整理して扱う局面を迎えた.国内のディサースリアの領域における一般情勢も変動した.ディサースリアは発話障害として正しく理解される時代を迎えつつあり,筆者たちが長年にわたり講演やセミナーで伝え続けてきた多様な言語治療技法が有効であることを臨床の場で実感する言語聴覚士たちの輪は全国的に大きく拡大した.国際的動向に関心を寄せて米国の言語治療セミナーに積極的に参加したり,学会で旺盛に言語治療効果を発表し始めた若手の言語聴覚士たちの成長ぶりは目覚ましい.
冒頭で述べたように,本書は言語聴覚士を目指す学生と現任の言語聴覚士のために著した.より着実に学習を進めることができるように章ごとにそのエッセンスを実力テストとしてまとめたので,読者が自らの知識を確認・再学習するのに活用していただきたい.また,現任の言語聴覚士が基礎から最先端の知識・技法までをわかりやすく学ぶことができるようにも配慮した.とくに第7章の「ディサースリアの言語治療」には多くのページを割き,多種多様な言語治療手技について具体的に解説した.治療手技の解説にさいしては,基本的にはANCDSから発表されている臨床ガイドラインに依拠するとともに,筆者らが日本ディサースリア臨床研究会の協力を得て行ったディサースリアの言語治療効果にかかわる研究から得たエビデンスに基づいた.
また,学生や諸種のセミナーや講習会などで出会った現任の言語聴覚士の方から寄せられた多くの要望に対して,本書をもって応えるように努めた.たとえば,「ディサースリアの基礎理論が難しくて苦手意識を拭いきれない」という声はしばしば聞き及ぶものであり,本書の第1章〜第5章でわかりやすく具体的に解説した.「標準ディサースリア検査(AMSD)の解釈の仕方について教えてほしい」という声もしばしば耳にするものであり,第6章で詳しく解説した.
「空白の25年間」を乗り越えて質の高い言語聴覚士が育成され,そしてそれによりディサースリアのある人が国内のどこの施設でも一定水準のリハビリテーションを受けることができるために,本書がわずかでも寄与することができれば,筆者としてはこれほど嬉しいことはない.
最後に,本書の完成を長年にわたり待ち続けて出版にまで導いて下さった医歯薬出版の担当者に心よりお礼申し上げます.
2007年5月
西尾正輝
推薦のことば(新美成二)
序文(西尾正輝)
第1章 ディサースリアとは何か
1 コミュニケーション障害とディサースリア
2 ディサースリアの定義
3 ディサースリアの障害構造
4 臨床的プロフィールの特徴
・文献
・実力テスト
第2章 ディサースリアの基礎理解
1 発症時の年齢
2 発現率と患者数
1)発現率 2)患者数
3 タイプ分類
4 原因疾患
5 運動系における障害される部位
6 発声発語器官の運動機能障害
1)運動麻痺 2)筋力低下 3)痙性 4)弛緩性 5)運動失調症 6)筋固縮 7)不随意運動 8)筋萎縮
7 聴覚的な発話特徴
1)呼吸・発声機能 2)鼻咽腔閉鎖機能 3)口腔構音機能 4)プロソディー機能 5)呼吸・発声機能 6)鼻咽腔閉鎖機能 7)口腔構音機能 8)プロソディー機能
8 臨床経過
9 社会復帰状況
・文献
・実力テスト
第3章 運動系の基礎理解
1 運動系の概要
2 錐体路系
3 錐体外路系
4 小脳系
5 下位運動ニューロン
6 筋(骨)系
・文献
・実力テスト
第4章 運動系の障害
1 錐体路系の障害
2 錐体外路系の障害
1)運動低下 2)運動過多
3 小脳系の障害
4 下位運動ニューロンの障害
5 筋の障害
6 脊髄損傷
・文献
・実力テスト
第5章 タイプごとの病態特徴と重症度
1 弛緩性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
2 痙性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
3 失調性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
4 運動低下性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
5 運動過多性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
6 UUMNディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
7 混合性ディサースリア
[筋萎縮性側索硬化症(ALS)]
1)運動系の損傷部位 2)発声発語器官の運動機能障害 3)聴覚的な発話特徴と重症度
[多発性硬化症(MS)]
1)運動系の損傷部位 2)発声発語器官の運動機能障害 3)聴覚的な発話特徴と重症度
[ウィルソン病(WD)]
1)運動系の損傷部位 2)発声発語器官の運動機能障害 3)聴覚的な発話特徴
8 タイプ間の発話の重症度の比較
・文献
・実力テスト
第6章 ディサースリアの評価
1 臨床の流れ
1)入院から退院までの臨床の流れ 2)病期別にみたリハビリテーションの流れ
2 ディサースリアにおける評価と検査
3 言語病理学的鑑別診断
1)失語症との鑑別 2)発語失行との鑑別
4 ディサースリアの臨床で行う標準的検査の概要
1)一般的情報の収集 2)発話の検査 3)発声発語器官検査
5 標準ディサースリア検査結果の解釈の仕方
1)呼吸機能 2)発声機能 3)鼻咽腔閉鎖機能 4)口腔構音機能
6 関連スタッフから得る情報
1)医師・歯科医師からの情報 2)看護師からの情報 3)医療ソーシャルワーカーからの情報 4)理学療法士・作業療法士からの情報 5)管理栄養士からの情報
7 国際生活機能分類(ICF)に基づいたディサースリアの評価
1)国際生活機能分類(ICF) 2)ICFに基づいたディサースリアの評価 3)ディサースリアにおけるICFの言語治療への応用
8 検査結果のまとめ方
・文献
・実力テスト
第7章 ディサースリアの言語治療
1 治療アプローチの分類
2 言語治療目標
3 運動療法的アプローチの基本
1)運動の種類 2)筋力増強訓練
4 タイプごとの言語治療ガイドライン
1)脳血管障害に伴う弛緩性ディサースリア 2)脳血管障害に伴う痙性ディサースリア 3)脊髄小脳変性症などに伴う失調性ディサースリア 4)パーキンソン病などに伴う運動低下性ディサースリア 5)脳血管障害に伴うUUMNディサースリア 6)ALSに伴う混合性ディサースリア 7)頭部外傷に伴うディサースリア
5 脳卒中後の中枢神経系の再組織化とリハビリテーション
6 誤った言語治療
7 呼吸機能へのアプローチ
1)姿勢の調整 2)脊柱・胸郭の関節可動域の拡大訓練 3)呼吸筋力増強訓練 4)補装的アプローチ(腹帯の活用) 5)胸腹部の圧迫 6)リスク管理
8 発声機能へのアプローチ
1)声のハンディキャップ指数(Voice Handicap Index:VHI) 2)声帯内転訓練 3)あくび─ため息法 4)リー・シルバーマンの音声治療(The Lee Silverman Voice Treatment:LSVT) 5)バイオフィードバック法 6)痙攣性発声障害に伴う運動過多性ディサースリアに対するアプローチ 7)拡声器の活用 8)電気式人工喉頭の活用 9)発話改善装置の活用 10)有声-無声の調節訓練
9 鼻咽腔閉鎖機能
1)持続的陽圧呼吸療法(CPAP療法) 2)バイオフィードバック法 3)補装的アプローチ(軟口蓋挙上装置の利用)
10 口腔構音機能
1)舌の機能的訓練 2)口唇の機能的訓練 3)下顎の機能的訓練 4)構音訓練
11 発話速度の調節法
1)概説 2)ペーシングボード 3)タッピング法とモーラ指折り法 4)ポインティング・スピーチ 5)フレージング法 6)リズミック・キューイング法 7)遅延聴覚フィードバック法(delayed auditory feedback:DAF)
12 拡大・代替コミュニケーション・アプローチ
1)概説 2)ジェスチャー 3)筆談 4)絵,シンボル,文字板,透明文字板,日用用語集を用いたコミュニケーション・ノートなど 5)VOCA(voice output communication aids:音声出力コミュニケーション・エイド) 6)意思伝達装置と関連機器およびソフトウェア 7)重度ディサースリア例とのコミュニケーションの効果を高めるための技法
・文献
・実力テスト
和文索引
欧文索引
序文(西尾正輝)
第1章 ディサースリアとは何か
1 コミュニケーション障害とディサースリア
2 ディサースリアの定義
3 ディサースリアの障害構造
4 臨床的プロフィールの特徴
・文献
・実力テスト
第2章 ディサースリアの基礎理解
1 発症時の年齢
2 発現率と患者数
1)発現率 2)患者数
3 タイプ分類
4 原因疾患
5 運動系における障害される部位
6 発声発語器官の運動機能障害
1)運動麻痺 2)筋力低下 3)痙性 4)弛緩性 5)運動失調症 6)筋固縮 7)不随意運動 8)筋萎縮
7 聴覚的な発話特徴
1)呼吸・発声機能 2)鼻咽腔閉鎖機能 3)口腔構音機能 4)プロソディー機能 5)呼吸・発声機能 6)鼻咽腔閉鎖機能 7)口腔構音機能 8)プロソディー機能
8 臨床経過
9 社会復帰状況
・文献
・実力テスト
第3章 運動系の基礎理解
1 運動系の概要
2 錐体路系
3 錐体外路系
4 小脳系
5 下位運動ニューロン
6 筋(骨)系
・文献
・実力テスト
第4章 運動系の障害
1 錐体路系の障害
2 錐体外路系の障害
1)運動低下 2)運動過多
3 小脳系の障害
4 下位運動ニューロンの障害
5 筋の障害
6 脊髄損傷
・文献
・実力テスト
第5章 タイプごとの病態特徴と重症度
1 弛緩性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
2 痙性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
3 失調性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
4 運動低下性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
5 運動過多性ディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
6 UUMNディサースリア
1)運動系の損傷部位 2)原因疾患 3)発声発語器官の運動機能障害 4)聴覚的な発話特徴と重症度
7 混合性ディサースリア
[筋萎縮性側索硬化症(ALS)]
1)運動系の損傷部位 2)発声発語器官の運動機能障害 3)聴覚的な発話特徴と重症度
[多発性硬化症(MS)]
1)運動系の損傷部位 2)発声発語器官の運動機能障害 3)聴覚的な発話特徴と重症度
[ウィルソン病(WD)]
1)運動系の損傷部位 2)発声発語器官の運動機能障害 3)聴覚的な発話特徴
8 タイプ間の発話の重症度の比較
・文献
・実力テスト
第6章 ディサースリアの評価
1 臨床の流れ
1)入院から退院までの臨床の流れ 2)病期別にみたリハビリテーションの流れ
2 ディサースリアにおける評価と検査
3 言語病理学的鑑別診断
1)失語症との鑑別 2)発語失行との鑑別
4 ディサースリアの臨床で行う標準的検査の概要
1)一般的情報の収集 2)発話の検査 3)発声発語器官検査
5 標準ディサースリア検査結果の解釈の仕方
1)呼吸機能 2)発声機能 3)鼻咽腔閉鎖機能 4)口腔構音機能
6 関連スタッフから得る情報
1)医師・歯科医師からの情報 2)看護師からの情報 3)医療ソーシャルワーカーからの情報 4)理学療法士・作業療法士からの情報 5)管理栄養士からの情報
7 国際生活機能分類(ICF)に基づいたディサースリアの評価
1)国際生活機能分類(ICF) 2)ICFに基づいたディサースリアの評価 3)ディサースリアにおけるICFの言語治療への応用
8 検査結果のまとめ方
・文献
・実力テスト
第7章 ディサースリアの言語治療
1 治療アプローチの分類
2 言語治療目標
3 運動療法的アプローチの基本
1)運動の種類 2)筋力増強訓練
4 タイプごとの言語治療ガイドライン
1)脳血管障害に伴う弛緩性ディサースリア 2)脳血管障害に伴う痙性ディサースリア 3)脊髄小脳変性症などに伴う失調性ディサースリア 4)パーキンソン病などに伴う運動低下性ディサースリア 5)脳血管障害に伴うUUMNディサースリア 6)ALSに伴う混合性ディサースリア 7)頭部外傷に伴うディサースリア
5 脳卒中後の中枢神経系の再組織化とリハビリテーション
6 誤った言語治療
7 呼吸機能へのアプローチ
1)姿勢の調整 2)脊柱・胸郭の関節可動域の拡大訓練 3)呼吸筋力増強訓練 4)補装的アプローチ(腹帯の活用) 5)胸腹部の圧迫 6)リスク管理
8 発声機能へのアプローチ
1)声のハンディキャップ指数(Voice Handicap Index:VHI) 2)声帯内転訓練 3)あくび─ため息法 4)リー・シルバーマンの音声治療(The Lee Silverman Voice Treatment:LSVT) 5)バイオフィードバック法 6)痙攣性発声障害に伴う運動過多性ディサースリアに対するアプローチ 7)拡声器の活用 8)電気式人工喉頭の活用 9)発話改善装置の活用 10)有声-無声の調節訓練
9 鼻咽腔閉鎖機能
1)持続的陽圧呼吸療法(CPAP療法) 2)バイオフィードバック法 3)補装的アプローチ(軟口蓋挙上装置の利用)
10 口腔構音機能
1)舌の機能的訓練 2)口唇の機能的訓練 3)下顎の機能的訓練 4)構音訓練
11 発話速度の調節法
1)概説 2)ペーシングボード 3)タッピング法とモーラ指折り法 4)ポインティング・スピーチ 5)フレージング法 6)リズミック・キューイング法 7)遅延聴覚フィードバック法(delayed auditory feedback:DAF)
12 拡大・代替コミュニケーション・アプローチ
1)概説 2)ジェスチャー 3)筆談 4)絵,シンボル,文字板,透明文字板,日用用語集を用いたコミュニケーション・ノートなど 5)VOCA(voice output communication aids:音声出力コミュニケーション・エイド) 6)意思伝達装置と関連機器およびソフトウェア 7)重度ディサースリア例とのコミュニケーションの効果を高めるための技法
・文献
・実力テスト
和文索引
欧文索引