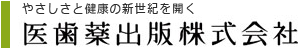はじめに
大阪大学大学院医学系研究科薬理学講座分子細胞薬理学教室
倉智嘉久
本書の前身である週刊・医学のあゆみ第五土曜特集“イオンチャネルの最前線”が出版となってから,はや3年あまりの年月が流れた.しかし,この短い期間においてもイオンチャネル研究は長足の進歩を遂げている.そのため,医歯薬出版株式会社のご好意で編集されたこの改訂新版は各分野における最新の話題を盛り込んだものとなった.
イオンチャネルという膜蛋白質の存在は,イカの巨大神経軸索における活動電位発生のメカニズムとして,約半世紀前の1952年に Hodgkinと Huxleyによってはじめて概念的に発表された.近年に至るまでに,Neherと Sakmannら(1976,1981)によるパッチクランプ法の開発と種々の細胞への適応,1980 年代後半から1990年代までにおけるチャネル遺伝子のクローニングなどの発展があり,チャネルの理解は大きく進歩した.とくに後者においては故・沼 正作博士を筆頭に,日本人研究者の貢献には甚大なものがあった.近年,多くのゲノム遺伝子が解読され,チャネル遺伝子自体の単離・同定という作業は一応の集結を迎えつつあるといえるかもしれない.一方で,生理的あるいは病態時における種々のイオンチャネルの働きや薬物作用の動態の理解,チャネル病の概念の確立などの発展を著者らは目の当たりにしてきた.また,イオンチャネルの三次元構造の解読にも格段の進歩がみられ,その権威である MacKinnon博士が,水チャネルをはじめて見出した Peter Agre博士とともに,2003 年,ノーベル化学賞を受賞したことは記憶に新しい.最近ではこのような構造生物学的研究を通じてイオンチャネルの機能動態が原子レベルで理解できるようになってきたと同時に,組織・臓器レベルの生理現象を説明するためには,他のチャネルやトランスポーターなどのイオン輸送体,多彩なシグナル伝達分子やアンカー蛋白質などと協調する複合体形成とその機能や位置の制御機構を理解しなければならないことがより明確になってきた.また,実験結果をもとに,コンピュータ上でチャネル素子から生体システムを再構成し統合的に扱おうとする“マルチスケール・マルチフィジクス・シミュレーション”という新しい研究分野も開かれつつある.
以上のことを踏まえ,イオンチャネルに関しての最近の進歩をもうすこし詳しく列挙してみると,つぎのようにあげることができる.
(1)多くのイオンチャネルの遺伝子が単離・同定された.
(2)ノックアウトマウスやノックインマウスなどのチャネル遺伝子改変動物が多く作成され,解析が進みつつある.
(3)遺伝性のチャネル病の概念が確立し,その解析と理解が進んでいる.
(4)イオンチャネルの発現機構や機能・位置制御の分子基盤が明らかになってきた.
(5)イオンチャネルのみならず,トランスポーターやシグナル分子を含む蛋白複合体の実証と生理機能の理解が進みつつある.
(6)多くのイオンチャネル蛋白質の結晶構造が明らかになり,機能制御のメカニズムが原子レベルで解明されるようになった.
(7)イオンチャネルの多機能性が明らかになってきている.
(8)translational researchと適切な病態モデルの重要性がますます認識されてきた.
(9)in silicoの研究を進め,臓器機能をモデル化し,病態理解や薬物開発に結びつけようとする気運が高まってきた.
これらの最近の進歩をもとに,予想される将来のイオンチャネル研究の方向性や発展性などについてチャネル研究の特徴などをいろいろ考えながら私見を述べてみたい.
●チャネル病(Channelopathy)から考えるイオンチャネルの特徴
遺伝性 QT延長症候群,種々の筋肉病,Liddle症候群や Bartter症候群などの腎疾患,遺伝性痙攣や癲癇など,多くの疾患の原因がチャネル遺伝子の異常であることが明らかになり,“チャネル病(Channelopathy)”という概念が定着してきた1).このときに気づくチャネル病の大きな特徴は,多くの場合,その原因遺伝子の異常が loss of functionの表現系でありながら,autosomal dominantな遺伝形式を示す場合が多々認められることである.一般的に loss of functionの遺伝子異常は autosomal recessiveな遺伝形式を示すものであるので,これはかなり特徴的であると思われる.この現象の説明のために遺伝子異常産物による dominant negative効果が強調されることが多いが,実際には haploinsufficiencyとなる異常でも autosomal dominantな遺伝形式を示すことが多くある.このことはイオンチャネルが細胞生理機能の制御に必須の役割を果たしていることを物語っていると考えられる.それではイオンチャネルの生理的な働きとはどのようなものであろうか.
イオンチャネルの第1の役割は細胞自体の電気的特性を規定することである.つまりイオンチャネルはある細胞の静止膜電位や活動電位の形成を行う.Loss of functionの異常が autosomal dominantの遺伝形式をとるイオンチャネルはこれらの働きを中心的に担っている場合が多い.イオンチャネルは,そのほか電気活動の伝導をつかさどったり,Ca2+などのイオンシグナルを細胞内へ供給したりする.骨格筋の Ca2+チャネルは電位センサーとして働いている.さらには上皮系やグリア系細胞のように,Na+・K+・Cl-チャネルがイオン輸送体としての役割を果たしている場合もある.代表的なものに,CFTR-Cl-チャネルの異常による cystic fibrosisや ROMK-K+チャネルの異常による Bartter症候群などがある.
また,イオンチャネルの gain of functionの異常によっても,いくつかの疾患が誘引されるという事実も,ここ数年で徐々に明らかとなってきた.このことはイオンチャネルの機能が欠損していても過剰になっていても生体にとっては不適で,適切な発現レベルや活性の範囲が存在することを示している.考えてみればそれほど驚くことではないかもしれないが,細胞機能におけるイオンチャネルの重要性をより際立たせる証拠であろう.Liddle症候群における腎尿細管頂上膜での上皮型 Na+チャネルの過剰発現は有名であるが,そのほかにも癲癇におけるα1H-Ca2+チャネルや SCN1A-Na+チャネルの gain of function,家族性心房細動における KCNQ1・Kir2.1 などの K+チャネルの gain of functionの報告がみられるようになった.癲癇の場合のように,疾患の症状が一見同じであっても,いくつかのチャネルの loss of functionと gain of functionが原因となる場合があり,今後,このような原因の特定がイオンチャネルの生理的意義の理解のみならず,その治療法の進歩にも不可欠な情報となってくる.
●イオンチャネルの生理的役割を決定している因子と異常を起こす機序
上記のように,あるイオンチャネルの異常,あるいは薬理学的修飾がどのような結果をもたらすかは,それぞれのチャネルが担っている生理的役割に大きく依存していると考えられる.よって,それぞれのイオンチャネルの生理機能を決定している要素について明らかにすることは重要な研究項目である.
これらの要素には,(1)イオンチャネル蛋白質をコードする遺伝子発現制御,(2)蛋白質合成から細胞膜への細胞内輸送,(3)細胞膜上での局在制御機構,(4)イオンチャネル蛋白質の機能制御機構(イオン透過・ゲート機構),(5)細胞内へのエンドサイトーシスからの分離機構,などが含まれる.これらの要素のいずれかの段階の異常によって種々のチャネル病が引き起こされることが同定されてきている.それぞれの要素に関しても解決していない生理学的疑問点が数多くあり,今後の研究の発展が期待される.これらの疑問は現在の生命科学の中心課題を数多く包含している.さらには,最近のチャネル蛋白質分子の原子構造解析の進歩や,脂質―蛋白質相互作用によるチャネル機能・局在の制御機構の解明などにより以前には考えられなかった階層での研究が推進されている.しかし,イオンチャネルの生理的役割を規定している各要素についての細胞生物学的な研究ははじまったばかりである.
例として心筋細胞のイオンチャネルを考えてみる.近年,心臓特異的なホメオボックス遺伝子(Csx/Nkx2.5)の異常が心房中壁欠損などの先天性心臓奇形を起こすこと,さらにある種のコネキシンや K+チャネルの発現を低下させることにより心房細動や房室伝導障害など種々の不整脈を遺伝的に引き起こすことが,Harvard大学の出雲らにより明らかにされた2).心臓奇形,ある種の不整脈など,従来は散発的なものと考えられてきた種々の心疾患が,実は転写因子レベルでの異常が関与する場合があることが判明したわけである.これは従来にはなかった疾患概念であり,基礎的な生物科学としての心臓発生の研究が不整脈やイオンチャネルの研究に根本的な impactを与えている端的な例である.さらに,心臓イオンチャネルの発現制御に関してはまったく基本的な事項も手つかずのままである.すなわち,心筋細胞のイオンチャネルは,心臓各部で特異的な発現・分布様式を示すことにより心臓内の電気的分化を形づくっており,このことにより心臓のポンプ機能を保証している.心臓発生過程における心臓各部での種々のイオンチャネルの発現制御機構などはまだよく検討されていない.
ある細胞膜ドメインへのイオンチャネルの制御機構に関しての研究は,当初より神経細胞や上皮細胞において進んでおり,尿崩症における AQP2 変異体(本来,尿細管上皮頂上膜に分布すべきものが変異体では基底側膜へ局在する)のように,正常なチャネルの局在が生理機能の恒常性維持には重要で,その異常が重大な疾患につながることがわかってきた.その分子基盤として,PDZドメインを含むアンカー蛋白質などの重要性が神経細胞や上皮細胞で唱えられてから10年余が過ぎた3,4).最近では心筋細胞でも同じようなメカニズムが報告されている.また,アンカー蛋白質や scaffold蛋白質によるシグナル分子群の集積によるチャネル機能制御の機構が明らかになりつつあり5),チャネルもひとつの素子とだけ考えるのではなく,他の多彩な蛋白質を含めた機能蛋白質複合体として理解していかなければならない時代となっている.こういったチャネルの局在機構や機能複合体形成は現在では蛋白質―蛋白質結合に基づくシステムを考える方向性が主流であるが,アンカー蛋白質のノックアウトマウスなどの結果をみていると,予想されたチャネル局在や複合体形成の異常が観察できない例が多々報告されており,蛋白質―蛋白質結合以外のメカニズム,たとえばチャネル蛋白質―脂質結合などの可能性も視野に入れて統合的に研究を進めていく必要がある.事実,心筋細胞では“カベオラ”とよばれる脂質に富んだマイクロドメインに,多彩な機能的チャネルが集積していることが判明している6,7).こういった発生・細胞生物学的研究の進展によって種々の細胞における電気活動の生理的制御機構の解明や,さらには再生医療も含めたイオンチャネル研究に大きく影響していくであろうことは疑う余地がない.
●構造生物学のイオンチャネル研究に与えるインパクト
イオンチャネルに関した近年の特記すべき進歩は MacKinnonらによるチャネル蛋白質の結晶構造解析の成功である8).この業績は2003年にノーベル化学賞として評価された.たとえば,KcsAという原核生物型 K+チャネルの構造が2Aの解像度で解明された.このことにより,とくにイオンの選択性や透過性の分子機構の理解が大きく進展した.また,チャネルの不活性化の機構に関しても構造的理解が飛躍的に進歩した.最近ではアクアポリン水チャネルや Cl-チャネル,またイオンチャネル型アセチルコリン受容体など生理的に重要なチャネル分子の結晶が解かれたのみならず,アミンやグルタミン酸トランスポーター,P型ポンプ,さらに ABC蛋白質など多くの機能膜蛋白質の三次元構造が原子レベルで明らかとなり,それぞれの機能に関連した構造の特異性や多様性に驚嘆することも少なくない.しかし,忘れてはならないのは,これらのイオンチャネルの構造は従来の電気生理学的検討から導かれたイオン透過機構の理論に実体的根拠を与えたが,これまでの理論がほぼ正しかったことが確認された点である.
いずれにしても構造生物学の進歩はチャネル蛋白質の機能の理解に根拠を与える.以前は膜蛋白質の結晶化には多くの経験と直感が必要とされていたが,市販キットや試薬の進歩,また工学的な方法論を応用することによって,その問題が解決されるようになりつつある.しかし,他の蛋白質の結晶化に比べてイオンチャネルに代表される膜蛋白質の結晶化はいまだ相当難しいものであることに変わりはなく,よりいっそうの方法論の進歩が待ち望まれる.また,チャネル蛋白質の静的な構造ばかりではなく,動的制御に関しての理解もかなり進んできている.アゴニスト効果による構造の変化を構造生物学的に解明した報告も散見できるようになってきた9).現在ではこのような結晶構造の実験的データを基盤として多くのチャネル蛋白質の立体構造をコンピュータ上でシミュレーションすることが可能となってきており,それにより種々の蛋白質相互作用や薬物作用などの検討も実体を想定した解釈が可能となってきている.とくに後者に関しては“創薬”という範疇において今後ますます重要となってくる方法論と位置づけられる.
一方,これからのチャネル機能のさらなる研究が蛋白質構造と機能相関の理解を格段に進歩させ,in silico研究も飛躍的に促進してくるであろうと予想される.パッチクランプ法では1個のチャネル蛋白質の機能を直接観察してきたわけであるが,さらに蛋白質の構造変化を高感度に計測できるようになれば,情報量が増大し,分子機械としてのイオンチャネルの実像がよりリアルかつ正確に理解されるようになると考えられる.この分子機械を自由に制御したりなにかに組み込んだりするナノレベルの操作技術も進展してくるであろう.また,コンピュータ技術の進歩に伴うシミュレーション精度の向上は,ある意味約束された分野であってウエット研究とドライ研究を上手く組み合わせることにより,いままで考えもつかなかったイオンチャネルの側面がみえてくる可能性も十分にある.しかし,それらの実現のためには,何のためにどのような操作が必要か,ある開発された操作を用いてなにを明らかにできるのか,など,それらを客観的に判断するための統合的な視点が重要となる.
●Drug-likeという概念の重要性
イオンチャネルは重要な創薬標的である.ヒトのゲノム配列が解読され,創薬標的になる遺伝子約 7,000 個のなかで,イオンチャネル遺伝子は約 1,000 個もあると考えられている.種々の薬剤のなかで,イオンチャネルを標的とするものは約 5%であるとされているので,イオンチャネルはこれからも有望な創薬標的である.チャネル病において,loss of functionの異常が autosomal dominantな遺伝形式を示すような役割を担うイオンチャネルの薬理学的修飾がいかに工夫を要することであるかは容易に想像できるし,また薬理学的な修飾が比較的容易な対象となるイオンチャネルを考えることもできる.最近では SNPsによって薬剤の効果に差がでるといった事実も確認されてきており,その個々の SNPsの集団に対応するような薬物開発のデザインが必要になってくる可能性も十分に考えられる.
チャネル病や SNPによるチャネル機能の差の特性を考えると,イオンチャネルを標的とする薬物は,さらにその作用動態の特性をよく検討することが drug-like compoundsを見出すときに非常に重要であると考えられる.すなわち,イオンチャネルを標的とする創薬においては,単に標的蛋白質を活性化したり阻害したりする薬剤を合成すればよいというものではない.たとえば,現在,抗不整脈薬として広く一般に使用されている Na+チャネル阻害薬は,すべてコカインの誘導体である.つまり現在の classI薬は Na+チャネルの1カ所の作用部位に作用する薬物群である.Na+チャネルにはその機能を阻害しうる作用部位は何個所も確認されているが,代表的な Na+チャネル阻害薬であるテトロドトキシンやその誘導体は治療薬として使用されてはいない.このことはイオンチャネルが細胞機能制御において必須の役割を果たしていることを意味するとともに,疾患治療に有効なイオンチャネルの修飾法が非常に限られていることを端的に示している.また,従来は単独のチャネルに対する作用薬と考えられてきた薬剤が,実際には複数の異なったチャネルに影響するといった事実も近年報告されている.したがって,実際にある疾患に対して有効性があることがこれまでに確立しているイオンチャネル作用薬物の研究が非常に重要であると著者は考えている.
たとえば,K+チャネル開口薬(KCO)について考えてみよう.血管拡張薬である KCOの標的は ATP感受性 K+チャネルである.薬理実験では血管の弛緩拡張を起こすという非常に明確な効果を示した.KCOは多くのものが知られているが,実際の臨床治療に用いられている KCOは diazoxideと nicorandilのみ(発毛剤の minoxidilは除いている)である.その他の pinacidilや cromakalimといった,典型的な KCOは実際の臨床治療には用いられていない.これまでに著者らの実験的検討から diazoxideと nicorandilの作用には細胞内のヌクレオシド二リン酸の存在が必要であることが明らかとなった10).この特性は他の KCOには存在しない.この特性と実際の臨床効果,あるいは副作用発生との関連には今後検討の余地があるが,drug-like compoundsを選択するためのひとつの指標が指摘できると考えられる.
つぎに,classIIIの抗不整脈薬について考えてみる.Amiodaroneが classIIIに分類されていること,あるいは活動電位の延長による不応期の延長が強く,実験的に不整脈治療効果が高かったことから,dofetilideや E-4031 などの種々の classIIIの抗不整脈が開発された.ところが,遺伝性 QT延長症候群の原因が HERG(IKr)や KCNQ1(IKs)など,心筋細胞の外向き K+チャネルを構成する遺伝子の loss of functionの異常であることが明らかになったことや,抗ヒスタミン薬の心臓への副作用の原因が IKr電流の抑制によることなどがわかってきた背景があり,急速に開発の熱が冷めてしまっている.ClassIII,とくに IKr電流に特異的に作用する薬物は,逆頻度依存的な活動電位の延長を起こすと考えられている.著者らの検討では vesnarinoneは IKr電流を特異的に阻害するが,dofetilideなどとはまったく異なった作用動態を示すために逆頻度依存性を示しにくいと考えられた11).いまだ結論に達したわけではないが,薬物作用動態をさらに検討することにより,より安全性の高い classIII薬を開発できる可能性があると考えている.
以上のように,有用性が明確な薬物の作用を詳細に検討するという研究は地味ではあるが,イオンチャネルを標的とした有用な薬物の開発にとって非常に重要であると考えられる.その意味では amiodaroneの研究はとくに重要であるといえよう.
●Translation researchのための病態生理研究
イオンチャネルの研究は,これまで主として生理的条件下での実験研究が中心であった.その結果を基礎に,病態生理の機構を推定していたわけで,病態自体を真正面から扱うことは少なかったといわざるをえない.最近の分子生物学的なイオンチャネルをはじめとした種々の生体機能構成要素に関しての研究の進歩,あるいはゲノム情報を基盤にした網羅的解析法の発展は状況を変化させつつある.このときに必要不可欠な研究のひとつは適切な病態モデルの確立であろう.遺伝子改変動物の作成の技術進歩は多くのモデル動物の提供を可能にしている.従来のノックアウトマウスに加え,最近は,臓器特異的なノックアウトマウスの作成や,遺伝病で見出された遺伝子変異をノックインの技術で動物に導入するといった手法により,よりいっそう実際のヒトの病態生理に近いモデル動物を解析することが可能になってきた.さらに,他の種々の方法による病態モデルの確立と,その網羅的な検討がある病態の治療戦略を考えるためには重要である.これはイオンチャネルをめぐる研究にとって,ひとつの不可欠な領域である.
心筋肥大と不整脈に関して,近年,シカゴ Loyolla大学の Donald Bersらは高率に心室頻拍で死亡する圧・容量負荷による心肥大のモデルをウサギで確立した12).このモデルでは Na+,Ca2+交換蛋白の up-regulation,SERCA2 の down-regulation,そしてβ受容体シグナル系の残存による修飾機構などが心室頻拍の発生と心収縮力の減弱の基盤となっていることを示し,Na+,Ca2+交換機構がひとつの治療標的となりうることを示した.基礎研究をいかに実際の臨床治療へと還元していくかという translational researchを考えたときには,このような適切な疾患モデルの確立とその綿密な検討がさらに重要となってくる.
●in silico研究の重要性とフィジオーム(Physiome)プロジェクト
前述したように,イオンチャネルの素子としての実体や特性,あるいは細胞生物学的側面に関しての研究は進みつつある.しかし,統合的にそれぞれの器官機能を解明し,病態を理解するためには,種々の素過程から組織,器官全体へと理解を積み上げていくことが必要である.すなわち,器官におけるイオンチャネル分子などの生理的役割や病態時の働きなどを定量的に理解し,その治療法を考えて薬物などを開発するためには,器官全体としての実験検討(ウエット研究)が必要であるばかりでなく,そのすべての過程を再構成する方向性の研究が不可欠である.そのためには in silico(コンピュータ上)において分子機能から器官機能や生体機能を計算しシミュレーションすることが重要であると認識している.
世界的にみれば,イギリス Oxford大学 Denis Noble教授などの心筋細胞の活動電位のシミュレーションなど,細胞生体機能のモデル化と再構成の試みは30年も前から継続されているが,ここ数年,その傾向はいっそう活発化している.遺伝子レベルから細胞・組織レベルを経て生物の全システムに至るまでの現象を,コンピュータモデルを用いて統合的に扱う“フィジオーム(Physiome)プロジェクト”が1993年の国際生理学連合(IUPS)の第32回世界大会で最初に提示されて以来,徐々にその気運は高まり Noble教授やニュージーランドの Peter Hunter教授などにより IUPS内にフィジオームプロジェクト委員会が1998年に設けられている.とくにアメリカではすでに medical engineering分野に巨額の研究費が投下され,かなりの成果をあげている.
ゲノム情報から生命機能をコンピュータで再現しようとする試みは,日本においても,近年はじまっており,北野宏明博士の ERATOプロジェクトや富田勝教授の e-cellに代表される.また,平成15年度より文部科学省リーディングプロジェクトとして“細胞生体機能シミュレーション”が複数の研究拠点を中心に進められている.こういった in silicoでのドライ研究による生体機能のシミュレーションとモデル化は,今後,薬物作用や毒性の評価・予想,また予防医学にとって非常に重要な項目となり,ますます社会的ニーズが高まると推測される.
●おわりに
以上,イオンチャネルをめぐる最近の動向と将来の展望について著者自身の関心のあることについて私見を述べてみた.
本稿においてイオンチャネル研究のすべてを網羅することはできないが,現在までの一人ひとりの研究者の地道な研究成果が基礎となり,チャネル研究は新しい時代へと移ってきたように感じる.21 世紀は生命科学がさらに大きく発展するのは間違いがないし,その社会に対する影響は計りしれない.さらなる生命科学の進歩には新しい概念の確立と方法論の開発が必要であることはいうまでもない.そのなかで,とくに工学などとの異分野融合による方法論の発展をはかることの重要性とそれによってもたらされる概念の革新がひとつの鍵になると考えている.
文献
1)倉智嘉久:心筋細胞イオンチャネル.文光堂,2000.
2)Jay,P. Y.et al.:Anat.Rec.A.Discov.Mol.Cell.Evol.Biol.,280:966-972,2004.Review.
3)Kim,E.and Sheng,M.:Nature.Rev.Neurosci.,5:771-781,2004.
4)Roh,M. H.and Margolis,B.:Am.J.Physiol.,285:F377-F387,2003.
5)Marx,S. O.et al.:Science,295:496-499,2002.
6)Yarbrough,T. L.et al.:Circ.Res.,90:443-449,2002.
7)Barbuti,A.et al.:Circ.Res.,94:1325-1331,2004.
8)Doyle,D. A.et al.:Science,280:69-77,1998.
9)Inanobe,A.et al.:Neuron,(in press)
10)Matsuoka,T.et al.:Circ.Res.,87:873-880,2000.
11)Katayama,Y.et al.:J.Pharmacol.Exp.Ther.,294:339-346,2000.
12)Bers,D. M.et al.:Circ.Res.,93:487-490,2003.
大阪大学大学院医学系研究科薬理学講座分子細胞薬理学教室
倉智嘉久
本書の前身である週刊・医学のあゆみ第五土曜特集“イオンチャネルの最前線”が出版となってから,はや3年あまりの年月が流れた.しかし,この短い期間においてもイオンチャネル研究は長足の進歩を遂げている.そのため,医歯薬出版株式会社のご好意で編集されたこの改訂新版は各分野における最新の話題を盛り込んだものとなった.
イオンチャネルという膜蛋白質の存在は,イカの巨大神経軸索における活動電位発生のメカニズムとして,約半世紀前の1952年に Hodgkinと Huxleyによってはじめて概念的に発表された.近年に至るまでに,Neherと Sakmannら(1976,1981)によるパッチクランプ法の開発と種々の細胞への適応,1980 年代後半から1990年代までにおけるチャネル遺伝子のクローニングなどの発展があり,チャネルの理解は大きく進歩した.とくに後者においては故・沼 正作博士を筆頭に,日本人研究者の貢献には甚大なものがあった.近年,多くのゲノム遺伝子が解読され,チャネル遺伝子自体の単離・同定という作業は一応の集結を迎えつつあるといえるかもしれない.一方で,生理的あるいは病態時における種々のイオンチャネルの働きや薬物作用の動態の理解,チャネル病の概念の確立などの発展を著者らは目の当たりにしてきた.また,イオンチャネルの三次元構造の解読にも格段の進歩がみられ,その権威である MacKinnon博士が,水チャネルをはじめて見出した Peter Agre博士とともに,2003 年,ノーベル化学賞を受賞したことは記憶に新しい.最近ではこのような構造生物学的研究を通じてイオンチャネルの機能動態が原子レベルで理解できるようになってきたと同時に,組織・臓器レベルの生理現象を説明するためには,他のチャネルやトランスポーターなどのイオン輸送体,多彩なシグナル伝達分子やアンカー蛋白質などと協調する複合体形成とその機能や位置の制御機構を理解しなければならないことがより明確になってきた.また,実験結果をもとに,コンピュータ上でチャネル素子から生体システムを再構成し統合的に扱おうとする“マルチスケール・マルチフィジクス・シミュレーション”という新しい研究分野も開かれつつある.
以上のことを踏まえ,イオンチャネルに関しての最近の進歩をもうすこし詳しく列挙してみると,つぎのようにあげることができる.
(1)多くのイオンチャネルの遺伝子が単離・同定された.
(2)ノックアウトマウスやノックインマウスなどのチャネル遺伝子改変動物が多く作成され,解析が進みつつある.
(3)遺伝性のチャネル病の概念が確立し,その解析と理解が進んでいる.
(4)イオンチャネルの発現機構や機能・位置制御の分子基盤が明らかになってきた.
(5)イオンチャネルのみならず,トランスポーターやシグナル分子を含む蛋白複合体の実証と生理機能の理解が進みつつある.
(6)多くのイオンチャネル蛋白質の結晶構造が明らかになり,機能制御のメカニズムが原子レベルで解明されるようになった.
(7)イオンチャネルの多機能性が明らかになってきている.
(8)translational researchと適切な病態モデルの重要性がますます認識されてきた.
(9)in silicoの研究を進め,臓器機能をモデル化し,病態理解や薬物開発に結びつけようとする気運が高まってきた.
これらの最近の進歩をもとに,予想される将来のイオンチャネル研究の方向性や発展性などについてチャネル研究の特徴などをいろいろ考えながら私見を述べてみたい.
●チャネル病(Channelopathy)から考えるイオンチャネルの特徴
遺伝性 QT延長症候群,種々の筋肉病,Liddle症候群や Bartter症候群などの腎疾患,遺伝性痙攣や癲癇など,多くの疾患の原因がチャネル遺伝子の異常であることが明らかになり,“チャネル病(Channelopathy)”という概念が定着してきた1).このときに気づくチャネル病の大きな特徴は,多くの場合,その原因遺伝子の異常が loss of functionの表現系でありながら,autosomal dominantな遺伝形式を示す場合が多々認められることである.一般的に loss of functionの遺伝子異常は autosomal recessiveな遺伝形式を示すものであるので,これはかなり特徴的であると思われる.この現象の説明のために遺伝子異常産物による dominant negative効果が強調されることが多いが,実際には haploinsufficiencyとなる異常でも autosomal dominantな遺伝形式を示すことが多くある.このことはイオンチャネルが細胞生理機能の制御に必須の役割を果たしていることを物語っていると考えられる.それではイオンチャネルの生理的な働きとはどのようなものであろうか.
イオンチャネルの第1の役割は細胞自体の電気的特性を規定することである.つまりイオンチャネルはある細胞の静止膜電位や活動電位の形成を行う.Loss of functionの異常が autosomal dominantの遺伝形式をとるイオンチャネルはこれらの働きを中心的に担っている場合が多い.イオンチャネルは,そのほか電気活動の伝導をつかさどったり,Ca2+などのイオンシグナルを細胞内へ供給したりする.骨格筋の Ca2+チャネルは電位センサーとして働いている.さらには上皮系やグリア系細胞のように,Na+・K+・Cl-チャネルがイオン輸送体としての役割を果たしている場合もある.代表的なものに,CFTR-Cl-チャネルの異常による cystic fibrosisや ROMK-K+チャネルの異常による Bartter症候群などがある.
また,イオンチャネルの gain of functionの異常によっても,いくつかの疾患が誘引されるという事実も,ここ数年で徐々に明らかとなってきた.このことはイオンチャネルの機能が欠損していても過剰になっていても生体にとっては不適で,適切な発現レベルや活性の範囲が存在することを示している.考えてみればそれほど驚くことではないかもしれないが,細胞機能におけるイオンチャネルの重要性をより際立たせる証拠であろう.Liddle症候群における腎尿細管頂上膜での上皮型 Na+チャネルの過剰発現は有名であるが,そのほかにも癲癇におけるα1H-Ca2+チャネルや SCN1A-Na+チャネルの gain of function,家族性心房細動における KCNQ1・Kir2.1 などの K+チャネルの gain of functionの報告がみられるようになった.癲癇の場合のように,疾患の症状が一見同じであっても,いくつかのチャネルの loss of functionと gain of functionが原因となる場合があり,今後,このような原因の特定がイオンチャネルの生理的意義の理解のみならず,その治療法の進歩にも不可欠な情報となってくる.
●イオンチャネルの生理的役割を決定している因子と異常を起こす機序
上記のように,あるイオンチャネルの異常,あるいは薬理学的修飾がどのような結果をもたらすかは,それぞれのチャネルが担っている生理的役割に大きく依存していると考えられる.よって,それぞれのイオンチャネルの生理機能を決定している要素について明らかにすることは重要な研究項目である.
これらの要素には,(1)イオンチャネル蛋白質をコードする遺伝子発現制御,(2)蛋白質合成から細胞膜への細胞内輸送,(3)細胞膜上での局在制御機構,(4)イオンチャネル蛋白質の機能制御機構(イオン透過・ゲート機構),(5)細胞内へのエンドサイトーシスからの分離機構,などが含まれる.これらの要素のいずれかの段階の異常によって種々のチャネル病が引き起こされることが同定されてきている.それぞれの要素に関しても解決していない生理学的疑問点が数多くあり,今後の研究の発展が期待される.これらの疑問は現在の生命科学の中心課題を数多く包含している.さらには,最近のチャネル蛋白質分子の原子構造解析の進歩や,脂質―蛋白質相互作用によるチャネル機能・局在の制御機構の解明などにより以前には考えられなかった階層での研究が推進されている.しかし,イオンチャネルの生理的役割を規定している各要素についての細胞生物学的な研究ははじまったばかりである.
例として心筋細胞のイオンチャネルを考えてみる.近年,心臓特異的なホメオボックス遺伝子(Csx/Nkx2.5)の異常が心房中壁欠損などの先天性心臓奇形を起こすこと,さらにある種のコネキシンや K+チャネルの発現を低下させることにより心房細動や房室伝導障害など種々の不整脈を遺伝的に引き起こすことが,Harvard大学の出雲らにより明らかにされた2).心臓奇形,ある種の不整脈など,従来は散発的なものと考えられてきた種々の心疾患が,実は転写因子レベルでの異常が関与する場合があることが判明したわけである.これは従来にはなかった疾患概念であり,基礎的な生物科学としての心臓発生の研究が不整脈やイオンチャネルの研究に根本的な impactを与えている端的な例である.さらに,心臓イオンチャネルの発現制御に関してはまったく基本的な事項も手つかずのままである.すなわち,心筋細胞のイオンチャネルは,心臓各部で特異的な発現・分布様式を示すことにより心臓内の電気的分化を形づくっており,このことにより心臓のポンプ機能を保証している.心臓発生過程における心臓各部での種々のイオンチャネルの発現制御機構などはまだよく検討されていない.
ある細胞膜ドメインへのイオンチャネルの制御機構に関しての研究は,当初より神経細胞や上皮細胞において進んでおり,尿崩症における AQP2 変異体(本来,尿細管上皮頂上膜に分布すべきものが変異体では基底側膜へ局在する)のように,正常なチャネルの局在が生理機能の恒常性維持には重要で,その異常が重大な疾患につながることがわかってきた.その分子基盤として,PDZドメインを含むアンカー蛋白質などの重要性が神経細胞や上皮細胞で唱えられてから10年余が過ぎた3,4).最近では心筋細胞でも同じようなメカニズムが報告されている.また,アンカー蛋白質や scaffold蛋白質によるシグナル分子群の集積によるチャネル機能制御の機構が明らかになりつつあり5),チャネルもひとつの素子とだけ考えるのではなく,他の多彩な蛋白質を含めた機能蛋白質複合体として理解していかなければならない時代となっている.こういったチャネルの局在機構や機能複合体形成は現在では蛋白質―蛋白質結合に基づくシステムを考える方向性が主流であるが,アンカー蛋白質のノックアウトマウスなどの結果をみていると,予想されたチャネル局在や複合体形成の異常が観察できない例が多々報告されており,蛋白質―蛋白質結合以外のメカニズム,たとえばチャネル蛋白質―脂質結合などの可能性も視野に入れて統合的に研究を進めていく必要がある.事実,心筋細胞では“カベオラ”とよばれる脂質に富んだマイクロドメインに,多彩な機能的チャネルが集積していることが判明している6,7).こういった発生・細胞生物学的研究の進展によって種々の細胞における電気活動の生理的制御機構の解明や,さらには再生医療も含めたイオンチャネル研究に大きく影響していくであろうことは疑う余地がない.
●構造生物学のイオンチャネル研究に与えるインパクト
イオンチャネルに関した近年の特記すべき進歩は MacKinnonらによるチャネル蛋白質の結晶構造解析の成功である8).この業績は2003年にノーベル化学賞として評価された.たとえば,KcsAという原核生物型 K+チャネルの構造が2Aの解像度で解明された.このことにより,とくにイオンの選択性や透過性の分子機構の理解が大きく進展した.また,チャネルの不活性化の機構に関しても構造的理解が飛躍的に進歩した.最近ではアクアポリン水チャネルや Cl-チャネル,またイオンチャネル型アセチルコリン受容体など生理的に重要なチャネル分子の結晶が解かれたのみならず,アミンやグルタミン酸トランスポーター,P型ポンプ,さらに ABC蛋白質など多くの機能膜蛋白質の三次元構造が原子レベルで明らかとなり,それぞれの機能に関連した構造の特異性や多様性に驚嘆することも少なくない.しかし,忘れてはならないのは,これらのイオンチャネルの構造は従来の電気生理学的検討から導かれたイオン透過機構の理論に実体的根拠を与えたが,これまでの理論がほぼ正しかったことが確認された点である.
いずれにしても構造生物学の進歩はチャネル蛋白質の機能の理解に根拠を与える.以前は膜蛋白質の結晶化には多くの経験と直感が必要とされていたが,市販キットや試薬の進歩,また工学的な方法論を応用することによって,その問題が解決されるようになりつつある.しかし,他の蛋白質の結晶化に比べてイオンチャネルに代表される膜蛋白質の結晶化はいまだ相当難しいものであることに変わりはなく,よりいっそうの方法論の進歩が待ち望まれる.また,チャネル蛋白質の静的な構造ばかりではなく,動的制御に関しての理解もかなり進んできている.アゴニスト効果による構造の変化を構造生物学的に解明した報告も散見できるようになってきた9).現在ではこのような結晶構造の実験的データを基盤として多くのチャネル蛋白質の立体構造をコンピュータ上でシミュレーションすることが可能となってきており,それにより種々の蛋白質相互作用や薬物作用などの検討も実体を想定した解釈が可能となってきている.とくに後者に関しては“創薬”という範疇において今後ますます重要となってくる方法論と位置づけられる.
一方,これからのチャネル機能のさらなる研究が蛋白質構造と機能相関の理解を格段に進歩させ,in silico研究も飛躍的に促進してくるであろうと予想される.パッチクランプ法では1個のチャネル蛋白質の機能を直接観察してきたわけであるが,さらに蛋白質の構造変化を高感度に計測できるようになれば,情報量が増大し,分子機械としてのイオンチャネルの実像がよりリアルかつ正確に理解されるようになると考えられる.この分子機械を自由に制御したりなにかに組み込んだりするナノレベルの操作技術も進展してくるであろう.また,コンピュータ技術の進歩に伴うシミュレーション精度の向上は,ある意味約束された分野であってウエット研究とドライ研究を上手く組み合わせることにより,いままで考えもつかなかったイオンチャネルの側面がみえてくる可能性も十分にある.しかし,それらの実現のためには,何のためにどのような操作が必要か,ある開発された操作を用いてなにを明らかにできるのか,など,それらを客観的に判断するための統合的な視点が重要となる.
●Drug-likeという概念の重要性
イオンチャネルは重要な創薬標的である.ヒトのゲノム配列が解読され,創薬標的になる遺伝子約 7,000 個のなかで,イオンチャネル遺伝子は約 1,000 個もあると考えられている.種々の薬剤のなかで,イオンチャネルを標的とするものは約 5%であるとされているので,イオンチャネルはこれからも有望な創薬標的である.チャネル病において,loss of functionの異常が autosomal dominantな遺伝形式を示すような役割を担うイオンチャネルの薬理学的修飾がいかに工夫を要することであるかは容易に想像できるし,また薬理学的な修飾が比較的容易な対象となるイオンチャネルを考えることもできる.最近では SNPsによって薬剤の効果に差がでるといった事実も確認されてきており,その個々の SNPsの集団に対応するような薬物開発のデザインが必要になってくる可能性も十分に考えられる.
チャネル病や SNPによるチャネル機能の差の特性を考えると,イオンチャネルを標的とする薬物は,さらにその作用動態の特性をよく検討することが drug-like compoundsを見出すときに非常に重要であると考えられる.すなわち,イオンチャネルを標的とする創薬においては,単に標的蛋白質を活性化したり阻害したりする薬剤を合成すればよいというものではない.たとえば,現在,抗不整脈薬として広く一般に使用されている Na+チャネル阻害薬は,すべてコカインの誘導体である.つまり現在の classI薬は Na+チャネルの1カ所の作用部位に作用する薬物群である.Na+チャネルにはその機能を阻害しうる作用部位は何個所も確認されているが,代表的な Na+チャネル阻害薬であるテトロドトキシンやその誘導体は治療薬として使用されてはいない.このことはイオンチャネルが細胞機能制御において必須の役割を果たしていることを意味するとともに,疾患治療に有効なイオンチャネルの修飾法が非常に限られていることを端的に示している.また,従来は単独のチャネルに対する作用薬と考えられてきた薬剤が,実際には複数の異なったチャネルに影響するといった事実も近年報告されている.したがって,実際にある疾患に対して有効性があることがこれまでに確立しているイオンチャネル作用薬物の研究が非常に重要であると著者は考えている.
たとえば,K+チャネル開口薬(KCO)について考えてみよう.血管拡張薬である KCOの標的は ATP感受性 K+チャネルである.薬理実験では血管の弛緩拡張を起こすという非常に明確な効果を示した.KCOは多くのものが知られているが,実際の臨床治療に用いられている KCOは diazoxideと nicorandilのみ(発毛剤の minoxidilは除いている)である.その他の pinacidilや cromakalimといった,典型的な KCOは実際の臨床治療には用いられていない.これまでに著者らの実験的検討から diazoxideと nicorandilの作用には細胞内のヌクレオシド二リン酸の存在が必要であることが明らかとなった10).この特性は他の KCOには存在しない.この特性と実際の臨床効果,あるいは副作用発生との関連には今後検討の余地があるが,drug-like compoundsを選択するためのひとつの指標が指摘できると考えられる.
つぎに,classIIIの抗不整脈薬について考えてみる.Amiodaroneが classIIIに分類されていること,あるいは活動電位の延長による不応期の延長が強く,実験的に不整脈治療効果が高かったことから,dofetilideや E-4031 などの種々の classIIIの抗不整脈が開発された.ところが,遺伝性 QT延長症候群の原因が HERG(IKr)や KCNQ1(IKs)など,心筋細胞の外向き K+チャネルを構成する遺伝子の loss of functionの異常であることが明らかになったことや,抗ヒスタミン薬の心臓への副作用の原因が IKr電流の抑制によることなどがわかってきた背景があり,急速に開発の熱が冷めてしまっている.ClassIII,とくに IKr電流に特異的に作用する薬物は,逆頻度依存的な活動電位の延長を起こすと考えられている.著者らの検討では vesnarinoneは IKr電流を特異的に阻害するが,dofetilideなどとはまったく異なった作用動態を示すために逆頻度依存性を示しにくいと考えられた11).いまだ結論に達したわけではないが,薬物作用動態をさらに検討することにより,より安全性の高い classIII薬を開発できる可能性があると考えている.
以上のように,有用性が明確な薬物の作用を詳細に検討するという研究は地味ではあるが,イオンチャネルを標的とした有用な薬物の開発にとって非常に重要であると考えられる.その意味では amiodaroneの研究はとくに重要であるといえよう.
●Translation researchのための病態生理研究
イオンチャネルの研究は,これまで主として生理的条件下での実験研究が中心であった.その結果を基礎に,病態生理の機構を推定していたわけで,病態自体を真正面から扱うことは少なかったといわざるをえない.最近の分子生物学的なイオンチャネルをはじめとした種々の生体機能構成要素に関しての研究の進歩,あるいはゲノム情報を基盤にした網羅的解析法の発展は状況を変化させつつある.このときに必要不可欠な研究のひとつは適切な病態モデルの確立であろう.遺伝子改変動物の作成の技術進歩は多くのモデル動物の提供を可能にしている.従来のノックアウトマウスに加え,最近は,臓器特異的なノックアウトマウスの作成や,遺伝病で見出された遺伝子変異をノックインの技術で動物に導入するといった手法により,よりいっそう実際のヒトの病態生理に近いモデル動物を解析することが可能になってきた.さらに,他の種々の方法による病態モデルの確立と,その網羅的な検討がある病態の治療戦略を考えるためには重要である.これはイオンチャネルをめぐる研究にとって,ひとつの不可欠な領域である.
心筋肥大と不整脈に関して,近年,シカゴ Loyolla大学の Donald Bersらは高率に心室頻拍で死亡する圧・容量負荷による心肥大のモデルをウサギで確立した12).このモデルでは Na+,Ca2+交換蛋白の up-regulation,SERCA2 の down-regulation,そしてβ受容体シグナル系の残存による修飾機構などが心室頻拍の発生と心収縮力の減弱の基盤となっていることを示し,Na+,Ca2+交換機構がひとつの治療標的となりうることを示した.基礎研究をいかに実際の臨床治療へと還元していくかという translational researchを考えたときには,このような適切な疾患モデルの確立とその綿密な検討がさらに重要となってくる.
●in silico研究の重要性とフィジオーム(Physiome)プロジェクト
前述したように,イオンチャネルの素子としての実体や特性,あるいは細胞生物学的側面に関しての研究は進みつつある.しかし,統合的にそれぞれの器官機能を解明し,病態を理解するためには,種々の素過程から組織,器官全体へと理解を積み上げていくことが必要である.すなわち,器官におけるイオンチャネル分子などの生理的役割や病態時の働きなどを定量的に理解し,その治療法を考えて薬物などを開発するためには,器官全体としての実験検討(ウエット研究)が必要であるばかりでなく,そのすべての過程を再構成する方向性の研究が不可欠である.そのためには in silico(コンピュータ上)において分子機能から器官機能や生体機能を計算しシミュレーションすることが重要であると認識している.
世界的にみれば,イギリス Oxford大学 Denis Noble教授などの心筋細胞の活動電位のシミュレーションなど,細胞生体機能のモデル化と再構成の試みは30年も前から継続されているが,ここ数年,その傾向はいっそう活発化している.遺伝子レベルから細胞・組織レベルを経て生物の全システムに至るまでの現象を,コンピュータモデルを用いて統合的に扱う“フィジオーム(Physiome)プロジェクト”が1993年の国際生理学連合(IUPS)の第32回世界大会で最初に提示されて以来,徐々にその気運は高まり Noble教授やニュージーランドの Peter Hunter教授などにより IUPS内にフィジオームプロジェクト委員会が1998年に設けられている.とくにアメリカではすでに medical engineering分野に巨額の研究費が投下され,かなりの成果をあげている.
ゲノム情報から生命機能をコンピュータで再現しようとする試みは,日本においても,近年はじまっており,北野宏明博士の ERATOプロジェクトや富田勝教授の e-cellに代表される.また,平成15年度より文部科学省リーディングプロジェクトとして“細胞生体機能シミュレーション”が複数の研究拠点を中心に進められている.こういった in silicoでのドライ研究による生体機能のシミュレーションとモデル化は,今後,薬物作用や毒性の評価・予想,また予防医学にとって非常に重要な項目となり,ますます社会的ニーズが高まると推測される.
●おわりに
以上,イオンチャネルをめぐる最近の動向と将来の展望について著者自身の関心のあることについて私見を述べてみた.
本稿においてイオンチャネル研究のすべてを網羅することはできないが,現在までの一人ひとりの研究者の地道な研究成果が基礎となり,チャネル研究は新しい時代へと移ってきたように感じる.21 世紀は生命科学がさらに大きく発展するのは間違いがないし,その社会に対する影響は計りしれない.さらなる生命科学の進歩には新しい概念の確立と方法論の開発が必要であることはいうまでもない.そのなかで,とくに工学などとの異分野融合による方法論の発展をはかることの重要性とそれによってもたらされる概念の革新がひとつの鍵になると考えている.
文献
1)倉智嘉久:心筋細胞イオンチャネル.文光堂,2000.
2)Jay,P. Y.et al.:Anat.Rec.A.Discov.Mol.Cell.Evol.Biol.,280:966-972,2004.Review.
3)Kim,E.and Sheng,M.:Nature.Rev.Neurosci.,5:771-781,2004.
4)Roh,M. H.and Margolis,B.:Am.J.Physiol.,285:F377-F387,2003.
5)Marx,S. O.et al.:Science,295:496-499,2002.
6)Yarbrough,T. L.et al.:Circ.Res.,90:443-449,2002.
7)Barbuti,A.et al.:Circ.Res.,94:1325-1331,2004.
8)Doyle,D. A.et al.:Science,280:69-77,1998.
9)Inanobe,A.et al.:Neuron,(in press)
10)Matsuoka,T.et al.:Circ.Res.,87:873-880,2000.
11)Katayama,Y.et al.:J.Pharmacol.Exp.Ther.,294:339-346,2000.
12)Bers,D. M.et al.:Circ.Res.,93:487-490,2003.
・はじめに(倉智嘉久)
第1章 イオンチャネルの一般的特性
1. イオンチャネルの構造と機能(稲野辺 厚・倉智嘉久)
2. イオンチャネルの機能と位置の制御(日比野 浩・倉智嘉久)
第2章 細胞膜イオンチャネル
〔Na+チャネル〕
3. 電位依存性Na+チャネル――分子と機能の多様性に関する知見(岡村康司)
4. 上皮型Na+チャネル――構造・機能と制御機構(丸中良典・新里直美)
〔Ca2+チャネル〕
5. 高閾値活性化型電位依存性Ca2+チャネル――L,P/Q,N,R型Ca2+チャネル(赤羽悟美・中瀬古寛子)
6. T型Ca2+チャネル――分子機能と病態生理学的かかわり(小野克重・賀来俊彦)
7. TRPチャネル――生体内環境センサーとして機能するCa2+透過型カチオンチャネル(原 雄二・森 泰生)
〔K+チャネル――Kvチャネル〕
8. 膜電位依存性Kチャネル――構造と機能(魚住信之)
9. HERGチャネルとKCNQ/KCNE1チャネル(保坂幸男・倉智嘉久)
〔K+チャネル――Kirチャネル〕
10. 内向き整流性K+チャネル IRK1の構造機能連関とその遺伝子異常による疾患(久保義弘・藤原祐一郎)
11. G蛋白質制御内向き整流性Kチャネル(石井 優・倉智嘉久)
12. ヌクレオチドと薬物による心血管系ATP感受性K+チャネル活性化の分子機構(山田充彦)101
13. カリウムイオン輸送を担うKirチャネル(日比野 浩)108
14. 膜4回貫通型two-pore domain K+チャネル(藤田秋一)116
15. カルシウム活性化K+チャネル(藤田秋一)122
〔Cl-チャネル〕
16. CLCクロライドチャネルの多彩な機能――CLCクロライドチャネル病の世界(内田信一・佐々木 成)127
17. 容積感受性外向整流性Cl-チャネルとCFTR(岡田泰伸・サビロブ・ラブシャン)133
〔リガンド作動性チャネル〕
18. グルタミン酸受容体チャネル(小澤瀞司・掛川 渉)139
19. シナプス前神経終末部上のGABAA受容体とストリキニーネ感受性グリシン受容体活性による伝達調節――活動電位依存性および自発性の伝達物質放出を指標として(赤池紀扶・桂林秀太郎)146
20. カプサイシン受容体――カプサイシン,酸,熱の3つの痛み刺激を受容するイオンチャネル(富永真琴)150
21. 水チャネルの分類と機能(石橋賢一)156
〔機械受容チャネル〕
22. 機械刺激を感知するイオンチャネル――TRPチャネルを中心に(岸上明生・曽我部正博)162
第3章 細胞内・細胞間のチャネル
23. リアノジン受容体――結合膜構造におけるリアノジン受容体によるCa2+放出(竹島 浩)171
24. IP3受容体とCa2+シグナル――Ca2+シグナルのダイナミズムの分子基盤(飯野正光)176
25. ギャップジャンクションチャネル――ギャップジャンクションの構造と心筋興奮伝導(本荘晴朗・児玉逸雄)183
26. タイトジャンクションにおけるイオン透過性制御(西信裕美子・古瀬幹夫)189
第4章 臓器でのイオンチャネルの働きと疾患
〔神経・骨格筋系〕
27. 神経伝達物質放出の制御分子群とCa2+チャネル(坂根亜由子・佐々木卓也)197
28. PSDの構造とシナプス伝達(平林 享・畑 裕)203
29. グリア細胞機能とイオンチャネル(内田一郎)209
30. グルタミン酸受容体チャネルとシナプス可塑性――海馬CA3シナプスにおける入力・サブユニット特異的AMPA受容体輸送機構(掛川 渉・小澤瀞司)214
31. 電位依存性Na+チャネル・Ca2+チャネルと神経疾患 井本敬二・松下かおり)222
32. ポリグルタミン病――脊髄小脳失調症6型を中心に 常深泰司・水澤英洋)227
33. Kチャネルと末梢神経疾患 亀山正樹・林 茂昭)232
34. ニコチン性アセチルコリン受容体と神経疾患 尾方克久・後藤 順)237
35. 電位依存性チャネルと骨格筋疾患――機能異常と病態への関与 木村 卓・他)243
〔感覚系〕
36. 感覚受容細胞とcyclic nucleotide-gatedチャネル 倉橋 隆)248
37. 網膜の非活動電位性細胞におけるCaポンプの役割について――計算機シミュレーションによる考察(高見涼太郎・八木哲也)253
38. 内耳蝸牛におけるイオン環境と聴覚機能との関連(柴田敏章・日比野 浩)259
39. 痛覚受容イオンチャネル――痛み刺激のコーディングとイオンチャネル(吉村 恵・中塚映政)267
40. 味覚受容におけるイオンチャネルとその役割(島田昌一・他)272
〔心臓・血管系〕
41. 遺伝性QT延長症候群――遺伝子型と表現型の関連(清水 渉)277
42. 心筋細胞イオンチャネルのリモデリングと疾患――不整脈の生化学的基質(山下武志)284
43. 血管平滑筋細胞イオンチャネルとリモデリング(村木克彦・今泉祐治)290
〔腎〕
44. 腎尿細管におけるイオン・水のtransporterの異常(五十嵐 隆)296
〔分泌系〕
45. KATPチャネルによるインスリン分泌と糖尿病(長嶋一昭・稲垣暢也)302
46. 外分泌細胞のイオンチャネル・水チャネル(大城社子・丸山芳夫)308
47. 脂肪細胞とアクアポリン――脂肪細胞特異的グリセロールチャネル分子・アクアポリンアディポース(岸田 堅・下村伊一郎)313
〔消化管系〕
48. 消化管上皮組織機能とイオンチャネル(浅野真司)322
49. 消化管平滑筋の歩調とり電位発生のイオン機序(鈴木 光・鬼頭佳彦)327
50. 下痢原性細菌毒素の戦略――細菌毒素はいかにして腸管上皮細胞の選択的イオン透過性を破壊するか(堀口安彦)332
第5章 その他の機能をもつイオンチャネル
51. 免疫システムとイオンチャネル――抗原刺激によるTリンパ球活性化・アポトーシスにおけるイオンチャネルの役割(古川哲史・小倉武彦)341
サイドメモ目次
PDZドメイン蛋白質
ニューロンにおける電位依存性Naチャネルによるリズム形成の機構
L型Ca2+チャネルと不整脈
T型Ca2+チャネルのクローニング
RGS(regulators of G protein signaling)
ATP感受性K+チャネルのアロステリックモデル
Bartter症候群
AMPA受容体サブユニットGluR2におけるRNA編集
単一神経終末部刺激法の開発
冷刺激から熱刺激まで
NPAボックス
Huntington病
Ca2+ウェーブとCa2+オシレーション
Heteromeric connexsonとheterotypic channels
オクルディンの謎
PSD構成分子のプロテオーム解析
グリア細胞の機能
小脳におけるシナプス可塑性
チャネルの構造変化と薬剤の作用
ムスカリン性アセチルコリン受容体
筋強直性ジストロフィー症の遺伝子学的メカニズム
Mechanoelectrical transduction channel(METチャネル)
難治性疼痛
心房細動リモデリング予防にmibefradilが有効
KCaチャネル
外分泌腺における水チャネルとSjogren症候群
Adipocentric hypothesis(脂肪細胞中心仮説)
イオン輸送蛋白質の極性分布
Cajalの間質細胞
ウエルシュ菌エンテロトキシンはタイトジャンクションを開口するか
免疫シナプス
第1章 イオンチャネルの一般的特性
1. イオンチャネルの構造と機能(稲野辺 厚・倉智嘉久)
2. イオンチャネルの機能と位置の制御(日比野 浩・倉智嘉久)
第2章 細胞膜イオンチャネル
〔Na+チャネル〕
3. 電位依存性Na+チャネル――分子と機能の多様性に関する知見(岡村康司)
4. 上皮型Na+チャネル――構造・機能と制御機構(丸中良典・新里直美)
〔Ca2+チャネル〕
5. 高閾値活性化型電位依存性Ca2+チャネル――L,P/Q,N,R型Ca2+チャネル(赤羽悟美・中瀬古寛子)
6. T型Ca2+チャネル――分子機能と病態生理学的かかわり(小野克重・賀来俊彦)
7. TRPチャネル――生体内環境センサーとして機能するCa2+透過型カチオンチャネル(原 雄二・森 泰生)
〔K+チャネル――Kvチャネル〕
8. 膜電位依存性Kチャネル――構造と機能(魚住信之)
9. HERGチャネルとKCNQ/KCNE1チャネル(保坂幸男・倉智嘉久)
〔K+チャネル――Kirチャネル〕
10. 内向き整流性K+チャネル IRK1の構造機能連関とその遺伝子異常による疾患(久保義弘・藤原祐一郎)
11. G蛋白質制御内向き整流性Kチャネル(石井 優・倉智嘉久)
12. ヌクレオチドと薬物による心血管系ATP感受性K+チャネル活性化の分子機構(山田充彦)101
13. カリウムイオン輸送を担うKirチャネル(日比野 浩)108
14. 膜4回貫通型two-pore domain K+チャネル(藤田秋一)116
15. カルシウム活性化K+チャネル(藤田秋一)122
〔Cl-チャネル〕
16. CLCクロライドチャネルの多彩な機能――CLCクロライドチャネル病の世界(内田信一・佐々木 成)127
17. 容積感受性外向整流性Cl-チャネルとCFTR(岡田泰伸・サビロブ・ラブシャン)133
〔リガンド作動性チャネル〕
18. グルタミン酸受容体チャネル(小澤瀞司・掛川 渉)139
19. シナプス前神経終末部上のGABAA受容体とストリキニーネ感受性グリシン受容体活性による伝達調節――活動電位依存性および自発性の伝達物質放出を指標として(赤池紀扶・桂林秀太郎)146
20. カプサイシン受容体――カプサイシン,酸,熱の3つの痛み刺激を受容するイオンチャネル(富永真琴)150
21. 水チャネルの分類と機能(石橋賢一)156
〔機械受容チャネル〕
22. 機械刺激を感知するイオンチャネル――TRPチャネルを中心に(岸上明生・曽我部正博)162
第3章 細胞内・細胞間のチャネル
23. リアノジン受容体――結合膜構造におけるリアノジン受容体によるCa2+放出(竹島 浩)171
24. IP3受容体とCa2+シグナル――Ca2+シグナルのダイナミズムの分子基盤(飯野正光)176
25. ギャップジャンクションチャネル――ギャップジャンクションの構造と心筋興奮伝導(本荘晴朗・児玉逸雄)183
26. タイトジャンクションにおけるイオン透過性制御(西信裕美子・古瀬幹夫)189
第4章 臓器でのイオンチャネルの働きと疾患
〔神経・骨格筋系〕
27. 神経伝達物質放出の制御分子群とCa2+チャネル(坂根亜由子・佐々木卓也)197
28. PSDの構造とシナプス伝達(平林 享・畑 裕)203
29. グリア細胞機能とイオンチャネル(内田一郎)209
30. グルタミン酸受容体チャネルとシナプス可塑性――海馬CA3シナプスにおける入力・サブユニット特異的AMPA受容体輸送機構(掛川 渉・小澤瀞司)214
31. 電位依存性Na+チャネル・Ca2+チャネルと神経疾患 井本敬二・松下かおり)222
32. ポリグルタミン病――脊髄小脳失調症6型を中心に 常深泰司・水澤英洋)227
33. Kチャネルと末梢神経疾患 亀山正樹・林 茂昭)232
34. ニコチン性アセチルコリン受容体と神経疾患 尾方克久・後藤 順)237
35. 電位依存性チャネルと骨格筋疾患――機能異常と病態への関与 木村 卓・他)243
〔感覚系〕
36. 感覚受容細胞とcyclic nucleotide-gatedチャネル 倉橋 隆)248
37. 網膜の非活動電位性細胞におけるCaポンプの役割について――計算機シミュレーションによる考察(高見涼太郎・八木哲也)253
38. 内耳蝸牛におけるイオン環境と聴覚機能との関連(柴田敏章・日比野 浩)259
39. 痛覚受容イオンチャネル――痛み刺激のコーディングとイオンチャネル(吉村 恵・中塚映政)267
40. 味覚受容におけるイオンチャネルとその役割(島田昌一・他)272
〔心臓・血管系〕
41. 遺伝性QT延長症候群――遺伝子型と表現型の関連(清水 渉)277
42. 心筋細胞イオンチャネルのリモデリングと疾患――不整脈の生化学的基質(山下武志)284
43. 血管平滑筋細胞イオンチャネルとリモデリング(村木克彦・今泉祐治)290
〔腎〕
44. 腎尿細管におけるイオン・水のtransporterの異常(五十嵐 隆)296
〔分泌系〕
45. KATPチャネルによるインスリン分泌と糖尿病(長嶋一昭・稲垣暢也)302
46. 外分泌細胞のイオンチャネル・水チャネル(大城社子・丸山芳夫)308
47. 脂肪細胞とアクアポリン――脂肪細胞特異的グリセロールチャネル分子・アクアポリンアディポース(岸田 堅・下村伊一郎)313
〔消化管系〕
48. 消化管上皮組織機能とイオンチャネル(浅野真司)322
49. 消化管平滑筋の歩調とり電位発生のイオン機序(鈴木 光・鬼頭佳彦)327
50. 下痢原性細菌毒素の戦略――細菌毒素はいかにして腸管上皮細胞の選択的イオン透過性を破壊するか(堀口安彦)332
第5章 その他の機能をもつイオンチャネル
51. 免疫システムとイオンチャネル――抗原刺激によるTリンパ球活性化・アポトーシスにおけるイオンチャネルの役割(古川哲史・小倉武彦)341
サイドメモ目次
PDZドメイン蛋白質
ニューロンにおける電位依存性Naチャネルによるリズム形成の機構
L型Ca2+チャネルと不整脈
T型Ca2+チャネルのクローニング
RGS(regulators of G protein signaling)
ATP感受性K+チャネルのアロステリックモデル
Bartter症候群
AMPA受容体サブユニットGluR2におけるRNA編集
単一神経終末部刺激法の開発
冷刺激から熱刺激まで
NPAボックス
Huntington病
Ca2+ウェーブとCa2+オシレーション
Heteromeric connexsonとheterotypic channels
オクルディンの謎
PSD構成分子のプロテオーム解析
グリア細胞の機能
小脳におけるシナプス可塑性
チャネルの構造変化と薬剤の作用
ムスカリン性アセチルコリン受容体
筋強直性ジストロフィー症の遺伝子学的メカニズム
Mechanoelectrical transduction channel(METチャネル)
難治性疼痛
心房細動リモデリング予防にmibefradilが有効
KCaチャネル
外分泌腺における水チャネルとSjogren症候群
Adipocentric hypothesis(脂肪細胞中心仮説)
イオン輸送蛋白質の極性分布
Cajalの間質細胞
ウエルシュ菌エンテロトキシンはタイトジャンクションを開口するか
免疫シナプス