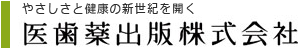はじめに
ここ数年来,日中の医学交流が緊密さをまし,中国の新しい医学としての中西医結合医学や伝統的な中医学が我国に新鮮なショックを与え注目を集めるとともに,健康保険収載の漢方薬が大幅にふえて医師・薬剤師が手軽に使用できる状況となり,漢方医学や漢方薬が一種のブームといえるような活況を呈している・ただし,伝統的な経験にもとづく治療医学の体系と西洋医学の体系が大きく異なるところから,一見神秘的に見える漢方医学に過大な期待を抱いたり・適応が明確でない臨床治験によって過少評価を受けたり・概念の混同による当惑や混乱がみられることも否めない現況である.
日本では「方証相対」の漢方医学が浸透しており,この方法で一定の成果をあげている.ただ,「証に随って治療する」とはいいながら,単なる古典記載の症候の羅列にすぎなかったり,腹証と処方を短絡的に結びつけたりで,病態や病理の把握・薬物の効能にもとづいた処方の効果などがかなりなおざりにされており,「どのような病態に,どのような根拠で,なにゆえに効果があるのか」を示しているとは言いがたく,「言いすぎ」「見逃し」も散見する.このような状況にあきたらず,体系的な漢方医学としての「中医学」が学ばれはじめ,次第に我国でも定着しつつある.しかしながら,せっかく中医学を学んでも,成書に記載された処方が耳慣れたものではなく,現時点で保険適用の処方とは大幅な食い違いをみせるために,臨床面での応用は困難である.また,中医学や日本漢方に取り組んでいない人達にとっては,西洋医学的な考えのみで漢方薬を用いることはさらに困難である.このほか,中医学と日本漢方では用語が異なっており,用語が同じでも意味が違うこともあり,日本漢方でも流派によっては必ずしも用語の意味が同一でないという困った状況もある.
本書は,以上のような現況をふまえて,中医学・日本漢方そして西洋医学を結びつけることを意図している.処方のカテゴリー分け・効能・適応などは中医学にもとづいており,我国でも入手できる中医の「方剤学」の書籍内容と変るところはないが,過去に日本で刊行された漢方の「処方解説書」とは大いに異なっている.また,中医の「方剤学」では,処方の解説が全面的に中医学的見地に立っているために,単なる翻訳調の解説では理解できないものが大半であるところから,でき得るかぎり西洋医学的な解説を試みている.しかし,処方や処方を構成する薬物の現代薬理学的・現代医学的な分析はまだ非常に初歩的であり・処方が適応する病態についての確実な定義とその根拠についての情報も乏しいところから,いずれについても推論にすぎないが,ある程度の確実性をもった推論であると考えている.
本書では,体系的医学として当然そなえるべき基本処方と有効で便利と考えられる処方を新旧をとわず取り上げ,さらに現時点(1982年)で健康保険収載の処方をすべて含めている.ここで気付くことは,現行の保険収載の処方だけでは,基本的にそなえるべき処方がかなりの部分で欠落していることである.処方は,元来特定の病態を改善するために薬物の効能をもとにして目的に合うよう構成されたものであり,弁証論治が基本になっている.ただ,薬物の効能は多岐にわたるので,個々の生薬の作用を十分に知れば,同一の処方を本来の目的とは別の病態に適応させることも可能である.また,既存の処方を運用する場合には,対象となる患者の特殊性・個別性にも注意を払い,適当な加減を行って状態に適応させるべきで,処方を固定したものと考えてはならない.病態に処方を適応させることが大切で,処方をむりやり病態にあてはめることはよいことではない.最近の中国では,中医学と西洋医学の知識を結びつけて,既存の処方を手本にしてより病態に適合した改変を加え,特定の疾患に対して非常に有効な処力をつくりあげ,めざましい成果をあげているが,今後の漢方医学はこのような方向へと努力をすべきである.
治療は,弁証論治を基本にした診断・治法の確立,薬物の選択・処方の決定という方法で行うべきであるが,エキス剤しか使用できない状況であれば,各処方の効能や構成薬物を十分に知り,弁証論治になるべく近くなるように積極的に処方を組み合わせ(合方)て対応するとよい.ただし,エキス剤が原処方の煎剤・散剤と同様の効果を示し得るか否かについては,さらに検討を要するものと考える.
なお,保険収載エキス剤しか使用できない人たちが多い現況を考慮し,繁用処方については実際的な運用の方法を付け加え,臨床家への便をはかった.「運用の実際」は山本巌が担当し,本書の教科書的生硬さを具体的な記述によって補足するとともに,他処方を運用するうえでもヒントをあたえ,臨床的に認識を深めて行くのに役立つことが多いと信じている(“処方の「運用の実際」によせて”を参照).ただ,処方によっては「処方解説」と「運用の実際」でその適応する病態と効能に関して解釈の違いがみられるが,本質的に相違するものではなく,重点のおき方が異なるためである.いずれが正しいというのではなく,処方の構成上多面的な対応がとれることの証左と考えていただきたい.
今後は,基礎研究や臨床経験からのフィードバックをもとに,さらに明確で分りやすく有効な医学にまで高める必要がある.本書が将来の礎石となることを望むものである.
1982年10月 神戸中医学研究会
ここ数年来,日中の医学交流が緊密さをまし,中国の新しい医学としての中西医結合医学や伝統的な中医学が我国に新鮮なショックを与え注目を集めるとともに,健康保険収載の漢方薬が大幅にふえて医師・薬剤師が手軽に使用できる状況となり,漢方医学や漢方薬が一種のブームといえるような活況を呈している・ただし,伝統的な経験にもとづく治療医学の体系と西洋医学の体系が大きく異なるところから,一見神秘的に見える漢方医学に過大な期待を抱いたり・適応が明確でない臨床治験によって過少評価を受けたり・概念の混同による当惑や混乱がみられることも否めない現況である.
日本では「方証相対」の漢方医学が浸透しており,この方法で一定の成果をあげている.ただ,「証に随って治療する」とはいいながら,単なる古典記載の症候の羅列にすぎなかったり,腹証と処方を短絡的に結びつけたりで,病態や病理の把握・薬物の効能にもとづいた処方の効果などがかなりなおざりにされており,「どのような病態に,どのような根拠で,なにゆえに効果があるのか」を示しているとは言いがたく,「言いすぎ」「見逃し」も散見する.このような状況にあきたらず,体系的な漢方医学としての「中医学」が学ばれはじめ,次第に我国でも定着しつつある.しかしながら,せっかく中医学を学んでも,成書に記載された処方が耳慣れたものではなく,現時点で保険適用の処方とは大幅な食い違いをみせるために,臨床面での応用は困難である.また,中医学や日本漢方に取り組んでいない人達にとっては,西洋医学的な考えのみで漢方薬を用いることはさらに困難である.このほか,中医学と日本漢方では用語が異なっており,用語が同じでも意味が違うこともあり,日本漢方でも流派によっては必ずしも用語の意味が同一でないという困った状況もある.
本書は,以上のような現況をふまえて,中医学・日本漢方そして西洋医学を結びつけることを意図している.処方のカテゴリー分け・効能・適応などは中医学にもとづいており,我国でも入手できる中医の「方剤学」の書籍内容と変るところはないが,過去に日本で刊行された漢方の「処方解説書」とは大いに異なっている.また,中医の「方剤学」では,処方の解説が全面的に中医学的見地に立っているために,単なる翻訳調の解説では理解できないものが大半であるところから,でき得るかぎり西洋医学的な解説を試みている.しかし,処方や処方を構成する薬物の現代薬理学的・現代医学的な分析はまだ非常に初歩的であり・処方が適応する病態についての確実な定義とその根拠についての情報も乏しいところから,いずれについても推論にすぎないが,ある程度の確実性をもった推論であると考えている.
本書では,体系的医学として当然そなえるべき基本処方と有効で便利と考えられる処方を新旧をとわず取り上げ,さらに現時点(1982年)で健康保険収載の処方をすべて含めている.ここで気付くことは,現行の保険収載の処方だけでは,基本的にそなえるべき処方がかなりの部分で欠落していることである.処方は,元来特定の病態を改善するために薬物の効能をもとにして目的に合うよう構成されたものであり,弁証論治が基本になっている.ただ,薬物の効能は多岐にわたるので,個々の生薬の作用を十分に知れば,同一の処方を本来の目的とは別の病態に適応させることも可能である.また,既存の処方を運用する場合には,対象となる患者の特殊性・個別性にも注意を払い,適当な加減を行って状態に適応させるべきで,処方を固定したものと考えてはならない.病態に処方を適応させることが大切で,処方をむりやり病態にあてはめることはよいことではない.最近の中国では,中医学と西洋医学の知識を結びつけて,既存の処方を手本にしてより病態に適合した改変を加え,特定の疾患に対して非常に有効な処力をつくりあげ,めざましい成果をあげているが,今後の漢方医学はこのような方向へと努力をすべきである.
治療は,弁証論治を基本にした診断・治法の確立,薬物の選択・処方の決定という方法で行うべきであるが,エキス剤しか使用できない状況であれば,各処方の効能や構成薬物を十分に知り,弁証論治になるべく近くなるように積極的に処方を組み合わせ(合方)て対応するとよい.ただし,エキス剤が原処方の煎剤・散剤と同様の効果を示し得るか否かについては,さらに検討を要するものと考える.
なお,保険収載エキス剤しか使用できない人たちが多い現況を考慮し,繁用処方については実際的な運用の方法を付け加え,臨床家への便をはかった.「運用の実際」は山本巌が担当し,本書の教科書的生硬さを具体的な記述によって補足するとともに,他処方を運用するうえでもヒントをあたえ,臨床的に認識を深めて行くのに役立つことが多いと信じている(“処方の「運用の実際」によせて”を参照).ただ,処方によっては「処方解説」と「運用の実際」でその適応する病態と効能に関して解釈の違いがみられるが,本質的に相違するものではなく,重点のおき方が異なるためである.いずれが正しいというのではなく,処方の構成上多面的な対応がとれることの証左と考えていただきたい.
今後は,基礎研究や臨床経験からのフィードバックをもとに,さらに明確で分りやすく有効な医学にまで高める必要がある.本書が将来の礎石となることを望むものである.
1982年10月 神戸中医学研究会