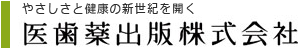第2版の序文
筆者が受けもつ患者さんは,介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)などで生活する認知症を有する要介護高齢者や遷延性意識障害の若年者である.2009年に初版を執筆した動機は,当時の摂食嚥下リハビリテーションの評価法や対応法が,指示に従って作業が可能な脳卒中後の患者さんや発達障害を有する小児を対象とするものであり,筆者の患者さんにはほとんど適用できなかったことにある.つまり,本来適用できない不適切な情報に基づいたケアやリハビリテーションが患者さんに行われることで,むしろ誤嚥や窒息のリスクを高めることになったことから,生理学に基づいた正しい情報を提供したいという気持ちが初版執筆の大きな背景である.しかしながら,初版出版後8年経過した現在でも,経験則に基づく評価法や対応法が流布しており,ほとんど変わっていないといわざるを得ない.
一方,この間に脳血管障害患者の救命率が上昇するとともに,その後の機能障害のために何度も誤嚥性肺炎を繰り返して亡くなる人が増加している.さらに,全国老人保健施設協会の調査では,本来リハビリテーション施設とされている老健施設の約41%が看取りを行い,85%の利用者が認知症であるとし,老健の実態はほとんど特養と相違なくなっていることが明らかになった.これらのことから,外来通院が可能な患者さんを念頭に置いた摂食咀嚼嚥下リハビリテーションの考え方とは異なる概念の対応が求められるようになった.また,この間には関連する新たな知見も多く得られた.たとえば,咀嚼嚥下機能と食物物性や食事量との関係,意識レベルによって口腔ケアは循環動態に影響すること,眼前の患者さんの障害の評価を無視した無定見な口腔清拭程度の口腔ケアは医療介護関連肺炎の原因となることなどである.
このような状況の変化から,実効性の高い対応を現場で行うための考え方を,得られた多くの新たな知見に基づいて追加する必要があること,また一般的に広く流布する評価法や対応法が患者さんの様態によっては生理学的に危ういことを示す必要があることを感じた.第2版では初版と同様に「病態や責任疾患に依存しない」「居宅や施設でも」「対象者とコミュニケーションが可能かどうかにかかわらず」という共通して適用が可能な「臨床の口腔生理学」に基づいて執筆した.第2版のポイントは以下のとおりである.
・病歴,現症採取時の確認事項を提示し,どのような因子がかかわるかを示したうえで,因子相互の関連性について整理した.また,この確認事項に基づき現場で使えるような新たなチェックリストを提示した.
・初版の評価法は項目の羅列に近かったが,第2版では現場での利便性を考慮し,問診,病歴採取,現症確認までの時系列に従って,経口摂取の有無から始まる評価のためのフローチャートの考え方を導入した.
・近年の食品物性と筋電図学的研究の結果から,既存の「反復唾液嚥下テスト」「改訂水飲みテスト」「フードテスト」を用いるうえでの問題点を口腔生理学的見地から解説した.
・対応法については,同一の患者であっても身体状況によって生活環境が変化することから,初版で紹介したフローチャートに基づく対応法を適用する前の段階で,対象者の状況によって口腔清掃を優先するか口腔機能療法を優先するか,さらに治療的か維持的かの4つの組み合わせのいずれから行う考え方を紹介した.
私たち日本人は,1947年に寿命50歳を越え,その後の70年ほどで40歳近く寿命が伸び,複数の治っていない疾患を有しつつ生活するようになった.その結果,障害や背景疾患に応じて,居宅だけでなく病院,施設などのさまざまな環境で生活するようになり,生活参加の支援が求められるようになった.近年,低栄養からのサルコペニアを経て生じるフレイルティサイクルが形成されると生活参加が難しくなるという考えが広がり,医療現場だけでなく介護の現場でも低栄養の改善のための摂食咀嚼嚥下リハビリテーションが必要であることが認識されるようになった.
第2版は,再現性の高い新たな情報を基本に,いかなる生活環境であっても実践できる方法を著したつもりである.その結果,改訂前に想定していた以上に原稿が増加してしまったことをお許しいただきたい.初版からの『実践なき理論は無力である,理論なき実践は暴力である』の精神は変わらない.
2017年9月 舘村 卓
序文
30年近く,種々の原因で生じた口腔機能(食べる機能や話す機能)の障害の治療を担当している.担当させていただいているのは,口蓋裂や口腔咽頭腫瘍術後,外傷性頭部障害,神経筋難病,脳血管障害,近年では遷延性意識障害,認知症の方々である.口腔機能の障害に関わりだした当初は,音声言語障害の原因の一つである口蓋帆咽頭閉鎖不全(いわゆる鼻咽腔閉鎖不全)の診断と治療を担当していた.摂食・嚥下障害に関わるようになったきっかけは,音声言語障害を有する方々のなかに同時に,口からうまく食べられないケースが多いことであった.残念ながら,当時はこのような多様な障害の方々に対応するための適切なテキストはわが国にはなかった.
1990年代に口蓋帆咽頭閉鎖機能の共同研究のために頻回にDavid P.Kuehn教授(元ASHA副会長,The University of Illinois at Urbana-Champaign)の下を訪れていたので,たびたびキャンパスの書店で関連する書物を探した.すでに講義用のテキストとして出版されているものがあったが,多くは,私が担当していた方々の障害には適用できないものであった.彼の隣室には米国Dysphagia学会副会長でもあったAdrienne Perlman教授(2006年Dysphagia学会会長)がおられた.彼女が,私やKuehn教授同様に,筋電図研究を行っていたことから親しくさせていただき,彼我でのST職の資格制度や教育,職域について話を聞かせていただくなかで,私が求めるテキストが少ない理由がわかった.当時(おそらく現在も),米国での嚥下障害の臨床は全米のCCC-SLP*の85%が専従的排他的に関わる領域であり,臨床現場で他職種(たとえば医師や歯科医師)の入る余地はきわめて少なく,これはspeechの臨床とまったく同じである(正確には speechの研究に関わる歯科医師や医師はいる)ことに拠っていると気づくに至った.
寡聞にして現在の状況はわからないが,米国のCCC-SLPが臨床を行うのは病院であることから,対象となる摂食・嚥下障害の方々は,通院でき,なんらかの手段で意思疎通ができる人となる.したがって,米国で出版されている嚥下障害に関わる成書(Perlman教授もDeglutition and its Disordersという名著を著している)は,それを利用するCCC-SLPの要求に従うものである.したがって,遷延性意識障害に陥っている人々,脳血管性認知症か脳血管障害を有するアルツハイマー病の方が80%を超える老人保健施設の利用者,在宅で要介護状態にある方々には,それらのテキストに記載されている検査や訓練治療法がうまく適用できないのは当然であった.
現在,私が担当させていただく方々では,急性期での対応が漫然と継続されていたり,誤った口腔ケアであったり,なかには急性期に医師から「生涯,口では食べられません」と言われたことで未介入のまま陥った廃用性変化が原因であったりすることが多い.しかも,在宅や施設で生活することが余儀なくされている方が多いため,正しく生理学的に評価されることなく,ご家族やケアを担当する方々が,「通院でき,指示に従える人」向けの方法を試行錯誤的に用いられていることが多い.このことにより,障害像がいっそう複雑になっていることも経験する.
米国でASHA(American Speech,Language,and Hearing Association)がその前身も含めて1925年に設立されたこととわが国でSTの国家資格が設立された年から考えると,speechに関しては70年以上もの大きな歴史の差がある.しかしながら,米国とわが国での嚥下障害の研究や臨床が始まった時期は,speechに比較して大差なく,この分野でのエビデンスは彼我ともに日々に変化していると考えられる.すなわち,関連した書物は出版と同時に陳腐化する可能性があり,個人的には,本書を著すことには研究者としての後ろめたさをもっていた.
しかしながら,多様な原因と,多様な介入のために,多様化した嚥下障害に対して,コホートスタディやケースコントロールスタディが人道上も可能とは思えず,またメタアナリシスを待つのも無責任であるとの思いで,現在流布する診断方法や治療法に欠けることの多い臨床口腔生理の立場から,ケアの視点でヒントを提供できるかもしれないとの気持ちで恐る恐る著した.本書をお読みくださった方々からのご意見を頂戴して,内容を修正するという考え方でお許しいただこうと思っている.
著すにあたって,「病態や責任疾患に依存しない」「在宅や施設でも」「対象者とコミュニケーションが可能かどうかにかかわらず」共通して適用が可能な「臨床の口腔生理学」に基づいた考え方を述べることに気をつけたが,多くのご批判やご指摘が殺到するものと思っている.それによって,このような方々での口から食べるための臨床や研究が進み,より多くのご家族や関わられる方のお役に立つエビデンスが生まれることを望んでいる.
最後になったが,本書の企画段階から数々のご助言と励ましのお言葉を頂戴した紙屋克子先生(筑波大学名誉教授)ならびに吉田春陽先生(守口市歯科医師会)には満腔の謝意を表し,執筆期間中の診療に当たっては自身の学位研究に多忙を極めるなかで協力をいただいた河合利彦博士に深く感謝する.また医歯薬出版の担当の方には,企画から出版にいたるまでたくさんのご提案をいただいたことを感謝し,尋常ではない長い時間お待たせしたことをお詫び申し上げる.
『実践なき理論は無力である,理論なき実践は暴力である』を心して.
2009年6月 舘村 卓
*CCC-SLP:Certificate of Clinical Competence in Speech-Language Pathologyの略で,アメリカ言語聴覚士学会(American Speech-Language and Hearing Association:ASHA)が認定するスピーチパソロジストのための民間資格の名称.
筆者が受けもつ患者さんは,介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)などで生活する認知症を有する要介護高齢者や遷延性意識障害の若年者である.2009年に初版を執筆した動機は,当時の摂食嚥下リハビリテーションの評価法や対応法が,指示に従って作業が可能な脳卒中後の患者さんや発達障害を有する小児を対象とするものであり,筆者の患者さんにはほとんど適用できなかったことにある.つまり,本来適用できない不適切な情報に基づいたケアやリハビリテーションが患者さんに行われることで,むしろ誤嚥や窒息のリスクを高めることになったことから,生理学に基づいた正しい情報を提供したいという気持ちが初版執筆の大きな背景である.しかしながら,初版出版後8年経過した現在でも,経験則に基づく評価法や対応法が流布しており,ほとんど変わっていないといわざるを得ない.
一方,この間に脳血管障害患者の救命率が上昇するとともに,その後の機能障害のために何度も誤嚥性肺炎を繰り返して亡くなる人が増加している.さらに,全国老人保健施設協会の調査では,本来リハビリテーション施設とされている老健施設の約41%が看取りを行い,85%の利用者が認知症であるとし,老健の実態はほとんど特養と相違なくなっていることが明らかになった.これらのことから,外来通院が可能な患者さんを念頭に置いた摂食咀嚼嚥下リハビリテーションの考え方とは異なる概念の対応が求められるようになった.また,この間には関連する新たな知見も多く得られた.たとえば,咀嚼嚥下機能と食物物性や食事量との関係,意識レベルによって口腔ケアは循環動態に影響すること,眼前の患者さんの障害の評価を無視した無定見な口腔清拭程度の口腔ケアは医療介護関連肺炎の原因となることなどである.
このような状況の変化から,実効性の高い対応を現場で行うための考え方を,得られた多くの新たな知見に基づいて追加する必要があること,また一般的に広く流布する評価法や対応法が患者さんの様態によっては生理学的に危ういことを示す必要があることを感じた.第2版では初版と同様に「病態や責任疾患に依存しない」「居宅や施設でも」「対象者とコミュニケーションが可能かどうかにかかわらず」という共通して適用が可能な「臨床の口腔生理学」に基づいて執筆した.第2版のポイントは以下のとおりである.
・病歴,現症採取時の確認事項を提示し,どのような因子がかかわるかを示したうえで,因子相互の関連性について整理した.また,この確認事項に基づき現場で使えるような新たなチェックリストを提示した.
・初版の評価法は項目の羅列に近かったが,第2版では現場での利便性を考慮し,問診,病歴採取,現症確認までの時系列に従って,経口摂取の有無から始まる評価のためのフローチャートの考え方を導入した.
・近年の食品物性と筋電図学的研究の結果から,既存の「反復唾液嚥下テスト」「改訂水飲みテスト」「フードテスト」を用いるうえでの問題点を口腔生理学的見地から解説した.
・対応法については,同一の患者であっても身体状況によって生活環境が変化することから,初版で紹介したフローチャートに基づく対応法を適用する前の段階で,対象者の状況によって口腔清掃を優先するか口腔機能療法を優先するか,さらに治療的か維持的かの4つの組み合わせのいずれから行う考え方を紹介した.
私たち日本人は,1947年に寿命50歳を越え,その後の70年ほどで40歳近く寿命が伸び,複数の治っていない疾患を有しつつ生活するようになった.その結果,障害や背景疾患に応じて,居宅だけでなく病院,施設などのさまざまな環境で生活するようになり,生活参加の支援が求められるようになった.近年,低栄養からのサルコペニアを経て生じるフレイルティサイクルが形成されると生活参加が難しくなるという考えが広がり,医療現場だけでなく介護の現場でも低栄養の改善のための摂食咀嚼嚥下リハビリテーションが必要であることが認識されるようになった.
第2版は,再現性の高い新たな情報を基本に,いかなる生活環境であっても実践できる方法を著したつもりである.その結果,改訂前に想定していた以上に原稿が増加してしまったことをお許しいただきたい.初版からの『実践なき理論は無力である,理論なき実践は暴力である』の精神は変わらない.
2017年9月 舘村 卓
序文
30年近く,種々の原因で生じた口腔機能(食べる機能や話す機能)の障害の治療を担当している.担当させていただいているのは,口蓋裂や口腔咽頭腫瘍術後,外傷性頭部障害,神経筋難病,脳血管障害,近年では遷延性意識障害,認知症の方々である.口腔機能の障害に関わりだした当初は,音声言語障害の原因の一つである口蓋帆咽頭閉鎖不全(いわゆる鼻咽腔閉鎖不全)の診断と治療を担当していた.摂食・嚥下障害に関わるようになったきっかけは,音声言語障害を有する方々のなかに同時に,口からうまく食べられないケースが多いことであった.残念ながら,当時はこのような多様な障害の方々に対応するための適切なテキストはわが国にはなかった.
1990年代に口蓋帆咽頭閉鎖機能の共同研究のために頻回にDavid P.Kuehn教授(元ASHA副会長,The University of Illinois at Urbana-Champaign)の下を訪れていたので,たびたびキャンパスの書店で関連する書物を探した.すでに講義用のテキストとして出版されているものがあったが,多くは,私が担当していた方々の障害には適用できないものであった.彼の隣室には米国Dysphagia学会副会長でもあったAdrienne Perlman教授(2006年Dysphagia学会会長)がおられた.彼女が,私やKuehn教授同様に,筋電図研究を行っていたことから親しくさせていただき,彼我でのST職の資格制度や教育,職域について話を聞かせていただくなかで,私が求めるテキストが少ない理由がわかった.当時(おそらく現在も),米国での嚥下障害の臨床は全米のCCC-SLP*の85%が専従的排他的に関わる領域であり,臨床現場で他職種(たとえば医師や歯科医師)の入る余地はきわめて少なく,これはspeechの臨床とまったく同じである(正確には speechの研究に関わる歯科医師や医師はいる)ことに拠っていると気づくに至った.
寡聞にして現在の状況はわからないが,米国のCCC-SLPが臨床を行うのは病院であることから,対象となる摂食・嚥下障害の方々は,通院でき,なんらかの手段で意思疎通ができる人となる.したがって,米国で出版されている嚥下障害に関わる成書(Perlman教授もDeglutition and its Disordersという名著を著している)は,それを利用するCCC-SLPの要求に従うものである.したがって,遷延性意識障害に陥っている人々,脳血管性認知症か脳血管障害を有するアルツハイマー病の方が80%を超える老人保健施設の利用者,在宅で要介護状態にある方々には,それらのテキストに記載されている検査や訓練治療法がうまく適用できないのは当然であった.
現在,私が担当させていただく方々では,急性期での対応が漫然と継続されていたり,誤った口腔ケアであったり,なかには急性期に医師から「生涯,口では食べられません」と言われたことで未介入のまま陥った廃用性変化が原因であったりすることが多い.しかも,在宅や施設で生活することが余儀なくされている方が多いため,正しく生理学的に評価されることなく,ご家族やケアを担当する方々が,「通院でき,指示に従える人」向けの方法を試行錯誤的に用いられていることが多い.このことにより,障害像がいっそう複雑になっていることも経験する.
米国でASHA(American Speech,Language,and Hearing Association)がその前身も含めて1925年に設立されたこととわが国でSTの国家資格が設立された年から考えると,speechに関しては70年以上もの大きな歴史の差がある.しかしながら,米国とわが国での嚥下障害の研究や臨床が始まった時期は,speechに比較して大差なく,この分野でのエビデンスは彼我ともに日々に変化していると考えられる.すなわち,関連した書物は出版と同時に陳腐化する可能性があり,個人的には,本書を著すことには研究者としての後ろめたさをもっていた.
しかしながら,多様な原因と,多様な介入のために,多様化した嚥下障害に対して,コホートスタディやケースコントロールスタディが人道上も可能とは思えず,またメタアナリシスを待つのも無責任であるとの思いで,現在流布する診断方法や治療法に欠けることの多い臨床口腔生理の立場から,ケアの視点でヒントを提供できるかもしれないとの気持ちで恐る恐る著した.本書をお読みくださった方々からのご意見を頂戴して,内容を修正するという考え方でお許しいただこうと思っている.
著すにあたって,「病態や責任疾患に依存しない」「在宅や施設でも」「対象者とコミュニケーションが可能かどうかにかかわらず」共通して適用が可能な「臨床の口腔生理学」に基づいた考え方を述べることに気をつけたが,多くのご批判やご指摘が殺到するものと思っている.それによって,このような方々での口から食べるための臨床や研究が進み,より多くのご家族や関わられる方のお役に立つエビデンスが生まれることを望んでいる.
最後になったが,本書の企画段階から数々のご助言と励ましのお言葉を頂戴した紙屋克子先生(筑波大学名誉教授)ならびに吉田春陽先生(守口市歯科医師会)には満腔の謝意を表し,執筆期間中の診療に当たっては自身の学位研究に多忙を極めるなかで協力をいただいた河合利彦博士に深く感謝する.また医歯薬出版の担当の方には,企画から出版にいたるまでたくさんのご提案をいただいたことを感謝し,尋常ではない長い時間お待たせしたことをお詫び申し上げる.
『実践なき理論は無力である,理論なき実践は暴力である』を心して.
2009年6月 舘村 卓
*CCC-SLP:Certificate of Clinical Competence in Speech-Language Pathologyの略で,アメリカ言語聴覚士学会(American Speech-Language and Hearing Association:ASHA)が認定するスピーチパソロジストのための民間資格の名称.
本文中の略語
第1章 なぜ口から食べないといけないのか
1.大衆超高齢化時代の要請―生活参加の支援
2.日本人の死と医療の今昔
3.経口摂取で生活参加を支援するという考え方
1)なぜ口から食べないといけないのか
2)非経口摂取での経過が非経口摂取を継続させる
3)経口摂取の支援は難しい―口から食べることは恐ろしい
4.なぜ,どこで,誰が経口摂取を求めているのか
第2章 動物の嚥下,ヒトの嚥下―なぜ,ヒトは誤嚥し,動物は誤嚥しないのか
1.動物の口腔,鼻腔,気管,食道の位置関係
2.ヒトの口腔,鼻腔,気管,食道の位置関係
1)口蓋帆咽頭閉鎖機能の獲得
2)「食事」か「食餌」か
第3章 咀嚼嚥下機能の獲得と障害の生理―乳児から成熟型への摂食嚥下機能の獲得
1.離乳開始まで
1)生後直後~離乳前期
2)乳児嚥下―構造上の特徴
1 舌の形状と運動モード 2 肋骨の走行と呼吸 3 咽頭の発達
3)乳児嚥下―機能上の特徴
1 栄養摂取のための3つの反射 2 異物排除のための2つの反射
3 脱感作
2.離乳開始以後
1)離乳初期
1 離乳初期の口腔運動 2 離乳初期に摂取可能な食物の性質
3 口腔容積の低下した高齢者と離乳初期の舌運動との近似性
2)離乳中期
1 離乳中期の口腔運動 2 離乳中期に摂取可能な食物の性質
3 離乳中期の要介護高齢者との関係 4 離乳初期から離乳中期に誘導する方法
3)離乳後期
1 離乳後期の口腔運動 2 離乳後期に摂取可能な食物の性質
3 離乳中期から離乳後期に誘導する方法
3.離乳段階から学ぶ要介護高齢者(児)への対応の基本
第4章 成人型の摂食嚥下機能とその低下
1.4(5)期型嚥下モデル
1)先行期
2)準備期
1 準備期に必要とされる口腔機能と口腔器官の特性 2 食物物性と咀嚼機能
3)口腔期
1 口腔(前)期 2 口腔(後)期(移行期)
4)咽頭期
1 咽頭期前半 2 咽頭期後半
5)食道期
第5章 生理学に基づく対応
1.対応と評価にあたって
2.評価法
1 短期,長期目標を明確にし,最適な治療・訓練法をプログラムするために評価する
2 対象者の様態と変化する目標に応じた評価方法を選択する
3 日常生活環境を想定した評価を行う 4 家族・介護者からの情報を採取する
5 介護者を評価する 6 口腔機能に可塑性があることに基づいて評価する
3.効果的な評価の実際
1)病歴採取時に必ず確認すべき項目
2)現症採取時に必ず確認すべき項目
3)臨床検査
4)問診による摂食嚥下機能にかかわる因子の評価
5)介入,観察による摂食嚥下機能にかかわる因子の評価
1 指示に従えるか否かを問わない評価項目
2 指示に従うことが難しい場合に評価が困難な項目
4.フローチャートに従った摂食咀嚼嚥下機能の評価
1)経口摂取の場合
要衝1.嚥下障害を疑わせるイベントに一貫性があるのか 要衝2.安全な嚥下姿勢をとれるか
要衝3.末梢神経障害の有無 要衝4.歯垢が原因の発熱の特徴(四徴)の有無
2)非経口摂取の場合
要衝1.安全な嚥下姿勢である三点セット+側臥位がとれるか
要衝2.コミュニケーションがとれるか否か/意識障害の有無 要衝3.原始反射の有無
要衝4.歯垢が原因の発熱の特徴(四徴)の有無 要衝5.末梢神経機能の評価
5.既存の評価法の問題点
1)嚥下試験
2)機器による検査
6.関連職種からの情報収集
第6章 摂食嚥下障害への対応の実際
1.口腔ケアは口腔清掃と口腔咽頭機能療法の効果を同時に満たすことができるのか
1)「口腔ケア」という言葉の危うさ
2)tailor-made oral-careの考え方
2.口腔清掃によって得られる効果
3.口腔咽頭機能療法の効果
4.口腔清掃と口腔咽頭機能療法で使用するもの
5.口腔装置治療
6.フローチャートに基づく嚥下リハビリテーション
1)4象限のどこで生活しているのか
2)経口的に栄養摂取している場合
1 I型の対応 2 I型変法の対応 3 II型の対応
3)経口的に栄養摂取していない場合
1 III型の対応 2 IV型の対応 3 V型の対応
第7章 フローチャートに従った実際の取り組み
症例1 口蓋帆咽頭(いわゆる鼻咽腔)閉鎖不全が原因の嚥下障害を口腔装置によって改善できた舌咽神経鞘腫術後症例【I型】
症例2 歯科医師会,訪問歯科衛生士,専門医,施設スタッフの連携によって改善できた血管性認知症症例【I型変法】
症例3 支援学校卒業後に発症した嚥下障害を下肢機能の訓練を行うことで改善できた小児症例【II型】
症例4 長期の非経口摂取による廃用化が原因の咀嚼嚥下障害に対して,咬合状態の評価と筋電図所見に基づいて改善できた先天的消化管障害の小児症例【III型(III-1)】
症例5 口唇機能賦活のための口腔装置とIOE法によって改善できた下顎歯肉腫瘍術後症例【III型(III-1)】
症例6 歯科医師による早期の口腔環境の回復と居住環境の調整によって嚥下障害を改善できた脳卒中後症例(IV型)
症例7 脳外科手術後7年間非経口摂取による摂食嚥下障害に対して,口腔咽頭の廃用化を改善することで普通食まで誘導できた遷延性意識障害症例【V型】
付 歯科医科連携の一例 食道がん手術患者への口腔ケアを通じた摂食嚥下リハビリテーション
1.背景
歯科医科連携の経過
2.Stage I―術後にだけ対応したチームアプローチ―(1997年5月~1998年5月)
3.Stage II―術前後の全症例に対応したチームアプローチ―(1998年5月~2005年3月)
4.まとめ
食道がん術後における摂食嚥下障害発症の背景と対応 課題
索引
NOTE
1 歯周病と全身疾患
2 イヌ,ネコは咽頭があるのでときどき誤嚥する
3 健常者であっても高齢男性は高齢女性より誤嚥リスクが高い
4 顎骨,永久歯,栄養
5 上半身の前方への転倒を防ぐハーネスが嚥下障害の原因となる
6 成人での仰臥位での口腔ケアのリスク
7 なぜ,乳児は仰臥位でも誤嚥しないのに成人では誤嚥するのか
8 原始反射と要介護者(児)
9 脱感作が阻害される医学的介入
10 バギーを使っている乳幼児への対応
11 粘りのある食品とは
12 刻み食は人にやさしいか
13 健常児なのに小学校に入学したら給食が食べられなくなった
14 嚥下造影検査はゴールドスタンダードか(1)
15 暗い部屋で昼間独居だと,なぜ誤嚥するのか
16 なぜ,風邪をひくと「お粥」なのか
17 食前の口腔ケア(口腔清掃)の必要性
18 在宅要介護者や施設利用者で長期に軟食・刻み食を摂取していた人への義歯作成
19 歯垢は歯と歯周組織だけに影響するのか
20 エアコンの吹き出し口と仰臥位
21 尿量と唾液分泌量
22 咀嚼運動と唾液の性質
23 反復唾液嚥下テストは何を診ることができるのか
24 刻み食やミキサー食は食べやすいのか
25 なぜ口蓋帆張筋は三叉神経支配なのか
26 刻み食やミキサー食にとろみ食品を混ぜれば問題ないのか
27 一定量の「水飲みテスト」で嚥下機能が判定できるのか
28 神経障害がないのに軟口蓋が挙上しないことがある
29 嚥下造影検査はゴールドスタンダードか(2)
30 フードテストは何を診ているのか
31 お粥にするとうまく嚥下できるか―食事の途中でムセ出すのはなぜか
32 NGチューブの内面の白濁は栄養剤の残渣か栄養剤の逆流か
33 カウンターバーでコリンズカクテルは飲めるか,すし屋の湯飲みはなぜ広口か
34 構音訓練は嚥下機能の訓練になるのか
35 Albの検査方法による値の誤差
36 物性が同一だと同じように嚥下できるのか
37 肌のケアと口腔ケア
38 長期仰臥する人にベッド上での安全な嚥下姿勢をとるための蒸しタオル,ホットパック,成人用おむつの使用
39 食後のソファでのくつろぎは危ない
40 食べてすぐに横になると「牛」になるのは本当か
41 なぜ厳密に回数や時間を決めた訓練は継続されないのか
42 なぜチューインガムやスルメが咀嚼訓練によいのか
43 上口唇と下口唇は同じ役割か
44 体幹保持の道具
45 膝と腰の位置で曲がるベッドは本当に優しいのか
46 胃瘻造設後に経口摂取が可能になれば胃瘻を抜去してよいのか
47 IOE法を用いたNGチューブから離脱するためのプログラム
48 気管カニューレから離脱するためのプログラム
49 市販離乳食でうまくいくのか
50 なぜ成長期に長期非経口摂取だと小顎症になり,叢生になるのか
第1章 なぜ口から食べないといけないのか
1.大衆超高齢化時代の要請―生活参加の支援
2.日本人の死と医療の今昔
3.経口摂取で生活参加を支援するという考え方
1)なぜ口から食べないといけないのか
2)非経口摂取での経過が非経口摂取を継続させる
3)経口摂取の支援は難しい―口から食べることは恐ろしい
4.なぜ,どこで,誰が経口摂取を求めているのか
第2章 動物の嚥下,ヒトの嚥下―なぜ,ヒトは誤嚥し,動物は誤嚥しないのか
1.動物の口腔,鼻腔,気管,食道の位置関係
2.ヒトの口腔,鼻腔,気管,食道の位置関係
1)口蓋帆咽頭閉鎖機能の獲得
2)「食事」か「食餌」か
第3章 咀嚼嚥下機能の獲得と障害の生理―乳児から成熟型への摂食嚥下機能の獲得
1.離乳開始まで
1)生後直後~離乳前期
2)乳児嚥下―構造上の特徴
1 舌の形状と運動モード 2 肋骨の走行と呼吸 3 咽頭の発達
3)乳児嚥下―機能上の特徴
1 栄養摂取のための3つの反射 2 異物排除のための2つの反射
3 脱感作
2.離乳開始以後
1)離乳初期
1 離乳初期の口腔運動 2 離乳初期に摂取可能な食物の性質
3 口腔容積の低下した高齢者と離乳初期の舌運動との近似性
2)離乳中期
1 離乳中期の口腔運動 2 離乳中期に摂取可能な食物の性質
3 離乳中期の要介護高齢者との関係 4 離乳初期から離乳中期に誘導する方法
3)離乳後期
1 離乳後期の口腔運動 2 離乳後期に摂取可能な食物の性質
3 離乳中期から離乳後期に誘導する方法
3.離乳段階から学ぶ要介護高齢者(児)への対応の基本
第4章 成人型の摂食嚥下機能とその低下
1.4(5)期型嚥下モデル
1)先行期
2)準備期
1 準備期に必要とされる口腔機能と口腔器官の特性 2 食物物性と咀嚼機能
3)口腔期
1 口腔(前)期 2 口腔(後)期(移行期)
4)咽頭期
1 咽頭期前半 2 咽頭期後半
5)食道期
第5章 生理学に基づく対応
1.対応と評価にあたって
2.評価法
1 短期,長期目標を明確にし,最適な治療・訓練法をプログラムするために評価する
2 対象者の様態と変化する目標に応じた評価方法を選択する
3 日常生活環境を想定した評価を行う 4 家族・介護者からの情報を採取する
5 介護者を評価する 6 口腔機能に可塑性があることに基づいて評価する
3.効果的な評価の実際
1)病歴採取時に必ず確認すべき項目
2)現症採取時に必ず確認すべき項目
3)臨床検査
4)問診による摂食嚥下機能にかかわる因子の評価
5)介入,観察による摂食嚥下機能にかかわる因子の評価
1 指示に従えるか否かを問わない評価項目
2 指示に従うことが難しい場合に評価が困難な項目
4.フローチャートに従った摂食咀嚼嚥下機能の評価
1)経口摂取の場合
要衝1.嚥下障害を疑わせるイベントに一貫性があるのか 要衝2.安全な嚥下姿勢をとれるか
要衝3.末梢神経障害の有無 要衝4.歯垢が原因の発熱の特徴(四徴)の有無
2)非経口摂取の場合
要衝1.安全な嚥下姿勢である三点セット+側臥位がとれるか
要衝2.コミュニケーションがとれるか否か/意識障害の有無 要衝3.原始反射の有無
要衝4.歯垢が原因の発熱の特徴(四徴)の有無 要衝5.末梢神経機能の評価
5.既存の評価法の問題点
1)嚥下試験
2)機器による検査
6.関連職種からの情報収集
第6章 摂食嚥下障害への対応の実際
1.口腔ケアは口腔清掃と口腔咽頭機能療法の効果を同時に満たすことができるのか
1)「口腔ケア」という言葉の危うさ
2)tailor-made oral-careの考え方
2.口腔清掃によって得られる効果
3.口腔咽頭機能療法の効果
4.口腔清掃と口腔咽頭機能療法で使用するもの
5.口腔装置治療
6.フローチャートに基づく嚥下リハビリテーション
1)4象限のどこで生活しているのか
2)経口的に栄養摂取している場合
1 I型の対応 2 I型変法の対応 3 II型の対応
3)経口的に栄養摂取していない場合
1 III型の対応 2 IV型の対応 3 V型の対応
第7章 フローチャートに従った実際の取り組み
症例1 口蓋帆咽頭(いわゆる鼻咽腔)閉鎖不全が原因の嚥下障害を口腔装置によって改善できた舌咽神経鞘腫術後症例【I型】
症例2 歯科医師会,訪問歯科衛生士,専門医,施設スタッフの連携によって改善できた血管性認知症症例【I型変法】
症例3 支援学校卒業後に発症した嚥下障害を下肢機能の訓練を行うことで改善できた小児症例【II型】
症例4 長期の非経口摂取による廃用化が原因の咀嚼嚥下障害に対して,咬合状態の評価と筋電図所見に基づいて改善できた先天的消化管障害の小児症例【III型(III-1)】
症例5 口唇機能賦活のための口腔装置とIOE法によって改善できた下顎歯肉腫瘍術後症例【III型(III-1)】
症例6 歯科医師による早期の口腔環境の回復と居住環境の調整によって嚥下障害を改善できた脳卒中後症例(IV型)
症例7 脳外科手術後7年間非経口摂取による摂食嚥下障害に対して,口腔咽頭の廃用化を改善することで普通食まで誘導できた遷延性意識障害症例【V型】
付 歯科医科連携の一例 食道がん手術患者への口腔ケアを通じた摂食嚥下リハビリテーション
1.背景
歯科医科連携の経過
2.Stage I―術後にだけ対応したチームアプローチ―(1997年5月~1998年5月)
3.Stage II―術前後の全症例に対応したチームアプローチ―(1998年5月~2005年3月)
4.まとめ
食道がん術後における摂食嚥下障害発症の背景と対応 課題
索引
NOTE
1 歯周病と全身疾患
2 イヌ,ネコは咽頭があるのでときどき誤嚥する
3 健常者であっても高齢男性は高齢女性より誤嚥リスクが高い
4 顎骨,永久歯,栄養
5 上半身の前方への転倒を防ぐハーネスが嚥下障害の原因となる
6 成人での仰臥位での口腔ケアのリスク
7 なぜ,乳児は仰臥位でも誤嚥しないのに成人では誤嚥するのか
8 原始反射と要介護者(児)
9 脱感作が阻害される医学的介入
10 バギーを使っている乳幼児への対応
11 粘りのある食品とは
12 刻み食は人にやさしいか
13 健常児なのに小学校に入学したら給食が食べられなくなった
14 嚥下造影検査はゴールドスタンダードか(1)
15 暗い部屋で昼間独居だと,なぜ誤嚥するのか
16 なぜ,風邪をひくと「お粥」なのか
17 食前の口腔ケア(口腔清掃)の必要性
18 在宅要介護者や施設利用者で長期に軟食・刻み食を摂取していた人への義歯作成
19 歯垢は歯と歯周組織だけに影響するのか
20 エアコンの吹き出し口と仰臥位
21 尿量と唾液分泌量
22 咀嚼運動と唾液の性質
23 反復唾液嚥下テストは何を診ることができるのか
24 刻み食やミキサー食は食べやすいのか
25 なぜ口蓋帆張筋は三叉神経支配なのか
26 刻み食やミキサー食にとろみ食品を混ぜれば問題ないのか
27 一定量の「水飲みテスト」で嚥下機能が判定できるのか
28 神経障害がないのに軟口蓋が挙上しないことがある
29 嚥下造影検査はゴールドスタンダードか(2)
30 フードテストは何を診ているのか
31 お粥にするとうまく嚥下できるか―食事の途中でムセ出すのはなぜか
32 NGチューブの内面の白濁は栄養剤の残渣か栄養剤の逆流か
33 カウンターバーでコリンズカクテルは飲めるか,すし屋の湯飲みはなぜ広口か
34 構音訓練は嚥下機能の訓練になるのか
35 Albの検査方法による値の誤差
36 物性が同一だと同じように嚥下できるのか
37 肌のケアと口腔ケア
38 長期仰臥する人にベッド上での安全な嚥下姿勢をとるための蒸しタオル,ホットパック,成人用おむつの使用
39 食後のソファでのくつろぎは危ない
40 食べてすぐに横になると「牛」になるのは本当か
41 なぜ厳密に回数や時間を決めた訓練は継続されないのか
42 なぜチューインガムやスルメが咀嚼訓練によいのか
43 上口唇と下口唇は同じ役割か
44 体幹保持の道具
45 膝と腰の位置で曲がるベッドは本当に優しいのか
46 胃瘻造設後に経口摂取が可能になれば胃瘻を抜去してよいのか
47 IOE法を用いたNGチューブから離脱するためのプログラム
48 気管カニューレから離脱するためのプログラム
49 市販離乳食でうまくいくのか
50 なぜ成長期に長期非経口摂取だと小顎症になり,叢生になるのか