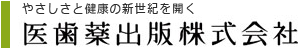“矯正治療後の咬合の安定性と保定”を読まれるにあたって
Ravindra Nanda and Joseph Zernik
序章
矯正治療後に後戻りの問題があることや,それを防止するためには保定が必要であることはよく知られている.治療着手にあたって,まず矯正医が考えるべき重要な事項は,矯正治療で得た咬合の安定をどのように確保するかである.しかし,咬合の長期安定性を達成するための学識や技能および咬合の安定性の裏にある種々の潜在的要因については,現在のところ十分に理論的に証明されたものはきわめて少ない.これは動的矯正治療終了後,治療で得た咬合を保定する操作が,ときとして長期にわたって継続する必要があることからも明らかである.
矯正治療後の咬合の不安定性に関与する要因は次の2つの項目に分類できる.
1.歯列と咬合の成長,成熟,老化の過程に関連する変化
2.矯正治療によって得られた咬合に特有の不安定性が関連する変化
1.に分類される咬合の不安定性は,しばしば長期にわたってみられる.このなかには,たとえば被蓋が深くなっていくなどの青年期前,あるいは青年期における成長に関連した変化が含まれる.このほか,極端な例では上下顎骨の成長の不調和に関連して生じる諸変化などもみられる.
成熟に関連する変化のなかには,治療前にみられた下顎切歯部の叢生が元の状態より,さらにその叢生程度が増悪した場合もあげられる(図1).歯列の加齢変化は,また歯根膜炎の発生率の増加に関連している.このような場合には,歯が一部喪失した患者にみられる複雑な歯の位置の変化や,前歯部の空 ,前歯の唇側への倒れこみを伴っていることもある.これらの加齢変化はいずれも,過去の矯正治療加療の有無に関係なく,どの患者にもよく起こりうることである(図2).このようなことがあるにもかかわらず,矯正患者は時間と費用を費やして得た矯正治療終了時の美しい歯並びが安定しているものと思っている.
これらの問題に関して第1章でIb Leth Nielsenが詳細に分析し,上下顎骨の成長とそれに付随する歯牙歯槽部の変化が,矯正治療の術後変化と治療結果の安定性にどのような影響を与えるかについての問題を論じている.Nielsenは,たとえば,かりにその患者に特有の下顎頭の成長方向に逆らって矯正治療効果が導かれたような場合に,とくに垂直方向への増加を生じさせたようなときには,その治療効果の安定性は疑わしいものであろうし,後戻りの傾向が生じることになると述べている.このNielsenの見解は,下顎の成長方向の予測を正確に行って,成長期間中を通じて成長制御に関与しようとする考え方をもつ矯正医に対して,一つの異論を唱えるものである.
Nielsenはさらに矯正治療後の咬合の安定性という観点からみて,現在,われわれがもつ成長発育についての知識をもとにして考えだされた矯正治療に最適な時期について疑問を投げかけている.そして彼は,一部の症例においてはおそらく成長変化が咬合の安定性を左右する主要な要因の一つであるという見解のもとに,これらの患者の最終的な治療,とくに抜歯療法は,顔面骨格の成長パターンが明らかにあらわれてくる時期まで遅らせるのがよい,との提案をしている.混合歯列期における矯正治療が一般的になりつつある現在,この見解はたしかに特筆に値するものであり,十分検討される必要がある.
序章
“矯正治療後の咬合の安定性と保定”を読まれるにあたって 第2章で,Ram S.NandaとSurender K.Nandaはともに,成長発育に関連する変化が矯正治療施術後の咬合の変化や後戻りに影響することがよくある,という立場をとっている.そして頭蓋顔面骨格の特定の構成部分の変化に関する彼らの研究成果から,骨格の変化はとくに男子において30歳代まで続くものであることを強調している.
2.に分類できる咬合の不安定性のなかには,明らかに後戻りという用語で表現できる変化と,矯正治療によってつくられた咬合に特有の不安定性によって発現したとすることができる変化とが含まれている.このような変化は比較的局所的なもので,たとえば,治療中に改善された小臼歯の捻転が治療後に後戻りした場合などがある.とくに前歯にみられる,このようなタイプの捻転の後戻りは,矯正医と患者の両者にとって深刻な悩みである.実際,診断や治療計画のいかんにかかわらず,上顎中切歯部に捻転がある場合には,これが患者の初診時の主訴となることが多い.したがって,その叢生の後戻りが比較的小さな局所的なものであっても,実際にはかなりの問題を引き起こすことになりかねない.また,後戻りはより広範囲にわたって咬合の様相に影響を与えるものである.たとえば,上顎あるいは下顎の前歯部や臼歯部の叢生の再発や,交叉咬合の再発,抜歯部位の空 閉鎖後の再開離,過蓋咬合治療例のオーバーバイトの増加などの咬合の変化が生じてくる.
安定した咬合をつくることが矯正治療の重要な目標であるので,矯正医ならだれも,できれば治療着手前に診断と治療計画をたてる際に,これらの事柄について分析検討を行い,考慮しておきたいと思うものである.第3章で,Charles Burstoneは咬合の安定性に影響すると考えられる多くの要因について考察している.歯根膜線維と歯肉線維は一見,矯正治療による歯の移動期間中に再構成されるようにみえるが,ある場合には,これらの線維が矯正治療後に短期間で後戻りを生じる原因となると考えられる.このような問題に対して,とくに捻転の改善後などの再発防止策に提案されているのがオーバートリートメント(不正な状態を過剰に矯正することによって後戻りの分をあらかじめ補っておくこと)や,保定,および歯槽頂部歯肉線維切断術である.上顎正中離開の症例で,矯正治療により閉鎖した空 が後戻りする原因として,上述のような再発の機構が関与するといわれている.
このほかに咬合の安定性を左右する重要な要因として軟組織が接触したときに加わる圧力があげられる.歯槽骨内での歯列の全体的な排列のあり方はきわめて重要な意味をもつものであるが,口腔内と口腔外の軟組織の均衡,およびその機能の均衡がとれていることが歯槽基底上の歯の最終的な位置を決める本質的な要因である(図3).
この考え方は,実際どの程度まで正しいのであろうか 矯正治療計画をたてるうえで選択に苦悩するのは,おもに叢生歯列における抜歯に関してである.このような場合は,矯正治療によって安定した咬合が得られるかどうかが,患者の抜歯の可否を決めるためのおもな要因であることは明らかである.近年の矯正治療では抜歯を少なくする傾向にある.このような傾向は,歯科矯正学の歴史のなかで不定期な変動の繰り返しとして起こってきたもののようである.このような傾向は,少なくともその一部分は,われわれの評価の根拠や評価行動が確かな事実に基づくものではなく,むしろ実証に基づかない主張による意見や風潮によって左右されるものであることを示すものといえる.
この抜歯に対する考え方についての最新の研究成績が,Jeffrey BurzinとRavindra Nandaによって第4章に,John C.Gormanによって第5章に,Robert M.Littleによって第6章に,Cyril Sadowskyによって第7章に著述されている.
Gormanは,矯正治療の結果から得た咬合が安定したものとなるかどうかが,抜歯・非抜歯論争に決着をつける一つの指標であると考えている.彼は矯正治療のなかで,抜歯による療法が歯列弓長の不足の著しい症例や上顎前突症例の治療などには必要であることは明らかだとしている.しかし,長期的にみた場合,適切な前歯の排列を達成するうえで,抜歯が本当に有効なものであるかどうかに疑問を投げかけている.この指摘は,歯列の前方限界を正しく見定めることが矯正治療で得た咬合の安定性を得るための鍵であるとする,C.H.Tweedの著述を検討しなおす必要があることを示すものである.実際,Tweedは,ほとんどの症例で,下顎切歯部に対して長期間にわたり固定式の保定を行う必要があると主張していたのである.Gormanは,小臼歯の抜去が下顎切歯の長期的な安定を保証するものではないと結論している.
Littleは,Seattleのワシントン大学で現在継続中の矯正治療後の咬合の安定性についての研究で得られた豊富な研究成績に付言して,この長期にわたる研究から得た結論のなかには,簡明な治療上の指針を示す理論を求める矯正医が失望するような事実がみられたと述べている.この一連の研究からみて,治療開始時に行った研究成績,あるいは治療終了時に行った研究成績のいずれからも,治療後の前歯の安定性や後戻りの可能性を予測できる指標は得られなかった.
これと同様の結論が,Chicagoのイリノイ大学で行われた研究から得られ,Sadowskyによってまとめられて本書に報告されている.そのなかで彼は,矯正治療後の患者の多くにわずかな程度の後戻りがみられるが,程度がわずかであれば,それがすぐに治療が不成功に終わったことを示すものだと考えるべきではないと主張している.むしろこの研究成績は,治療終了前に適切なディテーリング(仕上げ操作)を施すこと,および長期に保定をすることが必要であることを示したものといえる.
BurzinとNandaは 過蓋咬合の治療には慎重な治療計画が必要で また無定見な咬合平面のレベリングは治療後の咬合の安定性の観点からみて,正しい治療方法とはいえないと強調している.彼らは,過蓋咬合を改善する目的で切歯の圧下を行うことが,咬合の安定性からみて効果的な治療法の一つであることを示している.
第8章では,Richard G.Alexanderは矯正治療後の咬合の長期安定性は,診断と治療計画に始まり,治療操作を経て保定に至るまでの一連の治療と切り離して考えることができないものである,と強く主張している.彼は矯正装置の除去と保定に関して,その管理のあり方をよく整理されたかたちで経過を追って保定開始に至る手順を述べている.またそのなかで,大変困難でまた非常に重要なこの治療時期の効果的かつ実際的な患者管理を述べるとともに,長期にわたって保定を続けることの必要性を述べている.
第9章では,Bjorn U.Zachrissonが詳細な歯冠形態修正について多数の症例を提示している.このなかには,矯正治療で得た咬合の長期的安定性を得る目的で行う,意図的な歯の形態修正や審美的操作が含まれている.
第12章でArthur T.Storeyは,矯正治療後の咬合の安定性の問題と,矯正学分野のもう一つの大きい問題である顎関節機能と,その機能障害に関して矯正治療がどのような影響を及ぼすのかという問題を結びつけて述べている.これは,Storeyが矯正治療後の咬合の安定性の定義を単に形態的な基準で考えるところから,機能の維持を考えに入れるところまで拡大したことを意味する.彼は顎関節機能に対して矯正治療が影響を及ぼす可能性のあるいろいろな要因について慎重に調査を行い,その問題点を明らかにして,これに照準を合わせた調査研究の必要性を述べている.
第11章では,これと同様の手法で行われた研究についてDietmar Kubein-MeesenburgとHans Na gerlが著述している.彼らは咬合と顎関節の機能との関係について,生力学的な観点から分析した.この研究は,矯正治療によって咬合が細部にわたるまで正しく仕上げられていることが,治療後に健康な関節機能が保たれるかどうかを決定する重要な要因の一つであることを強く示している.
第10章で,Peter M.Sinclairは近年発展目覚ましい外科的矯正治療分野の後戻りについての見解を述べている.外科矯正の場合の後戻りは,本来手術によって切断された歯牙歯槽部が,外科矯正術後に互いに安定した位置関係を維持できるかどうかが問題であるが,近年,骨片の固定法が改良されたため術後の咬合の安定性は劇的に向上し,外科手術結果の経過予測も以前より改善されたと述べている.
近年,矯正治療後の咬合の安定を得るための基礎的機構ならびに矯正治療効果などについての客観的な臨床研究が開始されている.矯正治療後の歯列の安定性には複数の要因がかかわっており,矯正治療は,単に診断に始まり保定装置の装着で終わるだけのものではない.
矯正治療後に咬合を安定させるためには長期計画が必要である.この長期計画は最初の矯正相談のときから始めなければならないし,また治療中のみならず治療後もこれに協力してもらう必要があることを患者とその両親に説明しておくべきである(図4).また保定装置撤去後に軽度の叢生が再発することがあることも,よく説明しておく必要がある.さらに,多少の後戻りは一種の生理的な現象であることを患者に説明しておくことも大切である.しかし,矯正医がこのことを理由にして,自分の不適切な診断や治療計画あるいは不適当な保定装置の使用(図5〜8)を隠蔽してはならない.矯正医が後戻りや矯正治療後の咬合の安定性について,もっと深い理解と知識を得るようになるまでは,これらの問題について適切な患者教育を行うとともに,長期保定に努めることが必要である.
本書の紹介
本書は,1990年コネチカット大学において“矯正治療後の咬合の安定性と保定”をテーマとして開催されたシンポジウムの内容をまとめたものである.Richard G.Alexander,Charles J.Burstone,Jeffrey Burzin,John C.Gorman,Dietmar Kubein-Meesenburg,Robert M.Little,Hans Na gerl,Ram S.Nanda,Ravindra Nanda,Surender K.Nanda,Ib Leth Nielsen,Cyril Sadowsky,Peter M.Sinclair,Arthur T.Storey,Bjorn U.ZachrissonそしてJoseph Zernikら,多数の著名な臨床家や研究者により12章にわたって著述されている.従来,保定と再発に関する多くの研究が発表されてきたが,本書では,矯正治療のなかでもっとも重要な部分でありながら看過されがちであった,矯正装置撤去後に生じる臨床上の諸問題について,その解決のための分析と対応策を考えるうえで必要な広範囲にわたる学識を開陳した力作である.
本書では,成長発育と治療後の安定性,矯正治療結果の安定性に関する予後判定,過蓋咬合治療結果の安定性,下顎切歯部歯列弓形態の長期安定性に及ぼす小臼歯抜去の影響,矯正治療後の歯列弓形態の安定性と後戻り,そのほか,治療と保定ならびに治療結果の長期安定性,よりよい咬合のための仕上がりと保定の操作,外科矯正後の長期安定性,生力学的な観点での咬合の安定性,TMDの一因となるような咬合のありかた等々について,それぞれ各章で分担執筆されている.これらは,矯正治療施術後の管理期間中にみられる諸問題点をあらゆる角度から克服し,解決する助けとなるものである.本書の内容は読者にとってきわめて魅力的なものばかりである.
本書の意義は,矯正治療結果の長期にわたる安定性とそれに関連する問題点に重点をおいているところであろう.とくに再発の理由に関する包み隠しのない諸家の見解は,矯正医,大学院生ならびに歯学生にとって必読の価値がある.また,本書はW.B.Saunders社の見事な編集によって,的確な図解と多くの表が提示されており,歯科矯正学の知識に重要な知見を加えるものである.
T.M.Graber xixii
序
矯正治療結果の長期安定性の獲得は,歯科矯正臨床のめざす重要課題の一つである.
しかしながら,保定と咬合の安定性にかかわる要因については,診断や治療方針ならびに治療術式などの分野が注目されているほどには重要視されないところがあった.長年にわたって,歯科矯正学領域の諸問題について多くの優れた教科書が発刊されてきたが,本書は矯正患者の治療後の咬合の安定性を高め,保定効果の向上を達成するための最新にして,適切な学識をもたらすものとしてはじめて刊行された書籍である.
1990年の冬コネチカット州のHartfordにおいて著名な矯正家ならびに歯科矯正学の研究者たちが集まって,矯正患者の治療後の咬合の安定性と保定に関して,現在の最高水準のシンポジウムを開催した.コネチカットは極寒のなかにあり,窓外は吹雪が吹き荒れていたが,会場内は熱気にあふれて,講師も聴衆も参加者全員が熱中して矯正治療後の咬合の安定性の限界について考え,また,どのように治療術式を改良すれば,矯正治療後の咬合の安定性を短期あるいは長期にわたって強化することができるかについて検討した.そのときの努力の結果が,この本に盛り込まれている.かならずや,本書のなかから臨床家の諸氏は咬合の安定性に関する知識や,それを向上させる方法を知るための多くの情報を見つけだすことができるであろう.
ここであらためて,本書の執筆者諸氏の献身的な努力と苦労とご協力に感謝したい.またW.B.Saunders社の編集部主任Paymond R.Kersey氏ならびに編集部の諸氏のご協力に対して謝意を表し,とくに最終の編集にご協力くださったDr.Flena-Lee Ritoli,カバーデザインを作製されたDr.Andrew Kuhlbergに感謝する.
コネチカット州Farmingtonにて
1993年3月
Ravindra Nanda
Charles J.Burstone
訳者序
矯正治療後の保定をどのように行い,治療結果として得た咬合の長期安定性をどのように維持させるかは臨床家にとって一大命題であり,これこそ臨床矯正の根幹をなすものである.この問題の解明なくして矯正歯科に携わることはできない.矯正治療後の咬合の安定性成立に関する要因は多岐にわたり,互いに複雑に影響しあっているため,従来,このことに関する歯科矯正学の教育の実情は,いわゆる経験的な伝授に頼って行われてきたといっても過言ではなく,むしろその実体について明言を避けていたのではないかとの感すらある.われわれは日常矯正臨床上でこの問題をより深く,より幅広い範囲まで知りたいと思えば思うほど,むずかしさにつきあたることが多いものである.
本書は,矯正治療のなかでもっとも重要でありながら,ともすれば見過ごされがちであった矯正治療後の歯列・咬合の安定性について,欧米の多くの学識経験豊かな有名教授であり,有名矯正臨床家でもある諸氏が,合同執筆によりその考え方を開陳したものである.残念ながら,わが国においてはこのような著書はなく,アメリカにおいても,このような長期にわたる臨床成績を研究した結果をまとめて考察したものはみられない.本書のなかで引用された多くの臨床研究ならびに臨床成績や,この問題についての多くの権威者が著述した包み隠しのない見解はきわめて貴重なものであって,これらはわが国の矯正歯科界に対しても多大の貢献をなすものといえる.
われわれは,本書の意味するところがきわめて重大であることを十分に理解するものである.しかし,われわれ浅学非才の集まりゆえ,奥深い解釈に踏み込みえず,十分に考えを巡らすことができなかったため,本書の真意を伝ええなかったところも多々あることと思う.われわれがみずからの無知蒙昧を省みず本書の理解を試みた非礼に対し,ご寛容を乞うものであるが,真意は,本書がわが国の歯科矯正学ならびに矯正歯科臨床の一段の進歩発展に資することを心から願うものである.また本書は歯科矯正学教科書あるいは矯正臨床指導書としてきわめて優れた内容が盛られているので,大学院生や矯正専門医はもちろん,歯学部学生にとっても,学術研究・臨床研究の助けとして少しでも役だつことができれば,これに過ぎる喜びはない.
ここで,本書の訳書に関して多くの先輩,友人,同僚から数々のご助言・ご教示をいただいたことに対して感謝の意を表したい.さらに,表記の訳者のほかに別記する諸氏が尽力くださったことに心から感謝する.
終わりにあたり,翻訳許可をくださったR.Nanda先生,C.J.Burstone先生,翻訳許可に関して種々ご尽力くださったT.M.Graber先生ならびにW.B.Saunders社のF.McLaughlin氏に深く謝意を表したい.また医歯薬出版株式会社三浦裕士社長をはじめ編集部諸氏のご協力に心からお礼申し上げる.
平成7年5月 中後忠男
Ravindra Nanda and Joseph Zernik
序章
矯正治療後に後戻りの問題があることや,それを防止するためには保定が必要であることはよく知られている.治療着手にあたって,まず矯正医が考えるべき重要な事項は,矯正治療で得た咬合の安定をどのように確保するかである.しかし,咬合の長期安定性を達成するための学識や技能および咬合の安定性の裏にある種々の潜在的要因については,現在のところ十分に理論的に証明されたものはきわめて少ない.これは動的矯正治療終了後,治療で得た咬合を保定する操作が,ときとして長期にわたって継続する必要があることからも明らかである.
矯正治療後の咬合の不安定性に関与する要因は次の2つの項目に分類できる.
1.歯列と咬合の成長,成熟,老化の過程に関連する変化
2.矯正治療によって得られた咬合に特有の不安定性が関連する変化
1.に分類される咬合の不安定性は,しばしば長期にわたってみられる.このなかには,たとえば被蓋が深くなっていくなどの青年期前,あるいは青年期における成長に関連した変化が含まれる.このほか,極端な例では上下顎骨の成長の不調和に関連して生じる諸変化などもみられる.
成熟に関連する変化のなかには,治療前にみられた下顎切歯部の叢生が元の状態より,さらにその叢生程度が増悪した場合もあげられる(図1).歯列の加齢変化は,また歯根膜炎の発生率の増加に関連している.このような場合には,歯が一部喪失した患者にみられる複雑な歯の位置の変化や,前歯部の空 ,前歯の唇側への倒れこみを伴っていることもある.これらの加齢変化はいずれも,過去の矯正治療加療の有無に関係なく,どの患者にもよく起こりうることである(図2).このようなことがあるにもかかわらず,矯正患者は時間と費用を費やして得た矯正治療終了時の美しい歯並びが安定しているものと思っている.
これらの問題に関して第1章でIb Leth Nielsenが詳細に分析し,上下顎骨の成長とそれに付随する歯牙歯槽部の変化が,矯正治療の術後変化と治療結果の安定性にどのような影響を与えるかについての問題を論じている.Nielsenは,たとえば,かりにその患者に特有の下顎頭の成長方向に逆らって矯正治療効果が導かれたような場合に,とくに垂直方向への増加を生じさせたようなときには,その治療効果の安定性は疑わしいものであろうし,後戻りの傾向が生じることになると述べている.このNielsenの見解は,下顎の成長方向の予測を正確に行って,成長期間中を通じて成長制御に関与しようとする考え方をもつ矯正医に対して,一つの異論を唱えるものである.
Nielsenはさらに矯正治療後の咬合の安定性という観点からみて,現在,われわれがもつ成長発育についての知識をもとにして考えだされた矯正治療に最適な時期について疑問を投げかけている.そして彼は,一部の症例においてはおそらく成長変化が咬合の安定性を左右する主要な要因の一つであるという見解のもとに,これらの患者の最終的な治療,とくに抜歯療法は,顔面骨格の成長パターンが明らかにあらわれてくる時期まで遅らせるのがよい,との提案をしている.混合歯列期における矯正治療が一般的になりつつある現在,この見解はたしかに特筆に値するものであり,十分検討される必要がある.
序章
“矯正治療後の咬合の安定性と保定”を読まれるにあたって 第2章で,Ram S.NandaとSurender K.Nandaはともに,成長発育に関連する変化が矯正治療施術後の咬合の変化や後戻りに影響することがよくある,という立場をとっている.そして頭蓋顔面骨格の特定の構成部分の変化に関する彼らの研究成果から,骨格の変化はとくに男子において30歳代まで続くものであることを強調している.
2.に分類できる咬合の不安定性のなかには,明らかに後戻りという用語で表現できる変化と,矯正治療によってつくられた咬合に特有の不安定性によって発現したとすることができる変化とが含まれている.このような変化は比較的局所的なもので,たとえば,治療中に改善された小臼歯の捻転が治療後に後戻りした場合などがある.とくに前歯にみられる,このようなタイプの捻転の後戻りは,矯正医と患者の両者にとって深刻な悩みである.実際,診断や治療計画のいかんにかかわらず,上顎中切歯部に捻転がある場合には,これが患者の初診時の主訴となることが多い.したがって,その叢生の後戻りが比較的小さな局所的なものであっても,実際にはかなりの問題を引き起こすことになりかねない.また,後戻りはより広範囲にわたって咬合の様相に影響を与えるものである.たとえば,上顎あるいは下顎の前歯部や臼歯部の叢生の再発や,交叉咬合の再発,抜歯部位の空 閉鎖後の再開離,過蓋咬合治療例のオーバーバイトの増加などの咬合の変化が生じてくる.
安定した咬合をつくることが矯正治療の重要な目標であるので,矯正医ならだれも,できれば治療着手前に診断と治療計画をたてる際に,これらの事柄について分析検討を行い,考慮しておきたいと思うものである.第3章で,Charles Burstoneは咬合の安定性に影響すると考えられる多くの要因について考察している.歯根膜線維と歯肉線維は一見,矯正治療による歯の移動期間中に再構成されるようにみえるが,ある場合には,これらの線維が矯正治療後に短期間で後戻りを生じる原因となると考えられる.このような問題に対して,とくに捻転の改善後などの再発防止策に提案されているのがオーバートリートメント(不正な状態を過剰に矯正することによって後戻りの分をあらかじめ補っておくこと)や,保定,および歯槽頂部歯肉線維切断術である.上顎正中離開の症例で,矯正治療により閉鎖した空 が後戻りする原因として,上述のような再発の機構が関与するといわれている.
このほかに咬合の安定性を左右する重要な要因として軟組織が接触したときに加わる圧力があげられる.歯槽骨内での歯列の全体的な排列のあり方はきわめて重要な意味をもつものであるが,口腔内と口腔外の軟組織の均衡,およびその機能の均衡がとれていることが歯槽基底上の歯の最終的な位置を決める本質的な要因である(図3).
この考え方は,実際どの程度まで正しいのであろうか 矯正治療計画をたてるうえで選択に苦悩するのは,おもに叢生歯列における抜歯に関してである.このような場合は,矯正治療によって安定した咬合が得られるかどうかが,患者の抜歯の可否を決めるためのおもな要因であることは明らかである.近年の矯正治療では抜歯を少なくする傾向にある.このような傾向は,歯科矯正学の歴史のなかで不定期な変動の繰り返しとして起こってきたもののようである.このような傾向は,少なくともその一部分は,われわれの評価の根拠や評価行動が確かな事実に基づくものではなく,むしろ実証に基づかない主張による意見や風潮によって左右されるものであることを示すものといえる.
この抜歯に対する考え方についての最新の研究成績が,Jeffrey BurzinとRavindra Nandaによって第4章に,John C.Gormanによって第5章に,Robert M.Littleによって第6章に,Cyril Sadowskyによって第7章に著述されている.
Gormanは,矯正治療の結果から得た咬合が安定したものとなるかどうかが,抜歯・非抜歯論争に決着をつける一つの指標であると考えている.彼は矯正治療のなかで,抜歯による療法が歯列弓長の不足の著しい症例や上顎前突症例の治療などには必要であることは明らかだとしている.しかし,長期的にみた場合,適切な前歯の排列を達成するうえで,抜歯が本当に有効なものであるかどうかに疑問を投げかけている.この指摘は,歯列の前方限界を正しく見定めることが矯正治療で得た咬合の安定性を得るための鍵であるとする,C.H.Tweedの著述を検討しなおす必要があることを示すものである.実際,Tweedは,ほとんどの症例で,下顎切歯部に対して長期間にわたり固定式の保定を行う必要があると主張していたのである.Gormanは,小臼歯の抜去が下顎切歯の長期的な安定を保証するものではないと結論している.
Littleは,Seattleのワシントン大学で現在継続中の矯正治療後の咬合の安定性についての研究で得られた豊富な研究成績に付言して,この長期にわたる研究から得た結論のなかには,簡明な治療上の指針を示す理論を求める矯正医が失望するような事実がみられたと述べている.この一連の研究からみて,治療開始時に行った研究成績,あるいは治療終了時に行った研究成績のいずれからも,治療後の前歯の安定性や後戻りの可能性を予測できる指標は得られなかった.
これと同様の結論が,Chicagoのイリノイ大学で行われた研究から得られ,Sadowskyによってまとめられて本書に報告されている.そのなかで彼は,矯正治療後の患者の多くにわずかな程度の後戻りがみられるが,程度がわずかであれば,それがすぐに治療が不成功に終わったことを示すものだと考えるべきではないと主張している.むしろこの研究成績は,治療終了前に適切なディテーリング(仕上げ操作)を施すこと,および長期に保定をすることが必要であることを示したものといえる.
BurzinとNandaは 過蓋咬合の治療には慎重な治療計画が必要で また無定見な咬合平面のレベリングは治療後の咬合の安定性の観点からみて,正しい治療方法とはいえないと強調している.彼らは,過蓋咬合を改善する目的で切歯の圧下を行うことが,咬合の安定性からみて効果的な治療法の一つであることを示している.
第8章では,Richard G.Alexanderは矯正治療後の咬合の長期安定性は,診断と治療計画に始まり,治療操作を経て保定に至るまでの一連の治療と切り離して考えることができないものである,と強く主張している.彼は矯正装置の除去と保定に関して,その管理のあり方をよく整理されたかたちで経過を追って保定開始に至る手順を述べている.またそのなかで,大変困難でまた非常に重要なこの治療時期の効果的かつ実際的な患者管理を述べるとともに,長期にわたって保定を続けることの必要性を述べている.
第9章では,Bjorn U.Zachrissonが詳細な歯冠形態修正について多数の症例を提示している.このなかには,矯正治療で得た咬合の長期的安定性を得る目的で行う,意図的な歯の形態修正や審美的操作が含まれている.
第12章でArthur T.Storeyは,矯正治療後の咬合の安定性の問題と,矯正学分野のもう一つの大きい問題である顎関節機能と,その機能障害に関して矯正治療がどのような影響を及ぼすのかという問題を結びつけて述べている.これは,Storeyが矯正治療後の咬合の安定性の定義を単に形態的な基準で考えるところから,機能の維持を考えに入れるところまで拡大したことを意味する.彼は顎関節機能に対して矯正治療が影響を及ぼす可能性のあるいろいろな要因について慎重に調査を行い,その問題点を明らかにして,これに照準を合わせた調査研究の必要性を述べている.
第11章では,これと同様の手法で行われた研究についてDietmar Kubein-MeesenburgとHans Na gerlが著述している.彼らは咬合と顎関節の機能との関係について,生力学的な観点から分析した.この研究は,矯正治療によって咬合が細部にわたるまで正しく仕上げられていることが,治療後に健康な関節機能が保たれるかどうかを決定する重要な要因の一つであることを強く示している.
第10章で,Peter M.Sinclairは近年発展目覚ましい外科的矯正治療分野の後戻りについての見解を述べている.外科矯正の場合の後戻りは,本来手術によって切断された歯牙歯槽部が,外科矯正術後に互いに安定した位置関係を維持できるかどうかが問題であるが,近年,骨片の固定法が改良されたため術後の咬合の安定性は劇的に向上し,外科手術結果の経過予測も以前より改善されたと述べている.
近年,矯正治療後の咬合の安定を得るための基礎的機構ならびに矯正治療効果などについての客観的な臨床研究が開始されている.矯正治療後の歯列の安定性には複数の要因がかかわっており,矯正治療は,単に診断に始まり保定装置の装着で終わるだけのものではない.
矯正治療後に咬合を安定させるためには長期計画が必要である.この長期計画は最初の矯正相談のときから始めなければならないし,また治療中のみならず治療後もこれに協力してもらう必要があることを患者とその両親に説明しておくべきである(図4).また保定装置撤去後に軽度の叢生が再発することがあることも,よく説明しておく必要がある.さらに,多少の後戻りは一種の生理的な現象であることを患者に説明しておくことも大切である.しかし,矯正医がこのことを理由にして,自分の不適切な診断や治療計画あるいは不適当な保定装置の使用(図5〜8)を隠蔽してはならない.矯正医が後戻りや矯正治療後の咬合の安定性について,もっと深い理解と知識を得るようになるまでは,これらの問題について適切な患者教育を行うとともに,長期保定に努めることが必要である.
本書の紹介
本書は,1990年コネチカット大学において“矯正治療後の咬合の安定性と保定”をテーマとして開催されたシンポジウムの内容をまとめたものである.Richard G.Alexander,Charles J.Burstone,Jeffrey Burzin,John C.Gorman,Dietmar Kubein-Meesenburg,Robert M.Little,Hans Na gerl,Ram S.Nanda,Ravindra Nanda,Surender K.Nanda,Ib Leth Nielsen,Cyril Sadowsky,Peter M.Sinclair,Arthur T.Storey,Bjorn U.ZachrissonそしてJoseph Zernikら,多数の著名な臨床家や研究者により12章にわたって著述されている.従来,保定と再発に関する多くの研究が発表されてきたが,本書では,矯正治療のなかでもっとも重要な部分でありながら看過されがちであった,矯正装置撤去後に生じる臨床上の諸問題について,その解決のための分析と対応策を考えるうえで必要な広範囲にわたる学識を開陳した力作である.
本書では,成長発育と治療後の安定性,矯正治療結果の安定性に関する予後判定,過蓋咬合治療結果の安定性,下顎切歯部歯列弓形態の長期安定性に及ぼす小臼歯抜去の影響,矯正治療後の歯列弓形態の安定性と後戻り,そのほか,治療と保定ならびに治療結果の長期安定性,よりよい咬合のための仕上がりと保定の操作,外科矯正後の長期安定性,生力学的な観点での咬合の安定性,TMDの一因となるような咬合のありかた等々について,それぞれ各章で分担執筆されている.これらは,矯正治療施術後の管理期間中にみられる諸問題点をあらゆる角度から克服し,解決する助けとなるものである.本書の内容は読者にとってきわめて魅力的なものばかりである.
本書の意義は,矯正治療結果の長期にわたる安定性とそれに関連する問題点に重点をおいているところであろう.とくに再発の理由に関する包み隠しのない諸家の見解は,矯正医,大学院生ならびに歯学生にとって必読の価値がある.また,本書はW.B.Saunders社の見事な編集によって,的確な図解と多くの表が提示されており,歯科矯正学の知識に重要な知見を加えるものである.
T.M.Graber xixii
序
矯正治療結果の長期安定性の獲得は,歯科矯正臨床のめざす重要課題の一つである.
しかしながら,保定と咬合の安定性にかかわる要因については,診断や治療方針ならびに治療術式などの分野が注目されているほどには重要視されないところがあった.長年にわたって,歯科矯正学領域の諸問題について多くの優れた教科書が発刊されてきたが,本書は矯正患者の治療後の咬合の安定性を高め,保定効果の向上を達成するための最新にして,適切な学識をもたらすものとしてはじめて刊行された書籍である.
1990年の冬コネチカット州のHartfordにおいて著名な矯正家ならびに歯科矯正学の研究者たちが集まって,矯正患者の治療後の咬合の安定性と保定に関して,現在の最高水準のシンポジウムを開催した.コネチカットは極寒のなかにあり,窓外は吹雪が吹き荒れていたが,会場内は熱気にあふれて,講師も聴衆も参加者全員が熱中して矯正治療後の咬合の安定性の限界について考え,また,どのように治療術式を改良すれば,矯正治療後の咬合の安定性を短期あるいは長期にわたって強化することができるかについて検討した.そのときの努力の結果が,この本に盛り込まれている.かならずや,本書のなかから臨床家の諸氏は咬合の安定性に関する知識や,それを向上させる方法を知るための多くの情報を見つけだすことができるであろう.
ここであらためて,本書の執筆者諸氏の献身的な努力と苦労とご協力に感謝したい.またW.B.Saunders社の編集部主任Paymond R.Kersey氏ならびに編集部の諸氏のご協力に対して謝意を表し,とくに最終の編集にご協力くださったDr.Flena-Lee Ritoli,カバーデザインを作製されたDr.Andrew Kuhlbergに感謝する.
コネチカット州Farmingtonにて
1993年3月
Ravindra Nanda
Charles J.Burstone
訳者序
矯正治療後の保定をどのように行い,治療結果として得た咬合の長期安定性をどのように維持させるかは臨床家にとって一大命題であり,これこそ臨床矯正の根幹をなすものである.この問題の解明なくして矯正歯科に携わることはできない.矯正治療後の咬合の安定性成立に関する要因は多岐にわたり,互いに複雑に影響しあっているため,従来,このことに関する歯科矯正学の教育の実情は,いわゆる経験的な伝授に頼って行われてきたといっても過言ではなく,むしろその実体について明言を避けていたのではないかとの感すらある.われわれは日常矯正臨床上でこの問題をより深く,より幅広い範囲まで知りたいと思えば思うほど,むずかしさにつきあたることが多いものである.
本書は,矯正治療のなかでもっとも重要でありながら,ともすれば見過ごされがちであった矯正治療後の歯列・咬合の安定性について,欧米の多くの学識経験豊かな有名教授であり,有名矯正臨床家でもある諸氏が,合同執筆によりその考え方を開陳したものである.残念ながら,わが国においてはこのような著書はなく,アメリカにおいても,このような長期にわたる臨床成績を研究した結果をまとめて考察したものはみられない.本書のなかで引用された多くの臨床研究ならびに臨床成績や,この問題についての多くの権威者が著述した包み隠しのない見解はきわめて貴重なものであって,これらはわが国の矯正歯科界に対しても多大の貢献をなすものといえる.
われわれは,本書の意味するところがきわめて重大であることを十分に理解するものである.しかし,われわれ浅学非才の集まりゆえ,奥深い解釈に踏み込みえず,十分に考えを巡らすことができなかったため,本書の真意を伝ええなかったところも多々あることと思う.われわれがみずからの無知蒙昧を省みず本書の理解を試みた非礼に対し,ご寛容を乞うものであるが,真意は,本書がわが国の歯科矯正学ならびに矯正歯科臨床の一段の進歩発展に資することを心から願うものである.また本書は歯科矯正学教科書あるいは矯正臨床指導書としてきわめて優れた内容が盛られているので,大学院生や矯正専門医はもちろん,歯学部学生にとっても,学術研究・臨床研究の助けとして少しでも役だつことができれば,これに過ぎる喜びはない.
ここで,本書の訳書に関して多くの先輩,友人,同僚から数々のご助言・ご教示をいただいたことに対して感謝の意を表したい.さらに,表記の訳者のほかに別記する諸氏が尽力くださったことに心から感謝する.
終わりにあたり,翻訳許可をくださったR.Nanda先生,C.J.Burstone先生,翻訳許可に関して種々ご尽力くださったT.M.Graber先生ならびにW.B.Saunders社のF.McLaughlin氏に深く謝意を表したい.また医歯薬出版株式会社三浦裕士社長をはじめ編集部諸氏のご協力に心からお礼申し上げる.
平成7年5月 中後忠男
本書の紹介/ix
序/xi
訳者序/xiii
序章 “矯正治療後の咬合の安定性と保定”を読まれるにあたって……1
Ravindra Nanda and Joseph Zernik
第1章 成長変化が矯正治療後の咬合の安定性に及ぼす影響……9
Ib Leth Nielsen
はじめに……9
顔面の成長……12
下顎骨の成長……14
咬合の安定性と下顎骨の成長に伴う回転……17
前方回転……17
後方回転……18
咬合の安定性と上顎の成長……19
顎骨発育の異形成と補償……20
歯牙歯槽性の発育と咬合……20
抜歯治療と非抜歯治療,その治療結果の安定性……20
治療時期……21
要約……30
参考文献/30
第2章 矯正治療後の顎顔面成長が長期保定ならびに咬合の安定性に及ぼす影響……33
Ram S.Nanda and Surender K.Nanda
成長に伴う顎顔面骨格の変化……34
要約……38
参考文献/40
第3章 矯正治療結果の安定性について……41
Charles J.Burstone
正常な成長変化,整形的な治療変化,および術後変化(後戻り)……43
治療期間中に生じる下顎の回転と咬合の安定性……46
歯列弓幅径とその安定性……47
切歯の位置とその安定性……50
歯の位置の安定性に影響する歯列内の要因……51
機能時の咬合と歯列の安定性……52
要約……54
参考文献/55
第4章 過蓋咬合改善後の咬合の安定性……57
Jeffrey Burzin and Ravindra Nanda
圧下の生力学……58
動物実験による歯の圧下の研究……58
過蓋咬合改善後の咬合の安定性……59
研究資料と方法……60
被験者……60
上顎切歯圧下に応用した装置……62
研究方法……63
結果……65
考察……72
参考文献/74
第5章 小臼歯抜歯が矯正治療後の下顎切歯位置の長期安定性に及ぼす影響……77
John C.Gorman
文献的考察……78
考察――筆者の保定についての考え方……82
結論……85
参考文献/90
第6章 歯列の排列状態の安定性と後戻り……93
Robert M.Little
はじめに……93
歯列弓長が不足している場合……94
永久歯列初期における小臼歯抜歯とその長期経過……94
乳歯と小臼歯の連続抜去法とその長期経過……96
混合歯列期間中における歯列弓長の拡大とその長期経過……96
歯列弓長が十分な場合……98
正常咬合者についての長期経過観察(矯正治療を加えていない者)……98
空歯列についての長期経過観察……99
臨床的意義……100
要約……101
参考文献/102
第7章 矯正治療後の咬合の長期安定性……103
Cyril Sadowsky
はじめに……103
資料……103
研究結果……104
考察……107
参考文献/109
第8章 咬合の長期安定性を得るための矯正治療と保定……111
Richard G.Alexander
診断時ならびに治療計画時から保定を考えなければならない……111
診断と治療計画の目標……111
セファロから得られる診断情報の利用……112
上下切歯軸角……112
下顎第一大臼歯の位置……112
下顎切歯のアンギュレーション(近遠心的軸傾斜)(アーティスティックポジショニング)……113
筋組織……113
動的治療……113
治療結果の安定性を考慮にいれた矯正装置……114
開咬症例の場合の注意……115
捻転のオーバーコレクション……116
歯槽頂部歯肉線維切断術……116
保定への秒読み(保定準備)……116
バンド撤去と保定……117
透明リテーナー……118
永久保定……118
後戻り……119
後戻りの原因と考えられるもの……119
治療後の安定性……119
下顎歯列弓の形態とその安定性……120
新しい治療方法が保定の概念を変えることになるかもしれない……121
結論……121
第9章 審美性ならびに安定性増進のための仕上げ操作と保定……123
Bjorn U.Zachrisson
はじめに……123
仕上げ過程での歯の位置づけ……123
上顎犬歯を欠如側切歯の代わりに用いたときの頬舌的歯冠幅径の問題……124
臨床歯冠のトルク……124
審美的な仕上げ操作……124
削合による歯冠形態修正……124
歯肉切除……128
保定……129
接着術式……132
しなやかで弾力性のある撚り線を用いた接着式リテーナーの成功率……134
過蓋咬合と舌側接着式リテーナー……134
接着式リテーナーの修理……136
要約……138
参考文献/138
第10章 外科的矯正治療後の顎態の長期安定性……141
Peter M.Sinclair
はじめに……141
資料……143
下顎骨の前方移動手術……143
ワイヤーを用いた骨縫合による骨固定……143
強固な骨固定……144
下顎骨の後方移動手術……146
外科的矯正手術後の下顎骨の安定性に影響を及ぼす要因……148
上顎骨の上方移動手術……149
ワイヤーを用いた骨縫合による骨固定……149
上顎骨の上方移動手術と下顎骨の前方移動手術の併用……151
上顎骨の垂直的位置の術後変化……151
下顎骨の前後的位置の術後変化……152
上顎骨の前方移動手術……153
上顎骨の下方移動手術……154
要約……154
参考文献/156
第11章 生力学的にみた咬合の安定性……159
Dietmar Kubein-Meesenburg and Hans Na¨gerl
はじめに……159
生力学的にみた歯と顎関節の理想的な解剖学的配置……160
後方の咬合要素としての顎関節……160
下顎前進運動時ならびに下顎後退運動時における顎関節による下顎頭の誘導機構……162
顎関節の機能空間と下顎頭運動の軌跡……163
前方にある咬合要素としての歯……164
前歯の配置に関する静力学……164
下顎前進運動時の前方での誘導機構……166
下顎後退運動時の前方での誘導機構……166
生力学的にみた前方および後方の下顎運動誘導機構間の関係(リンク機構)……167
中心位からの下顎前進運動……167
中心位からの下顎後退運動……171
前進運動と後退運動の下顎ギアシステムの切り換え機構……171
理論と所見……171
前進運動の誘導機構(前歯部)と後退運動の誘導機構(小臼歯部)の切り換え……174
頭蓋全体からみた前進運動用のギアシステムの配置……175
連結棒LMDと成長……178
解剖学的ならびに機能的特質……178
連結棒L を基準とした頭蓋の成長の重ね合わせ……179
Spee彎曲……180
生力学的にみたSpee彎曲と頭蓋の解剖学的形態の配置……180
前進運動ギアシステムとSpee彎曲……182
要約と総括……184
参考文献/186
第12章 機能的にみた矯正治療結果の安定性顎機能異常(顎関節症)と咬合……187
Arthur T.Storey
参考文献/197
索引/201
序/xi
訳者序/xiii
序章 “矯正治療後の咬合の安定性と保定”を読まれるにあたって……1
Ravindra Nanda and Joseph Zernik
第1章 成長変化が矯正治療後の咬合の安定性に及ぼす影響……9
Ib Leth Nielsen
はじめに……9
顔面の成長……12
下顎骨の成長……14
咬合の安定性と下顎骨の成長に伴う回転……17
前方回転……17
後方回転……18
咬合の安定性と上顎の成長……19
顎骨発育の異形成と補償……20
歯牙歯槽性の発育と咬合……20
抜歯治療と非抜歯治療,その治療結果の安定性……20
治療時期……21
要約……30
参考文献/30
第2章 矯正治療後の顎顔面成長が長期保定ならびに咬合の安定性に及ぼす影響……33
Ram S.Nanda and Surender K.Nanda
成長に伴う顎顔面骨格の変化……34
要約……38
参考文献/40
第3章 矯正治療結果の安定性について……41
Charles J.Burstone
正常な成長変化,整形的な治療変化,および術後変化(後戻り)……43
治療期間中に生じる下顎の回転と咬合の安定性……46
歯列弓幅径とその安定性……47
切歯の位置とその安定性……50
歯の位置の安定性に影響する歯列内の要因……51
機能時の咬合と歯列の安定性……52
要約……54
参考文献/55
第4章 過蓋咬合改善後の咬合の安定性……57
Jeffrey Burzin and Ravindra Nanda
圧下の生力学……58
動物実験による歯の圧下の研究……58
過蓋咬合改善後の咬合の安定性……59
研究資料と方法……60
被験者……60
上顎切歯圧下に応用した装置……62
研究方法……63
結果……65
考察……72
参考文献/74
第5章 小臼歯抜歯が矯正治療後の下顎切歯位置の長期安定性に及ぼす影響……77
John C.Gorman
文献的考察……78
考察――筆者の保定についての考え方……82
結論……85
参考文献/90
第6章 歯列の排列状態の安定性と後戻り……93
Robert M.Little
はじめに……93
歯列弓長が不足している場合……94
永久歯列初期における小臼歯抜歯とその長期経過……94
乳歯と小臼歯の連続抜去法とその長期経過……96
混合歯列期間中における歯列弓長の拡大とその長期経過……96
歯列弓長が十分な場合……98
正常咬合者についての長期経過観察(矯正治療を加えていない者)……98
空歯列についての長期経過観察……99
臨床的意義……100
要約……101
参考文献/102
第7章 矯正治療後の咬合の長期安定性……103
Cyril Sadowsky
はじめに……103
資料……103
研究結果……104
考察……107
参考文献/109
第8章 咬合の長期安定性を得るための矯正治療と保定……111
Richard G.Alexander
診断時ならびに治療計画時から保定を考えなければならない……111
診断と治療計画の目標……111
セファロから得られる診断情報の利用……112
上下切歯軸角……112
下顎第一大臼歯の位置……112
下顎切歯のアンギュレーション(近遠心的軸傾斜)(アーティスティックポジショニング)……113
筋組織……113
動的治療……113
治療結果の安定性を考慮にいれた矯正装置……114
開咬症例の場合の注意……115
捻転のオーバーコレクション……116
歯槽頂部歯肉線維切断術……116
保定への秒読み(保定準備)……116
バンド撤去と保定……117
透明リテーナー……118
永久保定……118
後戻り……119
後戻りの原因と考えられるもの……119
治療後の安定性……119
下顎歯列弓の形態とその安定性……120
新しい治療方法が保定の概念を変えることになるかもしれない……121
結論……121
第9章 審美性ならびに安定性増進のための仕上げ操作と保定……123
Bjorn U.Zachrisson
はじめに……123
仕上げ過程での歯の位置づけ……123
上顎犬歯を欠如側切歯の代わりに用いたときの頬舌的歯冠幅径の問題……124
臨床歯冠のトルク……124
審美的な仕上げ操作……124
削合による歯冠形態修正……124
歯肉切除……128
保定……129
接着術式……132
しなやかで弾力性のある撚り線を用いた接着式リテーナーの成功率……134
過蓋咬合と舌側接着式リテーナー……134
接着式リテーナーの修理……136
要約……138
参考文献/138
第10章 外科的矯正治療後の顎態の長期安定性……141
Peter M.Sinclair
はじめに……141
資料……143
下顎骨の前方移動手術……143
ワイヤーを用いた骨縫合による骨固定……143
強固な骨固定……144
下顎骨の後方移動手術……146
外科的矯正手術後の下顎骨の安定性に影響を及ぼす要因……148
上顎骨の上方移動手術……149
ワイヤーを用いた骨縫合による骨固定……149
上顎骨の上方移動手術と下顎骨の前方移動手術の併用……151
上顎骨の垂直的位置の術後変化……151
下顎骨の前後的位置の術後変化……152
上顎骨の前方移動手術……153
上顎骨の下方移動手術……154
要約……154
参考文献/156
第11章 生力学的にみた咬合の安定性……159
Dietmar Kubein-Meesenburg and Hans Na¨gerl
はじめに……159
生力学的にみた歯と顎関節の理想的な解剖学的配置……160
後方の咬合要素としての顎関節……160
下顎前進運動時ならびに下顎後退運動時における顎関節による下顎頭の誘導機構……162
顎関節の機能空間と下顎頭運動の軌跡……163
前方にある咬合要素としての歯……164
前歯の配置に関する静力学……164
下顎前進運動時の前方での誘導機構……166
下顎後退運動時の前方での誘導機構……166
生力学的にみた前方および後方の下顎運動誘導機構間の関係(リンク機構)……167
中心位からの下顎前進運動……167
中心位からの下顎後退運動……171
前進運動と後退運動の下顎ギアシステムの切り換え機構……171
理論と所見……171
前進運動の誘導機構(前歯部)と後退運動の誘導機構(小臼歯部)の切り換え……174
頭蓋全体からみた前進運動用のギアシステムの配置……175
連結棒LMDと成長……178
解剖学的ならびに機能的特質……178
連結棒L を基準とした頭蓋の成長の重ね合わせ……179
Spee彎曲……180
生力学的にみたSpee彎曲と頭蓋の解剖学的形態の配置……180
前進運動ギアシステムとSpee彎曲……182
要約と総括……184
参考文献/186
第12章 機能的にみた矯正治療結果の安定性顎機能異常(顎関節症)と咬合……187
Arthur T.Storey
参考文献/197
索引/201