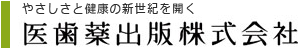訳者序文
1974年に初版が出版されたVojta教授の最初のモノグラフィーである“乳児の脳性運動障害“は,主として脳性運動障害の早期診断と早期治療について書かれたものであった.一方,本書は彼の治療原理である反射性移動運動の運動学について書かれたものである.実際に訓練を行うものにとっては永年にわたって本書の出版が待たれた.小児神経科医であるVojta教授が徹底して神経学を突き詰めていって,最終的に彼の恩師であるHenner教授の“神経学とは運動学”であるという考えを持ち続け,82歳という学究者としては高齢にもかかわらず,死の直前まで彼の生涯の仕事である乳児の運動障害の治療をまとめ上げていただいたことは,失礼な言い方かもしれないが,本当にほっとしている.
脳性運動障害の治療法は運動療法,薬物療法そして手術療法を含めると無数にあるといっても過言ではない.最近のように画像診断が進歩したといっても,運動発達過程の障害である本疾患の病的運動発達のメカニズムはまだ解明されていない.治療の根拠はあくまで筋トーヌスをいかにコントロールし,二次的に発生した変形をいかに矯正するかに集約されている.本書では反射性移動運動を運動学的に詳細に分析し,脊柱を含めた全身の四肢関節の分節を運動学的にそして筋活動を筋電図で分析して,反射性腹這いと反射性寝返りの運動のなかにヒトの赤ちゃんが生まれてから立位,そして歩行に至るまでの全身の筋活動が含まれていることを見出し脳性運動障害の治療に応用している.訳者は本法を導入して以来,脳性運動障害だけでなく,二分脊椎,運動発達遅延,脊柱の側彎,後彎そして腰椎前彎などの姿勢異常,そして最近では学童期の学習障害,感覚統合障害の治療にも適応しSCSITの検査からも効果のあることを明らかにしている.ドイツでは成人の脳出血後の片麻痺の患者に応用し良好な成績が得られ,本邦でもその効果が確認されている.最近,重症脳性運動障害児の呼吸および嚥下障害の治療には,気管切開および胃瘻術がよく行われている.しかし,重症の脳性運動障害児に対して本法を施行することによってこのような手術療法を避けることができる.
本法に対する非難として,泣かすことによって精神的に負担をかけ,精神的に異常な子供になるということがよく聞かれる.このことに関して,Vojta教授がケルン時代に一卵性双生児のうち一児に対して治療した子供について,ミュンヘン小児センターの心理療法士が学童期に達した他児と比較調査した結果では,双生児の間には精神的そして心理的には差はなかったと報告されている.われわれの調査でも,双生児間に情緒面および心理面での差異はみられなかった.問題はむしろ治療されている子供よりも,治療を受けなかった子供にみられたという母親もあった.自分の兄弟が訓練で泣いても,自分もしてくれと言われ真似事でもしなければならなかったという母親もいた.Vojta法による訓練は基本的に母親がセラピストから指導を受け,母親が家庭で訓練を継続するのが治療の基本になっているので,Vojta自身,講習会ではいつも,療育の面から従来の機能訓練(座位,四つ這い,立位,歩行など)の場合よりも訓練の後で母親の子供に対する接し方が訓練以上に大切であることを強調している.またVojta法を処方する医師にとって,療育の面から幼児期に訓練と同時に保育も行える地域の通園施設の役割は非常に重要である.しかし,この面ではさらに長期にわたる観察と分析が必要であることはいうまでもない.
本書がVojta法に関係したセラピストと医師だけでなく,乳幼児期における運動発達障害そしてリハビリテーション全般に携わっておられる医師,セラピストのお役にたつであろうことを確信している.
2002年1月
富 雅男
日本語版に対する序文
“ボイタ法の原理”の日本語版の製作が行われている2000年9月12日,私の尊敬しそして友人であるバツラフボイタ教授(Prof.Vaclav Vojta)が83歳でミュンヘンで亡くなられた.
V.Vojtaは傑出した小児神経科医であった.彼の知見と研究成果は世界中に広がり,脳性運動障害の早期診断と治療を考える場合,もはや無視することはできない.彼の神経生理学的治療法は成人のリハビリーションにもさらにその重要性を増してきており,彼の医学領域における学問的な業績は,多くの栄誉とともに,プラーグのカール大学教授とソウルのカトリック大学名誉教授の称号によってそのすばらしさが認められたのである.彼のライフワークであるボイタの診断と治療は,われわれにとって貴重な遺産であり,継承していく責務がある.
V.Vojtaはいつも日本のことを心にかけていた.彼は彼の講習会のチームとともにすでに1975年に,京都で医師の診断コースとボイタ法による理学療法士の養成コースを開催したが,この医師とセラピストのコースは現在まで定期的に行われている.
日本におけるボイタの診断と治療の導入に決定的な道を開いたのは富 雅男医師で,彼は1972年から1973年にケルン大学の整形外科でV.Vojtaとともに医師の同僚として働いていた.V.Vojtaと彼との密接な個人的な関係は,日本における今や25年にわたっているドイツと日本の講習会のチームに安心感を与えただけでなく,彼が母国語でボイタの“乳児の脳性運動障害”を翻訳したこともわれわれにとって幸いした.
すでに6カ国語に翻訳されているこのモノグラフィーが間もなく日本でも出版されることはわれわれにとっても喜びである.もし富医師の尽力と参画がなければ,翻訳はみられなかったであろう.ここに国際ボイタ協会の名のもとに彼に心より感謝したい.また彼のことを知っている私は,この日本語への翻訳をとくに喜んだであろうV.Vojtaになりかわりこの場を借りて感謝したい.
すばらしい文芸をもち,高度に発達した文化をもっている日本は,アジアと西洋世界に門戸を開いている.日本は“太陽の昇る国”で,新しい時代の流れと新しい理念に対して朝焼けのように輝いている国でもある.このような意味で,運動発達と運動療法に関して,新しい思考モデル,すなわちボイタの原理に基づくV.Vojtaによって彼の存命中に喚起された発達運動学が,現在進行中の日本語訳によってさらに開花するであろうことをわれわれは願っている.
ハイデルベルグにて
アンネグレテペータース
2000年9月
第2版序文
われわれは本書の第2版を出版できたことを喜んでいる.第1版は比較的多数の増刷をしていただいたが,早くも品切れになった.これもひとえにSpringer-Verlagの責任感とそして細心の気遣いによるところであることは確かである.これに対して,われわれは同社に心から感謝している.
新版にはさらに手が加えられ,“反射性腹這いにおける歩行相”について二節が追加された.
本書の成果は“運動発達における運動学”を中心に書き加えたことである.運動のリハビリーションと予防に関係しているセラピスト,整形外科医,小児科医,そして集中医療にかかわる医師に本書を推薦したい.また運動発達学は呼吸のテクニックそして心臓循環機能にも重要な意味をもっているので,たとえば乳児から成人に至るまでの集中医療や肺の呼吸にもかかわりをもっている.
本書では,“筋機能の分化“あるいは“固定点と動点”(Punctum fixtum und Punctum mobile)の変換によって起こる“筋収縮方向の変換“というような概念につき,読者に理解していただけるように述べた.その際,移動運動の視点から運動学的な問題の考察に際し“主動筋と拮抗筋”(Agonist und Antagonist)のような概念は時代遅れであるにちがいないことは明らかである.それは筋トーヌスと筋トーヌスの異常性の発達の意味についても新しい価値判断が必要である.この運動発達学は,治療的にもこれまで治療に影響を与えてきたものとは異なった形で役立つであろう.
本書がドイツ語圏以外でもすでに数多く翻訳され,急速に広まっていることはわれわれの喜びとするところであるが,運動のリハビリーション,予防医学そして集中治療の医療分野における運動発達学は,長い道のりのなかで始まったばかりである.
Martinsried bei Muenchen
Vaclav Vojta
und Schriesheim bei Heideilberg,
Annegret Peters
im August 1996
第1版序文
本書の生い立ちは,Vaclav Vojtaが小児痙直性両麻痺の学童を治療しようと操作しているときに,本児の痙性が変化するのを観察した50年前にさかのぼる.その後の4年間,経験に基づいたこの最初の観察をもとに,治療概念について研究した.学問という意味では研究の結果というよりもむしろこの概念は1つの仮説であり,そしてその目的は患者の臨床症状の改善であった.
その後,1957年から1958年にかけて,とくに彼の興味を呼び起こしたのは,学童前と学童期の脳性麻痺の子供に,ある一定の操作を加えると筋活動の変化を誘発することができ,そしてそれはある規則性をもって出現するということであった.これら脳性麻痺の子供がこれまでの人生のなかで,いままで発揮できるような状態でなかった筋機能が,骨格筋に初めて規則的・自動的にでてきたのである.さらに,脊髄分節とさらに高位の調節レベルから植物神経型の反応(ある一定の筋群の上にある皮膚の発赤と発汗,血圧と脈拍数の変化)が起こり,それはおのおのに該当した分節の刺激に対する反応であることを示していた.
これらの筋活動が初めて呼び覚まされると,患者はそれらの筋活動を自動的に,すなわち無意識のうちに自発運動のなかに組み入れることができる.
治療の効果は,“全体の”体位の変化であった.その最も単純なことは痙性の尖足位の改善が観察されたことであった.足部に直接刺激を加えることなく,規則的に刺激を与える経過のなかで,自発的に距腿関節に自動的な背屈運動がみられた.
50年代の終わりに,全体の運動パターン,すなわち体全体に広がった運動パターンであることが明らかとなった.このことは,当時すでにこのように誘発された運動が体全体の協調性複合運動体であることを示唆していた.
多発性側索硬化症と多発性脊髄根症の大人の患者で治療効果が得られたあと,このころから運動障害の乳児にこの治療を応用するようになった.
V.Vojtaがドイツ連邦共和国に移住してのち(1968),体全体の運動パターンとしてのこの協調性複合運動体はドイツ連邦共和国だけでなく,外国でもこの治療コースが定期的に開かれるようになった.まず,イタリア,日本とスウェーデン,その後オーストリア,韓国,フランス,ノルウェーとスペインで開かれるようになった.
しかし,非常に多くの主張すべきことがあったので,V.Vojtaが発表した一連のことを系統的にまとめるための時間がなかった.本書に関して,1976年以来,Vojtaの教育コースのインストラクターであるAnnegret Petersが,この長期にわたる気の遠くなりそうな仕事を引き受けてくれた.1983年以来,V.Vojtaがこの仕事に加わり,読者がこの新しい運動のリハビリテーションの治療原理をできるだけ理解できるようにするために多くの改変,さらに新しい概念も付け加えられた.
本書の基本にある新しいことは,人の個体発生の理想的な運動の筋活動と病的運動をたえず同時に対比させて,2つの反射性移動運動(反射性腹這いと反射性寝返り)の運動パターンにおける筋機能の分化を治療に導入したことである.
反射性移動運動によって,もはや小児脳性麻痺の症状が著明になり,そして症状が固定するまで治療を待つ必要はなくなった.というのは治療手段としてコントロールされた反射性移動運動によって,異常で痙性麻痺への危険性はあるが,まだ先天的な痙性麻痺の乳児としての範疇に入れることなく,そしてそのような状態にとどめることなく早期に治療できる可能性がでてきたからである.それに関連して,さらに脳性麻痺の予防もありうるということは,他の報告とともに1982年に富(Tomi1985,巻末文献参照)が示唆している.
反射性移動運動は,小児科領域以外に,整形外科そして外科領域においても意味がある.というのは整形外科的な姿勢異常の場合,反射性寝返りの治療によって手術の適応が減り,そしてそれ以外にも反射性移動運動を利用することによって手術成績に良好な結果を得ることができるようになった.
反射性移動運動によって,患者に生理的な運動の概念を提供し,“眠っている“かあるいは“阻害されている”運動機能を自動的に呼び覚まし,患者が反射性移動運動によって得られた生理的な運動の概念を運動機能のなかに組み入れようと試みることができるのである.
著者はこの全体の賦活の機構を障害のある患者の利益のために広く応用されることを希望している.
この場を借りて,本書の発展を促していただいたVaclav-Vojta協会(国際ボイタ協会)の会員の方々をはじめ,とくにRoswitha Blockと,とりわけEdith Schweizerさんに感謝する.
またVaclav-Vojta協会は,骨格のスケッチと,それに付け加えて筋肉のスケッチを書いていただいたAndrea Rose-Schallの協力に感謝する.また骨格と筋肉のスケッチを完成していただき,そして本書のほとんどの構成をしていただいた美術家のRagnit von Moschさんに心から感謝する.原稿の印刷前に最後まで読んでいただき,そして非常に手間のかかる詳細な校正をしていただいたリハビリテーション医のDr.CPeter Weberに感謝する.
最後になったが,原稿書きに努力していただいたLio Petersさんにも感謝する.
私達の講義,セミナーそして研究のグループに参加していただき,本書を書くきっかけを与えていただいた全世界の医師とセラピストに感謝する.
Martinsried bei Munchen
Vaclav Vojta
und Schriesheim bei Heidelberg,
Annegret Peters
im Marz 1992
1974年に初版が出版されたVojta教授の最初のモノグラフィーである“乳児の脳性運動障害“は,主として脳性運動障害の早期診断と早期治療について書かれたものであった.一方,本書は彼の治療原理である反射性移動運動の運動学について書かれたものである.実際に訓練を行うものにとっては永年にわたって本書の出版が待たれた.小児神経科医であるVojta教授が徹底して神経学を突き詰めていって,最終的に彼の恩師であるHenner教授の“神経学とは運動学”であるという考えを持ち続け,82歳という学究者としては高齢にもかかわらず,死の直前まで彼の生涯の仕事である乳児の運動障害の治療をまとめ上げていただいたことは,失礼な言い方かもしれないが,本当にほっとしている.
脳性運動障害の治療法は運動療法,薬物療法そして手術療法を含めると無数にあるといっても過言ではない.最近のように画像診断が進歩したといっても,運動発達過程の障害である本疾患の病的運動発達のメカニズムはまだ解明されていない.治療の根拠はあくまで筋トーヌスをいかにコントロールし,二次的に発生した変形をいかに矯正するかに集約されている.本書では反射性移動運動を運動学的に詳細に分析し,脊柱を含めた全身の四肢関節の分節を運動学的にそして筋活動を筋電図で分析して,反射性腹這いと反射性寝返りの運動のなかにヒトの赤ちゃんが生まれてから立位,そして歩行に至るまでの全身の筋活動が含まれていることを見出し脳性運動障害の治療に応用している.訳者は本法を導入して以来,脳性運動障害だけでなく,二分脊椎,運動発達遅延,脊柱の側彎,後彎そして腰椎前彎などの姿勢異常,そして最近では学童期の学習障害,感覚統合障害の治療にも適応しSCSITの検査からも効果のあることを明らかにしている.ドイツでは成人の脳出血後の片麻痺の患者に応用し良好な成績が得られ,本邦でもその効果が確認されている.最近,重症脳性運動障害児の呼吸および嚥下障害の治療には,気管切開および胃瘻術がよく行われている.しかし,重症の脳性運動障害児に対して本法を施行することによってこのような手術療法を避けることができる.
本法に対する非難として,泣かすことによって精神的に負担をかけ,精神的に異常な子供になるということがよく聞かれる.このことに関して,Vojta教授がケルン時代に一卵性双生児のうち一児に対して治療した子供について,ミュンヘン小児センターの心理療法士が学童期に達した他児と比較調査した結果では,双生児の間には精神的そして心理的には差はなかったと報告されている.われわれの調査でも,双生児間に情緒面および心理面での差異はみられなかった.問題はむしろ治療されている子供よりも,治療を受けなかった子供にみられたという母親もあった.自分の兄弟が訓練で泣いても,自分もしてくれと言われ真似事でもしなければならなかったという母親もいた.Vojta法による訓練は基本的に母親がセラピストから指導を受け,母親が家庭で訓練を継続するのが治療の基本になっているので,Vojta自身,講習会ではいつも,療育の面から従来の機能訓練(座位,四つ這い,立位,歩行など)の場合よりも訓練の後で母親の子供に対する接し方が訓練以上に大切であることを強調している.またVojta法を処方する医師にとって,療育の面から幼児期に訓練と同時に保育も行える地域の通園施設の役割は非常に重要である.しかし,この面ではさらに長期にわたる観察と分析が必要であることはいうまでもない.
本書がVojta法に関係したセラピストと医師だけでなく,乳幼児期における運動発達障害そしてリハビリテーション全般に携わっておられる医師,セラピストのお役にたつであろうことを確信している.
2002年1月
富 雅男
日本語版に対する序文
“ボイタ法の原理”の日本語版の製作が行われている2000年9月12日,私の尊敬しそして友人であるバツラフボイタ教授(Prof.Vaclav Vojta)が83歳でミュンヘンで亡くなられた.
V.Vojtaは傑出した小児神経科医であった.彼の知見と研究成果は世界中に広がり,脳性運動障害の早期診断と治療を考える場合,もはや無視することはできない.彼の神経生理学的治療法は成人のリハビリーションにもさらにその重要性を増してきており,彼の医学領域における学問的な業績は,多くの栄誉とともに,プラーグのカール大学教授とソウルのカトリック大学名誉教授の称号によってそのすばらしさが認められたのである.彼のライフワークであるボイタの診断と治療は,われわれにとって貴重な遺産であり,継承していく責務がある.
V.Vojtaはいつも日本のことを心にかけていた.彼は彼の講習会のチームとともにすでに1975年に,京都で医師の診断コースとボイタ法による理学療法士の養成コースを開催したが,この医師とセラピストのコースは現在まで定期的に行われている.
日本におけるボイタの診断と治療の導入に決定的な道を開いたのは富 雅男医師で,彼は1972年から1973年にケルン大学の整形外科でV.Vojtaとともに医師の同僚として働いていた.V.Vojtaと彼との密接な個人的な関係は,日本における今や25年にわたっているドイツと日本の講習会のチームに安心感を与えただけでなく,彼が母国語でボイタの“乳児の脳性運動障害”を翻訳したこともわれわれにとって幸いした.
すでに6カ国語に翻訳されているこのモノグラフィーが間もなく日本でも出版されることはわれわれにとっても喜びである.もし富医師の尽力と参画がなければ,翻訳はみられなかったであろう.ここに国際ボイタ協会の名のもとに彼に心より感謝したい.また彼のことを知っている私は,この日本語への翻訳をとくに喜んだであろうV.Vojtaになりかわりこの場を借りて感謝したい.
すばらしい文芸をもち,高度に発達した文化をもっている日本は,アジアと西洋世界に門戸を開いている.日本は“太陽の昇る国”で,新しい時代の流れと新しい理念に対して朝焼けのように輝いている国でもある.このような意味で,運動発達と運動療法に関して,新しい思考モデル,すなわちボイタの原理に基づくV.Vojtaによって彼の存命中に喚起された発達運動学が,現在進行中の日本語訳によってさらに開花するであろうことをわれわれは願っている.
ハイデルベルグにて
アンネグレテペータース
2000年9月
第2版序文
われわれは本書の第2版を出版できたことを喜んでいる.第1版は比較的多数の増刷をしていただいたが,早くも品切れになった.これもひとえにSpringer-Verlagの責任感とそして細心の気遣いによるところであることは確かである.これに対して,われわれは同社に心から感謝している.
新版にはさらに手が加えられ,“反射性腹這いにおける歩行相”について二節が追加された.
本書の成果は“運動発達における運動学”を中心に書き加えたことである.運動のリハビリーションと予防に関係しているセラピスト,整形外科医,小児科医,そして集中医療にかかわる医師に本書を推薦したい.また運動発達学は呼吸のテクニックそして心臓循環機能にも重要な意味をもっているので,たとえば乳児から成人に至るまでの集中医療や肺の呼吸にもかかわりをもっている.
本書では,“筋機能の分化“あるいは“固定点と動点”(Punctum fixtum und Punctum mobile)の変換によって起こる“筋収縮方向の変換“というような概念につき,読者に理解していただけるように述べた.その際,移動運動の視点から運動学的な問題の考察に際し“主動筋と拮抗筋”(Agonist und Antagonist)のような概念は時代遅れであるにちがいないことは明らかである.それは筋トーヌスと筋トーヌスの異常性の発達の意味についても新しい価値判断が必要である.この運動発達学は,治療的にもこれまで治療に影響を与えてきたものとは異なった形で役立つであろう.
本書がドイツ語圏以外でもすでに数多く翻訳され,急速に広まっていることはわれわれの喜びとするところであるが,運動のリハビリーション,予防医学そして集中治療の医療分野における運動発達学は,長い道のりのなかで始まったばかりである.
Martinsried bei Muenchen
Vaclav Vojta
und Schriesheim bei Heideilberg,
Annegret Peters
im August 1996
第1版序文
本書の生い立ちは,Vaclav Vojtaが小児痙直性両麻痺の学童を治療しようと操作しているときに,本児の痙性が変化するのを観察した50年前にさかのぼる.その後の4年間,経験に基づいたこの最初の観察をもとに,治療概念について研究した.学問という意味では研究の結果というよりもむしろこの概念は1つの仮説であり,そしてその目的は患者の臨床症状の改善であった.
その後,1957年から1958年にかけて,とくに彼の興味を呼び起こしたのは,学童前と学童期の脳性麻痺の子供に,ある一定の操作を加えると筋活動の変化を誘発することができ,そしてそれはある規則性をもって出現するということであった.これら脳性麻痺の子供がこれまでの人生のなかで,いままで発揮できるような状態でなかった筋機能が,骨格筋に初めて規則的・自動的にでてきたのである.さらに,脊髄分節とさらに高位の調節レベルから植物神経型の反応(ある一定の筋群の上にある皮膚の発赤と発汗,血圧と脈拍数の変化)が起こり,それはおのおのに該当した分節の刺激に対する反応であることを示していた.
これらの筋活動が初めて呼び覚まされると,患者はそれらの筋活動を自動的に,すなわち無意識のうちに自発運動のなかに組み入れることができる.
治療の効果は,“全体の”体位の変化であった.その最も単純なことは痙性の尖足位の改善が観察されたことであった.足部に直接刺激を加えることなく,規則的に刺激を与える経過のなかで,自発的に距腿関節に自動的な背屈運動がみられた.
50年代の終わりに,全体の運動パターン,すなわち体全体に広がった運動パターンであることが明らかとなった.このことは,当時すでにこのように誘発された運動が体全体の協調性複合運動体であることを示唆していた.
多発性側索硬化症と多発性脊髄根症の大人の患者で治療効果が得られたあと,このころから運動障害の乳児にこの治療を応用するようになった.
V.Vojtaがドイツ連邦共和国に移住してのち(1968),体全体の運動パターンとしてのこの協調性複合運動体はドイツ連邦共和国だけでなく,外国でもこの治療コースが定期的に開かれるようになった.まず,イタリア,日本とスウェーデン,その後オーストリア,韓国,フランス,ノルウェーとスペインで開かれるようになった.
しかし,非常に多くの主張すべきことがあったので,V.Vojtaが発表した一連のことを系統的にまとめるための時間がなかった.本書に関して,1976年以来,Vojtaの教育コースのインストラクターであるAnnegret Petersが,この長期にわたる気の遠くなりそうな仕事を引き受けてくれた.1983年以来,V.Vojtaがこの仕事に加わり,読者がこの新しい運動のリハビリテーションの治療原理をできるだけ理解できるようにするために多くの改変,さらに新しい概念も付け加えられた.
本書の基本にある新しいことは,人の個体発生の理想的な運動の筋活動と病的運動をたえず同時に対比させて,2つの反射性移動運動(反射性腹這いと反射性寝返り)の運動パターンにおける筋機能の分化を治療に導入したことである.
反射性移動運動によって,もはや小児脳性麻痺の症状が著明になり,そして症状が固定するまで治療を待つ必要はなくなった.というのは治療手段としてコントロールされた反射性移動運動によって,異常で痙性麻痺への危険性はあるが,まだ先天的な痙性麻痺の乳児としての範疇に入れることなく,そしてそのような状態にとどめることなく早期に治療できる可能性がでてきたからである.それに関連して,さらに脳性麻痺の予防もありうるということは,他の報告とともに1982年に富(Tomi1985,巻末文献参照)が示唆している.
反射性移動運動は,小児科領域以外に,整形外科そして外科領域においても意味がある.というのは整形外科的な姿勢異常の場合,反射性寝返りの治療によって手術の適応が減り,そしてそれ以外にも反射性移動運動を利用することによって手術成績に良好な結果を得ることができるようになった.
反射性移動運動によって,患者に生理的な運動の概念を提供し,“眠っている“かあるいは“阻害されている”運動機能を自動的に呼び覚まし,患者が反射性移動運動によって得られた生理的な運動の概念を運動機能のなかに組み入れようと試みることができるのである.
著者はこの全体の賦活の機構を障害のある患者の利益のために広く応用されることを希望している.
この場を借りて,本書の発展を促していただいたVaclav-Vojta協会(国際ボイタ協会)の会員の方々をはじめ,とくにRoswitha Blockと,とりわけEdith Schweizerさんに感謝する.
またVaclav-Vojta協会は,骨格のスケッチと,それに付け加えて筋肉のスケッチを書いていただいたAndrea Rose-Schallの協力に感謝する.また骨格と筋肉のスケッチを完成していただき,そして本書のほとんどの構成をしていただいた美術家のRagnit von Moschさんに心から感謝する.原稿の印刷前に最後まで読んでいただき,そして非常に手間のかかる詳細な校正をしていただいたリハビリテーション医のDr.CPeter Weberに感謝する.
最後になったが,原稿書きに努力していただいたLio Petersさんにも感謝する.
私達の講義,セミナーそして研究のグループに参加していただき,本書を書くきっかけを与えていただいた全世界の医師とセラピストに感謝する.
Martinsried bei Munchen
Vaclav Vojta
und Schriesheim bei Heidelberg,
Annegret Peters
im Marz 1992
訳者序文
日本語版に対する序文
第2版序文
第1版序文
1章 反射性移動運動の導入
1.1 個体発生の運動における反射性腹這いと反射性寝返りの分析
1.2 反射性腹這いと反射性寝返りの時間的そして空間的経過
1.3 反射性前進運動-固定点とその意義
1.4 反射性前進運動の作用
1.4.1 神経学的な状態
1.4.2 功緻運動,構音,立体知覚,植物神経
1.5 乳児,小児および成人における反射性移動運動の適応
1.5.1 乳児と小児における適応
1.5.2 中枢神経系における運動パターンの貯蔵
1.5.3 年長児と成人における適応
1.6 移動運動の原理
1.6.1 前進運動に関係した起き上がりと有角運動
1.6.2 重心の移動,把握機能そして前進運動
1.6.3 治療における移動運動の原理
1.6.4 自発的な前進運動における筋機能と反射性移動運動における筋機能
1.7 腹臥位における人の前進運動形態
1.7.1 腹這い
1.7.2 四つ這い
1.8 腹臥位と背臥位からの反射性前進運動パターン
1.8.1 反射性腹這い-腹臥位からの全身運動パターン
1.8.2 反射性寝返り-背臥位からの全身運動パターン
1.9 反射性前進運動の原理
1.9.1 反射性前進運動に関連した機能
1.9.2 筋群の前伸張
1.9.3 反射性前進運動の適応テクニック
1.9.4 相反性運動パターン
1.9.5 共同運動機能と姿勢の保持
2章 反射性腹這い
2.1 反射性腹這いの内容
2.1.1 出発肢位における関節の角度
2.1.2 誘発帯
2.1.3 誘発帯の刺激の時間的集積と空間的集積
2.1.4 四肢における誘発帯
2.1.5 体幹と四肢帯にある誘発帯
2.2 顔面側上肢と肩甲帯の運動
2.2.1 反射性腹這いにおける肩甲骨の機能
2.2.2 背側における体幹と肩甲骨の筋結合
2.2.3 腹側における上腕骨と肩甲帯の筋結合:大胸筋の特殊な機能
2.2.4 肩関節の筋結合
2.2.5 上腕の筋肉を例に上部脊椎の共同運動の筋機能と同時収縮との比較
2.2.6 大胸筋と肩甲骨筋群の抗重力機能による体幹の起き上がり
2.2.7 広背筋と肩甲帯回旋筋
2.2.8 手と前腕領域の活動
2.3 後頭側上肢の運動
2.3.1 肩関節の運動(上肢と肩甲帯)
2.3.2 前鋸筋の特殊な機能
2.3.3 肘関節の運動
2.3.4 手の運動
2.4 肩甲帯軸の斜位における頭の伸展と回旋
2.4.1 腹臥位における脳性麻痺の異常な頭の肢位
2.4.2 頭の運動を例に反射性腹這いにおける統合された協調レベルについての解釈
2.4.3 理想的な運動発達:第4期3カ月までの頭の運動と体幹の起き上がりとの関係
2.5 歩行,四つ這いそして反射性移動運動における歩行のサイクル
2.5.1 反射性腹這いにおける歩行サイクルと頭の回旋の関係
2.5.2 反射性腹這いにおける歩行の相とその際の相対的な時間の配分
2.6 下肢の運動
2.6.1 弛緩相と立脚相の関係
2.6.2 顔面側下肢の屈曲相
2.6.3 顔面側下肢の立脚相
2.6.4 後頭側下肢の立脚相と踏み切り相
2.7 軸器官の領域における運動
2.7.1 肩甲帯軸の運動
2.7.2 軸器官の伸展運動
2.7.3 腹筋の筋結合
2.7.4 腹圧,呼吸,膀胱と骨盤底
2.8 顔面領域における活動
2.8.1 視覚運動
2.8.2 病的な視線の固定に対する意味づけ
2.8.3 口唇と下顎の賦活
2.8.4 舌と口腔の運動そして嚥下機能
3章 反射性寝返り第一相
反射性寝返りと反射性腹這いの比較
3.1 反射性寝返り全運動パターンの歴史的な回顧
3.2 反射性寝返り第一相:寝返り運動の出発肢位である非対称性の背臥位
3.2.1 新生児の非対称性の姿勢
3.2.2 反射性寝返りのメカニズムに対する適切な刺激:胸部誘発帯
3.3 体幹の長軸の伸展での姿勢の変化
3.3.1 肩関節と股関節の運動:外旋
3.3.2 成人における反射性寝返り第一相
3.4 脊柱自動筋:脊柱の回旋と支持筋
3.5 横隔膜の収縮,腹圧,そして胸膜,縦隔,腹腔器官の内臓感覚受容,肋骨の運動,呼吸機能
3.6 反射性寝返り第一相における関節と筋機能
3.7 体幹の運動
3.7.1 骨盤の伸展と軸器官の腹側と背側の筋機能
3.7.2 骨盤の伸展のための支持面としての後頭部と僧帽筋
3.7.3 骨盤の斜位(前額面)
3.7.4 後頭側上肢への骨盤の回旋:第1の腹斜筋の筋結合
3.7.5 後頭側上肢への肩甲帯の回旋:第2の腹斜筋の筋結合
3.7.6 後頭側上肢と肩甲骨
3.7.7 上半身の回旋:後頭側の小胸筋と前鋸筋
3.8 健康な新生児の運動発達の注目点
3.9 反射性腹這いと反射性寝返りの肩甲骨にかかる負荷機能の比較
4章 反射性寝返り第二相
4.1 反射性寝返り第二相における四肢の肢位
4.1.1 下になった上肢
4.1.2 下になった下肢
4.1.3 上になった上肢
4.1.4 上になった下肢
4.2 反射性寝返り第二相における誘発帯
4.2.1 上になった半身にある誘発帯
4.2.2 四肢の誘発帯
4.3 四つ這い歩行における歩行サイクルの相と反射性寝返り第二相の四肢の運動との比較
4.4 支持している四肢の機能
4.4.1 支持している上肢
4.4.2 支持している下肢
4.5 負荷がかかっていない側の機能
4.5.1 負荷がかかっていない上肢
4.5.2 負荷がかかっていない下肢
4.6 反射性寝返り第二相における前進運動過程での軸器官
4.6.1 反射性移動運動における脊柱自動筋の起き上がり機能
4.6.2 脊柱自動筋の回旋機能と下後鋸筋の関係
4.6.3 脊柱自動筋の機能の要約
4.7 運動発達における頭の回旋の始まり
4.7.1 フェンシング様肢位における頭の回旋と支持面
4.7.2 反張弓の頭の回旋
4.7.3 小児脳性麻痺の病像における反張弓の頭の回旋
4.8 反射性寝返りの運動パターンにおける頭の回旋
4.8.1 頭長筋と頸長筋
4.8.2 上後鋸筋
4.8.3 斜角筋群
4.8.4 要 約
4.9 反射性寝返りにおける軸器官の背筋の分化
4.9.1 腹斜筋の拮抗筋としての腰方形筋と下後鋸筋
4.9.2 脳性麻痺と他の運動障害における回旋過程
4.9.3 回旋運動過程における下後鋸筋の特異的な機能
4.9.4 対抗筋としての下後鋸筋,腸腰筋そして共同筋としての肋間筋
4.9.5 回旋運動過程における腹斜筋の筋結合の始動筋としての前鋸筋
4.9.6 回旋運動過程における広背筋と脊柱自動筋の関係
4.10 肩甲帯の回旋運動過程
4.10.1 大小胸筋とその共同筋としての菱形筋と僧帽筋
4.10.2 肩甲骨-回旋運動過程における介在骨として支持するための骨
4.10.3 腹式呼吸,ハリソン溝,そして分節の脊柱回旋
4.10.4 腹壁の筋肉
4.10.5 反射性寝返り第二相における回旋運動過程における相の変換
4.10.6 運動発達における回旋運動過程
4.10.7 反射性寝返りにおける能動的な立位化の過程と他の運動療法との比較
文献
索引
日本語版に対する序文
第2版序文
第1版序文
1章 反射性移動運動の導入
1.1 個体発生の運動における反射性腹這いと反射性寝返りの分析
1.2 反射性腹這いと反射性寝返りの時間的そして空間的経過
1.3 反射性前進運動-固定点とその意義
1.4 反射性前進運動の作用
1.4.1 神経学的な状態
1.4.2 功緻運動,構音,立体知覚,植物神経
1.5 乳児,小児および成人における反射性移動運動の適応
1.5.1 乳児と小児における適応
1.5.2 中枢神経系における運動パターンの貯蔵
1.5.3 年長児と成人における適応
1.6 移動運動の原理
1.6.1 前進運動に関係した起き上がりと有角運動
1.6.2 重心の移動,把握機能そして前進運動
1.6.3 治療における移動運動の原理
1.6.4 自発的な前進運動における筋機能と反射性移動運動における筋機能
1.7 腹臥位における人の前進運動形態
1.7.1 腹這い
1.7.2 四つ這い
1.8 腹臥位と背臥位からの反射性前進運動パターン
1.8.1 反射性腹這い-腹臥位からの全身運動パターン
1.8.2 反射性寝返り-背臥位からの全身運動パターン
1.9 反射性前進運動の原理
1.9.1 反射性前進運動に関連した機能
1.9.2 筋群の前伸張
1.9.3 反射性前進運動の適応テクニック
1.9.4 相反性運動パターン
1.9.5 共同運動機能と姿勢の保持
2章 反射性腹這い
2.1 反射性腹這いの内容
2.1.1 出発肢位における関節の角度
2.1.2 誘発帯
2.1.3 誘発帯の刺激の時間的集積と空間的集積
2.1.4 四肢における誘発帯
2.1.5 体幹と四肢帯にある誘発帯
2.2 顔面側上肢と肩甲帯の運動
2.2.1 反射性腹這いにおける肩甲骨の機能
2.2.2 背側における体幹と肩甲骨の筋結合
2.2.3 腹側における上腕骨と肩甲帯の筋結合:大胸筋の特殊な機能
2.2.4 肩関節の筋結合
2.2.5 上腕の筋肉を例に上部脊椎の共同運動の筋機能と同時収縮との比較
2.2.6 大胸筋と肩甲骨筋群の抗重力機能による体幹の起き上がり
2.2.7 広背筋と肩甲帯回旋筋
2.2.8 手と前腕領域の活動
2.3 後頭側上肢の運動
2.3.1 肩関節の運動(上肢と肩甲帯)
2.3.2 前鋸筋の特殊な機能
2.3.3 肘関節の運動
2.3.4 手の運動
2.4 肩甲帯軸の斜位における頭の伸展と回旋
2.4.1 腹臥位における脳性麻痺の異常な頭の肢位
2.4.2 頭の運動を例に反射性腹這いにおける統合された協調レベルについての解釈
2.4.3 理想的な運動発達:第4期3カ月までの頭の運動と体幹の起き上がりとの関係
2.5 歩行,四つ這いそして反射性移動運動における歩行のサイクル
2.5.1 反射性腹這いにおける歩行サイクルと頭の回旋の関係
2.5.2 反射性腹這いにおける歩行の相とその際の相対的な時間の配分
2.6 下肢の運動
2.6.1 弛緩相と立脚相の関係
2.6.2 顔面側下肢の屈曲相
2.6.3 顔面側下肢の立脚相
2.6.4 後頭側下肢の立脚相と踏み切り相
2.7 軸器官の領域における運動
2.7.1 肩甲帯軸の運動
2.7.2 軸器官の伸展運動
2.7.3 腹筋の筋結合
2.7.4 腹圧,呼吸,膀胱と骨盤底
2.8 顔面領域における活動
2.8.1 視覚運動
2.8.2 病的な視線の固定に対する意味づけ
2.8.3 口唇と下顎の賦活
2.8.4 舌と口腔の運動そして嚥下機能
3章 反射性寝返り第一相
反射性寝返りと反射性腹這いの比較
3.1 反射性寝返り全運動パターンの歴史的な回顧
3.2 反射性寝返り第一相:寝返り運動の出発肢位である非対称性の背臥位
3.2.1 新生児の非対称性の姿勢
3.2.2 反射性寝返りのメカニズムに対する適切な刺激:胸部誘発帯
3.3 体幹の長軸の伸展での姿勢の変化
3.3.1 肩関節と股関節の運動:外旋
3.3.2 成人における反射性寝返り第一相
3.4 脊柱自動筋:脊柱の回旋と支持筋
3.5 横隔膜の収縮,腹圧,そして胸膜,縦隔,腹腔器官の内臓感覚受容,肋骨の運動,呼吸機能
3.6 反射性寝返り第一相における関節と筋機能
3.7 体幹の運動
3.7.1 骨盤の伸展と軸器官の腹側と背側の筋機能
3.7.2 骨盤の伸展のための支持面としての後頭部と僧帽筋
3.7.3 骨盤の斜位(前額面)
3.7.4 後頭側上肢への骨盤の回旋:第1の腹斜筋の筋結合
3.7.5 後頭側上肢への肩甲帯の回旋:第2の腹斜筋の筋結合
3.7.6 後頭側上肢と肩甲骨
3.7.7 上半身の回旋:後頭側の小胸筋と前鋸筋
3.8 健康な新生児の運動発達の注目点
3.9 反射性腹這いと反射性寝返りの肩甲骨にかかる負荷機能の比較
4章 反射性寝返り第二相
4.1 反射性寝返り第二相における四肢の肢位
4.1.1 下になった上肢
4.1.2 下になった下肢
4.1.3 上になった上肢
4.1.4 上になった下肢
4.2 反射性寝返り第二相における誘発帯
4.2.1 上になった半身にある誘発帯
4.2.2 四肢の誘発帯
4.3 四つ這い歩行における歩行サイクルの相と反射性寝返り第二相の四肢の運動との比較
4.4 支持している四肢の機能
4.4.1 支持している上肢
4.4.2 支持している下肢
4.5 負荷がかかっていない側の機能
4.5.1 負荷がかかっていない上肢
4.5.2 負荷がかかっていない下肢
4.6 反射性寝返り第二相における前進運動過程での軸器官
4.6.1 反射性移動運動における脊柱自動筋の起き上がり機能
4.6.2 脊柱自動筋の回旋機能と下後鋸筋の関係
4.6.3 脊柱自動筋の機能の要約
4.7 運動発達における頭の回旋の始まり
4.7.1 フェンシング様肢位における頭の回旋と支持面
4.7.2 反張弓の頭の回旋
4.7.3 小児脳性麻痺の病像における反張弓の頭の回旋
4.8 反射性寝返りの運動パターンにおける頭の回旋
4.8.1 頭長筋と頸長筋
4.8.2 上後鋸筋
4.8.3 斜角筋群
4.8.4 要 約
4.9 反射性寝返りにおける軸器官の背筋の分化
4.9.1 腹斜筋の拮抗筋としての腰方形筋と下後鋸筋
4.9.2 脳性麻痺と他の運動障害における回旋過程
4.9.3 回旋運動過程における下後鋸筋の特異的な機能
4.9.4 対抗筋としての下後鋸筋,腸腰筋そして共同筋としての肋間筋
4.9.5 回旋運動過程における腹斜筋の筋結合の始動筋としての前鋸筋
4.9.6 回旋運動過程における広背筋と脊柱自動筋の関係
4.10 肩甲帯の回旋運動過程
4.10.1 大小胸筋とその共同筋としての菱形筋と僧帽筋
4.10.2 肩甲骨-回旋運動過程における介在骨として支持するための骨
4.10.3 腹式呼吸,ハリソン溝,そして分節の脊柱回旋
4.10.4 腹壁の筋肉
4.10.5 反射性寝返り第二相における回旋運動過程における相の変換
4.10.6 運動発達における回旋運動過程
4.10.7 反射性寝返りにおける能動的な立位化の過程と他の運動療法との比較
文献
索引