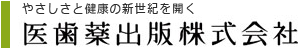�͂��߂�
�@�{���́C�ߐ��̖���E�������̒�����w�����Q���^�E�S�O����i�͖k�Ȋw�Z�p�o�ŎЁC1985�N�j���Q�Ƃ��Ȃ���|��E�ҏW�������̂ł���C�S���e�̖�1/4�ɑ�������D���҂͖L���ȋ��{�l�ł���ƂƂ��ɁC�u�ǂ܂Ȃ������͂Ȃ��v�Ə̂����قǂ̍L�ĂȒ���w�̊w���ƁC����Ɋ�Â��Ǝ��̐[���F���������Ă���C�����ȗ��_�̂��Ƃɕa���E�a�@�E�a�Ԃ���ю��@����ɂ��Ẳ�����s���Ă���D�܂��C�s���ώ@�͂Ɠ��@�͂�������^���ȗՏ��ԓx�̂��ƂɁC�L�x�Ȍo����ς�ł���C�u������10���N�ɂ킽��o�������W�߂�ƁC���x���p���Ď��؍ς݂̕������傤�Ǒ埥�k��Ռo�E�q�����ł̓V�n�̓�����~������㈂��鐔�l�̔{���k100�l�ɂȂ����D���܂̌�ɉ��߂Əd�v�ȏǗ���L�ڂ����D�v�Əq�ׂāC�\���ɋᖡ�������Ȃ��őg�����ꂽ�����̗L���ȕ��܂����ƂƂ��ɁC�����̏Ǘ��t�����ė�����e�Ղɂ��Ă���D�ǂ݂��̂Ƃ��Ėʔ��������[�������łȂ��C�Տ��I�ɂ����ɗL���ȕ��܂������C���ؒ��J�Ȏ��p���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���D
�@�������́C��������Ƃ����C�͖k�ȉ��R���̐l�ŁC1860�N�k���E���L10�N�C���{�̖������N�l�ɐ��܂�1933�N�k����22�N�C���{�̏��a8�N�l�ɖv�����ߐ��̖���ł���D�m���w�̉ƌn�ɐ��܂�C�c�������畃�e�̌O�����Ĉ炿�C������2�x�̉ȋ��̍l���ɒ���Ŏ��s�����̂��C�u�Ǒ��ׂ炴��C�K���Lj�ׂ��v�Ƃ̑c��̐��P������Ĉ�w�̓��֓������D���w�����Q���^�⎩���ɂ́C�u�����ōL��������ǂ݁C�Â��͔_�k�_�_�C�_�Ƃƈ��̐_�ł���C��{�o��Ɨ��̂�����_�_�{���o������Ƃ����l���k����C���v�q����r�̋u�ɏZ�Ƃ���C����o��̒��S�l���l����ŋ߂̍����k���l�̏��Ƃ̒��q�ɂ�����܂ō��v����Ƃ��炩��100��ȏ�̏��Ђ�ǂݒ��ׂ����C��{�o��Ɓ���o����āq�̂��r�����̂͊J�V焒n�̐��_�ƈ�w�̕@�c�ł���C���ꂱ�����C�k���e���[���C�L�͂ł��邱�Ɓl�Ȉ�w�ł���ƒm�����D�����ɂȂ�ƒ����i�q���傤���イ�����r������āᏝ���_�������v������Ă���C��{�o�����o��̌��b�Ƃ�����D�W��̉��f�a�q�������キ���r�k�ᖬ�o����C�������łɎU�킵�Ă��������i�́Ꮭ���G�a�_����S�����l�C����̑��v���q�����r�k�����j��ŏ��̈�w�S�ȑS���ł������}����v���������������l�E���Z�q�����Ƃ��r�k�c��ȑO�l�̈㏑��ҏS�����_�����Ǝ��Õ��܂��͂��߂ē�����������O���v����l�C�v��̐����ȁq�����ނ��r�k����o��Ɋ�Â������͒��߂����C�ᒍ�������_����l�C�����̚g�Ì��q�䂩����r�k�����_�̏ސ����������āᏮ�_�с���l����C��͂蒣���i�̌��b�ł���D�����ɂ͈�w�����W���Đl�˂��y�o���C���u���q���傤�������r�k��f��W�����쐕�W����Ȃǂ��l�E����ցq���傽������r�k���w�����_���_�_�{���S��^��Ȃǂ��l�E������q��������r�k��f����]��Ꮭ������������������Ȃǂ��l�E�O�c�q����˂r�k��_�_�{���o�ǁ�Ꮭ���_�������v����Ȃǂ��l��̏����́C������������i����ѕ������Ȃ���{�o�����o��P���Ă���D���������āC�ނ�̒������㏑�͂�����������Ȉ�w�ł���D�������C�W�E�����猻��ɂ����鏔�Ƃ̒��q�͂悭�ł��Ă͂��邪�C��������ɂ�����܂ŋ��Ԃ̓`���ɋ��X�Ƃ��C���߂�����i�������Ē��؈�w��i�������悤�Ƃ����Ӑ}���Ȃ��D�Â��t�Ƃ��ċM�ԂƂ������Ƃ́C�Ðl�̋K�鏀��ɔ����邱�Ƃł͂Ȃ��C�������i�Ƃ��Ď����̐���k�S�̗얭�ȓ����l��˂��Đ_�q�k���_�ƒm�b�l���v���邱�Ƃł���D����E�_�q�������ɂȂ�[�삷��C����ɌÐl�̋K�鏀����M��Ŏ��グ�C������g�[���C�ω����C���L�G���k�Ӗ��𐄂��L�ߓ��ނ̂��̂ɏo�����炷�ׂĂɋy�ڂ��l���āC�Ðl���w�㐢�̎҂������Ȃ��Ȃ��x�Ƃ��C�ꂢ��悤�ɂ��ׂ��ł���D���̒��̂��Ƃ͂��������������ׂ��ł���C��w�������Ⴄ�͂��͂Ȃ��D�������͂��������l���ʼn��N������܂���w���������C���܂��ܐl�̂��߂ɏ���������Ƃ����ɓ��S����k�v���ʂ�̌��ʂ�������l���C�h�}�̕a��҉邱�Ƃ��ł����D�����掜�k�S��l�̗����N�k�g���̍����w�l�ɗ^������̍��l���Ƃɂ����D���͐e�F�s���邢�Ƃ܂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����āC�����Čy�X�ɑ��l�̉��f�ɂ͉����Ȃ������D���܂��܋}�ǂł��邩��Ɛf�@�̋��߂������Ă��C�݂����篁q���킽���r����������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������D�掜�́w�a�Ƃ���҂�҂��]�ނ̂́C���ɓM�����̂����������߂Ă���悤�Ȃ��̂ł��D���Ȃ����������Ƃ��ł���̂Ȃ�C�}���ʼn����ċ~���Ă������Ȃ����D�������C�Տ��ł͏\���ɒ��ӂ��C�b�́q������r�k�e�G�l�Ȃ��Ƃ����Đl���Q���Ȃ��悤�ɐT���܂Ȃ���Ȃ�܂���x�Ƃ���ꂽ�̂ŁC�w�B�B�k�͂��͂��l�x�Ƌ������C�Ȍ�Տ��ƂƂ��ĂقƂ��1������Ƌx�ނ��ƂȂ��C�����܂�10�]�N�Ɏ����Ă���v�ƋL����Ă���D���̂悤�ɁC����o���_�_�{���o����͂��߂Ƃ��ĂقƂ�ǂ��ׂĂ̗��̓T�Ђ��������C����w�̌��r��ς�ŗ͗ʂ����߁C�����Čy���ɂ͗Տ��Ɍ����킸�C�������������̂��͐掜���̋�����S�ɍ��݂��čאS����_�ȗՏ����H���s�����D1918�N�ɕ�V�k�c�z�l�̗�������@�E�@���ɏA�C���C�n���I�ȗՏ��o����ςނƓ����ɁC�����̘_������w�G���ɓ��e���Ė����������Ă���C�����́u����l��Ɓv�̈�l�ɂ������C������E���R���ƂƂ��Ɂu����O���v�Ƃ��̂��ꂽ�D1926�N�ɓV�Âɋ����ڂ��C�����㙹�ʈ�Ёq������������r����э���̒ʐM����w�Z��ݗ����C�����̌�p�҂�{�������D�����ɑ����̎�Ɓk�t�ɑ����q�̎��́l���o�ꂷ��̂͂��̂��߂ł���D�����͐f�Â���Ԃ͒��q�ɂ������ނƂ��������𑱂��C1933�N8��8��74�ŕa�������D�^�ʖڂŔM�S�������ɖ������l���ł��邱�Ƃ��C�o������я����̋L�q���炭�݂Ƃ��D
�@�����Ɂu�����Q���v�Ɩ��Â����悤�ɁC�������͒����㙹�ʔh�k�����㌋���h�l�Ɩڂ���Ă���D�A�w���푈�ȍ~�ɉ��ė̐N�����������A���n�Ɖ����������ł́C��w�ɂ����Ă����m��w�̉e������������Ȃ��Ȃ������Ƃf���Ă���D�����Ɂu���m�����ɓ����Ĉȍ~�C�ېV��`�҂͋������Ă���ɑ���C�狌��`�҂͉���킵�����̂̂悤�ɂ݂Ȃ��̂ŁC���Ɍ݂����ుq�Ă����r�k�����Ⴂ�l���C�I���ɂ͌𗬂���Ȃ��Ă���D���͖}�˂ł��邪�C����̗p��Ɋ��ő����̐���̒�������肢��Ē���̒Z�������Ă���C�������痼�҂ɕ~���������Ă��Ȃ��D���������āC�ْ����Q���Ɩ��������D���m��w�̗p��͋Ǖ����Âŕa�̕W�ɏd�_�����邪�C����w�̗p��͌������Â����ߕa�̖{�ɏd�_������D���ǁC�W�{�͓��R���ڂ��ׂ��ł���C��̏ɋ������ꍇ�́C����ł��̕W����������Ŗ{�������ΕK����������͂��ŁC�Տ��ł��m���Ɏ艞���������Ă���v�Əq�ׁC�����̒����ł̈�w�E�̏������ƂƂ��ɁC���E������w�̓����͂��Ă���D���̑������ɂ����āC�u���͌Ðl����̎���ɐ��܂ꂽ�̂ŁC�Ðl�������ł��Ȃ������d��������������ׂ��ł���C�Â����̂������ĐV�������̂ɂ��C�킪����w�̋P����S�n����Ɍ��`�ł��Ȃ���C����͎��̍߂ł���D�������͖������̂��Ƃ�S�ɂƂ߂āC�V����Y��Ă���܂��w�͂𑱂��Ă���D����܂Ő��m��w���������C���͂܂����̖���ЂƂ�������ɂ��Ȃ��D����ɂ��̖�̑����͌���ł���C�܂��������y������킯�ɂ͂����Ȃ��̂ŁC�����̐��m����̗p���邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��D�������C�{�҂Ŏ����ꂽ���m��w�͈�w���_���̗p���������ł͂Ȃ��C��ɂ��̉��w���_���̗p���Ă���C����̉^�p�ɂ͒�����w��Z�������Ĉ�̉����C���̖���̗p�����ꍇ�ɂ��C�L��̊w�k���������ȗ����ł₽��u�߂���悤�Ȋw��ԓx�l�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��v�Ƃ��L���Ă���D���Ȃ킿�C�}�����Ė��ᔻ�ɐ��m��w��������Ă���̂ł͂Ȃ��C�u�����v���Ȃ킿����w�Ƃ����m�ł���y��̂��ƂɁC�u�Q���v���Ȃ킿���m��w�̊w���E���w�E�Ȃǂ���ѐ����������č̗p���C����w����蔭�W�����悤�Ƃ̈Ӑ}�������Ă���̂ł���D
�@�������Ȃ���C�����̐��m��w�͍������炷��Ƃ��Ȃ薢�n�ł���C���Öʂł��݂�ׂ��������Ȃ��C�����̖����݂ł͉ߋ��̈╨�ɂȂ��Ă��܂��Ă���C����ɂ͒���w�ɗ��r���钘�҂ɐ��m��w�ɑ������������⌡������݂��邽�߂ɁC�{���ł͑����̕����Ő��m��w�Ɋ֘A�����L�q���������Ă��邱�Ƃ��C��e�͊肢�����D
�@���w�����Q���^���1918�`34�N��16�N�ԂɎ��X�Ɗ��s����C�S����30������Ȃ��Ă���k1957�N�Ɉ�e���攪���Ƃ��ĉ�����ꂽ�l�D���s�͈̏ȉ��̂悤�ł���D
�@�����@�e��a�Ǝ����V�� 1918�N�o�ŁD
�@�����@�e��a�Ǝ����V�� 1919�N�o�ŁD
�@��O���@�e��a�Ǝ����V�� 1924�N�o�ŁD
�@�ȏ�́C�O�O�����ҏ㉺���E8���Ƃ��Ă܂Ƃ߂��C1929�N�o�ŁD
�@��l��5���@����@1924�N�o�ŁD
�@��܊��㉺���E8���@�e���_�@1928�N�o�ŁD
�@��Z��5���@�e��Ǘ�@1931�N�o�ŁD
�@�掵��4���@�����_�a�@1934�N�o�ŁD
�@���̌�C�S����30���ɑ攪���������C���w�����Q���^��㒆���̎O���{���C1934�N�ɉ͖k�l���o�ŎЂ��犧�s����C���ꂪ���݂Ɏ����Ă���D
�@�ȏ�̂悤�ɁC�����͖�16�N�ɂ킽�莟�X�Ƒ���������Ȃ��珑����Ă���C��ɂȂ��ĕa��������V���Ɉ�_���[������C�����a�̏Ǘ��lj�����Ƃ������z�����Ȃ���Ă���̂ŁC���݂ɎQ�Ƃ��邱�Ƃ�������[�߂邤���ōł��]�܂����D�����Ŗ{���ł́C�����̔z���������x���d���Ȃ���C���ݎQ�Ƃ��e�ՂɂȂ�悤�ɓ��ނ̋L�q���܂Ƃ߂�`�ɕҏW���Ȃ����Ă���D�c��ȓ��e���ꋓ�ɒł��Ȃ����߁C�܂����ȎG�a�̖��Ɩ���ɂ��ڂ��Ă���D�v�]��������C���̕��������������o�ł̗\��ł���D
�@�Ȃ��C�����͖���7�`23�N�ɏ�����C�Ӗ����Ƃ�ɂ����\���������̂ŁC�����ɖ��{���Č������c���z�����s���Ă͂��邪�C�S�̂����㕶�Ƃ��ĈӖĂ���D
�@�{���ɂ���ĐV���Ȑ[���F���������C�Տ��ł̐��ʂ���荂�߂��邱�Ƃ����҂��Ă���D
�@�}��
�@1�D�{���́��w�����Q���^��㒆�������甲�����ҏW���Ȃ����Ă���C���R�z�قȂ��Ă���̂ŁC�e���Ɂu��O���~���v�ƕ\�����Č������Q�Ƃ��₷�����Ă���D
�@2�D���㕶�Ƃ��ĈӖC�K�X�Ɂu�@�v�ł���������C���ė������₷�����Ă���C�s�K�v�ƍl�����鐼�m��w�I�L�ڂ͊��������D
�@3�D�i�@�j���͌����ł���C�k�@�l���͖ł���D
�@4�D�������܂ɂ��ẮC�g���Ɗ֘A�������r�ň͂݁C�������₷�����Ă���D
�@5�D���ł́C��_�_�{���o��̓��e���e�̐擪�̕����ɑ}�����Ă���D��{�o�▢���ڂ̖ɂ��Ă͂��̌���łȂ��D
�@6�D�����ɂ́C����p��E�a�E���ܖ��E�̍������Ă���D
�@�k�Q�l�����l
�@������w�厫�T�F�ӊϓ��Ҏ[�C�������X�C1990�N�D
�@�{���o�`�`�F����ώ�ҁC�l���q���o�ŎЁC1990�N�D
�@����w�F�琳�؎�ҁC�l���q���o�ŎЁC1991�N�D
�@��j�蒠�F����L猕Ғ��C���{TCM�������C1993�N�D
�ጾ�k�����̖}��l
�@1�D���𖾂������߂̏��́C��_�_�{���o��ł���D���̏��͕������g����悤�ɂȂ����ŏ��̏��i��Ձ�͂���ȑO�ɑ��݂������C���̂���͂܂������͂Ȃ������j�ł���C�ȍ�i�Ȃ�����Ñ�ɕ����������̂ɗp�����|�ЁD�ȍ�͏��Ђ̈Ӂj�̌Â����킩��D���̏��ɂ͍��v365���̖L�ڂ���C���̐���1�N�Ԃ̓���������킷�D������㒆����3�i�ɕ����C��i�͗{���̖�C���i�͎��a�̖�C���i�͍U�a�̖�Ƃ��Ă���D�e�i�̉��ɂ́C���ׂďڍׂɋC���Ǝ厡���L���C�C���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ��厡�̗��R�������Ă���D�܂��C���Ǝ��̗ǔ\��������C�C������O�����̂����邪�C�Ð��͂��ׂĂ�m��s���Ă�����ЂƂ�\�o���Ă���C��w�ɂ�����V�n�J蓂̕@�c�Ƃ�����D��l�͎������ł��邽�߂ɁC�Ǝ��̗ǔ\����Ă��Ă��C�C�����琄���ʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ���C���ׂč폜���L�ڂ��Ă��Ȃ��D���Ƃ��C�j�}�͏�C�f�z�i�z���Ă����B�����ɓf�o����C���Ȃ킿�b�̕s�[�C�ł���j�ɔ��Ɍ��ʂ�����C��{�o��ɋL�ڂ����邪�C�㐢�̖{���ɂ͋L�ڂ��Ȃ��D�܂��C�R��͊��M�����i�̋����ɂ܂����ꍇ�̊��M�����j�ɔ��Ɍ��ʂ�����C��{�o��ɋL�ڂ����邪�C�㐢�̖{���ɂ͋L�ڂ��Ȃ��D���̂悤�Ȃ��Ƃ͖����ɉɂ��Ȃ��D���͂������݂邽�тɐ[���Q���ɂ��݁C���̂��ߖ{���Ŗ�_�����ӏ��ł͂��ׂā�{�o��ɏ]���C�㐢�̖{���͌y�y�ɍ̗p���Ă��Ȃ��D�ǂ̑��D�ǂ̌o���ɓ��邩�̖��m�ȋL�ڂ��Ȃ��Ƌ^�����̂����邪�C�ǂ�ȕa����邩��m�炸�ɁC��͂��ǂ��Ɏ��邩��m�낤�Ƃ����̂ł��낤���D���߂�C����Ɩ�͋C���ɐ����ė��s������Ȃ����͂Ȃ��D�㐢�C�ڍׂɑ��D�o���ɕ����Ă���̂́C�������Ċw�Ԃ��̂ɍS�Ёk�������Ȃ��Ɓl�̕����c���悤�Ɏv����D
�@2�D�����Ȉ�w���_�́ቩ����o��Ɏn�܂�D���̏��͉���Ɛb���ł���E�����E�S�k�E�����̊Ԃ̖ⓚ�`���ŏ�����Ă���C��f���Ɓ�쐕��ɕ������D��f���̗v�|�͖�ɂ�鎡�a�ɂ���C��쐕��̗v�|�͐j���ɂ�鎡�a�ɂ���D�������C�N�オ���ɌÂ��̂Ō������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��D�Ñ�̑��`�͌����ɂ�邱�Ƃ������e�ՂɖS�������̂ŁC�W��̍c��捁k��b���o����l�͂��̏��͕s���S�ł���Ƃ����C�v��̗щ��͂��̏��ɂ͋U��k�U��l������̂ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă���D����ɒ��i�́Ꮭ���_��̏��Łu��f���9����p���ĕ��͂��������v�Əq�ׂĂ��邪�C���݁�f����24������C���̒��ɂ͋U����邱�Ƃ��킩��D�������C���̊j�S�����͐��_�̎c�������t�ł��邱�Ƃ͊m���ł���C�f���ċU��҂ׂ̈���킴�ł͂Ȃ��D���Ƃ��C�j���ɂ�鎡�Â͍��ł͐��E���ŔF������Ă��邪�C�����Ð����n�߂Ă��Ȃ���C�㐢�ɑn���ł����ł��낤��?�@���m��w�ŏڂ�����U���u�`������̂��n���ł���ł��낤���D����o���ǂޕ��@�Ƃ́C�����M�����镔�����ڂ����������ĉ���邱�Ƃł���C��������Ζ����̖@��k�w�ɓ��鏇�����@�l���J�����Ƃ��ł���D�M�����Ȃ������́C�㐢�̋U�������Ȃ��̂ŁC�_�y���Ȃ��Ă����܂�Ȃ��D����͖Ўq�̂�����u���s���͐M����v�̈ӂł���D���ݐ��m�I�ȕ��@�ɕΏd������̂́C����o��̐M����ɂ��镔���̌����ɓw�͂����C�M�p����������ɗ͎w�E����݂̂ł���D���̈ӌ��𐄂��i�߂�ƁC����o��̐^�{�͂Ƃ��Ɏ����Ă���C���ɓ`�����̂͂��ׂċU��ł��邱�ƂɂȂ�D����ȗ���������ł��낤��?�@����ꂷ�ׂĂ̓��E�݂͂ȉ���̎q���ł���ɂ�������炸�C��c����l�ɗ^�����T�Ђ������݈�w��ɕۑ����悤�Ƃ������C���ׂ����r���������ĂĔj�����Ă��܂��̂́C�܂������Q���킵�����Ƃł���D���������āC�{���̊e�咆�ł́���o��ɂ̂��Ƃ��ďq�ׂ����������ɑ������C���o��Ꮭ���_�������v����Ȃǂ̂悤�Ɂ���o��ɂ̂��Ƃ����㐢�̈㏑�����ɍ̗p���Ă���D
�@3�D�{���ɋL�ڂ������܂̑����͎����n���������̂ł���C���ɌÐl�̐�����p�����ꍇ�ł���ɉ������Ă���D�����ɓƎ��̌����������Ă���ꍇ�ɂ́C���̕����ꏏ�ɍڂ��ďڍׂɉ�������D�܂��e��̕��̌�ɐ��m��w�̏�p���C����ю����Ď��ۂɌ��ʂ����������m���t�^�Ƃ��ċL�����D���D�o����_����ۂɁC��ɓ��Ƃ̐����č̗p�����̂́C���Ƃ��ƌ𗬂����邩��ł���D�܂����ɐ��m��w�̐����̗p�����̂́C��U�Ŏ��ۂɍl���Ă��邩��ł���D
�@4�D�Ðl�̗p��̑����́C1�x�ɑ�ʂ������3��ɕ����ĕ��p�����C�a��������ΕK�������܂�s�������C�����Ȃ���ΕK��1���ł��ׂĕ��p������D���̕��@�ɂ��Ă͍��̐l�X�����ӂ��͂��Ȃ��Ȃ��ċv�����D���͏����Eu�Ƃ��ׂĂ̋}�������ɂ͕K�����̕��@��p���Ă���D�����̏̎��Â͏��Ɏ��Ă���C�����Ԃ�������Ɖΐ��͂�␊���邪�C���X�ɐ��������Â��Ȃ���Ή̐������Ă�����ɂȂ�C����܂ł̌��ʂ��܂������Ȃ��Ȃ�D���̎��Âł́C�K������1����3�p����K�v�͂Ȃ����C���[�e1�p�i�������c�Ԃ�����1�x�����ĕ��p����̂�1��Ƃ݂Ȃ��j���Ė�͂𒋖�p��������ƁC���ʂ����������D
�@5�D�T���ȉƂł͕���ۂɎ����k��Ԑ����l��p���Ȃ����Ƃ��������C�����͎������~�߂Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ𗝉����Ă��Ȃ��D�T�_�a���k����̑m�D��T�_������l�͉A���J�M�̎��Âɐ�玟����p�����D�����͖����W�Ŕ\���B�A��{���D�u�W�C�͈݂ɋA���v�Ɓ���o��ɂ��L�ڂ�����D�W�͔\���B�A��{���̈Ӗ��́C���Ƃ��Ɓu�W�C�͈݂ɋA���v���炫�Ă��邪�C���̗��R�𗝉����Ă��Ȃ����̂������D����فk����̈�ƁD����ցl�́C�u�^�́k�V�n�̑�@�D���o�̍^�͂��w���l�͌܍s�̖��ɂ��āw���͏�����H���C�������c���삷�D�͉����H���C����͋���삷�D�͋Ȓ���H���C�Ȓ��͎_���삷�D���͏]�v��H���C�]�v�͐h���삷�x�Ƃ������C����������̂��̖̂{�����q�ׂĂ���D�y�ɂ��ẮC���̕���ς��w�y�͉��p�k��܂��Ǝ��n�l��ুq�����r���C���p�͊Â��삷�x�Ƃ���D�y�͖{�������ł���C���p�̖�����Ė��Ƃ���̂ł���D�����Ƃ͂��Ȃ킿�W�ł���C���������Đl���B�݂͓y�ɑ����C�����W�ł�����̂͂��ׂĔ\���B�݂ɓ���v�Əq�ׂĂ���D�܂��C�A���̎��Â͐���B�ɏd�_�����邱�Ƃ��������Ă��Ȃ����̂������D�C���k����̈�ƁC�O�c�l�́u�B�͑��A�ł���C���Ȃ킿�O�A�̒��ł���D�̂ɉA���������ꍇ�́C�B�A���������Ƃ���ɂ��ׂ��ł���C�B�A�������Ύ����Ə����D����ł���v�Əq�ׂĂ���D
�@6�D���Փ����ɗp������ẮC�Õ��ł͐���p���C����ł�����p���Ă���D��䏐m�q�悭���ɂ�r�E�����q���r�E�R��̗ނ��C��ĂƓ����ł���D���Ƃ̖{���ł́C�u�u�p�v�ƒ��߂�����̂��������C�u�p�͊ێU�ɂ��Ă݂̂ł���D���݂ł͓��܂ɗp����ꍇ�ɂ��K���u�n���邪��������D��猒�B�݂݂̂ɗp����Ȃ��u���Ă��悢���C�~�b���Ɏg�p����Ƃ����u���ׂ��ł͂Ȃ��D���͏`�����f�S�ł��邩�環�݂ɗ������邪�C�u�n�������͎̂ςĂ��`���͂Ȃ�����ł���D���A�ɗp���悤�ƁC�W���ɗp���悤�ƁC�u�n���ׂ��łȂ����Ƃ́C�ɂ߂Ė����ł���D
�@7�D����̓}�Q�͌Ñ�̐l�Q�ł���C�R���n����}�̎R�J�ɐ��炷��̂œ}�Q�Ƃ����D�R���ܑ̌�R�ɐ�������͍̂ł��D��C���ʂɑ�}�Q�Ƃ����D���݂̗ɓ��l�Q�Ƃ͖{���킪�قȂ�C�C���E���a�ł���C���ۂɗɓ��l�Q���g�p���₷���C����ɔ��ɗ����ŕn�������̂ł����p�ł��C���ɍϐ��̗ǖ�ł���D���݂͗ɓ��n���ł��}�Q�������C���ׂĂ��R���Y�ł͂Ȃ��D�������K���}�Q�̔�ɂ͉��䂪����C�Ӂ����q���炢�ӂ��r�k�H�p�̐l�Q�l�̖�̂悤�ŌӁ����̖��肳��ɖ��Ȃ�Ζ�R�Ɏ�������}�Q�ł���C�����l�Q�̑�p�ɂ���Δ��Ɍ��ʂ�����D���䂪�Ȃ���C���n�͔̍|�ł���C�g�p�Ɋ����Ȃ��D�܂��C�{���ŗp����l�Q�͂��ׂĖ�}�Q�ő�p���Ă��悢���C�ɓ��ō͔|�����l�Q���p���Ă͂Ȃ�Ȃ��D�ɓ��ō͔|�����l�Q�͑��ɍ���Q�ƌĂ�C�����M�ł��邩��y�p���ׂ��łȂ��C�����Eu�q�����r�̏������Ɏg���͍̂ł��悭�Ȃ��D�܂����}�Q�q��Ƃ�����r�́C��̐F�����g�ł���C�����̎��c�R�ɐ��炷��̂ŁC���c�Q�Ƃ������D���}�Q�̕�͂͑�}�Q�ɕC�G���C�����ŔM���ł͂Ȃ��̂ŁC�C���L�M�ɍł��K���Ă���D
�@8�D���ˁq�������r�܂ɓ����ꍇ�́C���p���Ȃ킿�n�p�Ƃ������ƂɂȂ�C�K��������ɖ��t�q�݂�����r����K�v�͂Ȃ��D�ێU�ܒ��ŏn�p���ׂ��ꍇ�́C���t�����悢�D�ᇂ̎��Âł́C�ێU�ł��t�p���ׂ��ł͂Ȃ��D���^���k����̈�Ɓl�͂��̂��Ƃ���؎��S���W��ŏڂ����q�ׂĂ���D�u�����ɂ͐���p���C�~���ɂ͏n��p����v�Ƃ������Ɏ����ẮC�܂������ł���߂ł���D�C���̋��ׂ������Ŋ����o����̂́C���˂p��������Ɏ~�܂邪�C�z���A���������Ŋ����o��Ƃ��́C���˂p����������đ劾���o��D�C���Œ��O�o�ł��Ȃ��ꍇ�́C���\��Ɠ�������Ί����o�����Ƃ��ł���D���������āC�~�����邩�������邩�͐����n�̈Ⴂ�ł͂Ȃ��C�����ɂ����p���邩�ɂ��D
�@9�D�p�͊��Ŕ��U�ɓ����̂ŁC�O�����M�̎��Âɂ͋��O�̉��l������D��_�_�{�o��ɂ́u�����v�Ƃ���C���劦�ł͂Ȃ����Ƃ��킩��D����Ɂu�Y���������v�Ƃ���̂ŁC�����ɏ��ǂł��邱�Ƃ��킩��D���l�̑����͑劦�ƌ�F���ā��p���邽�߂ɐh�U�̐��������ʂɕς��Ă��܂��Ă���i�����̐����ɏ���������p�͕K�����q��r���̂́C���ʂ��邩��ł���j��p�q���������r���O�����M�ɗp�����1���p���Ă����l����̂́C�O���̔M�͎U����ׂ��Ŏ��ʂ��ׂ��ł͂Ȃ�����ł���D��ʂɁ��p��p���Ď��Â�������ꍇ�C�߂������������Ƃɂ����Đp�̂����ł͂Ȃ����Ƃ��킩�炸�C�t�Ɂu�p�́��p���Ă�����قǖҜ��ł��邩��C�����Ȃ�������Ēm��ׂ��ł���v�Ƃ����C���ɂ͐��p��|���邱�ƂɂȂ�D�����Ŏv�����ėp���Ă���������7�`8�K�Ɏ~�߂邪�C�p�̎��͔��ɏd���C7�`8�K�ł���B�q�܁r�݂ɉ߂��Ȃ��D�ɂ߂ďd�ǂ̊�����҉�̂ɔ������B�݂ł́C�Ƃ��Ă����ʂ����҂ł��Ȃ��D�����Ŏ��͊O�����M�̎��Âɂ́C�y�ł��K��1�����x�C���M�������Ȃ���3�`4���g�p���邱�Ƃ������D��𒃘q���t�ɐ�����3�`4��ɕ����ĉ���������̂́C�a�Ƃ̋^����Ƃꂽ�����߂ƁC��͂��ł��邾����łɂƂǂ߂Ċ��������ł�N�����b�������N�����Ȃ��悤�ɂ���������ł���D�p�p���ĊO�����M�����Â���Ȃ�f���Đl�����Q����͂��͂Ȃ��C����Ɏv�����đ�ʎg�p����Βf���ĔM���ނ��Ȃ��͂��͂Ȃ��D�������C��ǂōׂ����҂����p����p�������C����Ⳃɖ��m�ɐ��Ə����Ă����p���[�Ă邱�Ƃ������D���Ƃ��Ɣ��~���Ă�����̂����p�ł��邤���ɁC����ɖ�ǎ���T�d�ɂȂ��Ă���̂������ł���D���������āC���p��p����ꍇ�́C�͂�����Ɛ������p����w�����ׂ��ł���C�ׂ����҂��Ƃ���������ŊĎ����Ȃ���Ίm���ł͂Ȃ��D
�₢�F�����p�Ȃ̂ɁC�ǂ����Đ��͔\���U���C�����ΐ������U����}�ɝʂɕς��̂�?�@�����F�Ζ�̐����͑��ؖ�Ƃ͈قȂ�C���������̂Ɓ����Ȃ����̂ł͏�ɐ������ۗ����ĈقȂ�D�O���͖��łł��邪�C�����ΗL�łɂȂ�D�ΊD��������ƐΊD�ɂȂ�C����̐������}�Ɍ���C���𒍂��Ɖ̂悤�ɔM���Ȃ�D�p�͂��Ƃ��Ɨ����E�_�f�E���f�E�J���V�E�������������������̂ł���C�����Η����E�_�f�E���f�����ׂĔ��ł��܂��C�c�����J���V�E���͕ϐ����ĐΊD�ɂȂ�C�ُ�ɔS�a�ɂȂ�D�����ŏėm�D�͕K���p�𑽗p���邪�C�m�D�k�Z�����g�l�p�ł��邾�낤���D���������āC�p������Ċʂ̒�Ɏc�Ԃ��Ì�����Ƃ��́��p�ł��邩��C���̖�͐�ɕ��p���ׂ��ł͂Ȃ��D
�@10�D�אh�́u1�K�ȏ㕞�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̐�������C�㐢�̈�҂ɂ͂����ے肷��҂��������C���̐��͌������낻���ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�m��Ȃ��̂ł���D�אh�Ɍ��炸�Ԟ��E�V�Y�E�����Ă̂悤�ɁC�����h�œ����Ɍ������т��悤�Ȗ�́C�����Ă��݂ȕ��Q������D�������тꂳ������͔̂x�����тꂳ���C�x�����т��ƌċz�������ɒ�܂�D���Ĉݒ����₦���̂ʼnԞ���30�������Ĉ��݂��ނƁC�����ɋC����B���Ȃ��Ȃ�̂��킩��C���炭���Čċz���悤�₭���Ƃɂ��ǂ����D�����ŁC�Ðl�͎�N���Ђ߂�ƉЂ������邱�Ƃ�����C�Ԟ��𝑂��Čg�т���k�Ԟ������Ɋ܂��Ⴢꂳ���s�p�ӂɊЂ߂��肵�Ȃ��悤�ɂ���l���Ƃ�����Ӗ���������D���ꂩ��݂�Ɨp��͐T�d�ł���˂Ȃ�Ȃ��D
�@11�D���Ă͍~�t�~�q�̎��ł��邪�C���ݖ�ǂł͔��H�q�͂���r�Ő����Ă���D�~�t�C�E�~�q�f�ɗp����ƕ��p��ɋt�ɏǏ܂��܂��������Ȃ鋰�ꂪ����̂́C���H�����f���C��U�����邩��ł���D���͔��ĂŚq�f�����Â���ۂɂ́C�K���������Ŕ��Ă𐔉����Ė��H����������������悤�ɓw�߂Ă���D�������C�ۂɂ͊܂܂�閾�H�ʂ��l�����Č��߂�ꂽ�ʈȊO�ɑ����̔��Ă������Ă����C���ꂢ�ɐ����ĎN�������������̂����Ƃ̕��ʂɑ����悤�ɂ���D��ǂ̎��̂悢�����Ă͖��H����r�I���Ȃ����C�p����ۂɂ͂�͂�ׂ��ł���D��ႂ̖ړI�Ȃ�C�����Ă���Ȃ��Ă��\��Ȃ��D
�@12�D�����E���a�͎��G��ړI�Ƃ���ꍇ�́��p���Ă��悢�D���A�E�ʉ��邢�͎��ʂɌ��˂ĊJ�ʁi�����E���a�͂�������ʂ��Ĕ\���J���j��ړI�ɂ���Ȃ�C�����Ă͂Ȃ�Ȃ��D�ێU���ɗp����Ȃ�������Ă��悢�D���݁C���ׂā���p���Ă��邪�����Ă̂ق��ł���D
�@13�D�R��q�����r�̊j�k��l�͏��֕s���𗈂����̂ł��Ƃ��Ɩ�ɓ����ׂ��ł͂Ȃ��D�������C�c�ɂ̖�ǂŔ����Ă���R��͉��X�ɂ��Ċj�Ɖʓ������X�ł���C�r�������ꍇ�͊j���ʓ���葽�����Ƃ�����D�������Ɂu�j�����ׂď����v�Ɩ��m�ɒ��ӏ���������Ă��C��͂菜�����Ă��Ȃ����Ƃ������̂ŁC���Â̖W���ɂȂ邱�Ɛr�������D�{���ł͎R����ʂɎg�p�����d�Ăȏ̎����Ⴊ���ɑ����D���͎g�p���ɕK�������œ_�����邩�C�j�����ׂď����K�v������Ɛ������ĕa�Ƃɓ_�������C���������ʂ��܂��₤�悤�ɂ���ƁC�ԈႢ���N���Ȃ��D�R��̌��p�͋~�E�ɒ����Ă��邪�C�\���ŒE���闝�R�͎_�����ɂ߂ċ������Ƃɂ���D�������C���߂�Ǝ��X�_�����قƂ�ǂȂ����̂�����C���������R��͎g�p�Ɋ����Ȃ��D��}�̏ɂ́C�K�����߂Ď_�����ɂ߂ċ������Ƃ��m���߂Ă���p���Ȃ���C�D�ꂽ���ʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��D
�@14�D���j�͋C���Ƃ��Ɍ����C�����Ԑ�����̂��ł��悭�Ȃ��D��ǂł͝��q�r���čז��ɂ��Ă�����̂������C����������Ɩ�͂������Ɍ����C��10�������������ƂȂ�����ł���D�p�͋C���Ƃ��ɒW�ŐΎ��ł��邩��C�ׂ��������Đ����Ȃ���Ζ�͂��o�Ȃ����C��ǂłׂ͍��������Ă��Ȃ����̂������D�����Ŏ��́C�p�͕K�������čז��ɂ��Ă�������C���j�͑e����������邾���ʼn�̂܂ܐ�����D���j��p�ɗނ����́C���j�E�p�ɂȂ炤�̂��悢�D
�@15�D�����E�v��͐��p���ł��悭�C�J���J�����u���Ă͂Ȃ�Ȃ��D�ێU���ɗp����ꍇ�́C�܂��҂��đe�������ɂ��C����~������ɓ���Ĕ��Ηn����܂�����C��܂��Ă���҂��čז��ɂ���D���ꂪ�����E�v�����������������@�ł���D
�@16�D�З��E�ČӂȂǂ͖{�������p�Ƃ���D��ǂ̂��̂ɂ͕K���s��t�����݂��Ă���̂ŁC��҂ɑI�ʂ���m�����Ȃ��Ǝ������\��������D�אh�̗t�̌��p�͍��Ɣ�ׂ悤���Ȃ��̂ŁC���m�k����̈�ƁC�������l����{���j�ځ�Łu����p����v�Əq�ׂĂ���D������q����͂��Ёr�ƌK����́C����������̔��p���邪�C���ꂪ�{�����ۂ��͍ł��ٕʂ���̂ŁC�g�p����ꍇ�͎����ō̎悷��̂��m���ł���D��������͑傢�ɉ��ł��ŏa����D����C��t���̒��}����������͑�ւ�ʂ���D���ɓ`���֖@�ł́C��֕s�ʂɐ߂̒�����1���قǂ̔�t���̒��}7�߂ɐ����ĕ��p����Δ��Ɍ��ʂ�����D���̎}�ƍ��̐����͂��̂悤�ɈقȂ�̂ŁC�g�p�ɂ������Ă͐T�d�łȂ���Ȃ�Ȃ��D
�@17�D���ސ͓S�Ǝ_�f�̉������ŁC�����͓S�K�Ɠ����ł���C���Ƃ��Ɓ����ׂ��ł͂Ȃ��D����ق́u����������Đ|�ɐZ�������̂͏��x����v�Əq�ׂĂ���D�{���̏������ɂ�����ސ́C���ׂĐ����ސ��ׂ����҂��ėp����ׂ��ł���D
�@18�D��ɂ͏C�����Ă��Ȃ���ΐ�ɕ��p���Ă͂Ȃ�Ȃ����̂�����C���āE���q�E�ǐm�Ȃǂ̗L�Ŗ�͂��ׂĂ���ł���D�Õ����̕��q�́C���܂��܁u���p�v�Ƃ����Ă����ۂɂ͉����ɒЂ������̂ł���C�{�n�q�ق����キ�r�������q�ł͂Ȃ����C�̎�シ���g�p����̂ł͂Ȃ��D���̂悤�Ȗ́C�����ɂǂ̂悤���{������̂����m�Ȓ����Ȃ��Ă��C��ǂł͕K���C�����Ė��łɂ��Ă���D�{���ł��Ȃ��ŁC���Ƃ��Ɛ��p���Ă悢���̂́C�{���̕����ŏC���ɂ��Ă̖��m�Ȓ����Ȃ���C���ׂĐ��p���ׂ��ł���D�{���̏�����p����ꍇ�́C��̖{���̐����������悤�ȕʂ̏C���������Ă͂Ȃ�Ȃ��D
�@19�D�Ðl�̕�����@�́C�a�����ɂ���ΐH�O�ɕ��p���C�a����ɂ���ΐH��ɕ��p����̂����܂�ł���D�㐢�̐l�ɂ́C�u����ƕK���B�݂����������̂��ɖ�͂��l�B����D�a����ɂ����ĐH��ɕ��p����C�B�݂͕K���܂��h�H�k�O����̐H���l���������C���̌�ɖ���������̂ŁC���������߂Ă��t�ɒx���Ȃ�v�Ƃ������̂�����D���̐��������ɍ����Ă���悤�ł��邪�C�ԈႢ�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��̂ł���D��͂��S�g���s��̂́C�l�g�̋C������Ė�͂�`�B����̂ł���C���傤�Nj�C������`����悤�Ȃ��̂ł���D�����̊Ԃɋ�C���Ȃ���C�ǂ��Ő����悤�Ƃ��̏�Ŏ~�܂�D�l�g�̋C�����Ȃ����C�B�݂����������Ă��S�g�ɓ`�B���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��D�l�g�̋C���̗��s�ɂ͂��Ƃ��Ƒ��D�̋��E�͂Ȃ��C����������͂����ɋC���ƂƂ��ɍs��C���̓`�B���x�͋ɂ߂đ����C�����Ƃ����ԂɑS�g�ɍs���n��D�������C��C������`����̂͑������C���������قǐ��͂������Ȃ�D���̂��Ƃ���C���ɂ���̓`�B�𐄑�����ƁC���������Ɩ�͎͂���Ɍ��ނ���D���������āC�a�����ɂ���ΐH�O�ɕ��p���C�a����ɂ���ΐH��ɕ��p����̂́C���a�ϕ��ʂɋ߂Â������Ē��B����͂��ł����������邽�߂ł���D
�@20�D���܂ł͖�������t�ʂ����Ȃ��̂͂悭�Ȃ��D���Ȃ��Ɩ�`�̑唼�������Ԃ̒��Ɏc��D���A���̖�ł́C���ɖ�`�𑽂����Đ����Ȃ���Ό��ʂ��Ȃ��D���������Ė{���ł́C�d�܂�p����ꍇ�͕K�����`�𐔔t�Ƃ��Đ���ɕ����ĕ��p����D�܂��C����Ė������߂��Ċ��オ�����ꍇ�ɁC��������1�x����Đ����Ă���͖{���̐����������Ă���C���p����ƕa�͕K���������Ȃ�̂ŁC�p�����ׂ��ŕ��p���Ă͂Ȃ�Ȃ��D
�@21�D������Ƃ��ɓ˕����₷����́C��҂����炩���ߊ��Ƃɓ`���Ă����ׂ��ł���D���Ƃ��C�m���5�`6�K�ɂȂ�ƂƂ�Ő����Ă��˕����C1���ɂ��Ȃ�Ɛ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��D�������C�m��͍ł��e�Ղɐ����I���邱�Ƃ��ł���̂ŁC�܂�����������10���������m��������ĊW���J���������ɂ����܂ܐ���������Γ����ł���D�R��E���P�Ȃǂ̏`���̖�C�����E���a�E�p�E���E���ސȂǂ̖��ɝ�������́C��������˕����₷���D����͏��߂ɕ������Ƃ����ł��˕����₷���̂ŁC�����ĕ���������ɁC���炩���ߊW���J���Ĕ��ł���������Ƃ悢�D���߂̕����Ԃ肪�߂��C���̌�������Ă���ΊW���J�����܂܂ō����x���Ȃ��C�����Ȃ��Ƃ��ɏ��߂ĊW�����Đ�����Ƃ悢�D��}�̏ł́C����͂��̖�1�܂ɂ������Ă���̂ŁC������������j�≺���ɉ������C��������ۂ̕��o���͂�����Ƃ����Ă����Ȃ��ƁC������邱�Ƃ������D���������ČÂ̈�҂́C��a�͕K�������̎�ŏC�����C���t�������ɂ���͂�K�������ŊĎ����Ă����D
�@22�D�{���Ɏ��ڂ���Ă��鏔���ŁC�����̏d�v�Ȗ̐����E�\�͂��m���ɒm��Ȃ��Ȃ�C�l���̖w�u�`�Ɏ��ڂ��ꂽ��̒������ڂ����݂�Ƃ悢�D���͏��X�̖ɂ��āC�b����Ð��̂悤�Ȍ���Ƃ����ǂ��C�K�������ŏ��߂Ď������Ă���D�p������́C���ׂĐ����E�\�͂ɂ��Đ[���m��ʂ��Ă���C���Ƃ̖{���ɂ���ȊO�̐V���Ȓm���������Ă���D
�@23�D�Õ��̕��ʂ����̕��ʂɊ��Z����ꍇ�ɁC�����������Ĉӌ�����v���Ȃ��D�]�����͌Õ���p����̂ɂ��Ƃ��ƕ��ʂɂ͍S�D���Ȃ����C���܂��܌Â����ʂ��g�p����ꍇ�͒C���̐�����ɂ��Ă���D�i�ڂ����͖������m�ꓒ�̍��ɂ���k�C���͌Õ���p����ꍇ�͕K�������Â����̂ɍS�D����K�v�͂Ȃ��C�Ꮭ���_�������v����̕�����1���͍���3�K�Ɋ��Z�ł���Əq�ׂĂ���l�j
�@24�D�{���̏����́C����ނ̌Õ���������160�]�������̑n���ł���D����͂��ʂڂ�ŐV��Ȉ٘_���q�ׂČÐl�ɏ��Ƃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��D��҂͐l�̖����~�����̂ł��邩�炱���ƓV�E���܂��Ƃ����ׂ��ł���C��̏ɑ��������ꂱ�ꐬ���������Č��ʂ��Ȃ���C��S�S�邵�Ď����Ŏ��@���l�Ă�����Ȃ��D�n�������������L���ŁC���x���p���Ă��ׂČ��ʂ�����C���̕����������ɔE�т��ɏڂ����L�^���ĕۑ������D���ꂪ160�]���ł���C�w�͂�ɂ��܂��l�����~�����Ƃ����M��ɔ����C�����ƌ����Ɨݐς��Ċ�����Ȃ����̂ł���D
�@�{���́C�ߐ��̖���E�������̒�����w�����Q���^�E�S�O����i�͖k�Ȋw�Z�p�o�ŎЁC1985�N�j���Q�Ƃ��Ȃ���|��E�ҏW�������̂ł���C�S���e�̖�1/4�ɑ�������D���҂͖L���ȋ��{�l�ł���ƂƂ��ɁC�u�ǂ܂Ȃ������͂Ȃ��v�Ə̂����قǂ̍L�ĂȒ���w�̊w���ƁC����Ɋ�Â��Ǝ��̐[���F���������Ă���C�����ȗ��_�̂��Ƃɕa���E�a�@�E�a�Ԃ���ю��@����ɂ��Ẳ�����s���Ă���D�܂��C�s���ώ@�͂Ɠ��@�͂�������^���ȗՏ��ԓx�̂��ƂɁC�L�x�Ȍo����ς�ł���C�u������10���N�ɂ킽��o�������W�߂�ƁC���x���p���Ď��؍ς݂̕������傤�Ǒ埥�k��Ռo�E�q�����ł̓V�n�̓�����~������㈂��鐔�l�̔{���k100�l�ɂȂ����D���܂̌�ɉ��߂Əd�v�ȏǗ���L�ڂ����D�v�Əq�ׂāC�\���ɋᖡ�������Ȃ��őg�����ꂽ�����̗L���ȕ��܂����ƂƂ��ɁC�����̏Ǘ��t�����ė�����e�Ղɂ��Ă���D�ǂ݂��̂Ƃ��Ėʔ��������[�������łȂ��C�Տ��I�ɂ����ɗL���ȕ��܂������C���ؒ��J�Ȏ��p���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���D
�@�������́C��������Ƃ����C�͖k�ȉ��R���̐l�ŁC1860�N�k���E���L10�N�C���{�̖������N�l�ɐ��܂�1933�N�k����22�N�C���{�̏��a8�N�l�ɖv�����ߐ��̖���ł���D�m���w�̉ƌn�ɐ��܂�C�c�������畃�e�̌O�����Ĉ炿�C������2�x�̉ȋ��̍l���ɒ���Ŏ��s�����̂��C�u�Ǒ��ׂ炴��C�K���Lj�ׂ��v�Ƃ̑c��̐��P������Ĉ�w�̓��֓������D���w�����Q���^�⎩���ɂ́C�u�����ōL��������ǂ݁C�Â��͔_�k�_�_�C�_�Ƃƈ��̐_�ł���C��{�o��Ɨ��̂�����_�_�{���o������Ƃ����l���k����C���v�q����r�̋u�ɏZ�Ƃ���C����o��̒��S�l���l����ŋ߂̍����k���l�̏��Ƃ̒��q�ɂ�����܂ō��v����Ƃ��炩��100��ȏ�̏��Ђ�ǂݒ��ׂ����C��{�o��Ɓ���o����āq�̂��r�����̂͊J�V焒n�̐��_�ƈ�w�̕@�c�ł���C���ꂱ�����C�k���e���[���C�L�͂ł��邱�Ɓl�Ȉ�w�ł���ƒm�����D�����ɂȂ�ƒ����i�q���傤���イ�����r������āᏝ���_�������v������Ă���C��{�o�����o��̌��b�Ƃ�����D�W��̉��f�a�q�������キ���r�k�ᖬ�o����C�������łɎU�킵�Ă��������i�́Ꮭ���G�a�_����S�����l�C����̑��v���q�����r�k�����j��ŏ��̈�w�S�ȑS���ł������}����v���������������l�E���Z�q�����Ƃ��r�k�c��ȑO�l�̈㏑��ҏS�����_�����Ǝ��Õ��܂��͂��߂ē�����������O���v����l�C�v��̐����ȁq�����ނ��r�k����o��Ɋ�Â������͒��߂����C�ᒍ�������_����l�C�����̚g�Ì��q�䂩����r�k�����_�̏ސ����������āᏮ�_�с���l����C��͂蒣���i�̌��b�ł���D�����ɂ͈�w�����W���Đl�˂��y�o���C���u���q���傤�������r�k��f��W�����쐕�W����Ȃǂ��l�E����ցq���傽������r�k���w�����_���_�_�{���S��^��Ȃǂ��l�E������q��������r�k��f����]��Ꮭ������������������Ȃǂ��l�E�O�c�q����˂r�k��_�_�{���o�ǁ�Ꮭ���_�������v����Ȃǂ��l��̏����́C������������i����ѕ������Ȃ���{�o�����o��P���Ă���D���������āC�ނ�̒������㏑�͂�����������Ȉ�w�ł���D�������C�W�E�����猻��ɂ����鏔�Ƃ̒��q�͂悭�ł��Ă͂��邪�C��������ɂ�����܂ŋ��Ԃ̓`���ɋ��X�Ƃ��C���߂�����i�������Ē��؈�w��i�������悤�Ƃ����Ӑ}���Ȃ��D�Â��t�Ƃ��ċM�ԂƂ������Ƃ́C�Ðl�̋K�鏀��ɔ����邱�Ƃł͂Ȃ��C�������i�Ƃ��Ď����̐���k�S�̗얭�ȓ����l��˂��Đ_�q�k���_�ƒm�b�l���v���邱�Ƃł���D����E�_�q�������ɂȂ�[�삷��C����ɌÐl�̋K�鏀����M��Ŏ��グ�C������g�[���C�ω����C���L�G���k�Ӗ��𐄂��L�ߓ��ނ̂��̂ɏo�����炷�ׂĂɋy�ڂ��l���āC�Ðl���w�㐢�̎҂������Ȃ��Ȃ��x�Ƃ��C�ꂢ��悤�ɂ��ׂ��ł���D���̒��̂��Ƃ͂��������������ׂ��ł���C��w�������Ⴄ�͂��͂Ȃ��D�������͂��������l���ʼn��N������܂���w���������C���܂��ܐl�̂��߂ɏ���������Ƃ����ɓ��S����k�v���ʂ�̌��ʂ�������l���C�h�}�̕a��҉邱�Ƃ��ł����D�����掜�k�S��l�̗����N�k�g���̍����w�l�ɗ^������̍��l���Ƃɂ����D���͐e�F�s���邢�Ƃ܂��Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����āC�����Čy�X�ɑ��l�̉��f�ɂ͉����Ȃ������D���܂��܋}�ǂł��邩��Ɛf�@�̋��߂������Ă��C�݂����篁q���킽���r����������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������D�掜�́w�a�Ƃ���҂�҂��]�ނ̂́C���ɓM�����̂����������߂Ă���悤�Ȃ��̂ł��D���Ȃ����������Ƃ��ł���̂Ȃ�C�}���ʼn����ċ~���Ă������Ȃ����D�������C�Տ��ł͏\���ɒ��ӂ��C�b�́q������r�k�e�G�l�Ȃ��Ƃ����Đl���Q���Ȃ��悤�ɐT���܂Ȃ���Ȃ�܂���x�Ƃ���ꂽ�̂ŁC�w�B�B�k�͂��͂��l�x�Ƌ������C�Ȍ�Տ��ƂƂ��ĂقƂ��1������Ƌx�ނ��ƂȂ��C�����܂�10�]�N�Ɏ����Ă���v�ƋL����Ă���D���̂悤�ɁC����o���_�_�{���o����͂��߂Ƃ��ĂقƂ�ǂ��ׂĂ̗��̓T�Ђ��������C����w�̌��r��ς�ŗ͗ʂ����߁C�����Čy���ɂ͗Տ��Ɍ����킸�C�������������̂��͐掜���̋�����S�ɍ��݂��čאS����_�ȗՏ����H���s�����D1918�N�ɕ�V�k�c�z�l�̗�������@�E�@���ɏA�C���C�n���I�ȗՏ��o����ςނƓ����ɁC�����̘_������w�G���ɓ��e���Ė����������Ă���C�����́u����l��Ɓv�̈�l�ɂ������C������E���R���ƂƂ��Ɂu����O���v�Ƃ��̂��ꂽ�D1926�N�ɓV�Âɋ����ڂ��C�����㙹�ʈ�Ёq������������r����э���̒ʐM����w�Z��ݗ����C�����̌�p�҂�{�������D�����ɑ����̎�Ɓk�t�ɑ����q�̎��́l���o�ꂷ��̂͂��̂��߂ł���D�����͐f�Â���Ԃ͒��q�ɂ������ނƂ��������𑱂��C1933�N8��8��74�ŕa�������D�^�ʖڂŔM�S�������ɖ������l���ł��邱�Ƃ��C�o������я����̋L�q���炭�݂Ƃ��D
�@�����Ɂu�����Q���v�Ɩ��Â����悤�ɁC�������͒����㙹�ʔh�k�����㌋���h�l�Ɩڂ���Ă���D�A�w���푈�ȍ~�ɉ��ė̐N�����������A���n�Ɖ����������ł́C��w�ɂ����Ă����m��w�̉e������������Ȃ��Ȃ������Ƃf���Ă���D�����Ɂu���m�����ɓ����Ĉȍ~�C�ېV��`�҂͋������Ă���ɑ���C�狌��`�҂͉���킵�����̂̂悤�ɂ݂Ȃ��̂ŁC���Ɍ݂����ుq�Ă����r�k�����Ⴂ�l���C�I���ɂ͌𗬂���Ȃ��Ă���D���͖}�˂ł��邪�C����̗p��Ɋ��ő����̐���̒�������肢��Ē���̒Z�������Ă���C�������痼�҂ɕ~���������Ă��Ȃ��D���������āC�ْ����Q���Ɩ��������D���m��w�̗p��͋Ǖ����Âŕa�̕W�ɏd�_�����邪�C����w�̗p��͌������Â����ߕa�̖{�ɏd�_������D���ǁC�W�{�͓��R���ڂ��ׂ��ł���C��̏ɋ������ꍇ�́C����ł��̕W����������Ŗ{�������ΕK����������͂��ŁC�Տ��ł��m���Ɏ艞���������Ă���v�Əq�ׁC�����̒����ł̈�w�E�̏������ƂƂ��ɁC���E������w�̓����͂��Ă���D���̑������ɂ����āC�u���͌Ðl����̎���ɐ��܂ꂽ�̂ŁC�Ðl�������ł��Ȃ������d��������������ׂ��ł���C�Â����̂������ĐV�������̂ɂ��C�킪����w�̋P����S�n����Ɍ��`�ł��Ȃ���C����͎��̍߂ł���D�������͖������̂��Ƃ�S�ɂƂ߂āC�V����Y��Ă���܂��w�͂𑱂��Ă���D����܂Ő��m��w���������C���͂܂����̖���ЂƂ�������ɂ��Ȃ��D����ɂ��̖�̑����͌���ł���C�܂��������y������킯�ɂ͂����Ȃ��̂ŁC�����̐��m����̗p���邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��D�������C�{�҂Ŏ����ꂽ���m��w�͈�w���_���̗p���������ł͂Ȃ��C��ɂ��̉��w���_���̗p���Ă���C����̉^�p�ɂ͒�����w��Z�������Ĉ�̉����C���̖���̗p�����ꍇ�ɂ��C�L��̊w�k���������ȗ����ł₽��u�߂���悤�Ȋw��ԓx�l�Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ��v�Ƃ��L���Ă���D���Ȃ킿�C�}�����Ė��ᔻ�ɐ��m��w��������Ă���̂ł͂Ȃ��C�u�����v���Ȃ킿����w�Ƃ����m�ł���y��̂��ƂɁC�u�Q���v���Ȃ킿���m��w�̊w���E���w�E�Ȃǂ���ѐ����������č̗p���C����w����蔭�W�����悤�Ƃ̈Ӑ}�������Ă���̂ł���D
�@�������Ȃ���C�����̐��m��w�͍������炷��Ƃ��Ȃ薢�n�ł���C���Öʂł��݂�ׂ��������Ȃ��C�����̖����݂ł͉ߋ��̈╨�ɂȂ��Ă��܂��Ă���C����ɂ͒���w�ɗ��r���钘�҂ɐ��m��w�ɑ������������⌡������݂��邽�߂ɁC�{���ł͑����̕����Ő��m��w�Ɋ֘A�����L�q���������Ă��邱�Ƃ��C��e�͊肢�����D
�@���w�����Q���^���1918�`34�N��16�N�ԂɎ��X�Ɗ��s����C�S����30������Ȃ��Ă���k1957�N�Ɉ�e���攪���Ƃ��ĉ�����ꂽ�l�D���s�͈̏ȉ��̂悤�ł���D
�@�����@�e��a�Ǝ����V�� 1918�N�o�ŁD
�@�����@�e��a�Ǝ����V�� 1919�N�o�ŁD
�@��O���@�e��a�Ǝ����V�� 1924�N�o�ŁD
�@�ȏ�́C�O�O�����ҏ㉺���E8���Ƃ��Ă܂Ƃ߂��C1929�N�o�ŁD
�@��l��5���@����@1924�N�o�ŁD
�@��܊��㉺���E8���@�e���_�@1928�N�o�ŁD
�@��Z��5���@�e��Ǘ�@1931�N�o�ŁD
�@�掵��4���@�����_�a�@1934�N�o�ŁD
�@���̌�C�S����30���ɑ攪���������C���w�����Q���^��㒆���̎O���{���C1934�N�ɉ͖k�l���o�ŎЂ��犧�s����C���ꂪ���݂Ɏ����Ă���D
�@�ȏ�̂悤�ɁC�����͖�16�N�ɂ킽�莟�X�Ƒ���������Ȃ��珑����Ă���C��ɂȂ��ĕa��������V���Ɉ�_���[������C�����a�̏Ǘ��lj�����Ƃ������z�����Ȃ���Ă���̂ŁC���݂ɎQ�Ƃ��邱�Ƃ�������[�߂邤���ōł��]�܂����D�����Ŗ{���ł́C�����̔z���������x���d���Ȃ���C���ݎQ�Ƃ��e�ՂɂȂ�悤�ɓ��ނ̋L�q���܂Ƃ߂�`�ɕҏW���Ȃ����Ă���D�c��ȓ��e���ꋓ�ɒł��Ȃ����߁C�܂����ȎG�a�̖��Ɩ���ɂ��ڂ��Ă���D�v�]��������C���̕��������������o�ł̗\��ł���D
�@�Ȃ��C�����͖���7�`23�N�ɏ�����C�Ӗ����Ƃ�ɂ����\���������̂ŁC�����ɖ��{���Č������c���z�����s���Ă͂��邪�C�S�̂����㕶�Ƃ��ĈӖĂ���D
�@�{���ɂ���ĐV���Ȑ[���F���������C�Տ��ł̐��ʂ���荂�߂��邱�Ƃ����҂��Ă���D
�@�}��
�@1�D�{���́��w�����Q���^��㒆�������甲�����ҏW���Ȃ����Ă���C���R�z�قȂ��Ă���̂ŁC�e���Ɂu��O���~���v�ƕ\�����Č������Q�Ƃ��₷�����Ă���D
�@2�D���㕶�Ƃ��ĈӖC�K�X�Ɂu�@�v�ł���������C���ė������₷�����Ă���C�s�K�v�ƍl�����鐼�m��w�I�L�ڂ͊��������D
�@3�D�i�@�j���͌����ł���C�k�@�l���͖ł���D
�@4�D�������܂ɂ��ẮC�g���Ɗ֘A�������r�ň͂݁C�������₷�����Ă���D
�@5�D���ł́C��_�_�{���o��̓��e���e�̐擪�̕����ɑ}�����Ă���D��{�o�▢���ڂ̖ɂ��Ă͂��̌���łȂ��D
�@6�D�����ɂ́C����p��E�a�E���ܖ��E�̍������Ă���D
�@�k�Q�l�����l
�@������w�厫�T�F�ӊϓ��Ҏ[�C�������X�C1990�N�D
�@�{���o�`�`�F����ώ�ҁC�l���q���o�ŎЁC1990�N�D
�@����w�F�琳�؎�ҁC�l���q���o�ŎЁC1991�N�D
�@��j�蒠�F����L猕Ғ��C���{TCM�������C1993�N�D
�ጾ�k�����̖}��l
�@1�D���𖾂������߂̏��́C��_�_�{���o��ł���D���̏��͕������g����悤�ɂȂ����ŏ��̏��i��Ձ�͂���ȑO�ɑ��݂������C���̂���͂܂������͂Ȃ������j�ł���C�ȍ�i�Ȃ�����Ñ�ɕ����������̂ɗp�����|�ЁD�ȍ�͏��Ђ̈Ӂj�̌Â����킩��D���̏��ɂ͍��v365���̖L�ڂ���C���̐���1�N�Ԃ̓���������킷�D������㒆����3�i�ɕ����C��i�͗{���̖�C���i�͎��a�̖�C���i�͍U�a�̖�Ƃ��Ă���D�e�i�̉��ɂ́C���ׂďڍׂɋC���Ǝ厡���L���C�C���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃɂ��厡�̗��R�������Ă���D�܂��C���Ǝ��̗ǔ\��������C�C������O�����̂����邪�C�Ð��͂��ׂĂ�m��s���Ă�����ЂƂ�\�o���Ă���C��w�ɂ�����V�n�J蓂̕@�c�Ƃ�����D��l�͎������ł��邽�߂ɁC�Ǝ��̗ǔ\����Ă��Ă��C�C�����琄���ʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ���C���ׂč폜���L�ڂ��Ă��Ȃ��D���Ƃ��C�j�}�͏�C�f�z�i�z���Ă����B�����ɓf�o����C���Ȃ킿�b�̕s�[�C�ł���j�ɔ��Ɍ��ʂ�����C��{�o��ɋL�ڂ����邪�C�㐢�̖{���ɂ͋L�ڂ��Ȃ��D�܂��C�R��͊��M�����i�̋����ɂ܂����ꍇ�̊��M�����j�ɔ��Ɍ��ʂ�����C��{�o��ɋL�ڂ����邪�C�㐢�̖{���ɂ͋L�ڂ��Ȃ��D���̂悤�Ȃ��Ƃ͖����ɉɂ��Ȃ��D���͂������݂邽�тɐ[���Q���ɂ��݁C���̂��ߖ{���Ŗ�_�����ӏ��ł͂��ׂā�{�o��ɏ]���C�㐢�̖{���͌y�y�ɍ̗p���Ă��Ȃ��D�ǂ̑��D�ǂ̌o���ɓ��邩�̖��m�ȋL�ڂ��Ȃ��Ƌ^�����̂����邪�C�ǂ�ȕa����邩��m�炸�ɁC��͂��ǂ��Ɏ��邩��m�낤�Ƃ����̂ł��낤���D���߂�C����Ɩ�͋C���ɐ����ė��s������Ȃ����͂Ȃ��D�㐢�C�ڍׂɑ��D�o���ɕ����Ă���̂́C�������Ċw�Ԃ��̂ɍS�Ёk�������Ȃ��Ɓl�̕����c���悤�Ɏv����D
�@2�D�����Ȉ�w���_�́ቩ����o��Ɏn�܂�D���̏��͉���Ɛb���ł���E�����E�S�k�E�����̊Ԃ̖ⓚ�`���ŏ�����Ă���C��f���Ɓ�쐕��ɕ������D��f���̗v�|�͖�ɂ�鎡�a�ɂ���C��쐕��̗v�|�͐j���ɂ�鎡�a�ɂ���D�������C�N�オ���ɌÂ��̂Ō������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��D�Ñ�̑��`�͌����ɂ�邱�Ƃ������e�ՂɖS�������̂ŁC�W��̍c��捁k��b���o����l�͂��̏��͕s���S�ł���Ƃ����C�v��̗щ��͂��̏��ɂ͋U��k�U��l������̂ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă���D����ɒ��i�́Ꮭ���_��̏��Łu��f���9����p���ĕ��͂��������v�Əq�ׂĂ��邪�C���݁�f����24������C���̒��ɂ͋U����邱�Ƃ��킩��D�������C���̊j�S�����͐��_�̎c�������t�ł��邱�Ƃ͊m���ł���C�f���ċU��҂ׂ̈���킴�ł͂Ȃ��D���Ƃ��C�j���ɂ�鎡�Â͍��ł͐��E���ŔF������Ă��邪�C�����Ð����n�߂Ă��Ȃ���C�㐢�ɑn���ł����ł��낤��?�@���m��w�ŏڂ�����U���u�`������̂��n���ł���ł��낤���D����o���ǂޕ��@�Ƃ́C�����M�����镔�����ڂ����������ĉ���邱�Ƃł���C��������Ζ����̖@��k�w�ɓ��鏇�����@�l���J�����Ƃ��ł���D�M�����Ȃ������́C�㐢�̋U�������Ȃ��̂ŁC�_�y���Ȃ��Ă����܂�Ȃ��D����͖Ўq�̂�����u���s���͐M����v�̈ӂł���D���ݐ��m�I�ȕ��@�ɕΏd������̂́C����o��̐M����ɂ��镔���̌����ɓw�͂����C�M�p����������ɗ͎w�E����݂̂ł���D���̈ӌ��𐄂��i�߂�ƁC����o��̐^�{�͂Ƃ��Ɏ����Ă���C���ɓ`�����̂͂��ׂċU��ł��邱�ƂɂȂ�D����ȗ���������ł��낤��?�@����ꂷ�ׂĂ̓��E�݂͂ȉ���̎q���ł���ɂ�������炸�C��c����l�ɗ^�����T�Ђ������݈�w��ɕۑ����悤�Ƃ������C���ׂ����r���������ĂĔj�����Ă��܂��̂́C�܂������Q���킵�����Ƃł���D���������āC�{���̊e�咆�ł́���o��ɂ̂��Ƃ��ďq�ׂ����������ɑ������C���o��Ꮭ���_�������v����Ȃǂ̂悤�Ɂ���o��ɂ̂��Ƃ����㐢�̈㏑�����ɍ̗p���Ă���D
�@3�D�{���ɋL�ڂ������܂̑����͎����n���������̂ł���C���ɌÐl�̐�����p�����ꍇ�ł���ɉ������Ă���D�����ɓƎ��̌����������Ă���ꍇ�ɂ́C���̕����ꏏ�ɍڂ��ďڍׂɉ�������D�܂��e��̕��̌�ɐ��m��w�̏�p���C����ю����Ď��ۂɌ��ʂ����������m���t�^�Ƃ��ċL�����D���D�o����_����ۂɁC��ɓ��Ƃ̐����č̗p�����̂́C���Ƃ��ƌ𗬂����邩��ł���D�܂����ɐ��m��w�̐����̗p�����̂́C��U�Ŏ��ۂɍl���Ă��邩��ł���D
�@4�D�Ðl�̗p��̑����́C1�x�ɑ�ʂ������3��ɕ����ĕ��p�����C�a��������ΕK�������܂�s�������C�����Ȃ���ΕK��1���ł��ׂĕ��p������D���̕��@�ɂ��Ă͍��̐l�X�����ӂ��͂��Ȃ��Ȃ��ċv�����D���͏����Eu�Ƃ��ׂĂ̋}�������ɂ͕K�����̕��@��p���Ă���D�����̏̎��Â͏��Ɏ��Ă���C�����Ԃ�������Ɖΐ��͂�␊���邪�C���X�ɐ��������Â��Ȃ���Ή̐������Ă�����ɂȂ�C����܂ł̌��ʂ��܂������Ȃ��Ȃ�D���̎��Âł́C�K������1����3�p����K�v�͂Ȃ����C���[�e1�p�i�������c�Ԃ�����1�x�����ĕ��p����̂�1��Ƃ݂Ȃ��j���Ė�͂𒋖�p��������ƁC���ʂ����������D
�@5�D�T���ȉƂł͕���ۂɎ����k��Ԑ����l��p���Ȃ����Ƃ��������C�����͎������~�߂Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ𗝉����Ă��Ȃ��D�T�_�a���k����̑m�D��T�_������l�͉A���J�M�̎��Âɐ�玟����p�����D�����͖����W�Ŕ\���B�A��{���D�u�W�C�͈݂ɋA���v�Ɓ���o��ɂ��L�ڂ�����D�W�͔\���B�A��{���̈Ӗ��́C���Ƃ��Ɓu�W�C�͈݂ɋA���v���炫�Ă��邪�C���̗��R�𗝉����Ă��Ȃ����̂������D����فk����̈�ƁD����ցl�́C�u�^�́k�V�n�̑�@�D���o�̍^�͂��w���l�͌܍s�̖��ɂ��āw���͏�����H���C�������c���삷�D�͉����H���C����͋���삷�D�͋Ȓ���H���C�Ȓ��͎_���삷�D���͏]�v��H���C�]�v�͐h���삷�x�Ƃ������C����������̂��̖̂{�����q�ׂĂ���D�y�ɂ��ẮC���̕���ς��w�y�͉��p�k��܂��Ǝ��n�l��ুq�����r���C���p�͊Â��삷�x�Ƃ���D�y�͖{�������ł���C���p�̖�����Ė��Ƃ���̂ł���D�����Ƃ͂��Ȃ킿�W�ł���C���������Đl���B�݂͓y�ɑ����C�����W�ł�����̂͂��ׂĔ\���B�݂ɓ���v�Əq�ׂĂ���D�܂��C�A���̎��Â͐���B�ɏd�_�����邱�Ƃ��������Ă��Ȃ����̂������D�C���k����̈�ƁC�O�c�l�́u�B�͑��A�ł���C���Ȃ킿�O�A�̒��ł���D�̂ɉA���������ꍇ�́C�B�A���������Ƃ���ɂ��ׂ��ł���C�B�A�������Ύ����Ə����D����ł���v�Əq�ׂĂ���D
�@6�D���Փ����ɗp������ẮC�Õ��ł͐���p���C����ł�����p���Ă���D��䏐m�q�悭���ɂ�r�E�����q���r�E�R��̗ނ��C��ĂƓ����ł���D���Ƃ̖{���ł́C�u�u�p�v�ƒ��߂�����̂��������C�u�p�͊ێU�ɂ��Ă݂̂ł���D���݂ł͓��܂ɗp����ꍇ�ɂ��K���u�n���邪��������D��猒�B�݂݂̂ɗp����Ȃ��u���Ă��悢���C�~�b���Ɏg�p����Ƃ����u���ׂ��ł͂Ȃ��D���͏`�����f�S�ł��邩�環�݂ɗ������邪�C�u�n�������͎̂ςĂ��`���͂Ȃ�����ł���D���A�ɗp���悤�ƁC�W���ɗp���悤�ƁC�u�n���ׂ��łȂ����Ƃ́C�ɂ߂Ė����ł���D
�@7�D����̓}�Q�͌Ñ�̐l�Q�ł���C�R���n����}�̎R�J�ɐ��炷��̂œ}�Q�Ƃ����D�R���ܑ̌�R�ɐ�������͍̂ł��D��C���ʂɑ�}�Q�Ƃ����D���݂̗ɓ��l�Q�Ƃ͖{���킪�قȂ�C�C���E���a�ł���C���ۂɗɓ��l�Q���g�p���₷���C����ɔ��ɗ����ŕn�������̂ł����p�ł��C���ɍϐ��̗ǖ�ł���D���݂͗ɓ��n���ł��}�Q�������C���ׂĂ��R���Y�ł͂Ȃ��D�������K���}�Q�̔�ɂ͉��䂪����C�Ӂ����q���炢�ӂ��r�k�H�p�̐l�Q�l�̖�̂悤�ŌӁ����̖��肳��ɖ��Ȃ�Ζ�R�Ɏ�������}�Q�ł���C�����l�Q�̑�p�ɂ���Δ��Ɍ��ʂ�����D���䂪�Ȃ���C���n�͔̍|�ł���C�g�p�Ɋ����Ȃ��D�܂��C�{���ŗp����l�Q�͂��ׂĖ�}�Q�ő�p���Ă��悢���C�ɓ��ō͔|�����l�Q���p���Ă͂Ȃ�Ȃ��D�ɓ��ō͔|�����l�Q�͑��ɍ���Q�ƌĂ�C�����M�ł��邩��y�p���ׂ��łȂ��C�����Eu�q�����r�̏������Ɏg���͍̂ł��悭�Ȃ��D�܂����}�Q�q��Ƃ�����r�́C��̐F�����g�ł���C�����̎��c�R�ɐ��炷��̂ŁC���c�Q�Ƃ������D���}�Q�̕�͂͑�}�Q�ɕC�G���C�����ŔM���ł͂Ȃ��̂ŁC�C���L�M�ɍł��K���Ă���D
�@8�D���ˁq�������r�܂ɓ����ꍇ�́C���p���Ȃ킿�n�p�Ƃ������ƂɂȂ�C�K��������ɖ��t�q�݂�����r����K�v�͂Ȃ��D�ێU�ܒ��ŏn�p���ׂ��ꍇ�́C���t�����悢�D�ᇂ̎��Âł́C�ێU�ł��t�p���ׂ��ł͂Ȃ��D���^���k����̈�Ɓl�͂��̂��Ƃ���؎��S���W��ŏڂ����q�ׂĂ���D�u�����ɂ͐���p���C�~���ɂ͏n��p����v�Ƃ������Ɏ����ẮC�܂������ł���߂ł���D�C���̋��ׂ������Ŋ����o����̂́C���˂p��������Ɏ~�܂邪�C�z���A���������Ŋ����o��Ƃ��́C���˂p����������đ劾���o��D�C���Œ��O�o�ł��Ȃ��ꍇ�́C���\��Ɠ�������Ί����o�����Ƃ��ł���D���������āC�~�����邩�������邩�͐����n�̈Ⴂ�ł͂Ȃ��C�����ɂ����p���邩�ɂ��D
�@9�D�p�͊��Ŕ��U�ɓ����̂ŁC�O�����M�̎��Âɂ͋��O�̉��l������D��_�_�{�o��ɂ́u�����v�Ƃ���C���劦�ł͂Ȃ����Ƃ��킩��D����Ɂu�Y���������v�Ƃ���̂ŁC�����ɏ��ǂł��邱�Ƃ��킩��D���l�̑����͑劦�ƌ�F���ā��p���邽�߂ɐh�U�̐��������ʂɕς��Ă��܂��Ă���i�����̐����ɏ���������p�͕K�����q��r���̂́C���ʂ��邩��ł���j��p�q���������r���O�����M�ɗp�����1���p���Ă����l����̂́C�O���̔M�͎U����ׂ��Ŏ��ʂ��ׂ��ł͂Ȃ�����ł���D��ʂɁ��p��p���Ď��Â�������ꍇ�C�߂������������Ƃɂ����Đp�̂����ł͂Ȃ����Ƃ��킩�炸�C�t�Ɂu�p�́��p���Ă�����قǖҜ��ł��邩��C�����Ȃ�������Ēm��ׂ��ł���v�Ƃ����C���ɂ͐��p��|���邱�ƂɂȂ�D�����Ŏv�����ėp���Ă���������7�`8�K�Ɏ~�߂邪�C�p�̎��͔��ɏd���C7�`8�K�ł���B�q�܁r�݂ɉ߂��Ȃ��D�ɂ߂ďd�ǂ̊�����҉�̂ɔ������B�݂ł́C�Ƃ��Ă����ʂ����҂ł��Ȃ��D�����Ŏ��͊O�����M�̎��Âɂ́C�y�ł��K��1�����x�C���M�������Ȃ���3�`4���g�p���邱�Ƃ������D��𒃘q���t�ɐ�����3�`4��ɕ����ĉ���������̂́C�a�Ƃ̋^����Ƃꂽ�����߂ƁC��͂��ł��邾����łɂƂǂ߂Ċ��������ł�N�����b�������N�����Ȃ��悤�ɂ���������ł���D�p�p���ĊO�����M�����Â���Ȃ�f���Đl�����Q����͂��͂Ȃ��C����Ɏv�����đ�ʎg�p����Βf���ĔM���ނ��Ȃ��͂��͂Ȃ��D�������C��ǂōׂ����҂����p����p�������C����Ⳃɖ��m�ɐ��Ə����Ă����p���[�Ă邱�Ƃ������D���Ƃ��Ɣ��~���Ă�����̂����p�ł��邤���ɁC����ɖ�ǎ���T�d�ɂȂ��Ă���̂������ł���D���������āC���p��p����ꍇ�́C�͂�����Ɛ������p����w�����ׂ��ł���C�ׂ����҂��Ƃ���������ŊĎ����Ȃ���Ίm���ł͂Ȃ��D
�₢�F�����p�Ȃ̂ɁC�ǂ����Đ��͔\���U���C�����ΐ������U����}�ɝʂɕς��̂�?�@�����F�Ζ�̐����͑��ؖ�Ƃ͈قȂ�C���������̂Ɓ����Ȃ����̂ł͏�ɐ������ۗ����ĈقȂ�D�O���͖��łł��邪�C�����ΗL�łɂȂ�D�ΊD��������ƐΊD�ɂȂ�C����̐������}�Ɍ���C���𒍂��Ɖ̂悤�ɔM���Ȃ�D�p�͂��Ƃ��Ɨ����E�_�f�E���f�E�J���V�E�������������������̂ł���C�����Η����E�_�f�E���f�����ׂĔ��ł��܂��C�c�����J���V�E���͕ϐ����ĐΊD�ɂȂ�C�ُ�ɔS�a�ɂȂ�D�����ŏėm�D�͕K���p�𑽗p���邪�C�m�D�k�Z�����g�l�p�ł��邾�낤���D���������āC�p������Ċʂ̒�Ɏc�Ԃ��Ì�����Ƃ��́��p�ł��邩��C���̖�͐�ɕ��p���ׂ��ł͂Ȃ��D
�@10�D�אh�́u1�K�ȏ㕞�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̐�������C�㐢�̈�҂ɂ͂����ے肷��҂��������C���̐��͌������낻���ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�m��Ȃ��̂ł���D�אh�Ɍ��炸�Ԟ��E�V�Y�E�����Ă̂悤�ɁC�����h�œ����Ɍ������т��悤�Ȗ�́C�����Ă��݂ȕ��Q������D�������тꂳ������͔̂x�����тꂳ���C�x�����т��ƌċz�������ɒ�܂�D���Ĉݒ����₦���̂ʼnԞ���30�������Ĉ��݂��ނƁC�����ɋC����B���Ȃ��Ȃ�̂��킩��C���炭���Čċz���悤�₭���Ƃɂ��ǂ����D�����ŁC�Ðl�͎�N���Ђ߂�ƉЂ������邱�Ƃ�����C�Ԟ��𝑂��Čg�т���k�Ԟ������Ɋ܂��Ⴢꂳ���s�p�ӂɊЂ߂��肵�Ȃ��悤�ɂ���l���Ƃ�����Ӗ���������D���ꂩ��݂�Ɨp��͐T�d�ł���˂Ȃ�Ȃ��D
�@11�D���Ă͍~�t�~�q�̎��ł��邪�C���ݖ�ǂł͔��H�q�͂���r�Ő����Ă���D�~�t�C�E�~�q�f�ɗp����ƕ��p��ɋt�ɏǏ܂��܂��������Ȃ鋰�ꂪ����̂́C���H�����f���C��U�����邩��ł���D���͔��ĂŚq�f�����Â���ۂɂ́C�K���������Ŕ��Ă𐔉����Ė��H����������������悤�ɓw�߂Ă���D�������C�ۂɂ͊܂܂�閾�H�ʂ��l�����Č��߂�ꂽ�ʈȊO�ɑ����̔��Ă������Ă����C���ꂢ�ɐ����ĎN�������������̂����Ƃ̕��ʂɑ����悤�ɂ���D��ǂ̎��̂悢�����Ă͖��H����r�I���Ȃ����C�p����ۂɂ͂�͂�ׂ��ł���D��ႂ̖ړI�Ȃ�C�����Ă���Ȃ��Ă��\��Ȃ��D
�@12�D�����E���a�͎��G��ړI�Ƃ���ꍇ�́��p���Ă��悢�D���A�E�ʉ��邢�͎��ʂɌ��˂ĊJ�ʁi�����E���a�͂�������ʂ��Ĕ\���J���j��ړI�ɂ���Ȃ�C�����Ă͂Ȃ�Ȃ��D�ێU���ɗp����Ȃ�������Ă��悢�D���݁C���ׂā���p���Ă��邪�����Ă̂ق��ł���D
�@13�D�R��q�����r�̊j�k��l�͏��֕s���𗈂����̂ł��Ƃ��Ɩ�ɓ����ׂ��ł͂Ȃ��D�������C�c�ɂ̖�ǂŔ����Ă���R��͉��X�ɂ��Ċj�Ɖʓ������X�ł���C�r�������ꍇ�͊j���ʓ���葽�����Ƃ�����D�������Ɂu�j�����ׂď����v�Ɩ��m�ɒ��ӏ���������Ă��C��͂菜�����Ă��Ȃ����Ƃ������̂ŁC���Â̖W���ɂȂ邱�Ɛr�������D�{���ł͎R����ʂɎg�p�����d�Ăȏ̎����Ⴊ���ɑ����D���͎g�p���ɕK�������œ_�����邩�C�j�����ׂď����K�v������Ɛ������ĕa�Ƃɓ_�������C���������ʂ��܂��₤�悤�ɂ���ƁC�ԈႢ���N���Ȃ��D�R��̌��p�͋~�E�ɒ����Ă��邪�C�\���ŒE���闝�R�͎_�����ɂ߂ċ������Ƃɂ���D�������C���߂�Ǝ��X�_�����قƂ�ǂȂ����̂�����C���������R��͎g�p�Ɋ����Ȃ��D��}�̏ɂ́C�K�����߂Ď_�����ɂ߂ċ������Ƃ��m���߂Ă���p���Ȃ���C�D�ꂽ���ʂ邱�Ƃ��ł��Ȃ��D
�@14�D���j�͋C���Ƃ��Ɍ����C�����Ԑ�����̂��ł��悭�Ȃ��D��ǂł͝��q�r���čז��ɂ��Ă�����̂������C����������Ɩ�͂������Ɍ����C��10�������������ƂȂ�����ł���D�p�͋C���Ƃ��ɒW�ŐΎ��ł��邩��C�ׂ��������Đ����Ȃ���Ζ�͂��o�Ȃ����C��ǂłׂ͍��������Ă��Ȃ����̂������D�����Ŏ��́C�p�͕K�������čז��ɂ��Ă�������C���j�͑e����������邾���ʼn�̂܂ܐ�����D���j��p�ɗނ����́C���j�E�p�ɂȂ炤�̂��悢�D
�@15�D�����E�v��͐��p���ł��悭�C�J���J�����u���Ă͂Ȃ�Ȃ��D�ێU���ɗp����ꍇ�́C�܂��҂��đe�������ɂ��C����~������ɓ���Ĕ��Ηn����܂�����C��܂��Ă���҂��čז��ɂ���D���ꂪ�����E�v�����������������@�ł���D
�@16�D�З��E�ČӂȂǂ͖{�������p�Ƃ���D��ǂ̂��̂ɂ͕K���s��t�����݂��Ă���̂ŁC��҂ɑI�ʂ���m�����Ȃ��Ǝ������\��������D�אh�̗t�̌��p�͍��Ɣ�ׂ悤���Ȃ��̂ŁC���m�k����̈�ƁC�������l����{���j�ځ�Łu����p����v�Əq�ׂĂ���D������q����͂��Ёr�ƌK����́C����������̔��p���邪�C���ꂪ�{�����ۂ��͍ł��ٕʂ���̂ŁC�g�p����ꍇ�͎����ō̎悷��̂��m���ł���D��������͑傢�ɉ��ł��ŏa����D����C��t���̒��}����������͑�ւ�ʂ���D���ɓ`���֖@�ł́C��֕s�ʂɐ߂̒�����1���قǂ̔�t���̒��}7�߂ɐ����ĕ��p����Δ��Ɍ��ʂ�����D���̎}�ƍ��̐����͂��̂悤�ɈقȂ�̂ŁC�g�p�ɂ������Ă͐T�d�łȂ���Ȃ�Ȃ��D
�@17�D���ސ͓S�Ǝ_�f�̉������ŁC�����͓S�K�Ɠ����ł���C���Ƃ��Ɓ����ׂ��ł͂Ȃ��D����ق́u����������Đ|�ɐZ�������̂͏��x����v�Əq�ׂĂ���D�{���̏������ɂ�����ސ́C���ׂĐ����ސ��ׂ����҂��ėp����ׂ��ł���D
�@18�D��ɂ͏C�����Ă��Ȃ���ΐ�ɕ��p���Ă͂Ȃ�Ȃ����̂�����C���āE���q�E�ǐm�Ȃǂ̗L�Ŗ�͂��ׂĂ���ł���D�Õ����̕��q�́C���܂��܁u���p�v�Ƃ����Ă����ۂɂ͉����ɒЂ������̂ł���C�{�n�q�ق����キ�r�������q�ł͂Ȃ����C�̎�シ���g�p����̂ł͂Ȃ��D���̂悤�Ȗ́C�����ɂǂ̂悤���{������̂����m�Ȓ����Ȃ��Ă��C��ǂł͕K���C�����Ė��łɂ��Ă���D�{���ł��Ȃ��ŁC���Ƃ��Ɛ��p���Ă悢���̂́C�{���̕����ŏC���ɂ��Ă̖��m�Ȓ����Ȃ���C���ׂĐ��p���ׂ��ł���D�{���̏�����p����ꍇ�́C��̖{���̐����������悤�ȕʂ̏C���������Ă͂Ȃ�Ȃ��D
�@19�D�Ðl�̕�����@�́C�a�����ɂ���ΐH�O�ɕ��p���C�a����ɂ���ΐH��ɕ��p����̂����܂�ł���D�㐢�̐l�ɂ́C�u����ƕK���B�݂����������̂��ɖ�͂��l�B����D�a����ɂ����ĐH��ɕ��p����C�B�݂͕K���܂��h�H�k�O����̐H���l���������C���̌�ɖ���������̂ŁC���������߂Ă��t�ɒx���Ȃ�v�Ƃ������̂�����D���̐��������ɍ����Ă���悤�ł��邪�C�ԈႢ�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��̂ł���D��͂��S�g���s��̂́C�l�g�̋C������Ė�͂�`�B����̂ł���C���傤�Nj�C������`����悤�Ȃ��̂ł���D�����̊Ԃɋ�C���Ȃ���C�ǂ��Ő����悤�Ƃ��̏�Ŏ~�܂�D�l�g�̋C�����Ȃ����C�B�݂����������Ă��S�g�ɓ`�B���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��D�l�g�̋C���̗��s�ɂ͂��Ƃ��Ƒ��D�̋��E�͂Ȃ��C����������͂����ɋC���ƂƂ��ɍs��C���̓`�B���x�͋ɂ߂đ����C�����Ƃ����ԂɑS�g�ɍs���n��D�������C��C������`����̂͑������C���������قǐ��͂������Ȃ�D���̂��Ƃ���C���ɂ���̓`�B�𐄑�����ƁC���������Ɩ�͎͂���Ɍ��ނ���D���������āC�a�����ɂ���ΐH�O�ɕ��p���C�a����ɂ���ΐH��ɕ��p����̂́C���a�ϕ��ʂɋ߂Â������Ē��B����͂��ł����������邽�߂ł���D
�@20�D���܂ł͖�������t�ʂ����Ȃ��̂͂悭�Ȃ��D���Ȃ��Ɩ�`�̑唼�������Ԃ̒��Ɏc��D���A���̖�ł́C���ɖ�`�𑽂����Đ����Ȃ���Ό��ʂ��Ȃ��D���������Ė{���ł́C�d�܂�p����ꍇ�͕K�����`�𐔔t�Ƃ��Đ���ɕ����ĕ��p����D�܂��C����Ė������߂��Ċ��オ�����ꍇ�ɁC��������1�x����Đ����Ă���͖{���̐����������Ă���C���p����ƕa�͕K���������Ȃ�̂ŁC�p�����ׂ��ŕ��p���Ă͂Ȃ�Ȃ��D
�@21�D������Ƃ��ɓ˕����₷����́C��҂����炩���ߊ��Ƃɓ`���Ă����ׂ��ł���D���Ƃ��C�m���5�`6�K�ɂȂ�ƂƂ�Ő����Ă��˕����C1���ɂ��Ȃ�Ɛ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��D�������C�m��͍ł��e�Ղɐ����I���邱�Ƃ��ł���̂ŁC�܂�����������10���������m��������ĊW���J���������ɂ����܂ܐ���������Γ����ł���D�R��E���P�Ȃǂ̏`���̖�C�����E���a�E�p�E���E���ސȂǂ̖��ɝ�������́C��������˕����₷���D����͏��߂ɕ������Ƃ����ł��˕����₷���̂ŁC�����ĕ���������ɁC���炩���ߊW���J���Ĕ��ł���������Ƃ悢�D���߂̕����Ԃ肪�߂��C���̌�������Ă���ΊW���J�����܂܂ō����x���Ȃ��C�����Ȃ��Ƃ��ɏ��߂ĊW�����Đ�����Ƃ悢�D��}�̏ł́C����͂��̖�1�܂ɂ������Ă���̂ŁC������������j�≺���ɉ������C��������ۂ̕��o���͂�����Ƃ����Ă����Ȃ��ƁC������邱�Ƃ������D���������ČÂ̈�҂́C��a�͕K�������̎�ŏC�����C���t�������ɂ���͂�K�������ŊĎ����Ă����D
�@22�D�{���Ɏ��ڂ���Ă��鏔���ŁC�����̏d�v�Ȗ̐����E�\�͂��m���ɒm��Ȃ��Ȃ�C�l���̖w�u�`�Ɏ��ڂ��ꂽ��̒������ڂ����݂�Ƃ悢�D���͏��X�̖ɂ��āC�b����Ð��̂悤�Ȍ���Ƃ����ǂ��C�K�������ŏ��߂Ď������Ă���D�p������́C���ׂĐ����E�\�͂ɂ��Đ[���m��ʂ��Ă���C���Ƃ̖{���ɂ���ȊO�̐V���Ȓm���������Ă���D
�@23�D�Õ��̕��ʂ����̕��ʂɊ��Z����ꍇ�ɁC�����������Ĉӌ�����v���Ȃ��D�]�����͌Õ���p����̂ɂ��Ƃ��ƕ��ʂɂ͍S�D���Ȃ����C���܂��܌Â����ʂ��g�p����ꍇ�͒C���̐�����ɂ��Ă���D�i�ڂ����͖������m�ꓒ�̍��ɂ���k�C���͌Õ���p����ꍇ�͕K�������Â����̂ɍS�D����K�v�͂Ȃ��C�Ꮭ���_�������v����̕�����1���͍���3�K�Ɋ��Z�ł���Əq�ׂĂ���l�j
�@24�D�{���̏����́C����ނ̌Õ���������160�]�������̑n���ł���D����͂��ʂڂ�ŐV��Ȉ٘_���q�ׂČÐl�ɏ��Ƃ��Ƃ������̂ł͂Ȃ��D��҂͐l�̖����~�����̂ł��邩�炱���ƓV�E���܂��Ƃ����ׂ��ł���C��̏ɑ��������ꂱ�ꐬ���������Č��ʂ��Ȃ���C��S�S�邵�Ď����Ŏ��@���l�Ă�����Ȃ��D�n�������������L���ŁC���x���p���Ă��ׂČ��ʂ�����C���̕����������ɔE�т��ɏڂ����L�^���ĕۑ������D���ꂪ160�]���ł���C�w�͂�ɂ��܂��l�����~�����Ƃ����M��ɔ����C�����ƌ����Ɨݐς��Ċ�����Ȃ����̂ł���D
�͂��߂�
�}��
�ጾ�k�����̖}��l
�A���J�M����
�@�������q�������Ƃ��r
�@�\�S��^���q���イ��������Ƃ��r
�@�Ґ���q�ꂢ����r
�@�ꖡ���P���q�����݂���悢��r
�@�Q�����q������Ƃ��r
�@��ʓ�q���ガ�傭�ɂق�����r
�@���ᓒ�q�悭���Ƃ��r
�@�������q�������傤�Ƃ��r
�@���ϓ��q�������Ƃ��r
�@�������q�炢�ӂ��Ƃ��r
�@���ۓ��q���Ƃ��r
���J�b�u��
�@�A���E�z���A�k�q���r
�@���J���J��q�낤�낭�r�ߓx
�@���C���M�ɂ��x�J�P�u��
�@���J�P�u���O�����M��
�@�J�M�P�u
�@��`���̔x�J�P�u��
�@�x�Jႚb
�@�x�J�b�P
�@�x�J�b�u���s���q�ӂсr��
�@�x�a�P�u�f��
�@�x�a�̊P�f�^��
�@�x�a�P�fႌ�
���b����
�@�Q�ޒ��C���q���Ⴟ�Ƃ��r
�@���P�[�C���q�����̂����Ƃ��r
�@���|���q�����Ƃ��r
�b�؎��@�̑��_
���z����
�@�֕����q�Ƃ�ӂ��Ƃ��r
���S�a��
�@��S���q�Ă�����Ƃ��r
�@�������q����Ƃ��r
�S�a�̎��@��_��
�s���q�ӂсr�a��
�@�S���s��
�@�s��������
���x�a��
�@���ˍp�q�����������r
�@�����v�C���q�����������Ƃ��r
�@������œ��q�������ǂ��Ƃ��r
�@���x�J�u�ہq����͂��˂���������r
�@�����؊W���q������傤����������r
�x�a�̎��@��_��
�@�y���z�����O�q��������ɂ݂傤����r�E�O���O�q����݂傤����r
��់���
�@��႓��q�Ƃ�����Ƃ��r
�@��ႉ��Ð����q�Ƃ��������Ƃ��r
�@���C�{�_���q���傤���悤����Ƃ��r
់����S�̌����E���@��_��
��z់���
�@ᒕ����]�[��
�@�������傤�q�������傤�r
�@���B��
�@���B��
�@���B���̑O��
�@់����S
�@�_�o����
����C���ו�
�@���ד��q���傤����Ƃ��r
�@��z���ד��q�����悤���傤����Ƃ��r
�@���T���ד��q�肤���傤����Ƃ��r
�@���B���ד��q�����Ђ��傤����Ƃ��r
�����̎��@��_��
�C�a��
�@��C�������֕s��
�@��C����
�@��C���אg��
�@��C�������H
�@��C�����l�C
�@�ՋC��Ռ��z��
�@�C�s�~
�@�̋C�T���C�s�~
�@�C�s�~
�����O������
�@�{�����q�����ӂ��Ƃ��r
�@�������q�����ӂ��Ƃ��r
�@�������q�����ӂ��Ƃ��r
�@�������ˌܕ����q���݂����������Ƃ��r
�@�����ʛ����U�q���݂��傭�ւ��ӂ�����r
�@�����������q�����ӂ��Ƃ��r
�@�����⌌���q���݂ق��Ƃ��r
�]�[���̌�������ю��@��_��
�]�[���͗\�h�ł��邱�ƁC����т��̏Ɍ�蒆���Ɩ��Â����R��_��
�@�y���z���ꂢ���q����ꂢ�Ƃ��r
�@���ꂢ���q����ꂢ�Ƃ��r
�]�n�����@�_
�@�y���z�]���@
�@�⌌���q�ق��Ƃ��r
�]�n���ɂ���~�p�̎��@��_�����������E�k�K�O�搶�ɓ�����
�@�y���z�������q�����Ƃ��r�E��]�U�~���q�ق̂����Ƃ��r
�@�������q�����Ƃ��r
�@��]�U�~���q�ق̂����Ƃ��r
�]�[����
�@�]�[������
�@�]�[������
�@�]�[������
�@�]�[���������~��
�@�]�[����႙q���r
�@�]�[�����Ό�
�����a��
�@����
�@�Ꮎ
�@�ڕa���u
�@����
���������ؕ�
�@�蕗�O�q�Ă��ӂ�����r
�@�������q����ӂ��Ƃ��r
�@�y�����z�����������q��������Ƃ����傤�Ƃ��r
�@�y�����z���������n�����q���݂肿�イ�������Ƃ��r
�������~�p��
�@��Γ��q�قւ�Ƃ��r
�@�U�����q�����Ƃ��r
�@�U���ہq��������r
�@�I�P�p�q���傤���傤�����r
�����~�p�̌�������ю��@�̘_
�@�y���z�N�~���q�����Ƃ��r�E�{�]�������q�悤�̂��肵�Ƃ��r
�@�N�~���q�����Ƃ��r
�@�{�]�������q�悤�̂��肵�Ƃ��r
��
�@�p��
�@�l�Q��
�@���m�Q��
�@���ˁq�������r��
�@�R��q�����r��
�@���Q���q�тႭ����r
�@�ސk���ސl��
�@�R���
�@�n����
�@����
�@�鍻��
�@��_�q���i���Ɋ��`�q�Ƃ����C��Q�̎�q�j
�@�������i�������j
�@���a��
�@�Ό�����
�@���Q��
�@���A��
�@䉖��
�@���イ���イ�q���イ���イ�r�k�삫�イ�l��
�@�剩��
�@�p�ɁE�ɐΉ�
�@���p��
�@������
�@�ČӉ�
�@�j�}��
�@�O����
�@�O���̓��قȌ��\��_���i��܊���2���j
�@���Ή�
�@���G��
�@���u��
�@���_����
�@���ĉ�
�@���O��
�@�V�ԕ���
�@���I��
�@���I��
�@���q�E�G���E�V�Y��
�@���j��
�@�m���
�@�V��~��
�@����~��
�@���A��
�@������q��������r��
�@��������
�@���s������
�@�N���H����
�@�唞���
�@䟂���q����r��
�@�炢�ӂ��q�q�炢�ӂ����r��
�@�m�X�q��
�@�C�����E������
�@㠈��k��
�@�|����q��������r��
�@���Q��
�@���Q�͔x�J�iᔁj���Â̗v��̘_�i��܊���2���j
�@�A�ɉ�
�@����q��
�@����
�@䨗�q�Ԃ���傤�r�E䨐_�q�Ԃ�����r��
�@�ؒʉ��y���z�ؒʓ��q�������Ƃ��r
�@������
�@�O��傤�q�����傤�r�E䮞Q�q������r��
�@�����E�v���
�@��R��
�@�R���q���r��
�@�Ξցq������イ�r��
�@�������
�@���q�m��
�@�垥��
�@�ӓ����i�j���j�k�ӓ����E�ӓ��m�E�j�����l
�@�ܖ��q��
�@�Ђ����q�Ђ����r��
�@�Ђ����q�Ђ����r�͎��M�ɑ���v��ŗ҂ɗp���Ă͂Ȃ�Ȃ��̘_�i��܊���2���j
�@�{������
�@�{�����͏��q�����J�������v��̘_�i��܊���2���j
�@���R�b��
�@��n�q�������r��
�@���g�q�������r��
�@噎q�q�������r��
�@��ށq�����r��
�@㷗r�p�q�ꂢ�悤�����r��
�@㷗r�p�فy���z㷗r�p�̑�ւ����i��܊���2���j
�@�ØI���ň��q����낵�傤�ǂ�����r
�@���]�Y��
�@�w�b��
�@�ׂ��b�q�ׂ������r�k�y�ʍb�l�E�T�͋���ɗp���Ă͂Ȃ�Ȃ��̘_�i��܊���2���j
��܊���1�����
�@�l�g�_���F
�@���C�F
�@��C�F
�@�l�g�̌N�E���ɐ�V�E��V�̕�����̘_
�@�]�C�ؙ��q�ׂ�r
�@���z�͟����q�䂤�ԁr����̘_
������
���ܖ�����
������
�}��
�ጾ�k�����̖}��l
�A���J�M����
�@�������q�������Ƃ��r
�@�\�S��^���q���イ��������Ƃ��r
�@�Ґ���q�ꂢ����r
�@�ꖡ���P���q�����݂���悢��r
�@�Q�����q������Ƃ��r
�@��ʓ�q���ガ�傭�ɂق�����r
�@���ᓒ�q�悭���Ƃ��r
�@�������q�������傤�Ƃ��r
�@���ϓ��q�������Ƃ��r
�@�������q�炢�ӂ��Ƃ��r
�@���ۓ��q���Ƃ��r
���J�b�u��
�@�A���E�z���A�k�q���r
�@���J���J��q�낤�낭�r�ߓx
�@���C���M�ɂ��x�J�P�u��
�@���J�P�u���O�����M��
�@�J�M�P�u
�@��`���̔x�J�P�u��
�@�x�Jႚb
�@�x�J�b�P
�@�x�J�b�u���s���q�ӂсr��
�@�x�a�P�u�f��
�@�x�a�̊P�f�^��
�@�x�a�P�fႌ�
���b����
�@�Q�ޒ��C���q���Ⴟ�Ƃ��r
�@���P�[�C���q�����̂����Ƃ��r
�@���|���q�����Ƃ��r
�b�؎��@�̑��_
���z����
�@�֕����q�Ƃ�ӂ��Ƃ��r
���S�a��
�@��S���q�Ă�����Ƃ��r
�@�������q����Ƃ��r
�S�a�̎��@��_��
�s���q�ӂсr�a��
�@�S���s��
�@�s��������
���x�a��
�@���ˍp�q�����������r
�@�����v�C���q�����������Ƃ��r
�@������œ��q�������ǂ��Ƃ��r
�@���x�J�u�ہq����͂��˂���������r
�@�����؊W���q������傤����������r
�x�a�̎��@��_��
�@�y���z�����O�q��������ɂ݂傤����r�E�O���O�q����݂傤����r
��់���
�@��႓��q�Ƃ�����Ƃ��r
�@��ႉ��Ð����q�Ƃ��������Ƃ��r
�@���C�{�_���q���傤���悤����Ƃ��r
់����S�̌����E���@��_��
��z់���
�@ᒕ����]�[��
�@�������傤�q�������傤�r
�@���B��
�@���B��
�@���B���̑O��
�@់����S
�@�_�o����
����C���ו�
�@���ד��q���傤����Ƃ��r
�@��z���ד��q�����悤���傤����Ƃ��r
�@���T���ד��q�肤���傤����Ƃ��r
�@���B���ד��q�����Ђ��傤����Ƃ��r
�����̎��@��_��
�C�a��
�@��C�������֕s��
�@��C����
�@��C���אg��
�@��C�������H
�@��C�����l�C
�@�ՋC��Ռ��z��
�@�C�s�~
�@�̋C�T���C�s�~
�@�C�s�~
�����O������
�@�{�����q�����ӂ��Ƃ��r
�@�������q�����ӂ��Ƃ��r
�@�������q�����ӂ��Ƃ��r
�@�������ˌܕ����q���݂����������Ƃ��r
�@�����ʛ����U�q���݂��傭�ւ��ӂ�����r
�@�����������q�����ӂ��Ƃ��r
�@�����⌌���q���݂ق��Ƃ��r
�]�[���̌�������ю��@��_��
�]�[���͗\�h�ł��邱�ƁC����т��̏Ɍ�蒆���Ɩ��Â����R��_��
�@�y���z���ꂢ���q����ꂢ�Ƃ��r
�@���ꂢ���q����ꂢ�Ƃ��r
�]�n�����@�_
�@�y���z�]���@
�@�⌌���q�ق��Ƃ��r
�]�n���ɂ���~�p�̎��@��_�����������E�k�K�O�搶�ɓ�����
�@�y���z�������q�����Ƃ��r�E��]�U�~���q�ق̂����Ƃ��r
�@�������q�����Ƃ��r
�@��]�U�~���q�ق̂����Ƃ��r
�]�[����
�@�]�[������
�@�]�[������
�@�]�[������
�@�]�[���������~��
�@�]�[����႙q���r
�@�]�[�����Ό�
�����a��
�@����
�@�Ꮎ
�@�ڕa���u
�@����
���������ؕ�
�@�蕗�O�q�Ă��ӂ�����r
�@�������q����ӂ��Ƃ��r
�@�y�����z�����������q��������Ƃ����傤�Ƃ��r
�@�y�����z���������n�����q���݂肿�イ�������Ƃ��r
�������~�p��
�@��Γ��q�قւ�Ƃ��r
�@�U�����q�����Ƃ��r
�@�U���ہq��������r
�@�I�P�p�q���傤���傤�����r
�����~�p�̌�������ю��@�̘_
�@�y���z�N�~���q�����Ƃ��r�E�{�]�������q�悤�̂��肵�Ƃ��r
�@�N�~���q�����Ƃ��r
�@�{�]�������q�悤�̂��肵�Ƃ��r
��
�@�p��
�@�l�Q��
�@���m�Q��
�@���ˁq�������r��
�@�R��q�����r��
�@���Q���q�тႭ����r
�@�ސk���ސl��
�@�R���
�@�n����
�@����
�@�鍻��
�@��_�q���i���Ɋ��`�q�Ƃ����C��Q�̎�q�j
�@�������i�������j
�@���a��
�@�Ό�����
�@���Q��
�@���A��
�@䉖��
�@���イ���イ�q���イ���イ�r�k�삫�イ�l��
�@�剩��
�@�p�ɁE�ɐΉ�
�@���p��
�@������
�@�ČӉ�
�@�j�}��
�@�O����
�@�O���̓��قȌ��\��_���i��܊���2���j
�@���Ή�
�@���G��
�@���u��
�@���_����
�@���ĉ�
�@���O��
�@�V�ԕ���
�@���I��
�@���I��
�@���q�E�G���E�V�Y��
�@���j��
�@�m���
�@�V��~��
�@����~��
�@���A��
�@������q��������r��
�@��������
�@���s������
�@�N���H����
�@�唞���
�@䟂���q����r��
�@�炢�ӂ��q�q�炢�ӂ����r��
�@�m�X�q��
�@�C�����E������
�@㠈��k��
�@�|����q��������r��
�@���Q��
�@���Q�͔x�J�iᔁj���Â̗v��̘_�i��܊���2���j
�@�A�ɉ�
�@����q��
�@����
�@䨗�q�Ԃ���傤�r�E䨐_�q�Ԃ�����r��
�@�ؒʉ��y���z�ؒʓ��q�������Ƃ��r
�@������
�@�O��傤�q�����傤�r�E䮞Q�q������r��
�@�����E�v���
�@��R��
�@�R���q���r��
�@�Ξցq������イ�r��
�@�������
�@���q�m��
�@�垥��
�@�ӓ����i�j���j�k�ӓ����E�ӓ��m�E�j�����l
�@�ܖ��q��
�@�Ђ����q�Ђ����r��
�@�Ђ����q�Ђ����r�͎��M�ɑ���v��ŗ҂ɗp���Ă͂Ȃ�Ȃ��̘_�i��܊���2���j
�@�{������
�@�{�����͏��q�����J�������v��̘_�i��܊���2���j
�@���R�b��
�@��n�q�������r��
�@���g�q�������r��
�@噎q�q�������r��
�@��ށq�����r��
�@㷗r�p�q�ꂢ�悤�����r��
�@㷗r�p�فy���z㷗r�p�̑�ւ����i��܊���2���j
�@�ØI���ň��q����낵�傤�ǂ�����r
�@���]�Y��
�@�w�b��
�@�ׂ��b�q�ׂ������r�k�y�ʍb�l�E�T�͋���ɗp���Ă͂Ȃ�Ȃ��̘_�i��܊���2���j
��܊���1�����
�@�l�g�_���F
�@���C�F
�@��C�F
�@�l�g�̌N�E���ɐ�V�E��V�̕�����̘_
�@�]�C�ؙ��q�ׂ�r
�@���z�͟����q�䂤�ԁr����̘_
������
���ܖ�����
������