5月18日(土),19日(日)の両日,標記学会が福岡国際会議場(福岡市博多区)にて開催され,延べ2,400名以上の参加を得た(大会長:福岡歯科大学教授 佐藤博信氏).以下,メインホール等にて行われた各種講演を複数レポートする.
「咬合違和感に対し,歯科医師は何を考えなければならないか」 松香芳三氏(徳島大)が「臨床的に咬合異常が認められないにも関わらず六ヶ月以上持続する咬頭嵌合位での不快感(咬合感覚異常)」を訴える患者に行う各種検査について神経内科学的検査を中心に説明.同学会が定義した「咬合違和感症候群(Occlusal discomfort syndrome)への診断法として,玉置勝司氏(神奈川歯科大学)が大学病院で実践しているK式多軸診断シートをベースに診断・治療方針の手法を説明した(座長;明海大 藤澤政紀氏,大阪大 石垣尚一氏).
「ここまで来たデジタル補綴」 複雑な機能的咬合面を付与する補綴物製作において,下顎運動測定や模型製作~咬合器操作の一連の工程を三次元バーチャル画像上にて執り行う最新手法について小川 匠氏(鶴見大)が,internal scannerを用いたデジタル印象採得の有用性について風間龍之輔氏(東京医科歯科大)が,多用な素材を扱えるようになったCAD/CAMシステムによるデジタル歯科技工の現状について木村健二氏(協和デンタル・ラボラトリー)が,それぞれ自身のチェアサイド・ラボサイドワークに照らし合わせて解説した(座長;東京医科歯科大 三浦宏之氏,鶴見大 中村善治氏).
「超高齢化社会の中で社会,患者は何を求めているのか?」 居宅介護施設の田中靖代氏(ナーシングホーム気の里)が「食べられるか否かは健康長寿の要」との認識に基づいて要介護者への支援活動を報告した後,廃用症候群を有する要介護度5の患者に機能障害に見合った形態を付与した義歯で咀嚼機能を回復した症例を大川延也氏(大川歯科医院)が供覧.インプラント領域においても,今後は通院可能患者のみでなく有病者や要介護者をも意識した術式および術後のメインテナンスに取り組むことの必要性が萩原芳幸氏(日本大学)から指摘された(座長;東京歯科大 櫻井 薫氏,徳島大 市川哲雄氏).

「インプラントと天然歯の共存を考える補綴治療計画」 インプラントと天然歯のLongevityについて研究者の立場から話した松下恭之氏(九州大)は,インプラント自体への生体力学的ルールを遵守し,インプラントによる受圧・加圧条件を入念にコントロールする必要があると展開.城戸寛史氏(福岡歯科大)が患者のエイジングを見据えて将来的な欠損部位の拡大を考慮に入れた補綴設計を行うことを提唱した後,武田孝之氏(武田歯科医院)は自身の過去の約500症例・800本・15年以上経過のインプラント症例を統計的にまとめながら振り返り,インプラントを手掛ける歯科医師には欠損状態,歯列,咬合,顎堤の各要素において「先を読む力」が求められること,60歳以上の高齢者へのインプラント治療にあたっては患者の理解度と優先順位,経済面,健康面の将来予想を交えて判断するべきことを主張した.また,座長見解を含むまとめとして,①補綴後の口腔内組織の変化を予測しておく,②インプラントの特徴と経年的変化を考慮する,③将来的変化に対する対応を考慮しておく,④患者への十分な説明と,患者による治療選択,を提示.術者可撤式の単純設計や,治療オプションの提示,生涯治療費の相談などを歯科医師の立場から考えていく時代に入ったことを示した(座長;長崎大 澤瀬 隆氏,昭和大 尾関雅彦氏).
「Digital workflow in reconstructive dentistry」 Prof.Joerg Rudolf Strub氏(Albert-Ludwigs-University)が①Data acquisition,②Treatment planning,③CAD/CAM technology,④Future perspectiveの四項目を取り上げ,①においてはinternal scannerとexternal(3D-X ray)scannerについて,歯科メーカー各社の製品比較一覧で分けられた技術面の解説に加えて,臨床応用可能性に大きく関わる価格(コスト)の観点を踏まえた報告が行われた(座長;福岡歯科大 佐藤氏).
「垂直破折歯根の接着再植治療」 菅谷 勉氏(北海道大)が同大病院の症例をもとに,垂直歯根破折は歯冠側からも根尖側からも同程度の頻度で生じている,ポストが長いほど根尖部破折は少ない,との実態報告を行った.眞坂信夫氏(学会西関東支部)は「歯根破折歯をいかに抜かずに直すか」を念頭に診断方法と治療法を披露.峯 篤史氏(大阪大)はPub Medでの検索で選んだ14論文から歯根破折発生率などに関する文献的考察を行った(座長;日本大 松村英雄氏,東京歯科大 佐藤 亨氏).
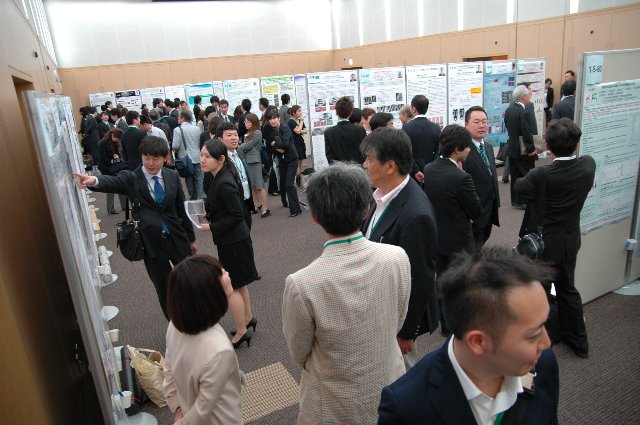
「全部床義歯の頂をめざす方たちへ」 総義歯臨床における重要事項である「咬合」を小出 馨氏(日本歯科大 新潟)が,「吸着」を阿部二郎氏(東北大)が,「デンチャースペース」を上濱 正氏(学会東関東支部)がオーソリティとして解説した.小出氏はフェイスボウや調節性咬合器,咬合様式は患者の顎堤条件に従って選択することを,阿部氏は世のいずれの総義歯製作法でも「快適な咬合高径と適正な水平下顎位」が共通命題であることを,上濱氏は総義歯の著名な成書を読むことの重要性と,「支持,維持,筋平衡,咬合平衡の機能時適応を図ってデンチャースペースを回復させるべきことを,それぞれ訴えた(座長;東北大 佐々木啓一氏,東京医科歯科大 水口俊介氏).

第123回学術大会(大会長;東北大学大学院歯学研究科教授 佐々木啓一氏)は2014年5月24~25日,仙台国際センター(仙台市青葉区)にて開催予定である.