7月2日(金)~4日(日),クロス・ウェーブ府中(東京都府中市)にて,2010年臨床歯科を語る会が,170名の参加者を集め開催された(実行委員長:松井宏榮氏/神奈川県開業).

実行委員長の松井氏
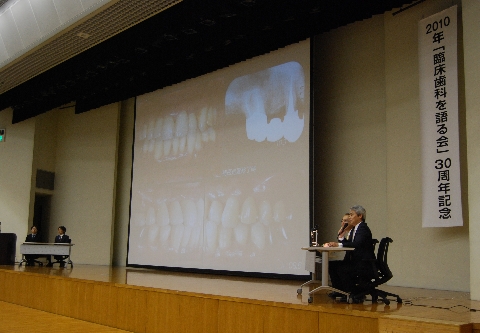
シンポジウムより
同会発足30周年という節目の開催であり,2日目午前には,「語る会30周年の伝承と継承」とのプログラムが組まれ,これまでの同会の活動を振り返るとともに,これからの歯科界における同会の存在意義についての提言が,歴代の実行委員長(金子一芳氏/東京都開業,北川原健氏/長野県開業,黒田昌彦氏/東京都開業,須貝昭弘氏/神奈川県開業)のリレー講演の形で展開された.
また,同日午後の全体会では,「欠損歯列における自家歯牙移植」とのテーマのもと,欠損歯列改変のための有効な手段である自家歯牙移植について,長期経過症例からその適応症を再検証する試みがなされた.
続く講演「次の一歩――臨床記録をデータベース化する意味」では,林康博氏(熊本県開業)が自院で活用しているデータベースを紹介し,データとしてみずからの臨床を振り返ることで初めて認識できることが多いことを報告.そのうえで,同会が蓄積してきた長期経過症例をデータとして発信していく作業が,これからの同会に求められると強調された.
シンポジウム「咬合と力のコントロールする」では,歯・歯周組織・歯列の崩壊原因としての“力”について,その診断のあり方と力のコントロールのためのさまざまな方策が検討された.牛島隆氏(熊本県開業)は,口腔内に発現する力の要素として,“grinding”“clenching”に分類されない“gnashing”の概念がブラキシズムの理解にとって重要であることを報告.森本達也氏(神奈川県開業)は,口腔内に現れる力の様相を豊富な臨床像から紹介.仲村裕之氏(神奈川県開業),千葉英史氏(千葉県開業)は,力の問題をコントロールする取り組みを長期の臨床経過から報告され,さらに永田省蔵氏(熊本県開業)は,ガイドの緩急や歯周病の罹患状況との関係のなかでパラファンクション発現の様相を整理された.
最終日には「私の考える総合歯科臨床」と題し,押見一氏(東京都開業)が特別講演.33年にわたる障害児歯科診療や,ブラキシズム患者の長期経過観察の経験から,多くの歯科疾患は結局は患者自身が治していくものと述べられ,歯科医療が提供すべきものについて再考していく必要性を強調された.
最後のプログラムである,シンポジウム「欠損改変のためのインプラント植立への考察」では,須貝氏,松田光正氏(熊本県開業),松井氏,金子氏が相次いで登壇.咬合支持や受圧条件の改変,あるいは義歯の安定など,補綴治療の目的によってインプラントの活用法方法が異なることを,特に可撤性義歯との共存のあり方を整理しつつ検証が試みられた.
同会がこれまで変わらずに大切にしてきた,口腔内写真やX線写真などディスカッションの大前提となる臨床記録.その膨大な臨床記録を歯科界全体の財産として活用していく道筋づくりが同会の今後の課題であるとの意識がプログラムの随所で提言され,30周年を迎え同会の新たな出発点との印象をもった3日間であった.
